| 1990年 「New Moon」 (1990/6/21発売) の頃 | |
|---|---|
| きかせてあげたい NHKみんなのうた Various Artists (1990) アポロン音楽工業 | |
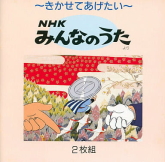 |
1. コロは屋根のうえ [作詞作曲 大貫妙子] CD2-2曲目 古川葉子: Vocal 1990年5月21日発売 1. Koro Wa Yane No Ue (Koro's On The Roof) [Words & Music: Taeko Onuki] CD2-2nd track by Yoko Furukawa from the album of various artists "Kikaseteagetai NHK Minnna N Uta" (I Want You To Listen NHK Everybody's Songs)" May 21, 1990 |
| 「コロは屋根のうえ」は、「みずうみ」1983、「メトロポリタン美術館」1984に続く大貫さん三作目の「NHKみんなのうた」で、初回放送は1986年12月〜1987年1月。大貫さんが歌ったオリジナル録音は、1991年6月に発売されたベスト・アルバム「Pure
Drops」に収められている。子供向けの歌でありながら、大人も楽しめるファンタスティックな歌詞とメロディーを持った曲だ。当時「NHKみんなのうた」曲集が多くのレコード会社から発売されたが、契約の関係でオリジナル録音を使えない場合、別の歌い手により録音したものを使うのが通例だった。以前はミュージック・テープを販売していたアポロン音楽工業が制作した本作CDでは古川葉子が歌っている。 彼女は、同社から発売された他の「NHKみんなのうた選集」アルバムの多くで、いろんな曲を歌っている。それ意外は彼女に関する資料がないことから、一定分野に特化したアポロンの専属歌手だったようだ。 編曲者のクレジットはないが、ほぼオリジナル通りの伴奏(キーも同じ)なので、同一譜面を使っているものと思われる。 なお本曲が収めらた2枚組CDのCD2-17曲目には1988年初出の井上美哉子による「メトロポリタン美術館」も収められている。この手の録音は、別のアルバムに使い回されることが普通なので、本曲についても本CDよりも以前の収録アルバムがあるかもしれない。 [2024年9月作成] |
|
| ピーターラビットとなかまたち 第1集 Various (1990) 東芝EMI | |
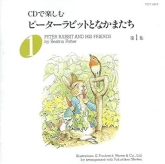 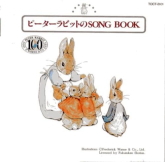 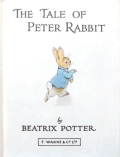 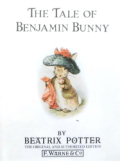 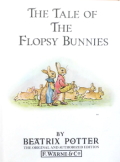 |
1. 主題歌「ピーターラビットとわたし」 歌:大貫妙子(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)歌 大貫妙子 2. イメージ曲「ピーターラビットのおはなし」 インストルメンタル (作曲 森山良子 編曲 溝口肇) 3. 朗読 「ピーターラビットのお話」朗読:五十嵐淳子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「ベンジャミン バニーのおはなし」 インストルメンタル (作曲 森山良子 編曲 中西俊博) 5. 朗読 「ベンジャミン バニーのおはなし」朗読:森本レオ(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ)) 6. イメージ曲「フロプシーのこどもたち」 インストルメンタル (作曲 森山良子 編曲 溝口肇) 7. 朗読 「フロプシーのこどもたち」朗読:渡辺美佐子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜スロー・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)チェロ 溝口肇 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 大貫妙子: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8) Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 菅野洋子: Piano (6) 古川昌義: Guitar (2,4,6) 斎藤誠: Bass (2) 渡辺等: Bass (6) 山川恵子: Harp (2) 悌郁夫: Marimba (2), Percussion (6) 溝口肇: Chello (2,6,8) 中西俊博: Violin (4) 桑野聖: Violin (4) 十亀有子: Flute (2) 一戸敦、須賀昭雄: Flute (4) 山根公男: Clarinet (2) 正司和夫: Oboe (2) 大沢昌生: Fagott (2) 五十嵐淳子、森本レオ、渡辺美佐子: 朗読 吉田新一 (英文学者): 寄稿 「耳で文を聞き、目で絵を読み、想像力を使っておはなしを楽しむ絵本」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 お断り: 1.は大貫さんが自分の曲を歌っているので、本ディスコグラフィーでは「Various シングル・コンピレーション」の部に掲載すべきなのですが、作品の構成上「Composer」の部に記載することにしました。 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第1集」 1990年6月27日発売 CD 「ピーターラビットのSong Book」 1993年8月25日発売 Book 「The Tale Of Peter Rabbit」 英語版 初版は1902年出版 Book 「The Tale Of Benjamin Bunny」 英語版 初版は1904年出版 Book 「The Tale Of The Flopsy Bunnies」 英語版 初版は1909年出版 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi" (Main Theme "Peter Rabbit And Me") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Taeko Onuki 2. Image Kyoku "Peter Rabbit No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Peter Rabbit") Instrumental [Music: Ryoko Moriyama, Arr: Hajime Mizoguchi] 3. Rodoku "Peter Rabbit No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Peter Rabbit") Reader: Jyunko Igarashi [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Benjamin Bunny No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Banjamin Bunny") Instrumental [Music: Ryoko Moriyama, Arr: Toshihiro Nakanishi] 5. Rodoku "Benjamin Bunny No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Benjamin Bunny") Reader: Leo Morimoto [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Flopsy No Kodomo Tachi" (Image Song "The Tale Of The Flopsy Bunnies") Instrumental [Music: Ryoko Moriyama, Arr: Hajime Mizoguchi] 7. Rodoku "Flopsy No Kodomotachi" (Recitation "The Tale Of The Flopsy Bunnies") Reader: Misako Watanabe [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watashi〜Slow Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Slow Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Cello: Hajime Mizoguchi Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |
| ベアトリス・ポッター(1866-1943)はロンドンの富裕家庭に生まれ、学校に行かずに家庭教師から教育を受けた。友人がいない孤独な環境に育ち、様々な動物をペットとして飼育・観察し、スケッチをする日々を送った。日記をつけ、親族にクリスマスカードを送ったり、家庭教師の子供等にお話しとスケッチを記した手紙を送っているうちに周りから認められるようになり、35歳の1901年に子供の頃から避暑地として過ごした湖水地方を舞台とした童話「ピーターラビットのおはなし」を自費出版し、好評を受けて翌1902年フレデリック・ウォーン社から商業出版されベストセラーとなった。以降ウォーン社から年に2冊出版されるようになり、その収入で1905年湖水地方のヒル・トップ農場を購入して自立し、親の束縛から解放されて当地に住みながら、その後も印税収入で土地や建物を買い増し、1913年(46歳)にその関係で知り合った弁護士と結婚した。その後は創作活動は少なくなり、農場経営や自然保護運動に力を注ぐようになる。前者ではハードウィック種という羊の保護・育成活動、後者では自然・建物の保護活動をナショナル・トラストへの参加などで功績を残し、死後に湖水地方の建物・土地はナショナル・トラストに寄贈された。自然・動物を愛し、優れた文学作品を残しただけでなく、農業または牧業の実践者としても功績をあげたという点で、日本の宮沢賢治との共通点が認められる。なお日本語翻訳の出版は意外に遅く、1971年の石井桃子(1907-2008)
訳・福音館書店出版が初めてである。私は彼女の作品が大好きで、大貫さんが1982年に「ピーターラビットとわたし」を発表した頃と同時期に、英語版の絵本やウェッジウッド製のマグカップと皿を購入し、好きが高じて80年代のイギリス旅行の際に、湖水地方ニア・ソーリー村にあるポッターの屋敷ヒルトップにレンタカーで訪れた思い出がある。 1990年東芝EMIは、版元フレデリック・ウォーン社および翻訳権を持つ福音館書店の許諾と協力のもと、多くの著名音楽家・俳優の参加を得て、彼女の絵本作品の大部分を収めた7枚組の音楽・朗読CDを発売した。タイトルは「ピーターラビットとなかまたち」で、正式にはその冒頭に「CDでたのしむ」が付いている。各CDには3つの「おはなし」の朗読が収録され、オープニングとエンディングに大貫さん作の「ピーターラビットとわたし」が、各「おはなし」の前には短いイメージ曲(インストルメンタル)が配されている。しかも各集のオープニングには1982年の作品にはなかった新しい歌詞が追加され、大貫さん以外の歌手が歌うという大変凝った構成になっているのだ。なお本CDは単発および福音館書店の本とセットとの2種類で発売されたが、当時の私は日本語版の本や朗読につき食指が動かなかったため、大貫さんの音楽が面白く展開されている事を知らず、実際に聴いたのはずっと後になってからだった。ちなみに本シリーズ発売から3年後の1993年に7枚のCDから音楽部分のみを抽出して1枚のCDにまとめた「ピーターラビットのSong Book」が発売されている。以下第1集から順次紹介してゆきたい。 第1集は大貫さん自らが歌う 1「ピーターラビットとわたし.」がオープニング。大貫さんのコメントの一部「10数年前、ウェッジウッド社のティーカップが出会いのきっかけでした。その後すぐに本を買い求めました」(こういう人が多いんですよね〜)。坂本龍一編曲によるアルバム「Cliche」1982収録のオリジナルに対し、ここでは清水信之がアレンジを担当。原曲のイメージを尊重しながら、シンセサイザーの刻みを微妙に変えている。また原曲の歌詞2番3分1秒に対し、ここでは歌詞1番のみの1分45秒と短くなっている。ちなみに本バージョンは後年2009年に大貫さんが発表したコンピレーション・アルバム「Palette」に「CD Book Version」として収められた。エンディングは清水信之と溝口肇(1960- 大貫さんのピュア・アコースティック・コンサートにも参加しているチェロ奏者)による同曲のインストルメンタル。原曲のシンセによるリズムを除いたクラシカルなアレンジによるスロー・バージョンとなっている。 朗読は「ピーターラビットのおはなし(The Tale Of Peter Rabbit 1902)」、「ベンジャミン バニーのはなし (The Tale Of Benjamin Bunny 1904)」、「フロプシーのこどもたち (The Tle Of The Flopsy Bunnies 1909)」の3つで、発行年より本CDの朗読は発行順ではなく、話の内容および収録時間に基づき配置されたものであることが分かる。朗読者は俳優の五十嵐淳子(1952- 女優、中村雅俊の奥さん)、森本レオ(1943- 俳優、ナレーター)、渡辺美佐子(1932- 女優)で、いずれも朗読で定評のある人たちだ。なお各「おはなし」の前(朗読中に音楽は入らない)にはイメージ曲として、クラシックのミュージシャンやシンセサイザーなどによる1〜2分の短いインストルメンタルが付されており、第1集では歌手の森山良子(1948- 彼女については説明不要)が作曲を担当している。彼女のコメントの一部「マグカップとお皿は子供用にと揃えましたが、こんなに素敵なお話があるって知りませんでした」。本CD制作当時は、日本におけるピーターラビットの知名度は今ほど高くはなかったようだ。 「おはなし」では、「フロプシーのこどもたち」でウサギの子供たちがレタスを食べて眠ってしまうシーンが興味深い。大貫さんの「ピーターラビットとわたし」の歌詞1番にも歌われていて、これは童話の世界なんだろうなと思っていたら、実際レタスに含まれるラクチュコピコリンという成分に催眠効果があるそうだ。 私は「おはなし」の鑑賞の際は英語版の絵本を広げて、本の英語と朗読の日本語を突き合わせて、その違いを楽しんでいる。 [2024年12月作成] |
|
| ピーターラビットとなかまたち 第2集 Various (1990) 東芝EMI | |
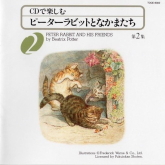 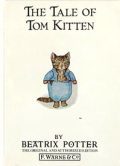 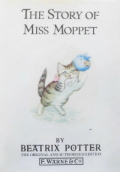 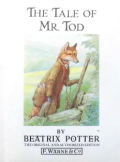 |
1. 主題歌「ピーターラビットとわたし」 歌:沢田聖子(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「こねこのトムのおはなし」 インストルメンタル (作曲編曲 山川恵津子) 3. 朗読 「こねこのトムのおはなし」朗読:小林聡美(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「モペットちゃんのおはなし」 インストルメンタル (作曲編曲 山川恵津子) 5. 朗読 「モペットちゃんのおはなし」朗読:高泉淳子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「キツネどんのおはなし」 インストルメンタル (作曲 原由子 編曲 門倉聡) 7. 朗読 「キツネどんのおはなし」朗読:岡田真澄(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜ミディアム・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)バイオリン 中西俊博 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 沢田聖子: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8) Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 山川恵津子: Synthesizer (2,4) 迫田到: Synthesizer Programming (2,4) 門倉聡: Synthesizer (6) 菅原弘明: Synthesizer Programming (6) ジェイク・E・コンセプション: Clarinet (2) 中西俊博: Violin (8) 小林聡美、高泉淳子、岡田真澄: 朗読 竹宮恵子 (漫画家): 寄稿 「"ペータ・ハーゼ"とイギリスの思い出」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第2集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of Tom Kitten」 英語版 初版は1907年出版 Book 「The Story Of Miss Moppet」 英語版 初版は1906年発売 Book 「The Tale Of Mr. Tod」 英語版 初版は1912年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi" (Main Theme "Peter Rabbit And Me") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Sawada Seiko 2. Image Kyoku "Koneko No Tom No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Tom Kitten") Instrumental [Music & Arr: Etsuko Yamakawa] 3. Rodoku "Koneko No Tom No Ohanash" (Recitation "The Tale Of Tom Kitten") Reader: Satomi Kobayashi [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Moppet Chan No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of ") Instrumental [Music & Arr: Etsuko Yamakawa] 5. Rodoku "Moppet Chan No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Miss Moppet") Reader: Atsuko Takaizumi [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Kitsune Don No Ohanash" (Image Song "The Tale Of Mr. Tod") Instrumental [Music: Yuko Hara, Arr: Satoshi Kadokura] 7. Rodoku "Kitsune Don No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Mr. Tod") Reader: Masumi Okada [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watashi〜Medium Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Medium Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Violin: Toshihiro Nakanishi Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |
第2集は「こねこのトムのおはなし (The Tale Of Tom Kitten 1907)」、「モペットちゃんのおはなし (The Tale Of Miss Moppet 1906)」、「キツネどんのおはなし (The Tale Of Mr. Tod 1912)」 の3作品を収録。第1集の朗読が各10数分だったの対し、ここでは7分、3分、45分と時間にばらつきがある。文章の多寡については、文章のページに収める文字数を調整することで、同じページ数で対応することが可能であり、CDの場合は収録時間の制限の関係でこういう組み合わせになったのだろう。特に「キツネどんのおはなし」はページ内の文字がびっしりで、45分間におよぶ朗読を聴くにはかなりの体力が要る感じ。 大貫さんファンにとって面白いのは主題曲だ。「ピーターラビットとわたし」という同じタイトルであるが、第1集と歌詞が異なっていて、1982年のオリジナル・バージョンで歌われていた歌詞の第2番が相当していて、1番のみだった第1集に続くかたちになってる。しかも大貫さんでなく別の人が歌っていることがミソ。沢田聖子(1962- )は赤ちゃんモデルとしてデビューし、子供俳優・歌手としてドラマ、CM、童謡作品に多数出演。17歳の時に当時全盛期だったイルカのオフィスからフォーク歌手としてレコード・デビューし、その後もマイペースで活動を続けている。ここでの清水信之アレンジによる伴奏はクラシック調のスローなもので、第1集のエンディング・テーマと同じものであることがわかる。沢田のボーカルは素直な感じでなかなかいいね。それにしても歌詞のなかにある「ふるぐつはひだりあしに かたおもいして こいびとのみぎのくつに ふられました」という1節は、私が知るかぎりベアトリス・ポッターの著作にはない話で、大貫さんが創った世界なのかな?でもしっくりはまっているところが流石だ。 エンディング・テーマは「ミディアム・バージョン」という副題の通りビートが効いた伴奏で、これは第1集の主題歌の伴奏トラックと同じだ。そこでは大貫さんの「Pure Acoustic」1987やNHKテレビ番組「サマーナイト・ミュージック」1988でお馴染みの中西俊博(1956- )がバイオリンを弾いている。これで7枚のCDにおける「ピーターラビットとわたし」のバッキングトラックは2種類あってそれらを使い回していることがわかった。 イメージ曲2,4の作曲・編曲・演奏を担当している山川恵理子(1956- )は、作曲家・編曲家・音楽プロデューサー・スタジオ・ミュージシャンで主にアイドル歌手系の仕事が多い人だ。そしてイメージ曲6の作曲・演奏はサザンオールスターズの原由子(1956- )が担当している。なおここでのイメージ曲は、第1集とは異なりシンセサイザーと打ち込みによる演奏になっているが、2.のみジェイク・E・コンセプションのクラリネットが入っていて、これが結構いい味を出している。 朗読者の小林聡美 (1965- )は女優、エッセイストで、テレビドラマ「3年B組金八先生」1979でデビューし、大林宣彦監督の傑作映画「転校生」1982の主役で地位を確立した人で、2000年代以降は大貫さんが音楽を担当した「めがね」2007、「マザーウォーター」2010、「東京アオシス」2011などのスローライフ系の映画の主演を務めるなど、大貫さんファンには馴染みの深い人だ。高泉淳子(1958- )は女優・劇作家・演出家で、男・女、子供・老人などあらゆる役を演じ分けることができ、歌も上手い人。岡田真澄(1935-2006)は俳優・タレントで日本人画家の父とデンマーク女性を母を持ち、外国人っぽい顔立ちとダンディーな振る舞いで人気を得た人だった。 この第2集から「ピーターラビットとわたし」の異なる人による歌唱が始まる。 [2024年12月作成] |
|
| ピーターラビットとなかまたち 第3集 Various (1990) 東芝EMI | |
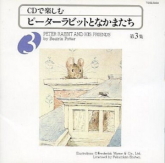 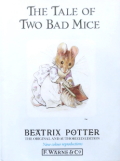 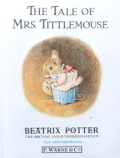 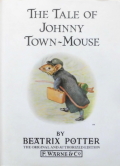 |
1. 主題歌 「ピーターラビットとわたし〜まちねずみジョニー」 歌:ラジ(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「2ひきのわるいねずみのおはなし」 インストルメンタル (作曲 西村由紀江 編曲 岡本洋) 3. 朗読 「2ひきのわるいねずみのおはなし」朗読:堺正章(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「のねずみチュウチュウおくさんのおはなし」 インストルメンタル (作曲 西村由紀江 編曲 岡本洋) 5. 朗読 「のねずみチュウチュウおくさんのおはなし」朗読:渡辺えり子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「まちねずみジョニーのおはなし」 インストルメンタル (作曲 西村由紀江 編曲 岡本洋) 7. 朗読 「まちねずみジョニーのおはなし」朗読:C.W. ニコル(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜スロー・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)チェロ 溝口肇 (第1集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック ラジ: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 西村由紀江: Piano (4,6) 斎藤誠: Bass (2) 篠田淳: Harp (6) 川村正明: Oboe (4) 金子ストリングス: Strings (2,4,6) 溝口肇: Cello (4,8) 堺正章、渡辺えり子、C.W.ニコル: 朗読 猪熊葉子(英文学者): 寄稿 「ポターランドに至る道」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第3集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of Two Bad Mice」 英語版 初版は1904年出版 Book 「The Tale Of Mrs. Tittlemouse」 英語版 初版は1910年発売 Book 「The Tale Of Johnny Town-Mouse」 英語版 初版は1918年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Machi Nezumi Johnny" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Johnny Town-Mouse") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Rajie 2. Image Kyoku "Nihiki No Warui Nezumi No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Two Bar Mice") Instrumental [Music: Yukie Nishimura, Arr: Hiroshi Okamoto] 3. Rodoku "Nihiki No Warui Nezumi No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Two Bad Mice") Reader: Masaaki Sakai [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Nonezumi Chu-Chu Okusan No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Mrs. Tittlemouse") Instrumental [Music: Yukie Nishimura, Arr: Hiroshi Okamoto] 5. Rodoku "Nonezumi Chu-Chu Okusan No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Mrs. Tittlemouse") Reader: Eriko Watanabe [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Machi Nezumi Johnny No Ohanash" (Image Song "The Tale Of Johnny Town-Mouse") Instrumental [Music: Yukie Nishimura, Arr: Hiroshi Okamoto] 7. Rodoku "Machi Nezumi Johnny No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Johnny Town-Mouse") Reader: C.W. Nicol [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Slow Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Slow Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Cello: Hajime Mizoguchi (Same Recording as 8. of Vol.1) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |
第3集は「2ひきのわるいねずみのおはなし (The Tale Of Two Bad Mice 1904)」、「のねずみチュウチュウおくさんのおはなし (The Tale Of Mrs. Tittlemouse 1910)」、「まちねずみジョニーのおはなし (The Tale Of Johnny Town-Mouse 1918)」 の3作品を収録。 主題歌 1.「ピーターラビットとわたし」の歌詞は、この集から1982年のオリジナルとは異なり、本CDに収められた朗読のひとつ「まちねずみジョニー」をもとに大貫さんが書き下ろしたものになっている。それを歌うラジは1985年のアルバム発表以来、本名の本田淳子としてセッション・シンガーとして活動していたため、この名義では久しぶりの登場となった。大貫さんの作品を多く取り上げた1970年代末のアルバムをこよなく愛する私にとって懐かしい歌声であるが、当時と声質が少し変わったかな?あのラジが「ピーターラビットとわたし」を歌うだなんて、私には衝撃的な出来事で、企画盤の主題曲ということで歌詞1番だけで終わってしまうのが誠にもったいない。コーラス部分の「陽がさんさん いちばん私の好きな場所 君もいつか たずねておいでよ」という歌詞はオリジナルを聴き慣れ過ぎた私にはとても不思議に響く。ちなみにここでの伴奏トラックはミディアム・バージョンのもの。なおエンディング・テーマについても、第3集からは第1集のスロー、第2集のミディアムのいずれかの使い回しとなり、ここでは溝口肇のチェロによるスロー・バージョンになっている。 イメージ曲を作曲した西村由紀江(1967- )はヒーリング・映画・現代音楽の分野で活躍するピアニスト、作曲家で、編曲者の岡本洋はジャズ・ピアニスト、アレンジャーだ。朗読者の堺正章(1946- )、渡辺えり子(1955- 現在の芸名は「渡辺えり」)は声に特徴のある歌手・俳優さん達(二人とも説明不要)で、この手の朗読はお手の物と思えるが、もう一人のW.C.ニコル(1940-2020) の達者な語り口には驚いた。彼はイギリス生まれで青年期から波乱万丈の人生を送り、13歳の時から習った柔術がきっかけで、日本を安住の地と決めて帰化し自然保護活動、作家として天寿を全うした人だった。 この第3集から「ピーターラビットとわたし」独自の歌詞になるなど面白い展開が始まる。 [2024年12月作成] |
|
| ピーターラビットとなかまたち 第4集 Various (1990) 東芝EMI | |
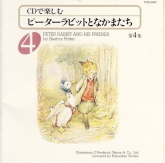  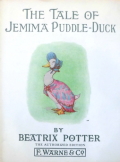 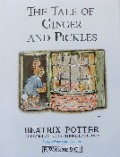 |
1. 主題歌「ピーターラビットとわたし〜リスのナトキン」 歌:由紀さおり(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「リスのナトキンのおはなし」 インストルメンタル (作曲 上田知華 編曲 岡本洋) 3. 朗読 「リスのナトキンのおはなし」朗読:斎藤晴彦(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「あひるのジマイマのおはなし」 インストルメンタル (作曲 上田知華 編曲 岡本洋) 5. 朗読 「あひるのジマイマのおはなし」朗読:由紀さおり(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「ジンジャーとピクルズやのおはなし」 インストルメンタル (作曲 上田知華 編曲 岡本洋) 7. 朗読 「ジンジャーとピクルズやのおはなし」朗読:竹中直人(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜ミディアム・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)バイオリン 中西俊博 (第2集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 由紀さおり: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 岡本洋: Keyboards (2,4), Piano (6) 迫田到: Synthesizer Programming (2,4) 内橋和久: Guitar (1) 納浩一: Bass (6) 八木のぶお: Harmonica (4) 香取良彦: Vibraphone (6) 数原晋: Piccoro Trumpet (6) 中西俊博: Violin (8) 斎藤晴彦、由紀さおり、竹中直人: 朗読 村井ミヨ子 (株・ファミリア取締役): 寄稿 「あの頃の思い出」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第4集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of Squirrel Nutkin」 英語版 初版は1903年出版 Book 「The Tale Of Jemima Puddle-Duck」 英語版 初版は1908年発売 Book 「The Tale Of Ginger And Pickles」 英語版 初版は1909年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Risu No Nutkin" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Squirrel Nutkin") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Saori Yuki 2. Image Kyoku "Risu No Nutkin No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Squirrel Nutkin") Instrumental [Music: Chika Ueda, Arr: Hiroshi Okamoto] 3. Rodoku "Risu No Nutkin No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Squirrel Nutkin") Reader: Haruhiko Saito [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Ahiru No Jemima No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Jemima Puddle-Duck") Instrumental [Music: Chika Ueda, Arr: Hiroshi Okamoto] 5. Rodoku "Ahiru No Jemima No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Jemima Puddle-Duck") Reader: Saori Yuki [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Ginger To Pickles Ya No Ohanash" (Image Song "The Tale Of Ginger And Pickles") Instrumental [Music: Chika Ueda, Arr: Hiroshi Okamot] 7. Rodoku "Ginger To Pickles Ya No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Ginger And Pickles") Reader: Naoto Takenaka [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Medium Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Medium Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Violin: Toshihiro Nakanishi (Same Recording as 8. of Vol.2) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |
第4集は「リスのナトキンのおはなし (The Tale Of Squirrel Nutkin 1903)」、「あひるのジマイマのおはなし (The Tale Of Jemima Puddle-Duck 1908)」、「ジンジャーとピクルズやのおはなし (The Tale Of Ginger And Pickles 1918)」 の3作品を収録。 主題曲は由紀さおり(1946- 彼女については説明不要)がスロー・バージョンの伴奏で歌っている。歌詞は「リスのナトキン」に基づく内容。また彼女は「あひるのジマイマのおはなし」の朗読を担当している。エンディング・テーマのインストルメンタルは、中西俊博のバイオリンによるミディアム・バージョンで、第2集と同じ録音。 イメージ曲を書いた上田知華(1957-2021)は、シンガー・アンド・ソングライター、作曲家、プロデューサー。朗読者の斎藤晴彦(1940-2014)は俳優。リスのナトキンが謎かけ唄を歌うシーン(それぞれの謎かけ唄は昔からあるマザーグースで、各答えがあるそうだ)で彼が歌うメロディーはオリジナルの英語版と同じなのかな?ということでYouTubeにあった複数の英語版の朗読を聴いてみた。単なる読み上げだったり、いろいろバリエーションがあるようだが、日本版もマザーグースの節回しを基に日本語に合うよう改変したものであることがわかった(翻訳もさぞかし大変だったろう)。リスということで、音程を高くしてクスクスと早口で歌うので、かなり難しそう。竹中直人(1956- )は俳優、映画監督で、大貫さんは彼に曲を提供したり、ゲストで歌ったり、映画「東京日和」1997の音楽を担当したりするなど、両者には親密な交流がある。ここでの彼の声はとても若々しく、現在の深みのある声とは全然違っているのが面白い。 [2024年12月作成] |
|
| ピーターラビットとなかまたち 第5集 Various (1990) 東芝EMI | |
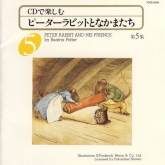 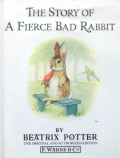 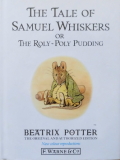 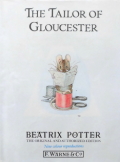 |
1. 主題歌「ピーターラビットとわたし〜ひげのサムエル」 歌:和田加奈子(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「こわいわるいうさぎのおはなし」 インストルメンタル (作曲編曲 山川恵津子) 3. 朗読 「こわいわるいうさぎのおはなし」朗読:岸田今日子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「ひげのサムエルのおはなし」 インストルメンタル (作曲 原由子 編曲 門倉聡) 5. 朗読 「ひげのサムエルのおはなし」朗読:松金よね子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「グロースターの仕たて屋」 インストルメンタル (作曲 原由子 編曲 門倉聡) 7. 朗読 「グロースターの仕たて屋」朗読:上條恒彦(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜スロー・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)チェロ 溝口肇 (第1集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 和田加奈子: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 田端元: Synthesizer Operation (1,8) 山川恵津子: Synthesizer (2) 迫田到: Synthesizer Programming (2) 門倉聡: Keyboards (4,6) 菅原正明: Synthesizer Programming (6) 吉川忠英: Guitar (2) 小倉博和: Guitar (6) 十亀有子: Flute (4) 十亀正司: Clarinet (4) 脇岡総一: Oboe (4) 吉田将: Fagott (4) 春奈禎子: Percussion (4) 金子ストリングス: Strings (4) 溝口肇: Cello (8) 岸田今日子、松金よね子、上條恒彦: 朗読 松居直 (児童文学者): 寄稿 「ことばの森を耳で旅する」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第5集」 1990年6月27日発売 Book 「The Story Of A Fierce Bad Rabbit」 英語版 初版は1906年出版 Book 「The Tale Of Samuel Whiskers」 英語版 初版は1908年発売 Book 「The Tailor Of Gloucester」 英語版 初版は1903年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Hige No Samuel" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Samuel Whiskers") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Kanako Wada 2. Image Kyoku "Kowai Warui Usagi No Ohanashi" (Image Song "The Story Of Fierce Bad Rabbit") Instrumental [Music & Arr: Etsuko Yamakawa] 3. Rodoku "Kowai Warui Usagi No Ohanashi" (Recitation "The Story Of Fierce Bad Rabbit") Reader: Kyoko Kishida [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Hige No Samuel No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Samuel Whiskers") Instrumental [Music: Yuko Hara, Arr: Satoshi Kadokura] 5. Rodoku "Hige No Samuel No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Samuel Whiskers") Reader: Yoneko Matsukane [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 6. Image Kyoku "Gloucester No Shitate-ya" (Image Song "The Tailor Of Gloucester") Instrumental [Music: Yuko Hara, Arr: Satoshi Kadokura] 7. Rodoku "Gloucester No Shitate-ya" (Recitation "The Tailor Of Gloucester") Reader: Tsunehiko Kamijyo [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Slow Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Slow Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Cello: Hajime Mizoguchi (Same Recording as 8. of Vol.1) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |
| 第5集は「こわいわるいうさぎのおはなし (The Story Of A Fierce Bad Rabbit 1906)」、「ひげのサムエルのおはなし (The Tale Of Samuel Whiskers 1908)」、「グロースターの仕たて屋 (The Tailor Of Gloucester 1903)」 の3作品を収録。 「こわいわるいうさぎのおはなし」の朗読は僅か2分20秒で、第7集の「わるいねこのおはなし」と並び本CD集中最短。絵本も活字がページあたり2〜3行とスカスカだ。その分、他のふたつの「おはなし」は各26分ちょっと長めのものを揃えている。 主題曲は「ひげのサムエル」の副題の通り、歌詞はその「おはなし」の内容に沿ったもので、伴奏トラックはミディアム・バージョン。歌っていてる和田加奈子(1963- )は歌手、作詞家。1985年〜1991年までの間にレコード・CDを出し、結婚を期に引退、離婚して現在はマイク真木夫人となりイベントなどで時々歌っているそうだ。彼女は1987年のアルバム「Quiet Storm」で 大貫さんの「あなたに似た人」(「A Slice Of Life」1987収録)を曲名を変えて歌っていた。エンディング・テーマは、溝口肇がチェロを弾くスロー・バージョン・ イメージ曲は、第2集と同じく山川恵津子と原由子が担当を分け合っている。特に「イメージ曲 グロースターの仕たて屋」は小倉博和のエレキギターがフィーチャーされ、より現代的な音作りになっているのが面白い。 朗読者の岸田今日子(1930-2006)は、その独特な容貌と声、強烈な存在感で、強烈なインパクトを与える人だった。彼女がポッター作品中でショートショートといえる「こわいわるいうさぎのおはなし」をさらっと語る様は圧巻だ。松金よね子(1949- )は女優・声優で、現在もおばあちゃん役でテレビドラマ等に出演している。上條恒彦(1940- )は歌手、俳優、声優で、六文銭と共演した「旅立ちの歌」1971、テレビドラマ「木枯らし文次郎」の主題歌「だれかが風の中で」1972 がとても印象的だった人。彼が読む「グロースターの仕たて屋 」は、人間の仕立て屋、猫とねずみ達の間で繰り広げられるクリスマスの素敵な話だ(本稿執筆が12月なので、来るクリスマスへの思いが重なったこともあるね)。上條さんがねずみに扮してマザーグースを歌う場面も面白いよ。 [2024年12月作成] |
|
| ピーターラビットとなかまたち 第6集 Various (1990) 東芝EMI | |
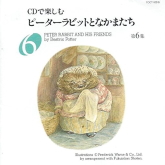 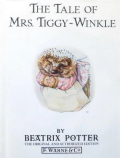 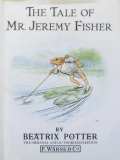 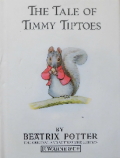 |
1. 主題歌「ピーターラビットとわたし〜カルアシ・チミー」 歌:大竹しのぶ(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之 2. イメージ曲「ティギーおばさんのおはなし」 インストルメンタル (作曲 沢田聖子 編曲 山川恵津子) 3. 朗読 「ティギーおばさんのおはなし」朗読:森山良子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし」 インストルメンタル (作曲 沢田聖子 編曲 山川恵津子) 5. 朗読 「ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし」朗読:小松方正(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「カルアシ・チミーのおはなし」 インストルメンタル (作曲 沢田聖子 編曲 山川恵津子) 7. 朗読 「カルアシ・チミーのおはなし」朗読:兵藤ゆき(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜ミディアム・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)バイオリン 中西俊博 (第2集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック 大竹しのぶ: Vocal (1) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 山川恵津子: Synthesizer (2,4,6) 石川鉄男: Synthesizer Programming (2,4,6) 平原智: Clarinet (2) 小山清: Fagott (6) 中西俊博: Violin (8) 森山良子、小松方正、兵藤ゆき: 朗読 角野栄子 (児童文学者): 寄稿 「やあ ソーリー」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第6集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of Mrs. Tiggy-Winkle」 英語版 初版は1905年出版 Book 「The Tale Of Mr. Jeremy Fisher」 英語版 初版は1906年発売 Book 「The Tale Of Timmy Tiptoes」 英語版 初版は1911年発売 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Karuashi Timmy" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Timmy Tiptoes") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Shinobu Otake 2. Image Kyoku "Tiggy Obasan No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Mrs. Tiggy-Winkle") Instrumental [Music Seiko Sawada, Arr: Etsuko Yamakawa] 3. Rodoku "Tiggy Obasan No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Mrs. Tiggy-Winkle") Reader: Ryoko Moriyama [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Jeremy Fisher Don No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Jeremy Fisher") Instrumental [Music: Seiko Sawada, Arr: Etsuko Yamakawa] 5. Rodoku "Jeremy Fisher Don No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Jeremy Fisher") Reader: Hosei Komatsu [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishi] 6. Image Kyoku "Karuashi Timmy No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Timmy Tiptoes") Instrumental [Music: Seiko Sawada, Arr: Etsuko Yamakawauko] 7. Rodoku "Karuashi Timmy No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Timmy Tiptoes") Reader: Yuki Hyodo [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishi] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Medium Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Medium Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Violin: Toshihiro Nakanishi (Same Recording as 8. of Vol.2) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |
第6集は「ティギーおばさんのおはなし (The Tale Of Mrs. Tiggy-Winkle 1905)」、「ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし (The Tale Of Mr. Jeremy Fisher 1906)」、「カルアシ・チミーのおはなし (The Tailor Of Timmy Tiptoes 1911)」 の3作品を収録。 スロー・バージョンのバックで主題歌を歌うはご存知大竹しのぶ(1957- )。ここでは「カルアシ・チミー」にちなんだ歌詞になっている。イメージ曲の作曲は第2集で主題歌を歌っていた沢田聖子、編曲は第2集と第5集に参加していた山川恵津子。主題歌がスローなので、エンディングはミディアム・バージョンだ。 森山良子は第1集のイメージ曲の作曲で既に登場済。この人の朗読は絶品だね。「ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし」 は7分ちょっとの短めの「おはなし」で、読み手の小松方正(1926-2003)は俳優・声優。特徴のある顔と声が印象的なバイプレイヤーだった。「おはなし」のなかでサー・アイザック・ニュートン卿という名前のイモリが登場するが、生きた時代は違うけどあの科学者のことを意識して付けたのかな?「カルアシ・チミー」を読む兵藤ゆき(1952- )はタレント、エッセイスト。よく「兵頭」と記されるが「藤」が正しい名前。登場人物が複数いるので、兵頭さんの声色使い分けの芸当が生かされている。また声色を使ったマザーグースの歌も愛らしくて素敵だ。 [2024年12月作成] |
|
| ピーターラビットとなかまたち 第7集 Various (1990) 東芝EMI | |
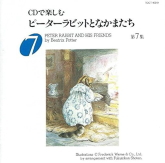 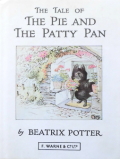 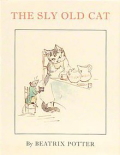 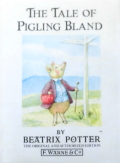 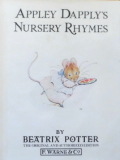 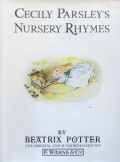  |
1. 主題歌「ピーターラビットとわたし〜ピグリン・ブランド」 歌:大貫妙子(作詞作曲 大貫妙子 編曲 清水信之) 2. イメージ曲「パイがふたつあったおはなし」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 小林武史) 3. 朗読 「パイがふたつあったおはなし」朗読:高見恭子(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 4. イメージ曲「ずるいねこのおはなし」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 小林武史) 5. 朗読 「ずるいねこのおはなし」朗読:もたいまさこ(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 6. イメージ曲「ピグリン・ブランドのおはなし」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 溝口肇) 7. 朗読 「ピグリン・ブランドのおはなし」朗読:大竹しのぶ(作 ベアトリス・ポッター 訳 いしいももこ) 8. エンディング・テーマ 「ピーターラビットとわたし〜ミディアム・バージョン」 Instrumental (作曲 大貫妙子 編曲 清水信之)バイオリン 中西俊博 (第2集 8. と同一録音) 黄色字: 大貫さんが関わったトラック お断り: 1.は大貫さんが自分の曲を歌っているので、本ディスコグラフィーでは「Various シングル・コンピレーション」の部に掲載すべきなのですが、作品の構成上「Composer」の部に記載することにしました。 大貫妙子: Vocal (1), Chorus (6) 清水信之: Synthesizer (1,8), Other Insturuments (1) 小林武史: Synthesizer (2,4) 角谷仁宣: Synthesizer Programming (2,4) 塩谷哲: Piano (6) 古川昌義: Guitar (6) 高水健司: Bass (6) 仙波清彦、平ケ倉良枝、悌郁夫: Percussion (6) 溝口肇: Cello (6) 藤山明: Recorder (6) 中西俊博: Violin (8) 高見恭子、もたいまさこ、大竹しのぶ: 朗読 斎藤惇夫 (児童文学者): 寄稿 「ピータラビットの最初の読者」 青字:大貫さんが関係するトラックに参加した人 1990年6月27日発売 写真上から CD 「CDでたのしむピーターラビットとなかまたち 第7集」 1990年6月27日発売 Book 「The Tale Of The Pie And The Patty-Pan」 英語版 初版は1905年出版 Book 「The Sly Old Cat」 英語版 初版は1971年発売 Book 「The Tale Of Pigling Bland」 英語版 初版は1913年発売 (参考: 絵本シリーズのなかで本CD集には収められなかったもの) Book 「アプリイ・ダプリイのわらべうた (Appley Dapply's Nursery Rhymes)」 英語版 初版は1917年出版 Book 「セシリ・パセリのわらべうた (Cecily Paesley's Nursery Rhymes)」 英語版 初版は1922年出版 Book 「こぶたのロビンソンのおはなし (The Tale Of Little Pig Robinson)」英語版 初版は1930年出版 1. Shudai Ka "Peter Rabbit To Watashi〜Pigling Bland" (Main Theme "Peter Rabbit And Me〜Pigling Bland") [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Sung By Taeko Onuki 2. Image Kyoku "Pie Ga Futatsu Atta Ohanashi" (Image Song "The Tale Of The Pie And The Patty-Pan") Instrumental [Music Taeko Onuki, Arr: Takeshi Kobayashi] 3. Rodoku "Pie Ga Futatsu Atta Ohanashi" (Recitation "The Tale Of The Pie And The Patty-Pan") Reader: Kyoko Takami [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishii] 4. Image Kyoku "Zurui Neko No Ohanashi" (Image Song "The Sly Old Cat") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Takeshi Kobayashi] 5. Rodoku "Zurui Neko No Ohanashi" (Recitation "The Sly Old Cat") Reader: Masako Motai [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishi] 6. Image Kyoku "Pigling Bland No Ohanashi" (Image Song "The Tale Of Pigling Bland") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Takeshi Kobayashi] 7. Rodoku "Pigling Bland No Ohanashi" (Recitation "The Tale Of Pigling Bland") Reader: Shinobu Otake [Author: Beatrix Potter, Translation: Momoko Ishi] 8. Ending Theme "Peter Rabbit To Watash〜Medium Version" (Ending Theme "Peter Rabbit And Me〜Medium Version") Instrumental [Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuyuki Shimizu] Violin: Toshihiro Nakanishi (Same Recording as 8. of Vol.2) Blue: Tracks in which Taeko Onuki is involved |
| 第7集は「パイがふたつあったおはなし (The Tale Of The Pie And The Patty-Pan 1905)」、「ずるいねこのおはなし (The Tale Of Sly Old Cat 1971)」、「ピグリン・ブランドのおはなし (The Tailor Of Pigling Bland 1913)」 の3作品を収録。「ずるいねこのはなし」は2分ちょっとの短い「おはなし」で、かつポッターの絵本シリーズには入っていない作品。というのは本作は1906年に書かれて、折りたたんだページをアコーディオンのように開いて読むという、当時異例な装丁で出版予定だったのがサンプルを見た販売者側からクレームが入って制作が頓挫し、お蔵入りした経緯がある。後にフレデリック・ウォーン社がシリーズとして出版しようとしたが、ポッターの情熱が農場経営にシフトしていたこと、彼女が加齢のため下書きだった挿絵をシリーズ用に書き直すことができなかったため、彼女の生前に世に出ることはなかった。結局彼女の死後30年近くなった1971年に下書きの挿絵とシリーズとは異なる装丁で出版された。 「ピーターラビットとなかまたち」7枚のCDには1枚あたり3つ = 計21の「おはなし」が収められたが、実際のところ絵本シリーズは23冊ある。うち「Appley Dapply's Nursery Rhymes」1917は、フレデリック・ウォーン社の財政難を救うためにポッターがかねてより集めていたナーサリーライムと書き溜めてあった絵をまとめて出版したもの。また「Cecily Paesley's Nursery Rhymes」1922はその続編的存在にあたる。したがってこれら2冊は「おはなし」ではなく挿絵がついた「わらべうた集」であり、本朗読集の対象外になったものと思われる。また「The Tale Of Little Pig Robinson」1930は、実際は1890年代という彼女の創作上初期に書かれたにもかかわらず、その長さと挿絵の少なさから当時は出版されず、ずっと後になってから世に出た作品。実際に本を手に取ると他の本の倍以上の厚みがあり、ページ内の活字もびっしり埋まっている。ポッターの絵本シリーズに含まれる「おはなし」でありながら、本朗読集から漏れたのは作品の長さによるものといえる。結果としてそのかわりに絵本シリーズ外の「ずるいねこのはなし」が選ばれたわけだ。ちなみに以上の3冊および上述の「ずるいねこのはなし」は、福音館書店からは他の絵本シリーズの作品よりも後に、石井桃子以外の翻訳で出版された。 第7集は最後ということで、主題曲は大貫さんが再登場し、「ピグリン・ブランド」の世界の歌詞をスロー・バージョンの伴奏で歌っている。第1集のミディアムと並んで、これで大貫さんの歌を両方のバージョンで聴けることになる。コーラス部分の「空のむこう はるかな ふたりの国がある 手をつないでふたりでダンスを踊ろう」という歌詞が、この「おはなし」のメルヘンチックなエンディングを表していて、このファンタスティックなCD集の主題曲の終わりを飾るに相応しい言葉になっている。そしてエンディング・テーマはミディアム・バージョン。 ここではイメージ曲も大貫さんによる作曲。ただし2.4.の編曲は清水ではなく、当時「New Moon」1990で一緒に組んでいた小林武史が担当している。そのアレンジは他のアーティストの作品と大きく異なり、「おはなし」の時代やイメージに囚われずに自由な創造力で音作りしている点がユニーク。その結果「New Moon」と似通ったサウンドになっていながら、それでいて「おはなし」とのチグハグ感はなく、それなりにしっくりきているのが凄い。なおイメージ曲 6.「ピグリン・ブランドのおはなし」はチェロ奏者溝口肇によるクラシカルなアレンジで、バック・コーラスで大貫さんの声が聞こえる。 朗読者の高見恭子(1959- )はタレント、エッセイスト。ふたつのパイをめぐる猫と犬のやりとりは可愛い系の彼女の声にぴったりだ。「ずるいねこのはなし」を読むもたいまさこ(1952- )は女優。個性的な人で、私的には大貫さんが音楽を提供した映画「かもめ食堂」2006(監督 荻上直子 主演 小林聡美)のマサコ役がとても印象的だった。そして朗読集のトリを務めるのは、第6集で主題歌を歌った大竹しのぶ。「ピグリン・ブランドのおはなし」は、ポッターの「おはなし」のなかで唯一若い男女(子ブタではあるが)のやりとりが描かれていて、二人で危機を脱するくだりなど爽やかで後味がとても良い作品だ。それを柔軟かつ自由な感覚で読みこなす大竹さんは大変魅力的で、彼女の持ち味が最大限に発揮されている。37分という長さを感じさせない朗読集の最後に相応しい名演といえるだろう。 本朗読集は原作(文と絵)、音楽、語りの全てが素晴らしい作品。ウェッジウッドの陶器や大貫さんの歌とともにポッターの作品を日本に広めた功績は大きい。しかし発売から30年以上経ち、音楽家・朗読者で亡くなった方や一線から退いた方も多く、時代の経過とともに彼らの知名度が下がったこともあり、商品価値減少の事実は否定できないだろう。しかし作品自体の本質的価値は不変であり、これからも多くの若い人たちに是非聴いてほしいものだ。そういう意味で、現在この朗読集が廃盤となり全然目立たないのは残念。 最後に原作のその後について。 1990年の本朗読集の発売以降、映像の時代となって壇ふみ朗読によるアニメDVD集(私としては静止画のほうが全然良いと思う)が出たり、2004年に原作の著作権が消滅してパブリック・ドメインとなった関係でインターネットによる配信もあったりして、作品の発信が多様化している。2018年にはCGによる映画も出たね(原作とはかなり趣が異なるコメディー作品になっていたが......)。絵本についても様々なサイズ・装丁で出版され、参考までに写真を掲載したフレデリック・ウォーン社の英語版ミニ本シリーズも、同社がペンギンブックスに吸収合併された後に新しい装丁に切り替わっている。そして2022年に早川書房が日本における公式出版社となり、芥川賞作家の川上未映子(1976- )による新訳の刊行が始まって、2024年春に絵本シリーズの全23巻(「ずるいねこのはなし」は対象外)が完結した。新訳では、今の感覚では古い・固いと感じられる石井桃子訳の表現をより現代的で躍動感ある言葉に変えたようだ。ちなみに旧来の石井桃子訳による福音館書店版も独自の装丁に変更して引き続き販売されている。 これらの名作が、これからも多くの人たちに読み継がれてゆくといいなと思います。 [2024年12月作成] |
|
| Long Long Way Home 鈴木祥子 (1990) Epic (Sony) | |
 |
1. 青い空の音符 [作詞 大貫妙子 作曲 鈴木祥子 編曲 佐橋佳幸] 8曲目 鈴木祥子: Vocal 門倉聡: Synthesizer, Acoustic Piano 西本明: Hammond Organ, Wurlitzer Piano 佐橋佳幸: Guitar, Co-Producer 美久月千晴: Acoustic Bass Guitar 青山純: Drums 浜口茂外也: Pandero 向井ヒロシ、佐橋佳幸、井上リエ、鈴木祥子: Back Vocal 藤井丈司: Programming, Producer 1990年11月21日発売 1. Aoi Sora No Onpu (Note For The Blue Sky) [Words: Taeko Onuki, Music: Shoko Suzuki, Arr: Yoshiyuki Sahashi] 8th Track |
| 80年代の音楽はテクノ、シンセ、打ち込みで覆いつくされて飽和状態になったが、その終わり頃に電子音楽とアコースティック・サウンドを上手く噛み合わせた新しい感覚の音楽が出てきた。そう書いてぱっと頭に思い浮かぶのが、スザンヌ・ヴェガの「Luka」1987
全米3位だ。鈴木祥子(1965- 東京都出身)もそういう流れにあった人だと思う。ドラム奏者として原田真二や小泉今日子のバックバンドで演奏した後、1988年にソロデビューし、他アーティストへの楽曲提供(代表作は小泉今日子の「優しい雨」1993)も積極的に行い、現在もマイペースで活動中。 アルバム「Long Way Home」は4枚目のアルバムで、YMOのアシスタントとして世に出て、幅広いジャンルの音楽を手掛けた藤井丈司がプロデュースとプログラミング、ギタリストの佐橋佳幸がコ・プロデュースを担当している。突出した曲はないけど、どの曲も水準以上の出来上がりで、トータルアルバムとしての色合いが強い。全10曲すべてが彼女の作曲(1曲のみ佐橋との共作)。作詞は自作が半分で、他は大貫さんの他に杉林恭雄(くじら)、西尾佐栄子、戸沢暢美が詩を提供している。洋楽志向が強い人のようで、英語のタイトル(歌詞は日本語)の曲や、ジャケットの歌詞には曲の英語名が記されている。西海岸の風が吹き抜けるような爽快な曲の印象が強いが、スローな曲を歌ってもロックを感じさせる歌唱スタイルが彼女の持ち味だと思う。 大貫さんが歌詞を提供した1.「青い空の音符」は、彼女が得意とする男女の別れの歌で、鈴木はそれに彼女としてはしっとり感のあるメロディーを付けて、比較的おとなしい感じで歌っている。それでもドラマー出身の人らしく、グルーヴ感に溢れた歌唱になっているのが面白い。間奏においる佐橋のギターソロ(前半はスライドギター)が聴きもの。 他の曲について。「夏のまぼろし」(作詞作曲 鈴木祥子 編曲 佐橋佳幸、藤井丈史)6曲目は、Sir Nikolai Kadokovという人(インターネットに情報がないので変名っぽい名前)のピアノのみの伴奏による曲で、若くして亡くなった人の事を思いながら、これからの人生を音楽で生きていこうという決意を歌う、本作の中では異色の存在。なお本曲は、1995年に矢野顕子が弾き語りアルバム「Piano Nightly」でカバーしている。 大貫さんの感性豊かな歌詞にキリッとした感じの曲を付けて、颯爽と歌う鈴木がかっこいい。 [2024年9月作成] |
|
| 1991年 「New Moon」 (1990/6/21発売) 「Drawing」 (1992/2/26発売)の頃 | |
| 音楽物語 星の王子様 (1991) 東芝EMI | |
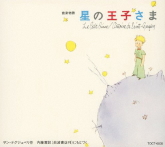 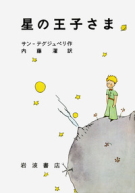 |
1. メインテーマ 星の王子様(Instrumental)」 [作曲 矢野顕子 編曲 大村雅朗、服部隆之] トラック1 2. 星の王子様(朗読)[作 Antoine de Saint-Exupery 和訳 内藤濯 音楽 服部隆之] トラック2〜20 3. メインテーマ 星の王子様 [作詞 大貫妙子 作曲 矢野顕子 編曲 大村雅朗、服部隆之] トラック21 薬師丸ひろ子: Vocal (3) 中島朋子: 朗読 (王子) (2) 森本レオ: 朗読 (わたし ほか) (2) 岸田今日子: 朗読(ばらの花) (2) 1991年2月20日発売 写真上: CD 音楽物語 星の王子様 東芝EMI 写真下: 本 星の王子様 岩波書店 3. Main Theme Hosi No Oji Sama (Main Theme Little Prince) [Words: Taeko Onuki, Music: Akiko Yano, Arr: Masaaki Omura, Takayuki Hattori] 21st Track by Hiroko Yakushimaru from the album "Ongaku Monogatari Hoshi No Oji Sama"(Music Story Little Prince) Febuary 20, 1991 |
| 「星の王子さま (原題 "La Petit Prince")」はフランスの飛行士・小説家アントワーヌ・サン=テグジュペリが書いた名作で、1943年に出版された(彼は翌1944年に従軍中の飛行機の行方不明で亡くなっている)。内藤濯による翻訳は1953年岩波書店から出版され、2005年に翻訳出版権が満了したため、以降数多くの翻訳が出ている。本CDは内藤濯による翻訳の朗読に服部隆之(服部良一の孫、服部克久の息子)が音楽をつけ、冒頭と末尾に本作のために作曲されたメインテーマを入れて「音楽物語」として制作した作品だ。朗読者は中島朋子、森本レオ、岸田今日子(2006年没)、メインテーマの作詞が大貫さん、作曲が矢野顕子という超豪華版。 CDをスタートさせると序曲として1. 「メインテーマ 星の王子様 (インストルメンタル)」が始まる、ピアノとオーケストラによる演奏で 1分11秒経って「わたし」役の森本レオの朗読が始まり、演奏はそのバックでフェイドアウトする。朗読内容を内藤濯訳の原本と比較すると、朗読には小説が長過ぎるため、作品の在り方と進行に影響を与えない部分をカットしていることがわかった。飛行機が砂漠に墜落するプロットは、サン=テグジュペリの実際の経験に基づいて書かれたものとのこと。第2章で中島朋子の王子さまが登場し、ヒツジの絵を巡る会話となる。第3章の最後でオケによる音楽が入り、第4-6章(バオバブの木)はカット。第7章は花に関する会話。ここでピアノによる音楽が入り、第8-9章では王子の星で岸田今日子のバラの花が登場し、王子との会話。そこでは森本は語り手の役。ここでオケが入る。 第10章から自分の星を出た王子の他の星での話で、まず王さま、第11章はうぬぼれ男、時折短いオケが入り第12章は呑み助、第13章は実業家、第14章は点燈夫、第15章は地理学者で、各人物(森本)と王子との会話。ここでテーマのメロディーを含むオケが入り、第16章で王子は地球にやってくる。第17章はヘビ、第18章(花)-19章(こだま)はカット。第20章はバラの花、第21章はキツネとの会話。ここでキツネが秘密と称して「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ、肝心なことは、目に見えないんだよ」という有名な語句を話す。オケ入って第22章(スイッチマン)-23章(あきんど)はカット。第24-25章はわたしと王子が井戸を探す話。第26章は王子が自分の星へ帰ってゆく話。ハープによる音楽が挿入される。飛行機の故障が直る示唆があるが、わたしがその後どうなったかは書かれていない。第27章は結びで、オケをバックに助かった6年後のわたしの想いが語られる。 朗読に長けた3人はベスト・セレクション。約73分のうち95%は朗読で、音楽の比重は少ない。この時間からメインテーマを含めてCD一枚の収録時間ぎりぎりに収めたことがわかる・ 最後に薬師丸ひろ子による 3.「メインテーマ 星の王子様」が流れる。同年少し後に発売された彼女のアルバム「Primavera」に収められた同曲と別ミックスで、アレンジが若干、歌詞がかなり異なる。その違いは「Primavera」で話そう。また作曲者の矢野顕子は、1995年のアルバム「Piano Nightly」において本アルバムの歌詞でセルフカバーしている。 素晴らしい曲なので願わくば大貫さんもセルフカバーしてほしいな〜 薬師丸ひろ子による「星の王子さま」オリジナル・バージョンは、他のベスト盤やボックスセットに収録されておらず、配信もないため聴けるのは本作品だけとなっている。 [2024年9月作成] |
|
| NHKみんなのうた 大全集2 Various Artists (1991) キング | |
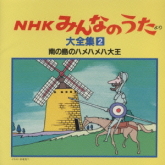 |
1. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子] 7曲目 新倉芳美: Vocal 1991年3月5日 キングより発売 1. Metropolitan Museum [Words & Music: Taeko Onuki] 7th song by Yoshimi Niikura (in various artists) from the album "NHK Minna No Uta Daizenshu 2" (Anthology 2 For The Songs For Everybody) March 5, 1991 |
| 大貫さんの「メトロポリタン美術館」は 1984年4月〜5月にNHKテレビ「みんなのうた」で初回放送された。清水信之編曲による大貫さんの録音は、1984年5月21日発売のシングル「宇宙みつけた」のB面としてディアハート(RVC)
レーベルから発売され、1986年3月21日発売のアルバム「Comin' Soon」に収められた。「みんなのうた」の中でも特に人気がある曲で、映像はその後も現在に至るまで頻繁に再放送され、各レコード会社が発売した「みんなのうた」曲集にも収められている。その際契約の関係で大貫さんのオリジナルを使えない場合、別の歌い手により録音したものを使うのが普通で、そのため本曲は他のアーティストによるカバーに加えてこの手の別録音が多く存在することとなった。本件はその中のひとつで、キング・レコードが制作したものだ。 新倉芳美 (2017年没)は、新倉よしみの名前でシングル盤2枚(1枚目「八色の幸福/狭山慕情」1980は歌謡曲、2枚目「白いページの中に/さよならへつづくハイウェイ」1981はニューミュージック)を出した後、子供向けの歌やアニメソングを多く歌ったシンガーで、中森明菜の専属仮歌シンガーとしても知られている。本曲はシンセサイザー、打ち込みが目立つ伴奏で、くせのない彼女の声はとても聞きやすい。なお編曲者は不明。 [2024年9月作成] |
|
| Primavera 薬師丸ひろ子 (1991) 東芝EMI | |
 |
1. 星の王子さま (Mattina Version) [作詞 大貫妙子 作曲 矢野顕子 編曲 大村雅朗] 7曲目 2. Destiny [作詞 大貫妙子 作曲 坂本龍一 編曲 坂本龍一、成田忍] 9曲目 大村雅朗: Keyboards (1) 鶴来正基: Keyboards (2) 松原正樹: Electric Guitar (1) 成田忍: Guitar (2) 吉川忠英: Acoustic Guitar (1) 荻原基文: Bass 浜口茂外也: Whistle (1) 中村哲: Sax (1) 迫田到、石川鉄男: Synthesizer Operator (1) 木本ヤスオ: Synthesizer Operator (2) 綿内克幸、前田康美: Chorus (2) 1991年3月13日発売 1. Hoshi No Oji Sama (Mattina Version) (Little Prince Morning Version) [Words: Taeko Onuki, Music: Akiko Yano, Arr: Masaaki Omura] 7th Track 2. Destiny [Words: Taeko Onuki, Music: Ryuichi Sakamoto, Arr: Ryuichi Sakamoto, Shinobu Narita] 9th Track by Hiroko Yakushimaru from the album "Primavera" (Spring) March 13, 1991 |
薬師丸ひろ子8枚目のアルバムで、「Primavera」はイタリア語で「春」の意味。 大貫さん作詞、矢野顕子作曲の1.「星の王子さま」は、約1ヵ月前に発売された「音楽物語 星の王子さま」にも収録されているが、本作では「Mattina Version」という副題(「Mattira」はイタリア語で「朝」の意味)がついていて、以下のとおりアレンジが異なっている。 A = 音楽物語 星の王子さま、B= Primavera (Mattina Version) ① Aはシンセサイザーのイントロから、Bは朝を思わせる小鳥の声とシンセサイザーのみ ② Aはファースト・ヴァースの第2節が「王さまも、うぬぼれも、実業屋も」に対し、Bは「大人たちは ひらけない 宝の箱」に歌詞が変えられている ③ オーケストラのアレンジが異なる。 Aのほうがオケの動きが多く、目立っている。 ④ Aはファースト・コーラスの後はオーケストラのみ、Bは中村哲のソプラノ・サックスが入る ⑤ Aはセカンド・ヴァースの第2節が「呑み助も、点燈夫も、地理学者も」に対し、Bは「いつの日か 消えてゆく ひとつの命」に歌詞が変えられている ⑥ Aはセカンド・コーラスの後はオーケストラの演奏のみでフェイドアウト、Bは中村哲のソプラノ・サックスソロが入る。結果Aの3分15秒に対し、Bは3分44秒と演奏時間がその分長くなっている。 ①小鳥の囀りを入れて朝の雰囲気を出したのは、アルバムの構成(特に次の曲「私の町は、今朝」)に合わせるためと思われる。②⑤歌詞を変えたのは、Aが原作の登場人物を歌うことで、原作との一体化を図っているのに対し、Bは薬師丸のソロアルバム用に普遍的な内容の歌詞に変えたものだろう。③オーケストラのアレンジが異なる点については、Aの編曲者に服部隆之が入っていたが、Bでは大村雅朗のみになっていることから、大村がオケのアレンジをしたものと推測する。なおABともレコード会社が東芝EMIであることから、キーボード、シンセサイザー、ベース等のバッキング・トラックは同じものを使用しているものと断定してよいだろう。 2.「Destiny」はいかにも坂本龍一らしいメロディーの曲。歌詞・メロディー・歌唱いずれも聴けば聴くほど味わいが深くなる佳曲。ギターでアレンジャーとして名を連ねている成田忍は、フュージョン、テクノポップのバンドを経験して、ギタリスト、作曲・編曲家、プロデューサーになった人。キーボードの鶴来正基は、沢田研二やThe Boomなどやアニメソングの編曲を手掛けているが、主にライブで本領を発揮する人らしい。ベースの荻原基文はセッション・ミュージシャンで、板倉文、清水一登、斉藤ネコ、青山純等による音楽ユニット、キリング・タイムのメンバーだった。バックコーラスの綿内克幸はシンガー・アンド・ソングライターで成田忍とバンドを組んでいたことがある。前田康美はサザンオールスターズのサポートで有名な人だ。 他の曲では「愛は勝つ」のKAN(1962-2023)が作曲した「私の町は、今朝」(作詞 風総堂美起 編曲 清水信之)8曲目と、シングルとして1月30日に先行発売されてNTT"パジャマ・コール"CMイメージ・ソングとなりヒットした「風に乗って」(作詞作曲 上田知華 編曲 清水信之)10曲目が素晴らしい。そのため、7曲目から最後の10曲目までの流れは最高! それにしても薬師丸の歌声は何故こんなに心に響くのだろう。27歳になって天性の表現力に益々磨きがかかったようだ。 大貫さんが作詞した2曲はいずれも素晴らしい出来です。 [2025年9月作成] |
|
| De eaya 中山美穂 (1991) King | |
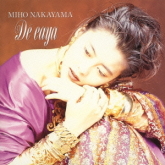 |
1. メロディー [作詞作曲 大貫妙子 編曲 林有三, ATOM] 1曲目 2. Crazy Moon [作詞作曲 大貫妙子 編曲 ATOM] 3曲目 3. ひとりごと [作詞 中山美穂 作曲 大貫妙子 編曲 ATOM] 10曲目 中山美穂: Vocal Atom: Keyboards, Synthesizer, Programming 林有三:Keyboards (1) 吉川忠英:Guitar (1) 斉藤毅 Group: Strings (1) 1991年3月15日発売 1. Melody [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Yuzo Hayashi, ATOM] 1st Track 2. Crazy Moon [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: ATOM] 3rd Track 3. Hitorigoto (Monologue) [Words: Miho Nakayama, Music: Taeko Onuki, Arr: ATOM] 10th Track by Miho Nakayama from the album "De eaya" March 15, 1991 |
| 中山美穂(1970-2024) 21歳の時13枚目のアルバム。タイトルは「でいいや」という日本語をスペイン語風にもじった造語だ。無国籍でダンサブルな曲が大半を占めていて、ATOMという井上ヨシマサ(キーボード、シンセサイザー)と久保幹(プログラミング)の二人からなるユニットが編曲と打ち込みを含む演奏の大部分を担当している。 冒頭の曲1.「メロディー」は、本アルバムの中で歌詞・メロディー共に大貫さんらしさが出た曲で、編曲・キーボードに林有三、ギターに吉川忠英、ストリングスに斉藤毅(ネコ)のグループが加わり、アコースティックなサウンドに仕上げられている。2.「Crazy Moon」はマンボ風のアレンジによるダンス・チューンで、大貫さんの曲作りも軽めな感じ。バックで聞こえるパーカッションやブラス・セクションも全部シンセ演奏と打ち込みによるもの。全11曲中7曲につき中山本人が詩を書いているが、ダンス曲のための歌詞を書くということが彼女にとって最適だったかどうか微妙な感じがする。「Mana」(作詞 上田知華 作曲 井上ヨシマサ 編曲 ATOM)2曲目など、ボ・ディドリー・リズムを使用するなどの聴きごたえがある曲はあるものの、この手の音楽にいまひとつ食指が動かない私の個人的な好みかもしれないが....。 そのなかで、彼女が書いた詞に大貫さんが曲をつけた3.「ひとりごと」はスローな曲で、彼女の本心をはっきり感じることができる作品だ。そして大貫さんのメロディーが歌詞にぴったり寄り添っていて、両者相まって素晴らしい曲に仕上がった。それを受けたドリーミーなアレンジ、お風呂場で歌っているかのようなヴォイス処理もぴったり嵌っている。 他の曲に比べて、大貫さん提供曲が群を抜いており、特に3.「ひとりごと」は名曲といってもよいレベル。 [2024年9月作成] [2024年12月追記] 中山美穂氏は2024年12月お亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。 |
|
| 夢で逢えたら 森丘祥子 (1991) Warner Pioneer | |
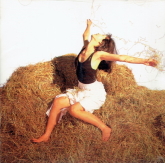 |
2. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子 編曲 小西康陽] 2曲目 森丘祥子: Vocal 小西康陽: Synthesizer, Arranger, Producer 中山努: Electric Piano 斉藤誠: Electric Guitar 野宮真貴: Background Vocal 1991年4月25日発売 1. Totsuzen No Okurimono (A Sudden Gift) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Yasuharu Konishi] 2nd track from the album "Yume De Aetara" (If We Meet In Dreams) by Shoko Morioka, April 25, 1991 |
森丘祥子(1967- 本名 柴田くに子、岐阜県出身)は 1984年雑誌ミスセブンティーンのラジマガ賞を受賞し、3人組アイドルグループ、セブンティーンクラブのメンバーとして本名でデビューした。ちなみに他の二人は工藤静香(後にソロ歌手として大成後、現木村拓哉夫人)と木村亜希(後の清原和博夫人→離婚)。同グループはシングル2枚とCM、バラエティー番組等に出演後1年で解散し、柴田は1990年に森丘祥子の芸名で歌手デビューしたが、シングル、アルバム各2枚を出した後に活動が途絶えた。 本作は2枚目のアルバムで、ピチカート・ファイブの小西康陽がプロデュースとアレンジを担当している。1984年結成のピチカート・ファイブは熱心なファンを獲得したが一般的な知名度は低い状態が続き、商業的成功を収めたのは1993年頃という状態だった。従って本アルバム制作時の小西はまだ売れていなかった時期になるが、ニューミュージック(当時はそう言われていて、現在はJ-Popとかシティ・ポップと呼ばれるようになった)の名曲カバーというマニアックな企画になっている。 彼らしいニューウェイブ調のアレンジの中で、2.「突然の贈りもの」は飛び抜けて過激だ。森丘は原曲通りのきれいなメロディーを素直に歌っているが、セカンドヴァースが終わるまで、伴奏のほとんどが打ち込みのドラムスとシンセベースのみで、ベース音もあるべきコード進行を無視したミニマムな音で決めている。その分ヴァースの終わりに入るシンセの音と野宮真貴のハミングがきらっとした光を放っている。そして間奏部分からエレキギターやキーボードが入りメロディックな演奏になってゆく。小西の偏執的な趣味性が遺憾なく発揮されたアレンジだ。ハミングの野宮真貴は当時ピチカート・ファイブの3代目ボーカリト、中山誠はオリジナル・ラブのメンバー、斉藤誠はサザン・オールスターズのサポートメンバーで、渋谷系というか青山学院派のミュージシャンが揃っている。 他の曲について (かっこはオリジナル・リリース) 1. 夢で逢えたら(Remix) [作詞作曲 大瀧詠一] (吉田美奈子 「Flapper」 1976) 2. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子] (大貫妙子 「Mignonne」1978) 3. 恋のブギウギ・トレイン [作詞 吉田美奈子 作曲 山下達郎] (アン・ルイス シングル 1979) 4. ムーンライト・サーファー [作詞作曲 Panta] (石川セリ 「気まぐれ」 1977) 5. 愛がなくちゃね [作詞 矢野顕子、ピーター・バラカン 作曲 矢野顕子] (矢野顕子「愛がなくちゃね」 1982) 6. ユー・メイ・ドリーム [作詞 柴山敏之、Chris Mosdell 作曲 鮎川誠、細野晴臣] (シーナ & ザ・ロケッツ「真空パック」1979) 7. ライディーン [作詞 小西康陽 作曲 高橋幸宏] (イエロー・マジック・オーケストラ「Solid State Survivor」 1979) 8. ソバカスのある少女 [作詞 松本隆 作曲 鈴木茂] (ティン・パン・アレー 「Caramel Mama」 1975) 9. ブルー・ヴァレンタイン・デイ [作詞作曲 大瀧詠一] (大瀧詠一 「ナイアガラ・カレンダー」 1977) 10. トゥインクル・クリスマス [作詞作曲 EPO] (EPO 非売品シングル 1986) 11. 夢で逢えたら [作詞作曲 大瀧詠一] (吉田美奈子 「Flapper」 1976) 11.「夢で逢えたら」は大瀧詠一の大名曲。吉田美奈子が「自分の音楽でない」と抵抗したため、直後にシリア・ポールに歌わせた実質的セルフカバーを出し、その後の数多くのカバーがある。森丘のバージョンはキリン「ワインクラブ DANCE」のCMソングになった。1.は間奏部の語りのみを延々と繰り返すリミックス・バージョン。3.「恋のブギウギ・トレイン」はダイエー1980年のヴァレンタイン・キャンペーン CMソングで、山下達郎はライブアルバム「Joy-Tatsuro Yamashita Live」 1989でセルフカバーしている。7.「ライディーン」はYMOの傑作インスト曲に小西が歌詩を付けた珍品で、よりソリッドなリズムのアレンジが面白い。8.「ソバカスのある少女」は鈴木茂と南佳孝(ゲスト)が歌ったうロマンチックな歌だったが、私的には南佳孝が鈴木のバックで出した1977年のカバー・シングルのほうに愛着を覚える。10.「トゥインクル・クリスマス」はEPOが札幌マルサのキャンペーン配布用に制作した非売品シングルで、アレンジャーが当時メジャー・デビューして間もなかった小西康陽だったという縁がある曲。そういえば大貫さんは前年の1985年に同様の企画で「森のクリスマス」を録音していたね。なおEPOの録音は、「森のクリスマス」とともに 2012年MIDI制作のコンピレーション・アルバム「Winter Tales II」に収録された。 1970〜1980年代の名曲を題材に、小西が1990年代のグルーヴで焼き直すことで新たなサウンドを生み出している。この手のマニアックな音楽が好きな人向けのアルバムだ。特に「突然の贈りもの」は数多くのカバーがある名曲であるが、ここでのアレンジは最も特異かつ独創的なものになっている。 [2024年8月作成] |
|
| Miracle Love/あいたい気持ち 牧瀬里穂 (1991) Pony Canyon | |
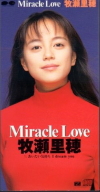 |
1. 会いたい気持ち I Dream Of You [作詞作曲 大貫妙子 編曲 中村哲] CDシングル2曲目 牧瀬里穂: Vocal 1991年10月30日発売 1. Aitai Kimochi I Dream Of You (I Want To Meet You I Dream Of You) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Satoshi Nakamura] CD Single 2nd Track, October 30, 1991 |
牧瀬里穂(1970- 福岡県出身)は、1989年12月山下達郎の「クリスマス・イブ」が流れるJR東海「クリスマス・エクスプレス」のCMで有名となり、1990年に出演した映画でトップスターへの仲間入りを果たした。そんな彼女が歌手に挑戦して最初に出したシングルが本作だ。メインは竹内まりや作詞作曲の「Miracle Love」(編曲 小林武史)で、本人が出演した三菱電機のビデオカメラ、郵便貯金のCMに採用され、売り上げ30万枚の大ヒットとなった。 大貫さんが書いた「会いたい気持ち」はそのカップリングにあたる。編曲の中村哲は、サックス、キーボード奏者、編曲家で、ホーン・スペクトラム、プリズムに参加した人。米国西海岸を思わせる爽やかなサウンドの曲だ。本曲は1993年9月に発売された彼女唯一のアルバム「PS. RIHO」には未収録で、2002年のベスト盤「My これ!クション 牧瀬里穂 Best」に収められた。なお彼女は1995年3月のシングル盤を最後に音楽活動を止め、女優業に専念している。 なお「Miracle Love」は、翌年に竹内が出したシングル「マンハッタン・キス」のカップリングとしてセルフカバーされた。こちらは夫君の山下達郎アレンジなので、牧瀬のバージョンとの聴き比べの面白さがある。 [2024年9月作成] |
|
| 1992年 「Drawing」 (1992/2/26発売)の頃 | |
| Super Folk Song 矢野顕子 (1992) Epic (Sony) | |
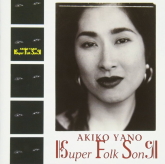 |
1. 横顔 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 矢野顕子] 4曲目 矢野顕子: Vocal, Piano 1992年6月1日発売 1. Yokogao (Face In Profile) [Music: Taeko Onuki, Arr: Akiko Yano] 4th Track by Akiko Yano from the album "Super Folk Song" June 1, 1992 |
| 文句なしの歴史的名盤。 矢野顕子(1955- 東京都生まれ、青森県育ち)は1976年「Japaese Girl」でデビュー後、コンサートの一部でピアノの弾き語りを演っていた。その模様は2枚目のライブアルバム「長月 神無月」1976のA面で伺うことができる。そして1982年からピアノが1台あれば何処へでも赴くという弾き語りライブ「出前コンサート」を始める。そして10年後の1992年満を持して制作したのが本作だ。録音にあたっては、スタジオではなく音響の良いコンサート・ホール(東京都千駄ヶ谷の津田ホールと長野県松本市のハーモニー・ホール)を借り切り、一切のテープ編集拒否にこだわって納得がゆくまで何度も録り直したという。その模様は同年公開された映画「Super Folk Song 〜ピアノが愛した女〜」(坂西伊作監督 その後VHS, DVDで発売)で観ることができる。弾き語りといっても、ジャズ、フォーク、ロックを跨いだ音楽性と比類なき演奏力・感性によって空前絶後のスタイルを確立し、彼女の琴線に触れた名曲をカバーするという離れ技をやってのけたのだ。 各曲毎に本人のコメントが付いていて、大貫さんの名曲1.「横顔」(アルバム「Mignonne」1978収録)は「世界有数のソングライターである大貫妙子は私の大切な友達でもあります。もっと歌いたい曲もあるのですが、早くうまく歌えるようになりたいと思います。そしたら又、聴いてきださいね」という彼女にしてはしおらしい内容。原曲とアーティストに対する尊敬の念がはっきり出ていて、歌が入る部分はピアノ演奏の独特なタイム感覚はあるものの比較的大人しいプレイだ。それに対して間奏とエンディングになってピアノのみになると、思い切りはっちゃけた感じに変貌するのが凄い。彼女はその後も本曲を演奏し続け、2007年発売のDVD「音楽のちから 吉野金次の復帰を願うコンサート」で大貫さんと共演、さらに2018年のアルバム「ふたりぼっちでゆこう」で二人のデュエットによる正式録音が実現した。 他の曲について。「Super Folk Song」(作詞 糸井重里 作曲 矢野顕子 編曲はすべて矢野顕子なので以下記載省略)1曲目は、糸井のアルバム「ペンギニズム」1980のセルフカバー。ナンセンンスながらもイメージが無限大に広がってゆく歌詞を縦横無尽に歌いこなしている。「大寒町」2曲目はムーンライダーズのベーシスト鈴木博文が書いた曲を素直に歌っていて、あがた森魚の名盤「噫無情(レ・ミゼラブル)」1974がオリジナル。「Someday」(作詞作曲 佐野元春)3曲目は1981年佐野4枚目のシングルが初出。ここでは原曲のメロディーとリズムを大幅に崩して自由気儘に歌っている。「夏が終わる」(作詞 谷川俊太郎 作曲 小室等)5曲目は、デビュー前に小室のアルバム「いま生きているということ」1976の録音に参加し、同曲でピアノを弾いたのが原点。草の名前が並んだ歌詞の中にカミソリのような鋭い言葉が差し込まれる恐ろしい曲だ。「How Can I Be Sure」(作詞作曲 Felix Cavaliere, Eddie Brigati) 6曲目はアメリカのグループ、ヤング・ラスカルズ1967年の曲で全米4位のヒットを記録。いかにも山下達郎が好きそうなメロディーだね。 「More And More Amor」(作詞作曲 Sol Lake) 7曲目は、ジャズ・ギタリストのウェス・モンゴメリーが1966年に出したライトな感じのアルバム「California Dreamin'」収録のインストルメンタルのカバーで、矢野はピアノを弾きながらメロディーをハミングしていて、若い頃聴いたジャズへの愛着が伺える。「スプリンクラー」(作詞作曲 山下達郎)8曲目は山下11枚目のシングル 1983から。「おおパリ」(作詞 イッセー尾形 作曲 矢野顕子)9曲目はイッセーの劇の幕間に使用された曲を歌ったもの。「それだけでうれしい」(作詞 宮沢和史 作曲 矢野顕子)10曲目は1992年5月2日にThe Boomが矢野とのコラボとして発表した曲をソロで取り上げたもの。「塀の上で」(作詞作曲 鈴木慶一)11曲目は、はちみつぱいのアルバム「センチメンタル通り」1973に収められていた名作。「中央線」(作詞作曲 宮沢和史)12曲目はThe Boomのアルバム「Japaneska」から。矢野はコメントで「中央線沿線に生まれ、長い時間そこで過ごし、そしてまた遠くの地に移っていった私のようなものにとって、宮沢さんがこの曲を書いてくれたことは大きなプレゼントでした」と述べている。最後の「Prayer」(作詞 矢野顕子 作曲 Pat Metheny) 13曲目は親交のあるギタリスト、パット・メセニーが矢野のために書いた曲に歌詞をつけたもので、歌詞・曲ともに素晴らしい作品。パットは16年後の2008年に制作されたライブ・アルバム「Tokyo Day Trip」で本曲をインストでセルフカバーしたが、これも最高の出来だ。 ということで全曲を紹介したが、そうする価値がある捨て曲がないアルバムなのだ。以前に矢野が大貫さんの曲を歌った「いらないもん」1981は実験的な曲だったため、本アルバムの「横顔」が本格的に大貫作品を歌った最初の曲ということになる。 [2024年10月作成] |
|
| Garden 原田知世 (1992) For Life | |
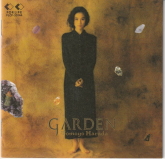 |
1. Walking [作詞 大貫妙子 作曲編曲 中西俊博] 4曲目 原田知世: Vocal, Co-Producer 中西俊博: Violin 桑野ストリングス: Strings Unknown: Piano, Guitar, Bass, Drums 鈴木慶一: Producer 1992年8月21日発売 1. Walking [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Toshihiro Nakanishi] 4th Track by Tomoyo Harada from the album "Garden" August 21, 1992 |
| 原田知世10枚目のアルバムは鈴木慶一プロデュース(原田はコ・プロデュース)で、全11曲中彼女の自作は2曲で、鈴木慶一は作詞作曲が2曲、作詞のみが1曲、作曲のみが3曲。編曲は鈴木と原田が2曲(彼女の自作曲)、鈴木が5曲という内訳。当時の鈴木はムーンライダースの新作のための曲作りとかち合ったため、一部の曲につき親しいアーティストに作曲作詞や編曲を依頼したそうで、結果的にそれが作品の多様性に貢献している ジャケットに掲載された鈴木の言葉によると、鈴木は制作にあたり彼女の事を徹底的に知ることから始めたという。鈴木と原田の共同作業(鈴木は「庭いじり」と呼んでいて、それがアルバムタイトルになっている)は、曲作りとアレンジにおいては各自がコンピューターでサンプルを作って持ち寄り、音の良し悪しにつき話し合いながら決めていったそうだ。結果として鈴木好みの音楽に仕上がったように聞こえるが、同時に原田の感性が強く反映された作品となった。シンセサイザーと打ち込みを中心としたサウンドで、少々奇をてらった感はあるが、1990年代の新しい波のなかで歌詞・メロディー・演奏すべてにおいてクリエイティブであることは確か。いままでのお仕着せの企画を歌うアイドル歌手的な立ち位置を抜け出して、主体性を持って自ら創造に携わるアーティストに変貌を遂げてゆくキャリア転換期の作品といえよう。 大貫さんが作詞しバイオリニストの中西俊博が作曲・編曲した1.「Walking」は、その中でも息抜きとなるアコースティックな音つくりになっていて、スローなリズムを奏でるリズムセクションとストリングスをバックに中西のバイオリン・ソロが甘く響くスタンダード・ジャズ風に仕上がっている。初期はか細く不安定だった彼女の声は、この頃になると進化を遂げて厚みのあるノンビブラートの個性を確立している。各曲の歌詞の下にはクレジットが表示されているが、本曲については中西とストリングスのみの記載でリズムセクションのミュージシャン達の名前はなかった。 また本作の最後には1985年の7枚目のシングル「早春物語」(作詞 康珍化 作曲 中崎英也)の再録音が収められていて、これも中西編曲によるストリングス中心の音作りとなっており、6年間における彼女の音楽的・人間的成長を目の当たりにすることができる。 「Walking」はニューウェイブ調のアルバムのなかにあって異色のクラシカルな曲で、大貫さんらしい持ち味がしっかり生かされている。 [2024年9月作成] |
|
| ツレちゃんのゆううつ イメージ・アルバム (1992) Pony Canyon | |
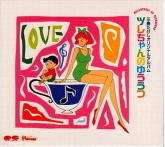 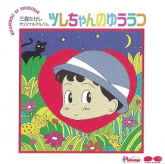 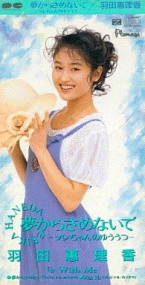 |
1. 夢からさめないで〜ツレちゃんのゆううつ [作詞作曲 大貫妙子 編曲 有賀啓雄] 1曲目 2. 色彩都市 [作曲 大貫妙子 編曲 vivre ensemble] (Instrumental) 8曲目 3. 横顔 [作曲 大貫妙子 編曲 vivre ensemble] (Instrumental) 9曲目 羽田恵理香: Vocal (1) かしぶち哲郎: Keyboards, Synthesizer, Drums 羽毛田丈史: Keyboards, Synthesizer, Piano 浜田均: Vibraphone (3) 武川雅寛: Violin (3) 千代正行: Guitar 渡辺等: Wood Bass (3), Cello (2) 注: vivre ensemble = かしぶち哲郎、羽毛田丈史 写真上: 紙ボックス 表紙 1992年9月18日発売 写真中: CDジャケット 表紙 写真下: CDシングル盤 表紙 1992年7月17日発売 1. Yume Kara Samenaide〜Tsurechan No Yuuutsu (Don't Wake Me Up From My Dreams〜Melancholy Of Tsurechan) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Nobuo Ariga] 1st Track, Sung by Erika Haneda 2. Shikisai Toshi (Colored City) [Music: Taeko Onuki, Arr: vivre ensemble] 8th Track, Instrumental 3. Yokogao (Face In Profile) [Music: Taeko Onuki, Arr: vivre ensemble] 9th Track, Instrumenta from the album "Tsurechan No Yuuutsu Image Album"(Melancholy Of Tsurechan Image Album) September 18, 1992 Note: vivre ensemble = Tesuro Kashibuchi, Takefumi Hakeda |
| 三島たけし作の漫画「ツレちゃんのゆううつ」は集英社「ヤングジャンプ」に1988年から1993年まで連載され、単行本は全13巻発売された。小学一年生の夢野ツレオは母親と二人暮らし。飛んでる彼女と恋人のような会話をし、マセた女の子の友達に振り回されて、時に憂鬱になりながらも楽しく暮らしているという筋で、動きのない静止画像のような画面や母親の長い足のデフォルメなど、ポップなイラストレーション風の描写が特色の漫画だ。 1992年9月1日刊行の単行本第8巻に合わせて発売されたのが本CDで、漫画自体はアニメ化されていないため、原作のイメージに合わせて制作されたアルバムになっている。紙ボックスとCDジャケットの装丁センスの良いデザインに三島が書いたイラストが満載で、見ているだけでも楽しい。音楽担当は、ムーンライダースのかしぶち哲郎(1950-2013) と作曲・編曲・プロデュースを数多く手掛けた羽毛田丈史(1960- ) の二人からなるユニット、vivre ensemble (「共に生きる」、「一緒に住む」、「一緒に行く」という意味)だ。そして歌い手は、アイドル・グループCoCoのメンバー羽田恵理香と、子供向け、アニメソングを多く手掛けたセッション・シンガーの新居昭乃(1988年に大貫さんの「メトロポリタン美術館」を歌った人)。一編の漫画のためのイメージアルバムといっても手抜きは一切なく、わくわくするような新鮮なアイデアがいっぱい詰め込まれていて、原作が持つペカペカしたふわふわ感が見事に表現されている。制作者達の当該漫画に対する愛着の成せる技だろう。 大貫さんが作詞・作曲した「夢からさめないで〜ツレちゃんのゆううつ」は主題歌に相当する位置づけで、軽くポップなテクノサウンドをバックに羽田が歌う。音程面で若干不安定な歌唱なんだけど、それがむしろ歌の雰囲気にあっている感じ。編曲は作曲家、プロデューサーの有賀啓雄(2023没)。なお本曲は7月17日に羽田恵理香名義のシングル盤で先行発売された。2.「色彩都市」、3.「横顔」は大貫さんの代表曲のインスト・アレンジで、アルバムに仕立てるための曲数不足を補うために製作された感があるが、単なる埋め合わせでなく、むしろvibre ensembreの二人が嬉々として取り組んだような形跡がある。前者はリズムが強調されて、曲の持つカラフルなイメージがさらに増幅されていて、特にラストのサンバっぽくなるあたりは最高!後者は一転しっとりしたジャズのアレンジで、バイオリン(ムーンライダースの武川雅寛)、ヴァイヴ、ピアノがソロを取っている。特にバイオリンの切ない響きが愛おしい。なお原作者と大貫さんの関係については不明だが、ツレちゃんのお友達で細野妙子という女の子がいて、そのキャラが何となく大貫さんに通じるものがあり、彼女に対する作者の思いが込められているのは明らかだ。それにしてもこの苗字は確信犯だね? その他の曲も捨て難い。羽田が歌う「With Me」(作曲作詞 Bob Crewe、Sandy Lizar, Denny Randell 日本語詞 及川眠子 編曲 有賀啓雄)3曲目は、作者のクレジットから調べてみたら、あのフォーシーズンズやフランキー・ヴァリの作曲(「Can't Take My Eyes Off You」など)やプロデュースをしたボブ・クルーで、曲は彼が制作したガールズ・グループ、ザ・ラグ・ドールズの「Dusty」1965 全米55位が原曲だった。女性版フォーシーズンズにビーチボーイズの香りを付けたサウンドの原曲も素晴らしいが、オリジナルに敬意を表したアレンジに日本語詞をつけて、羽田の可愛い声を載せた本作のプロダクションも最高。なお日本語歌詞を書いた及川眠子は、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のオープニング曲「残酷な天使のテーゼ」1995の歌詞を書いた人だ。なお本曲は上述のシングル盤「夢からさめないで〜ツレちゃんのゆううつ」のカップリングとして収録された。「星のHeartache」(作詞 及川眠子 作曲 かしぶち哲郎 編曲 vibre ensembre)6曲目は、羽田が歌うキュートなヨーロピアン・テクノポップ。なおこの曲については、テレビ番組などでの歌唱で使われた全く異なるアレンジがある。 新居昭乃の歌は3曲。「Nocturne」(作詞 森由里子 作曲 羽毛田丈史 編曲 vibre ensembre)4曲目は素敵なボサノヴァで、フランス語を散りばめた歌詞と囁くようなボーカルがコケティッシュ。「月に祈りを」(作詞 及川眠子 作曲 かしぶち哲郎 編曲 vibre ensembre)7曲目はかしぶちのカラーが良く出た作品だ。「ツレちゃんのゆううつ」(作詞 三島たけし 作曲 新居昭乃 編曲 vibre ensembre)10曲目は、作者が書いた歌詞に歌手の新居が作曲したドリーミィーな作品。新居は他に面白いインスト曲「きょうは 晴れ のち 曇り ときどき 雨 〜Morning Song〜」(編曲 vibre ensembre)2曲目の作曲も担当している。ちなみに「Nocturne」と「ツレちゃんのゆううつ」の2曲は、ずっと後の2019年に発売された新居のコンピレーション・アルバム「Another Planet」に収められている。 三島たけしは、その後1998年「少年ガンガン」に「MD五エ門」という漫画を発表したが不評だったようで、単行本1冊のみで終わってしまい、その後は作品発表の記録がない。 原作の漫画と本作の音楽ともに、今ではすっかり忘れ去られてしまったが、大貫さん以外の作品も含め、そのまま埋もれさせるには誠に勿体ないファンタスティックな作品。 [2024年9月作成] |
|
| 秋天的故事 陳艾玲 (チェン・アイリン) (1992) Wind Music (台湾) | |
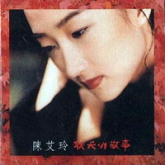 |
1. 我的心是一條舟 (Okabango) [作詞作曲 大貫妙子 中国語詞 葉寒輝 編曲 王豫民] 7曲目 陳艾玲(チェン・アイリン): Vocal 王豫民: Keyboards, Programming 徐徳昌: Drums Programming 倪方來: Guitar 李寶鐗、黄卓穎、黄國倫、黄秀偵: Back Vocal 1992年発売 1. My Heart Is Ship (Okabango) [Words: Yeh Han-hui, Music: Taeko Onuki, Arr: Wang Yu-min] 7th track by Chen Ai-ling from the album "Autumn Story" on 1992 |
| 1992年2月発売の大貫さんのアルバム「Drawing」に入っていた「Okavango」は、広大なアフリカの自然を感じさせるゆったりしたメロディー、サウンドと歌詞が印象的な歌だった。それを同じ年にカバーしたのが台湾の歌手陳艾玲(チェン・アイリン)だ。 1964年台北市生まれの彼女(本名 陳愛玲)は、当初は林雨如という女性と胡麻龍眼というグループ(ゴマは目が小さい陳艾玲、リュウガンは目の大きい林雨如のこと)を組んでアルバムを出したが、1989年二人は交通事故に遭い林雨如が亡くなったため、陳艾玲はソロ歌手として活動を続けたが、1990代後半から表舞台から身を引いて、プロデューサーなどの裏方として活躍するようになった。本作はそんな彼女の代表作で、タイトルは日本語で「秋物語」という意味。 1.「我的心是一條船」(「私の心は船」という意味)は、トーチソング(悲しく感傷的なラブソング)がほとんどを占めるアルバムのなかで、息抜き的な存在。歌詞の和訳は以下のとおり(お断り Google翻訳使用のため不正確な部分があると思います)。 私の心は船 自由で束縛なくさまよう 哀しみから解放され ただ歌いたい 私の心は船 流れに身を任せ 夢を拾い集める 純粋な心は 本当の気持ちを語ることが好き 優しく 偽善も偽りもない いつか 風が呼ぶとき 私は旅に出る 春 夏 秋 冬を渡り 谷や陽だまりをさまよう それでも求める方向は見つからない 停泊地を失ってしまったのだろうか なぜ馴染みの船着き場がないのだろう 船を泊められるような 私はさまよい さまよう さまよい さまよいたい 私の心はただ 安全な場所を探している 静かに休めるような 安全な場所を見つけたいだけ 少しだけ心が疲れている もう悲しみを感じたくない 私の心は船 自由で束縛なくさまよう いつになったら漂流をやめるのだろう いつになったら愛の家を見つけるのだろう いつになったら漂流をやめるのだろう いつになったら愛の故郷を見つけるのだろう いつになったら漂流をやめるのだろう さまよい さまよい続ける 愛の束縛から解放された心を「漂う船」に例えていて、悲しみよりも、さばさばした解放感が感じられる。イントロで聞こえる赤んぼの声、中ごろの鳥の囀り、そしてラストの本人による「クスッ」という微笑みの声などが入り、リラックスしてのびのびと歌っている。アレンジは原曲の小林武史のものに近く、アフリカ風のバックコーラスには不思議な空気が漂っている。歌詞の内容は大貫さんのオリジナルと全く異なるけど、それなりにとてもいい感じだ。 独自内容の中国語歌詞による、自由な雰囲気の「Okabango」が楽しめる。 [2025年9月作成] |
|
| Blue 劉文娟 (ラウ・マンクン) (1992) Rock-In (香港) | |
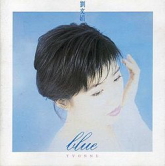 |
1. 生日的願望 (Retrospective Version) [作詞 夢劇院 作曲 大貫妙子 編曲 麥皓輪、李敏] A面3曲目 広東語歌詞による「黒のクレール」 劉文娟(Yvonne Lau): Vocal 1992年発売 1. Birthday Wishes (Retrospectove Version) [Words Paradox, Music Taeko Onuki] A-3 Cantonese Version of 「Kuro No Claire」 (Claire In Black) by Lau Man Kuen (Yvonne Lau) from the album "Blue" on 1992 |
| 李敏 (Li Min リ・ミン 1966- )と劉文娟 (Yvonne Lau Man Kuen ラウ・マンクン 1967- )による夢劇院(英語名
Dream Theater)は5枚のアルバムを出した後に解散した。李敏は香港に留まって作詞・作曲家となり、劉文娟はソロ歌手で活動をしばらく続けた後にカナダに移住してテレビ司会者になった。本作は劉文娟が香港で出した2枚目のアルバムになる。 そこには夢劇院のアルバム「Paradox」1988に収められていた大貫さんの「黒のクレール」の広東語詞版 「生日的願望」の再録音が「Retrospetive Version (回顧雇的バージョン)」として収められた。ヴォーカルはどちらも同じような感じであるが、伴奏は本アルバムのほうがすっきりした感じになっている(曲についての説明は1988年夢劇院の「生日的願望」を参照ください)。 2024年のCD再発にあたり、インターネットで入手できた広東語歌詞は以下のとおり(注: 翻訳ソフトを使用しているので、一部不正確な可能性があることをご了承ください)。 タンポポが風に散る 過ぎ行く年月のように 一瞬で去り二度と戻らない 古いアルバムを見て 何故母親はため息をつくのか 子ども時代を大切にしなければ すべて頭の中にある 大人になるという誘惑には勝てない 愛は新しい考えを生み出すから 笑い声が消え去り 無邪気さと美しさがなくなるのが怖い この日 あなたの幸せな人生を祈る 晴れでも雨でも向こう側に渡れるように キャンドルの明かりに目をとめて 真の善と美を求めて すべてが私を取り囲む 私は本当に貪欲だ 他に日本の曲のカバーが2曲ある。「浮光掠影」(作詞 劉文娟 作曲 S.E.N.S. 編曲 麥皓輪)2曲目で、インストメンタルグループS.E.N.S.の「Happy Arabia」1988 (NHK特集「海のシルクロード」で使用されたインスト曲でアルバム「Masaka Tea Waltz」収録)がオリジナル。もうひとつは、「雪夜」(作詞 劉文娟 作曲 中島みゆき 編曲 麥皓輪)5曲目で、中島みゆきの「サッポロ Snowy」1991 (アルバム「歌でしか言えない」収録。後に北海道放送制作のTBS系ドラマ「たった一度の恋〜SAPPORO・1972」2007の主題歌になった)のカバー。 ということで、広東語歌詞による「生日的願望」は、同じ歌手によるふたつのバージョンがあるということ。 [2024年6月作成] |
|
| 1993年 「Shooting Star In The Sky」 (1993/9/22発売) の頃 | |
| Everlastig Love / Not Crazy To Me 中森明菜 (1993) MCA Victor | |
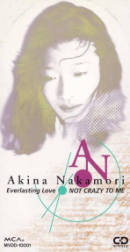 |
1. Everlasting Love [作詞 大貫妙子 作曲編曲 坂本龍一] シングルA面 中森明菜: Vocal 坂本龍一: Keyboards、Synthesizer Others: Unknown 1993年5月21日発売 1. Everlasting Love [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] Single A-Side by Akina Nakamori form the single May 21, 1993 |
中森明菜27枚目のシングルで、カップリングの「Not Crazy To Me」 [作詞 Nokko 作曲編曲 坂本龍一] と共にA面扱いで発売された。ワーナーを離れMCAヴィクターに移籍して初めてのリリースで、アルバム「Unbalance + Balance」と同時期に制作されたが、アルバムには「Not Crazy To Me」のみ収録された。 シンセサイザーが穏やかなリズムを刻む重厚なスローバラードで、中森の歌の上手さが際立っている。陰影のある大貫さんの歌詞と漂うような坂本のメロディーが素晴らしい。一方「Not Crazy To Me」はダンサブルな曲で、両曲合わせてオリコン10位のヒットを記録した。 なお本曲は、上記のアルバムが2002年「Unbalance + Balance +6」としてリイシューされた際にボーナス・トラックとして収録された。 [2024年10月作成] |
|
| Maracana Ana Caram (1993) Chesky (USA) | |
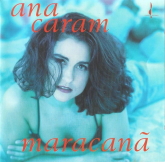 |
1. Bem Querer [作詞 大貫妙子 ポルトガル語詞 Nelson Motta 作曲 大貫妙子 編曲 Steve Sacks] 5曲目 原曲: 大貫妙子 「Chevalier Servante」1988 アルバム「Purissima」収録 Ana Caram: Vocal, Guitar Clifford Korman: Piano Al Hunt: Oboe Erik Friedlander: Cello David Finck: Bass Duduka Da Fonseca: Drums David Chesky, Nelson Motta: Producer 1993年8月5, 6, 9日 Queens, NYにて録音 1993年10月15日発売 1. Bem Querer [Words: Taeko Onuki, Portuguese Words: Nelson Motta, Music: Taeko Onuki, Arr: Steve Sacks] 5th track by Ana Caram form the album "Maracana" on October 15, 1993 (Original Song: "Chevalier Servante" by Taeko Onuki from the album "Purissima" 1988) |
| ブラジルの歌手、ギタリストのアナ・カラン(1958- アントニオ・カルロス・ジョビンの支持を受けて、ボサノヴァとアメリカ音楽をミックスした音楽を目指した人)がニューヨークのインディ・レーベルで制作したアルバムに大貫さんの曲のポルトガル語カバーが入っている。原曲はイタリア・ベニスの旅の体験を書いた「Chevalier
Servante」(アルバム「Purissima」1988収録)という曲で、「ゴンドラ」、「サンマルコ」(広場)、「仮面の下で笑うカサノヴァ」(仮面カーニバル)などの現地の情景が歌詞に散りばめられている。大貫さんのブラジル録音「Tchou」1995よりも前の録音であり、この曲が本アルバムに収められた経緯については不明。おそらく「Purissima」の曲の一部がニューヨークで録音されたこと(ただし「Chevalier
Servante」は日本録音)、そして出来上がったアルバムが現地で評判になったことが推測される。または坂本龍一と親交があったアート・リンゼイなどが絡んでいるかもしれない。 「Chevalier Servante」は、プロデューサーによりポルトガル語の歌詞が付けられ、ストリングス主体によるヨーロッパ風の音楽だった原曲に対し、ここではアナのギターにオーボエ、チェロ、ピアノが優しく寄り添い、ボサノヴァの微かな香りが付け加えられている。歌詞については、インターネットに資料が見つからなかったが、YouTubeの字幕機能とGoole翻訳により以下のとおり採取した(お断り: 前述の機能による聴き取り・翻訳なので、不正確な部分があると思います)。 ja me esqueci もう忘れた do amor que se foi 失った愛を sou novamente livre 私はまた自由になった a escolher 選ぶことができる quem vou querer 私は誰を欲しいか por quem voce queria あなたは誰が欲しいか chega de tanta historia tao triste 悲しい話はもうたくさん que ja passou da hora もう十分 tudo tem seu lugar seu momento すべてに場所がある seu tempo de viver 生きる時がきた eu sou meu sonho 私の夢 e meu desejo 私の望み minha vontade 私の意志 de bem querer 愛すること eu quero apenas beleza 求めるのは美 feita de poesia 詩で作られた e o que eu queria 私が欲しかったもの e tudo aqui そしてすべてが tao longe de mim 遠く離れて vive un sonho 夢に生きている novo longe daqui 遠く離れた新しい no fondo de mim 心の奥底で sonha uma vida nova 新しい人生を夢見る feita de fantasia e verdade 幻想と真実からなる feita de novidade 斬新なもの cheia de emocoes diferentes 様々な感情に満ちて dessas que eu ja vivi 今まで経験したことのない 以上の通り、大貫さんの歌詞とは全く異なる独自の内容で、別れと精神の解放を歌っている。故に「訳詩」ではなく「ポルトガル語詩」とした。 全体的にジャズ的な要素が強く、アメリカ的ということでアストラッド・ジルベルトに通じるところがあり、デビッド・チェスカイというアコースティックな音響に凝る個性の強いプロデューサーの影響下で作られた作品といえる。ちなみにアルバム・タイトルの「Maracana」は彼女の名前のアナグラム(文字の並び替え)とのこと。 異世界の「Chevalier Servante」がみれるよ! [2025年9月作成] |
|
| 1994年 「Shooting Star In The Blue Sky」 (1993/9/22発売) 「Tchou」 (1995/4/19発売)の頃 | |
| T'en Va Pas Creole (1994) For Life | |
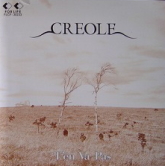 |
1. 彼と彼女のソネット (T'en Va Pas) [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 Taeko Onuki 編曲 Creole] 6曲目 キャット・ミキ : Vocal 駒沢裕城: Pedal Steel Guitar 桜井芳樹: Gut Guitar 角田敦: Producer 1994年2月18日発売 1. Kare To Kanojyo No Sonnet (T'en Va Pas) (His And Her Sonnet) (Don't Go) [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Creole] 6th Track by Creole from the album "T'en Va Pas" Febuary 18, 1994 |
| 1990年代の音楽は、目覚ましい技術進歩でシンセサイザーやコンピューター・プログラミングによる打ち込みなどが以前より遥かに安価かつ手軽にできるようになり、その恩恵をフルに生かした若い人たちが新しい音楽を作り始めるようになった。また演奏面でも以前のようなフルバンドを必要とせず、サウンドの全てまたは多くをプログラミングにより自分の手で生み出すことが可能になったのだ。それは以前よりもソリッドでメタリックな肌触りの音となったが、ダンス・ミュージック、DJの隆盛と相まって音楽界を席巻してゆく。そして1980年代との違いは、今までの古き良き伝統を頭ごなしに否定せず、むしろその良さを積極的に取り入れようとする度量の大きさにあり、その考えは2000年代以降も引き継がれて、現在の肥沃な音楽世界の土壌を生み出したといえる。 本作はそういう機運の黎明期の作品のひとつといえる。クリオールは、後にダンス・ミュージック、DJの分野で大成しJDDA (Japan Dance Music & DJ Association) の代表理事となるプロデューサー、作曲家、DJの角田敦を中心とした音楽ユニット。ユニット名の「クリオール」という言葉の元々の意味は、西インド諸島、中南米、インド洋西部、ルイジアナ州で生まれたスペイン・フランス人のことであるが、そこから派生して「異質なものの混淆から生まれて元とは異なる新しい存在になったもの」を意味する。ここではブラジル音楽を核として、様々な他の要素を取り入れることで新しい音楽を創り上げている。 大貫さんが日本語詞(元の詩と内容が全く異なるため「訳詞」ではない)を書いた1.「彼と彼女のソネット」は、フランスの歌手エルザが歌った1986年の「T'en Va Pas」がオリジナル(その名前が本アルバムのタイトルになっている)。日本語バージョンは1987年の原田知世が最初で、その少し後に大貫さんが「A Slice Of Life」でセルフカバーしている。いずれも原曲に近いリズミカルなフレンチ・ポップ風サウンドだったが、ここではガットギターによるアルペジオとペダル・スティールギターのみでリズムなしという大胆なアレンジが施されている。ギターの桜井芳樹は、クリオールのほとんどのセッションに参加したユニットの主要人物で、現在はロンサム・ストリングスというグループで活躍中。駒沢裕城はかつて荒井由美などティンパンアレイ系のセッションで大活躍した人だ。ここでの原曲をスローテンポに調理した試みは意外なほどうまくいっていると思う。ボサノバの歌唱に典型的な感情を押し殺したようなボーカルも良い。歌っているキャット・ミキはインターネットの資料が少なく、詳細不明(匿名シンガーかもしれない)であるが、フジテレビが制作した新感覚の子供番組「ウゴウゴ・ルーガ」1992 第1期のテーマソング「こどもなんだよ」(作詞 キャット・ミキ 作曲 近田春夫)というモノスゴイ曲を残している人。 他の曲について。アルバム帯のキャッチフレーズに「都市生活者のライフ・スタイルをスケッチするアンティミスト・ミュージック。シンプルでハートフルなアコースティック・サウンドが心地いいクレオールが贈るフェイク・ボサノバ」(「アンティミスト」とはフランスの印象派絵画の作風で、家族や友人の日常的な情景を親密な情感で描くことで「親密派」と訳される)とあるが、ガットギターやピアニカ前田によるピアニカなどの生楽器に対し、キーボードがシンセサイザー、打楽器は打ち込みであることがミソ。これも「クリオール」たる所以だろう。ブラジル風のリズムを打ち込みで処理することにより、新しい感覚のグルーヴが生まれていて、大貫さんの「Samba de Mar」1981(「Aventure」収録)を深化・発展させたようなサウンドなのだ。近田春夫作詞作曲による「Deja-vu」(編曲 クリオール)3曲目や、気怠い感じの「Holiday」(作詞作曲 森若香織 編曲 クリオール)4曲目、「海へ行こう」(作詞作曲 佐藤清喜 編曲 クリーオール、佐藤清喜)11曲目などが面白い。一方キャット・ミキによるアカペラ歌唱「みんな夢の中」(作詞作曲 浜口庫之助 高田恭子1969年のヒット曲)もある。 参加メンバーは、1970年代からずっと最先端で活躍してきた近田春夫と関係ある若い人達で、後に冨田ラボで一世を風靡する冨田恵一の名前もある。近田のような先人が打ち立てた音楽をベースとして新しいものを創造しようとする気概を感じるアルバム。ちなみに彼らは、同時期にほぼ同じメンバーで「Criola」というユニットのアルバムも出している。 大貫さんの「彼と彼女のソネット」のカバーの中で、最も大胆なバージョンのひとつ。 [2024年9月作成] |
|
| Weekend For Ladies Various Artists (Transistor Glamour ) (1994) 日本コロムビア | |
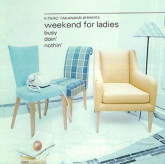 |
1. 恋人達の明日 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 細海魚] 8曲目 Artist Name: Transister Glomour 寺本りえ子: Vocal 細海魚: Keyboards, Synthesizer Programming 松田文: Ovation Guitar 木幡光邦: Trumpet, Piccolo Trumpet 高浪敬太郎: Producer 1994年6月1日発売 1. Koibito Tachi No Ashita (Lover's Tomorrow) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Sakana Hosomi] 8th Track by Transistor Glamour from the album "Weekend For Ladies" (Various Artists) on June 1, 1994 |
| 渋谷系のアーティスト高浪敬太郎が鈴木智文、細海魚と組んで制作した「働く女性の週末」をイメージしたコンピレーション・アルバム。 1994年ピチカート・ファイブを脱退した高浪は、ソロ活動と併行して自主インディー・レーベル Out Of Tune Records を立ち上げ、彼がプロデュースしたアルバムを発表した。本作は「K-Taro Takanami presents / performed by out of tune generation busy doin' nothin'」という副題がついていて、「多忙な働く女性たちがリラックスした週末を過ごすための音楽」というコンセプトで制作され、メジャーレーベルの日本コロムビアから発売された。全8曲のうち4曲はTM Networkへ歌詞を提供していた小室みつ子が作詞、高浪と彼の音楽仲間である鈴木と細海が作曲を担当し、残りの4曲は1970年代後半〜1980年代前半のニューミュージックから知る人ぞ知る名曲をカバーしている。そして彼らの演奏をバックに4人の女性ボーカリストが歌っている。 1.「恋人達の明日」は大貫さんのアルバム「Aventure」1981がオリジナル。Transistor Glamour という寺本りえ子と細海魚のユニットによる演奏で、彼らは同名義でOut Of Tune Recordsからアルバムを発表している。寺本はスピッツのアルバムやコンサートにも参加していたが、現在は音楽活動を止めて料理研究家として活躍している。細海魚は作曲・編曲家、プロデューサー、プレイヤーとして現在も元気に活動中。ここでは大胆なアレンジが施されていて、レゲエのリズムに乗せて、オリジナルのコード進行を無視した無色のエレクトロ・ポップから始まり、ヴァースの後半からコード進行が効いた色彩感あるサウンドに転換する対比が面白い。寺本のボーカルは、ゆったりしたサウンドのなかを漂うような感じで、7分間にわたりじっくり聴かせてくれるアルバム最後を飾るに相応しい出来。 他の曲について。「Just I Love」(作詞 小室みつ子 作曲編曲 鈴木智文)1曲目。サンバ・リズムの軽快な曲で、和泉恵のボーカルもいい感じであるが、彼女についはインターネット情報がない謎の歌手。「キッシング・フィッシュ」(作詞 佐藤奈々子 作曲 加藤和彦 編曲 高浪敬太郎)2曲目は、現在は写真家として活躍する佐藤奈々子1979年のアルバム・タイトル曲。私が大好きだった人で、洋楽風の日本語歌詞と加藤和彦のメロディーがファンタスティック。ここでは当時のドリーミーなサウンドを生かしながら1990年代のスパイスを上手くブレンドしている。ボーカルの戸川京子(2002年没)は子役でデビューした女優・歌手だった。 「パープル・モンスーン」(作詞作曲 上田知華 編曲 鈴木智文)6曲目は上田知華(2021年没)1980年の代表作。原曲を凌駕するアレンジで、歌っている野田幹子はシンガーソングライター以外にソムリエとしても活躍している。「ジュ・マンニュイ」(作詞 荒井由美 作曲 渡辺俊幸 編曲 鈴木智文)7曲目は、ハイファイセット1976年のアルバム「ファッショナブル・ラヴァー」に入っていた曲で、そこでは男性の大川茂が歌っていた。ここでのボーカル担当は和泉恵。 4曲のカバーが素晴らしいので上述したが、オリジナル作品もみな良い出来だと思う。 1970年代〜1980年代のニューミュージックのエッセンスを1990年代の音楽に取り込んで、新たなサウンドを作り出した人達による素敵なアルバム。大貫さんの「恋人達の明日」の一風変わったアレンジが楽しめる。 [2025年2月作成] |
|
| Sweet Revenge 坂本龍一 (1994) gut (For Life) | |
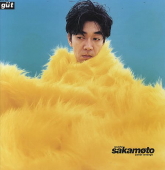  |
1. 二人の果て [作詞 大貫妙子 作曲編曲 坂本龍一] 3曲目 2. 君と僕と彼女のこと [作詞 大貫妙子 作曲編曲 坂本龍一] 13曲目 坂本龍一: Vocal, Keyboards, Computer Programming (1), Producer 今井美樹: Vocal (1) 高野寛: Vocal (2), Guitar (2) Lawrence Feldman: Flute (1) David Nadien: Strings Section Leader (1) Cyro Baptista: Percussion (1) Towa Tei: Studio Vision, Akai S-3200, SP-1200 (1), Drum Programming (2) 写真上: アルバム 1994年6月17日発売 写真下: シングル「二人の果て」 1994年11月18日発売 1. Futari No Hate (The End Of Two) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] 3rd Track 2. Kimi To Boku To Kanojo No Koto (You, Me And Her) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] 13th Track by Ryuchi Sakamoto from the album "Sweet Revenge" June 17, 1994 |
| 坂本10枚目のアルバムで、個人レーベル「グート」からのリリース。今回挑戦したヒップポップ・ラップ曲と、従来からのフランス映画音楽、ボサノヴァ、現代音楽風の曲からなる。 大貫さんが詩を書いた2曲は「フランス映画音楽」路線で、坂本・大貫のコラボ作品の曲調に近い。アンニュイなムードの詩とメロディーがヨーロッパ的な知的退廃の世界を醸し出していて、英語主体のアルバムの中で日本語で歌われていることもあって全体のなかで清涼剤的な役割を担っている。1.「二人の果て」の男女の愛の行き着く果ての情景はフランス映画「男と女」を連想する気怠いイメージ。坂本とユニゾンで歌っているのは今井美樹 (現在は布袋寅泰の奥さん)で、同時期に発表された彼女のアルバム「A Place In The Sun」のサウンド・プロデュースと作曲を担当していた縁からの参加だろう。エンディングのスキャットでボサノヴァのリズムになるところがお洒落。なお本曲はシングル盤で発売され、そのジャケット写真は大貫さんのアルバム「Mignonne」のオマージュ(パロディ?)になっている。また今井が出演した明治製菓のチョコレート「Melty Kiss」のCMで使用された。2.「君と僕と彼女のこと」は男性二人と女性の複雑な三角関係を描いた曲で、短いドラマを観ているような味わいがある。サウンド的に大貫さんが歌って自身のアルバムに収めても全く違和感がない感じ。ここでは高野寛が坂本と一緒に歌い、ギターも弾いている。なお本作は海外版(International Version)が別途制作されていて、そこではこれら2曲は同じバッキング・トラックに異なる内容の英語歌詞(作詞 Vivien Goldman) が付けられていて、各「Sentimental」、「Water's Edge」というタイトルで外人シンガー(Vivian Sessoms, Andy Caine)が坂本と歌っている。 他の曲について。ヒップポップ、ラップ曲については、自分の持ち味であるフランスやブラジル音楽、現代音楽のエッセンスを織り込んだ「SweetでRadical」な音楽を目指したというが、私はこの手の音楽はよくわからないのでなんとも言えない。ただ聴き手からみて坂本龍一が挑戦する必然性が本当にあったのかなという感じがする。私的にはボサノヴァ的な曲が好きで、「Anna」(作曲編曲 坂本龍一)9曲目、「Psychedelic Afternoon」(作詞 David Byrne 作曲編曲 坂本龍一 作詞者は元トーキング・ヘッズの人)11曲目がいいね。またボサノヴァとラップをかけ合わせた「Interuptions」(作詞 Latasha Natasha Diggs 作曲編曲 坂本龍一)12曲目もクリエイティブな感じでとても良いと思う。映画音楽・現代音楽路線では、もともとはベルナルド・ベルトリッチ監督の映画のために書かれたという「Sweet Revenge」(作曲編曲 坂本龍一)7曲目は坂本らしいサウンド。大貫さんの2曲とインストルメンタル以外はすべて英語の歌で、アズテック・カメラのロディ・フレイム、元フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドのホリー・ジョンソンなど著名なシンガーが参加している。 大貫さんが歌詞を提供した2曲は、日本版においてであるがアルバムのムードを決定付ける重要な曲だと思う。 [2024年10月作成] |
|
| French Lips Various Artists (1994) 日本コロンビア | |
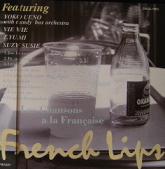 |
1. 哀愁のアダージョ(彼と彼女のソネット) [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 Taeko Onuki 編曲 池田健司] 8曲目 T. Yumi: Vocal 池田健司: Programming, Arrangement, Co-Producer 吉永多賀士: Producer 1994年7月21日発売 1. Aishu No Adagio (Kare To Kanojyo No Sonnet) "Adagio Of Sorrow" "His And Her Sonnet" [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Kenji Ikeda] 8th Track from the album "French Lips" by Various Artists, July 21, 1994 |
| 1990年代の新感覚女性アーティスト達がフレンチ・ガールズ・ポップを歌う企画盤。仕掛け人は全曲でプロデュースを担当した吉永多賀士(Takashi
"Gitane" Yoshinaga) のようだ。アーティスト4名によるオムニバス・アルバムで、全9曲中2曲を除き日本語で歌われている。また本場もののカバーは6曲で、残り3曲は日本で創られた和製フレンチポップという構成。 大貫さんが日本語詞を書いた「T'en Pa Vas (哀愁のアダージョ)」は原曲の曲名で、ここでは「彼と彼女のソネット」は副題となっている。歌っているT. Yumi はライナーノーツで「契約の関係で、彼女の正体を明かせないのが残念」とある通り変名であるが、当時の音楽シーンとその名前からシンガー・アンド・ソングライターの谷村有美と思われる(ただしインターネットで証拠が見つからなかったので、あくまで憶測です)。アレンジはエルザの原曲や原田知世のカバーに近く、打ち込みによる演奏。本アルバムの他の曲と異なり、奇をてらわず原曲の美しさに忠実なプロダクションとなっている。なお歌詞面では原田のバージョンにあったフレーズはなく、大貫さんのカバーと同じ内容だ。 T.Yumi のもう1曲「Chantons D'Amour (シャントン・ダムール)」(作詞 Jear Terisse 作曲 井上大輔 日本語詞 岩城由美)7曲目は、フランス系アメリカ人のナタリーという歌手が歌い、第一興商のCMソングに採用されたフランス語曲で、本アルバムと同じ日本コロンビアから発売された同名アルバムのボーナス・トラックとして収録された日本語バージョンのカバー。井上大輔(元ジャッキー吉川とブルーコメッツの井上忠夫(1941-2000))による明るく軽快なメロディーが素敵な佳曲。 他の曲について。Suzy Susieというガールズ・グループが3曲。1990年代前半に流行ったグランジ・ロック特有のチープな響きと少し投げやり風なボーカルが面白いサウンドのバンドだ。「Joe le Taxi (夢見るジョー)」(作詞作曲 Etienne Roda, Gil, Franck Langolff 日本語詞 岩城由美 編曲 Suzy Susie)1曲目、「Be My Baby」(作詞作曲 Lenny Kravitz, Henry Hirsch 日本語詞 岩城由美 編曲 Suzy Susie) 2曲目はいずれもフランスの歌手・俳優ヴァネッサ・パラディ(Vanessa Paradis) 1987、1992年のカバー。原曲とは大幅に異なるアレンジで、彼らの他の曲のようなヘビーなサウンドではないが、独特のチープな響きは魅力的。「Orages de Passions (嵐のデート)」(作詞作曲 Suzuy Susie, Kazu 編曲 池田健司) 9曲目は大阪でest-one というマンションのCMに使われたそうで、ノスタルジックな雰囲気がいい感じのキュートな曲だ。 シンガー・アンド・ソングライター、編曲家、プロデューサー、キーボード奏者のYoko Ueno with candy box orchestra (上野洋子)が2曲。いずれもフランスの男女二人組グループ、ブルース・トットワール(Blues Trottoir) 1989年のカバーで、「La Gosse (セルロイドの夢)」(作詞 Clemence Lhomme, 作曲 Pierre Papadiamadis 日本語詞 山田仁 編曲 池田健司)4曲目はジャズの香り漂うAOR、「Un Soir de Pluie (雨の舗道)」(作詞 Clemence Lhomme, 作曲 Jacques Davidovigi 日本語詞 山田仁 編曲 池田健司)5曲目はクールなボサノバで、上野のちょっとハスキーなヴォイスがコケティッシュ。 最後は5〜15歳をフランスで過ごしたというラジオ・パーソナリティー、歌手、声優のvie vieが2曲、流暢なフランス語で歌っている。「La Plus Belle Pour Aller Danser (アイドルを探せ)」(作詞 Georges Garvarentz 作曲 Charles Aznavour 編曲 池田健司)5曲目は1964年シルヴィ・バルタンの大ヒット曲のカバー。「Le Visiteur」 (作詞 vie vie 作曲 Yamazaki Suga 編曲 池田健司)6曲目は和製フレンチ・ポップス。いずれもボサノバ・アレンジで、後者は終盤に名曲「Summer Samba (So Nice)」のサンプリングが入る。 日本人がすなる洒落たフレンチ・ガール・ポップ。 [2024年10月作成] |
|
| Mauve Miki fr Creole (1994) For Life | |
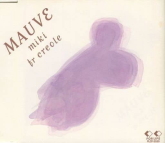 |
1. 彼と彼女のソネット (T'en Va Pas) [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 Taeko Onuki 編曲 渡辺貴浩] 2曲目 キャット・ミキ : Vocal 渡辺貴浩: Programming, Keyboards 桜井芳樹: Acoustic Guitar 角田敦: Producer 1994年7月21日発売 1. Kare To Kanojyo No Sonnet (T'en Va Pas) (His And Her Sonnet) (Don't Go) [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Creole] 6th Track by Creole from the album "T'en Va Pas" July 21, 1994 |
| アルバム「T'en Va Pas」から5ヵ月後に発売された6曲入りミニアルバムで、名義上ボーカルの(キャット)ミキがメインで、クリオールは「fr」
(フィーチャリング) となっている。タイトルの「モーヴ」は薄くグレーがかった紫色のことで、表紙の裸婦の抽象的イラストの色だ。 ここでも大貫さんが日本語詞を書いた1.「彼と彼女のソネット」を取り上げているが、全く異なるアレンジが施されている。編曲者でキーボード、打ち込み担当の渡辺貴浩は、近田春夫のバンド Vibrastone のメンバーだった人で、彼も他のメンバーと同じく近田人脈からの参加。オリジナルのメロディーはそのままに、コード進行を大胆に変えて桜井のギター、渡辺のシンセと打ち込みのパーカッションで一丁前のサンバに仕上がっている。それをバックにキャット・ミキがクールなボサノバ・ヴォイスで歌っていて、これも前作と同じく意外なほど良い感じ。 他の曲について。本作は歌手メインで制作されているため、実験的な要素があった前作と異なり、聴きやすい曲がそろっている印象。ほぼタイトル曲の「モーブの彼方」(作詞 桜井りさ 作曲編曲 桜井芳樹)1曲目、「時のないフィエスタ」(作詞 工藤順子 作曲編曲 角田敦)5曲目、特に「Wagamama」(作詞作曲 近田春夫 編曲 渡辺貴浩)4曲目がいい。特筆すべきは最後の曲「東京の伝書鳩」(作詞 外間隆史)で、作曲編曲そしてすべての演奏を冨田恵一が担当している。そしてこの曲は、2011年に発売された彼のベスト盤「冨田恵一 Works Best 〜Beautiful songs to remember〜」に最も初期の曲として収録されているのだ。歌詞がちょっと飛んでいるけど、本作のなかではシンセサイザーによるブラスセクションの音が入ったりして、とても新鮮に聞こえる。当時の彼はまだ無名で、名前が売れ出すのは3年後のキリンジと組んだ1997年頃からだ。 同じアーティストが、ほぼ同時期に、全く異なるアレンジでカバーした二つの「彼と彼女のソネット」.....。 [2024年9月作成] |
|
| T'en Va Pas/彼と彼女のソネット 原田知世 (1994) For Life | |
  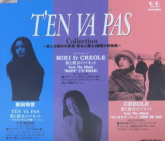 |
1. 彼と彼女のソネット (T'en Va Pas) [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 Taeko Onuki 編曲 鈴木慶一] 8cm CDシングル カップリング 鈴木慶一: Additional Programming, Piano 土岐幸男: Computer Programming 鈴木智文: Acoustic Guitar, Electric Guitar 写真上: 8cm CDシングル (1994年7月21日発売) 写真中: カコ (1994年7月21日発売) フランス語版 「T'en Va Pas」のみ収録 写真下: For Lifeから出た非売品CD 「T'en Va Pas Collection」 Creole, Miki ft. Creole, 原田知世(フランス語版)、原田知世(日本語版) 計4曲入り 1. Kare To Kanojo No Sonnet (T'en Va Pas) (His And Her Sonnet) (Don't Go) [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Keiichi Suzuki] coupling track by Tomoyo Harada from CD Single "T'en Va Pas" on July 21, 1994 |
| 1987年の原田知世「彼と彼女のソネット」7年後のセルフカバーで、編曲者は当時原田をプロデュースしていた鈴木慶一。今回は原曲のフランス語による録音がメインで、日本語版は同じバッキング・トラックに吹き込んだもの。同時発売の洋曲カバーアルバム「カコ」にはフランス語版のみ収録され、日本語盤は入っていない。 1990年代の再録ということで、かなり大胆なエレクトロポップのアレンジになっていて、シンセサイザーが刻むダンサブルなリズムが前面に出たサウンドになっている。聴き比べて感じるのは原田の歌唱力の飛躍的向上だ。19歳の若い娘のか細い声は、26歳の深みのある大人の声になっていて、さらに単なる声の質だけでない内面の成長を強く感じさせる。鈴木慶一のアレンジも秀逸。 同日に発売された7曲入りミニアルバム「カコ」は、鈴木慶一プロデュースによる1960年代〜1970年代の洋曲カバーアルバムで、スキーター・デイビスの「The End Of The World」1963 全米2位、イタリアの歌手ミーナの「Un Buco Nella Sabbia」(砂にきえた恋)1964、マリアンヌ・フェイスフルの「The Little Bird」1965 全米32位、イギリスのグループ、ニュー・ヴォードヴィル・バンドの「Winchester Cathedaral」 全英4位、全米1位(この曲のみ徳武弘文の編曲、他は鈴木慶一)、ジュディ・コリンズ(作曲はジョニ・ミッチェル)の「Both Sides Now」全米8位、クローディヌ・ロンジェ(ドノバン作曲)の「Electric Moon」1971という通好みの曲。エレクトリック、アコースティック・サウンドによるひとくせ・ふたくせもあるアレンジ。原田のボーカルも素晴らしく、英語は当然としても、フランス語、イタリア語の発音に全く違和感を感じさせないのが凄い。洋曲カバー集ということで、日本語版「彼を彼女のソネット」を収めなかったのだね。 同じ年に同じレーベルから4通りの「彼と彼女のソネット(T'en Va Pas)」が出た事になり、これら4曲を収めた非売品CD「T'en Va Pas Collection」が作られ配布された。その表紙には「恋にお悩みの貴男・貴女に送る4種類の特効薬」というキャッチ・フレーズがついている。 鈴木慶一の独創的なアレンジによる「彼と彼女のソネット」。原田知世の7年間の成長がはっきりわかる逸品。 [2025年5月作成] |
|
| Elephant Hotel 矢野顕子 (1994) Epic (Sony) | |
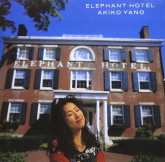 |
1. Oh Dad [作詞 菊池真美、矢野顕子 作曲 大貫妙子 編曲 Jeff Bova コーラスアレンジ 矢野顕子] 7曲目 矢野顕子: Vocal Jeff Bova: Keyboards, Drums Programming Chuck Loeb: Guitar Will Lee: Bass Tawatha Agee, Curtis King Jr., Brenda White King: Back Vocal 1994年10月1日発売 1. Oh Dad [Words: Mami Kikuchi, Akiko Yano, Music: Taeko Onuki, Arr: Jeff Bova, Chorus Arr: Akiko Yano] 7th Track by Akiko Yano from teh album "Elephant Hotel" October 1, 1994 |
| エレファント・ホテルはマンハッタンの北に位置するウェストチェスター郡ソマースにある歴史的建造物。もとはホテルだったが、現在は市役所・資料館になっている。ハチャリア・ベイリーという農夫が1825年に建てたもので、彼はホテル名前の由来となる象をはじめとする珍しい動物を見世物として巡業することで成功した。それがアメリカにおけるサーカスの起源になり、彼の名を冠したサーカス団は2017年まで続いた。本アルバムは当該建物をタイトルとし、ジャケットの矢野のポートレイトもその前で撮影したものだ。 1990年のニューヨーク移住後4作目にあたり、後に「The Hammonds」という共同ユニットを結成してアルバムを出したキーボード奏者、作曲家、編曲家のジェフ・ボヴァや、ジャズ・ピアニスト、作曲家、編曲家のギル・ゴールドスタインが、編曲・演奏の核となり、ニューヨークを本拠地とする名だたるセッション・ミュージシャンが参加して、現地の空気感が漂う作品になっている。 1.「Oh Dad」は大貫さんの名曲「色彩都市」(アルバム「Cliche」1982所収)のメロディーに別の英語詞を付けたもの。矢野と共作した菊池真美は、アルバム・ジャケットに記された矢野の賛辞から高校時代の同窓生だったことがわかる。彼女はグレープを解散した吉田正美と茶坊主というデュオを結成して1976年「Tree Of Life」というレコードを出した他に、1980年代前半に矢野誠・顕子等が参加したレコードを製作するなど矢野と縁が深かった人だ。本曲は、青森在住時に一緒にジャズ喫茶に通って同音楽に目覚めるなど、矢野の音楽形成に大変重要な貢献をした大好きな父親に捧げる内容となっており、彼女にとっても大事な曲に違いない。ここでは彼女はコーラス以外のアレンジをジェフに任せ、自ら楽器の演奏もせずに歌に専念している。本アルバム中数曲がそんな感じで、人に任せることによってどう仕上がるかを楽しんている風がある。 アルバム全体的にクロスオーバーを矢野独特のスパイスで調理した感のあるサウンド。糸井重里作詞、矢野顕子作曲の「サヨナラ」3曲目、「夢のヒヨコ」 5曲目(テレビ番組ポンキッキーズの主題歌)、ナンセンス童話「にぎりめしとえりまき」10曲目が特に面白い。「すばらしい日々」 8曲目 (作詞作曲 奥田民生 編曲 矢野顕子)はユニコーン1993年のカバー。最後の沖縄民謡「てぃんさぐぬ花」13曲目は宮澤和史の歌唱指導で録音したもので、矢野はかなり本格的に歌っている。それに対し間奏で挿入されるピアノソロ、ギターソロは思いっきりジャズしていて、その対比が鮮やかだ。 「色彩都市」のメロディーで、独自内容の英語詞と斬新なアレンジを楽しめる。 [2024年11月作成] |
|
| Tripping Triplets Three Graces (1994) 東芝EMI | |
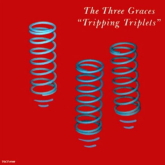 |
1. ワニのチャーリー [作詞作曲 大貫妙子 編曲 井上鑑] 3曲目 星野操: Vocal (Melody) 森本政江: Vocal (Alto) 白鳥華子: Vocal (Soprano) 井上鑑: Keyboards 松原正樹: Electric Guitar 高水健司: Bass 山田秀夫: Drums 1994年10月19日発売 1. Wani No Charlie (Charlie The Crocodile) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Akira Inoue] 3rd track by Three Graces (Misao Hoshino, Masae Morimoto, Hanako Shiratori) from the album "Tripping Triplets" October 19, 1994 |
| スリーグレイセスは星野操(旧姓 石井 メロディ担当)、森本雅恵(旧姓 石井 操の姉 アルト担当)、白鳥華子(旧姓 長尾 ソプラノ担当)の3人からなるコーラスグループで、1958年に結成され1961年「山のロザリア」が大ヒットした。完璧なハーモニー・ボーカルを誇り、レコードの他に数多くのCMソングを歌った。1967年に3人の結婚を機として活動を休止したが、22年後の1989年に再結成し、CMソング、レコード、コンサート、テレビ出演などで活躍した。彼女等の歌で記憶に残っているのは、「魔法使いサリーのうた」1966で、園田憲一とディキシーキングスの演奏も最高だった。CMでは「明治チョコレート」、「セキスイハウス」かな。テレビでは「タモリの世界は音楽だ」1990-1991にハウスバンドのメンバーで出演(これは後から調べてわかったはなしだけど.....)。 本作は彼女等が1994年に出したアルバムで、タイトルは「飛び跳ねる三連音符」という意味でグループの音楽を表している。大貫さんの他に、岩沢二弓、矢野顕子、糸井重里、杉真理、上田知華、リンダ・ヘンリック、Epo、吉田美奈子、メリッサ・マンチェスター等という大変豪華な人達が書き下ろしで曲を提供。そして1曲を除き井上鑑がアレンジを担当することで、ジャズやスタンダード曲が主体だった彼女等の音楽に新しい風を吹き込んでいる。 大貫さんが作詞作曲した1.「ワニのチャーリー」 (アフリカのワニなので英語は「Crocodile」)は、「ピーターラビットとわたし」や「メトロポリタン美術館」系のメルヘン・ソングで、抽象的な歌詞に彼女のアフリカに対する思いと自然観が投影されている。3人の素晴らしいハーモニー・ボーカルを聴いていると生理的快感を覚えるほどだ。 他の曲では、ブレッド・アンド・バターの岩沢二弓作詞作曲の「Silvery Moon」1曲目のスタンダード・ソング的な味わい、フュージョン・ジャズっぽい「アフリカの夢を」(作詞 糸井重里 作曲 矢野顕子)2曲目、一転ストリングスとバイオリンの伴奏でJR東日本のCFソングに採用されシングル・カットされた「秋」(作詞作曲 矢野顕子)8曲目がとても良い感じで、矢野ファンにとってもコレクター・アイテムになる存在。「3度目の恋」(作詞 田口俊 作曲 杉真理)4曲目、Epoの作詞作曲による「七色の絵の具」10曲目 といったジャズっぽい曲も捨てがたい。本作唯一のカバー曲「恋はメレンゲ」(作詞作曲 大瀧詠一)9曲目は大瀧の「Niagara Moon」1975がオリジナルであるが、ここでは星野操による英訳詞で歌っており、大瀧と縁が深かった井上のアレンジも面白い。吉田美奈子の「Tomorrow」11曲目は彼女らしいゴスペルの香りがする曲で、ソロボーカル・プラス・バックコーラスのスタイルでじっくり歌われる。最後の曲「Flowers For Emily」(作詞作曲 Amy Sky, Melissa Manhester)12曲目はメリッサ本人による録音はなく、どのような経緯で彼女等が歌う事になったのかは不明。なお演奏面では土岐英史のサックスソロ、松原正樹のギターソロが随所で楽しめる。 発売後30年経ち、すっかり忘れ去られてしまった感があるが、豪華な作家陣と素晴らしい歌唱・演奏による掘り出しもの作品と断言できる。 [2024年10月作成] |
|
| 晴れた日、雨の夜 区麗情 (1994) Sony | |
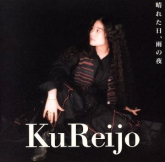 |
1. 蜃気楼の街 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Robbie Buchanan コーラス・アレンジ 西脇辰弥] 5曲目 区麗情: Vocal Robbie Buchanan: Keyboards Bob Mann: Guitar Jimmy Johnson: Bass Rus Kunkel: Drums Mike Fisher: Percussion Arnie Watts: Tenor Sax 河合夕子、井上照代: Back Vocal 1994年11月21日発売 1. Shinkiro No Machi (The City Of Mirage) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Robbie Buchanan, Chorus Arr: Tetsuya Nishiwaki] 5th Track by Ku Reijo form the album "Hareta Hi, Ame No Yoru" (Sunny Day, Rainy Night) November 21, 1994 |
| 区麗情(1994- 東京都出身)は中国人と日本人のハーフの父親と日本人の母親との間に生まれ、父親は千代田区有楽町にあった中華料理の老舗「慶楽」(2018年閉店)の料理長だった。幼い頃から父親が聴いていたアメリカン・ポップスに親しみ、上智大学在学中の1983年にCDデビュー。2002年までの間にシングル11枚、アルバム10枚を出した。現在はブログを更新しながら、時たま音楽活動を行っているようだ。 本作は彼女3枚目のアルバムで、全10曲中オリジナルが6曲(彼女の自作は作詞1曲のみ)、カバーが4曲。また半分の5曲がアメリカ・ロサンゼルス録音。西脇辰弥がオリジナル曲の作曲と大半の曲の編曲を担当している。バック・ミュージシャンについては、著名なセッション・プレイヤーが多く参加している海外録音が面白い。 大貫さんの「蜃気楼の街」(オリジナルはシュガーベイブ「Songs」1975収録)は米国録音で、アレンジとキーボードがプロデューサー、アレンジャー、作曲家、キーボード・プレイヤーとして無数の作品に参加したロビー・ブキャナン。ギターとベース、ドラムスが当時ジェイムス・テイラーのバックをやっていた人達、テナーサックスがジャズ・クロスオーバのアルバムを出したアーニー・ワッツという大変豪華な顔ぶれ。バック・コーラスの河合夕子は1980年代に自己名義のアルバムやシングルを出し、その後セッション・シンガーに転向した人だ。そういう人達が大貫さんの作品をソリッドなボサノヴァで演奏していて、区麗情のボーカルもちょっとエッジがあって悪くない。シュガーベイブのバージョンを「陰」とすると本作は「陽」といえるかな。 他の曲では、やはりカバー曲に興味が集中する。「12月の雨」(作詞作曲 荒井由美 編曲 西脇辰弥)3曲目はユーミンの「ミスリム」1974 収録の名曲。この米国録音は西脇のキーボードにワディ・ワクテル(ギター)、リー・スクラー(ベース)という、これまたジェイムス・テイラー所縁のミュージシャンが入り、オリジナルとは異なるリズム・アレンジで迫っている。「Snowman」(作詞 青木景子、村松邦男 作曲 村松邦男 編曲 Bill Elliott コーラス・アレンジ 村松邦男)7曲目は村松1986年の3曲入り自主制作レコード「Christmas Presents」収録曲のカバーで、当時セッション・ミュージシャンで、後2000年代以降ブロードウェイ・ミュージカルで大成功するビル・エリオットが編曲を担当している。オリジナルでのスローなイントロなしのアレンジで、村松本人がコーラスで歌っている。はっぴいえんどの名盤「風街ろまん」1971収録の「花いちもんめ」(作詞 松本隆 作曲 鈴木茂 編曲 西脇辰弥)8曲目は鈴木が初めて歌った曲として鮮烈な印象が残った曲だったが、ここではアコースティック・ギターとピアノ、シンセサイザー、パーカッションというシンプルなアレンジ。吉川忠英のアコギが良く、区麗情のボーカルも曲に合っている。 オリジナル曲は西脇の作曲とアレンジが光っている。彼は1964年生まれでキーボード以外の楽器もこなすマルチプレイヤー。國府田マリ子、谷村有美、メロキュアなどの中堅歌手やロックグループ Pierrotなどのの作曲・編曲を手掛けた人で、デビッド・フォスターのようなパンチが効いた音楽を好む人のようだ。曲としては最後のタイトル曲「晴れた日、雨の夜」(作詞 竹花いち子 作曲 西脇辰弥 編曲 Robbie Buchanan、西脇辰弥)10曲目が、歌詞・メロディーと「蜃気楼の街」と同じミュージシャンによる演奏でいい感じ。他の曲もそれなりの水準であるが、彼女の歌い方と声に良い意味での癖があって、そして記憶に残るような曲が1曲でもあったら、もっとよかったのにと思う。 当時ジェイムス・テイラーのバックをやっていた人達が大貫さんの「蜃気楼の街」を演奏するという、私にとっては夢のような趣向。 [2024年11月作成] |
|
| 1995年 「Tchou」 (1995/4/19発売)の頃 | |
| 風の中のダンス/誓いのブリッジ 安達祐実 (1995) Victor | |
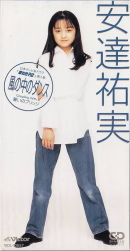 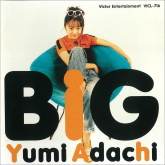 |
1. 風の中のダンス [作詞作曲 大貫妙子 編曲 千住明] 8cm シングル 安達祐実: Vocal 写真上: 8cmシングル 1995年5月24日発売 写真下: アルバム「BiG」 1995年12月16日発売 1. Kaze No Naka No Dance (Dance In The Wind) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Akira Senju] by Yumi Adachi from 8cm CD single on May 24, 1995, also included in the album "BiG" on December 16, 1995 |
安達祐実(1981- 東京都出身)5枚目のシングル。2歳からモデルとして芸能界に身を置いた安達は、子役としてドラマやCMに出演。1993年の映画「Rex 恐竜物語」の主演に続くテレビドラマ「家なき子」1994年で、貧困家庭に育ち家庭内暴力やいじめを受けながらも立ち向かってゆく少女(「同情するなら金をくれ!」という台詞が有名)を演じて一世を風靡し、子役女優としての地位を確立した。 大貫さん作詞作曲の1.「風の中のダンス」は続編ドラマ「家なき子2」1995の挿入歌。編曲者の千住明と大貫さんとは、彼が音楽を担当したアニメ「アリーテ姫」2001の主題歌を歌ったり、彼の指揮による「シンフォニック・コンサート」を開催したりなど親密な音楽関係が続いている。オーケストラをバックに歌う当時13歳の彼女の歌声には幼さが残っているが、若々しさ、初々しさが勝っていて、歌詞・メロディーが明るく前向き(ドラマのイメージと正反対)なので、聴いてて心地よい。大貫さんのセルフカバーや他の人によるカバーがあってもよい位の出来だと思う。カップリングの「誓いのブリッジ」(作詞 サエキケンゾウ 作曲 佐藤清喜 編曲 門倉聡)も爽やかな後味が残る佳曲。オリコン最高位25位を記録し15万枚売れたそうで、かなりの枚数が中古市場に出回っている。なお上記2曲は7ヵ月後の12月に発売されたアルバム「BiG」に収録された。 歌手として彼女が出した最後のシングルは1997年、アルバムは1998年。女優としての安達は、その後20代後半(2000年代後半)に子役のイメージから脱却できずに低迷期を迎えるが、30代後半(2010年代後半)から演技派女優として再ブレイクを果たした。 1.「風の中のダンス」は埋もれるにはもったいない曲。大貫さん、今後行われる「シンフォニック・コンサート」で是非取り上げてください! [2024年11月作成] |
|
| Merci Boku 竹中直人 (1995) Consipio | |
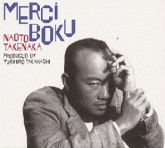 |
1. つぼみ [作詞 大貫妙子 竹中直人 作曲 竹中直人 編曲 高橋幸宏] 7曲目 2. ドクトクくん [作詞作曲 竹中直人 編曲 高橋幸宏] 6曲目 竹中直人: Vocal 大貫妙子: Doku-Toku Voice (2) 高橋幸宏: Drums, Keyboards 徳武弘文: Electric Guitar (1) 矢口博康: Sax (1) 高橋幸宏: Producer 1995年5月25日発売 1. Tsubomi (Bud) [Words: Taeko Onuki, Naoto Takenaka, Music: Naoto Takenaka, Arr: Yukihiro Takahashi] 7th Track by Naoto Takenaka from the album "Merci Boku" on September 25, 1995 |
| 俳優、映画監督、声優、歌手、コメディアン、タレントと、なんでもこなす竹中直人(1956- 神奈川県出身)が高橋幸宏と組んで制作したアルバム。お得意のコント、ギャグが一杯詰まっているが、音楽面でも十分面白い作品に仕上がっている。本アルバムにあるネタの多くは、1994年7月20日から1995年1月4日まで毎週水曜日の深夜にテレビ朝日系で放送された「竹中直人の恋のバカンス」(以下「恋バカ」)がベースとなっているようだ。 大貫さんは竹中と親しく、彼のソロアルバムに曲提供やボーカル・コーラスで参加した他に、彼が監督した映画「東京日和」1997の音楽を担当している。本作は二人のコラボとしては初めての作品。1.「つぼみ」は二人の共作による作詞で、大貫さんらしい瑞々しい歌詞を竹中が真面目に歌っていて、彼の声の良さが際立つ歌唱だ。ギターを弾く徳武弘文はブレッド&バター、山本コータローのバックを経てセッション・ギタリストとして活躍し、ラスト・ショウというバンドのメンバーだった。ソプラノ・サックスを吹く矢口博康はエスパー矢口という異名を持つ、ジャズの範疇に収まりきらない独自の音楽を展開する人だ。 2.「ドクトクくん」は大貫さんの提供作品ではないが、彼女がヴォイスで参加しているため本記事に挙げた。自分の顔やうなじが独特であることを執拗に歌うギャグソングで、テクノっぽい伴奏で歌う竹中に掛け声・合いの手が入る。その一部「本当 独特よ!」、「あらあらやだ ドクトクなうなじよぉ」で大貫さんの声が聞こえる。彼女がくだけて話す際の男っぽい感じの声がいいね。 他の曲について。「砂山」(作詞 北原白秋 作曲 中山晋平 編曲 上野耕路)1曲目 は「生肉を食べるターザンです」という自己紹介の後に歌われるが、ストリングスのバックがつく歌唱自体は真面目で、むしろそうなのが面白い。「僕の嫁さん」(作詞 岩谷時子 作曲 弾厚作 編曲 高橋幸宏)2曲目 は加山雄三1969年のカバー。彼は1990年に元アイドル歌手の木ノ内みどりと結婚しているので、そのノロケかな?「じろう」 (作詞作曲 竹中直人 編曲 高橋幸宏)3曲目は大昔の歌謡曲風の小品であるが、そのモチーフがアルバムの他の曲のなか随所に現れる仕掛けになっている。「ねえ」(作詞 竹中直人 作曲編曲 高橋幸宏)4曲目は高橋のアンビエントな音楽をバックにした語りのギャグ。「おぼえていること」(作詞作曲 忌野清四郎 編曲 高橋幸宏、岸利至)5曲目は書き下ろし曲で、カントリーロック風のバックで竹中が忌野風にシャウトする。「カーテンレールを引いて」(作詞作曲 シェスタコビッチ・三郎太 編曲 高橋幸宏、岸利至) 6曲目の作者は竹中の変名で、「恋バカ」に登場したキャラクターの一人。彼と親交があり番組にも出演していた東京スカパラダイス・オーケストラが切れ味抜群の伴奏をつけていて、竹中はジェームス・ブラウン張りにシャウトしまくっている。 「坊主 -スチャラダパーに捧ぐ- (金々節より)」(作詞 添田唖蝉坊 作曲 後藤紫雲)の添田唖蝉坊は竹中の変名ではなく、明治大正期に活躍した演歌師(1949年没)で、「坊主」は代表作「金々節」の中盤の歌詞にあたる。何故ヒップポップ・グループの「スチャラダパー」が出てくるかというと、彼らは竹中が在籍したギャグ集団「ラジカル・ガジネリビンバ・システム」の影響を受け、グループ名を集団の公演名「スチャラダ」からとってきており、竹中と親交があるためと思われる。「メルシイ・僕」(作詞 竹中直人 作曲高橋幸宏 編曲 高橋幸宏、岸利至)11曲目は、フランス語の「Merci Beaucoup (Thank You Very Much)」をもじったもので、スティールドラム風のシンセによるカリブ音楽は高橋の趣味が反映している。「流しのふたり」(作詞作曲編曲 チャーリー・ボブ彦)12曲目のチャーリーは竹中の変名で、アベックに対し臭い歌の押し売りをするギターの流しチャーリーと、高橋扮する流しのドラマー、ジャッキー・テル彦とのコンビによるコントで、「恋バカ」テレビにおけるふたりも傑作だった。最後は3曲目「じろう」のリフレインで終わる。 竹中得意のシュールなギャグが一杯詰まっているが、高橋幸宏がプロデュースした音楽作品としても十分楽しめる作品。 [2024年12月作成] |
|
| Nature 日置明子 (1995) Fun House | |
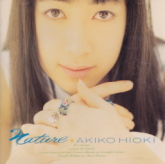 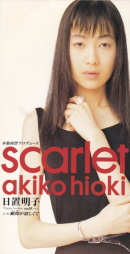 |
1. 瞬間が眩しくて [作詞 大貫妙子 作曲 木根尚登 編曲 清水信之] 6曲目 日置明子: Vocal, Chorus 清水信之: Keyboards, Synthesizer, Guitar, Bass, Flute, Drums & Percussion Programming 田中はじめ: Fairlight Operation 木根尚登: Producer 写真上: アルバム 1995年8月2日発売 写真下: シングル「Scarlet」1995年7月15日発売 1. Toki Ga Mabushikute (The Moment Is Dazzling) [Words: Taeko Onuki, Music: Naoto Kine, Arr: Nobuyuki Shimizu] 6th Track by Akiko Hioki from the album "Nature" on August 2, 1995 |
| 日置明子(1974- 鳥取県出身)は雑誌モデルからスタートして、1995年1月にTM Network の木根尚登のプロデュースによる「Winter
Comes Around」(TM Networkのアルバム「Carol〜A Day In A Girl's Life 1991〜」1988 収録曲のカバー)のシングル盤でデビューした。「Nature」(「ナチュール」とフランス風に読む)はその7ヵ月後、彼女が20歳の時に発売されたデビュー・アルバム。タイトルのみでなくアルバム・ジャケットにフランス語が散りばめられているが、音楽的にフランス臭さはなく、ヨーロピアン・ポップスの雰囲気を出すための演出と思われる。どちらかと言えば洋楽調の歌謡曲に近い感じの歌唱と音楽で、全てを作曲した木根尚登と1曲を除き全曲の編曲と演奏を担当した清水信之により、そこそこのレベルに仕上がっている。日置も無難に歌っていて、聴いてて大変心地良いのだが、歌い手の存在感・個性が今一つ伝わってこない感もある。 その中で、大貫さんが作詞した1.「瞬間(とき)が眩しくて」は、彼女らしい瑞々しさに溢れた歌詞で、アルバムの中で異彩を放っている。それに呼応するかのように、木根がつけたメロディー、清水のボサノバ風アレンジも垢抜けていて爽やかだ。マルチプレイヤーの清水はすべての演奏をこなしているが、楽器クレジットにあった「Brackscreen」は内容不明。またフェアライト・シンセサイザー操作担当の田中という人の名前の漢字は確認できなかった。なお本曲はアルバムに先駆けて同年7月15日発売されたシングル「Scarlet」のカップリングにもなっている。 日置はテレビ番組のテーマソング・挿入歌、CM、テレビ番組や映画に出ていたがあまり売れず、1999年にsonoと改名して、スウェーデンのアレンジャー、トーレ・ヨハンソンのプロデュースでアルバムを2枚出したが、それらも売れなかった。そして2002年に市川新之助(現 市川團十郎)とのスキャンダルが発覚して、表舞台から姿を消して現在に至っている。 20年以上経った現在、完全に忘れ去られた存在。歌謡曲風であるが、それなりにいい曲。 [2025年1月作成] |
|
| Beautiful Days 伊東ゆかり (1995) Alfa | |
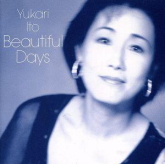 |
1. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Derek Nakamoto] 7曲目 伊東ゆかり: Vocal Derek Nakamoto: Keyboards, Synthesizer Programming Tim Godwin: Guitar Paul Taylor: Soprano Sax Brad Cummings: Bass Bernie Dresel: Drums, African Percussion 1995年10月18日発売 1. Totsuzen No Okurimono (A Sudden Gift) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Derek Nakamoto] 7th track from the album "Beautiful Day"by Yukari Ito on October 18, 1995 |
| 伊東ゆかり(1947- 東京都出身)48歳の時のアルバムで、1曲を除き米国ロサンゼルス録音の意欲作。伊東は1960年代に中尾ミエ、園まりと「スパーク3人娘」としてポップス歌謡で活躍したが1970年代は低迷。その後1977年から1981年まで続いたテレビ音楽番組「サウンド・イン
"S"」の司会で大人の歌手として復活した。本作ではそんな彼女が米国のミュージシャンをバックに自由な境地で歌っている。本アルバムで1曲を除きアレンジを担当したデレク・ナカモトはハワイ州生まれの日系人で、ロサンゼルスを拠点に活動、オージェイズ、テディー・ペンダーグラス、マイケル・ボルトン等の演奏・編曲に携わったが、ジャズピアニスト松居慶子の諸作品への関与が最も有名な人だ。ここでは彼が得意とするクロスオーバー・ジャズ、ニューエイジ・サウンドをベースとしたサウンド作りになっている。 1.「突然の贈り物」は大貫さんのアルバム「Mignonne」1978収録の名曲で、1978年竹内まりや、1991年森丘祥子に続く3番目のカバー。ベース(あるいはシンセ・ベース)によるリズミカルなリフがついた斬新なアレンジとなっているが、伊東の落ち着いたボーカルが曲本来の持ち味をしっかり保っている。間奏とエンディングで入るソプラノ・サックスとパーカッションもいい感じ。全体的に静かなバラードが多いアルバムのなかで、本トラックは程よいアクセントになっているといえる。 他の曲について。「七色の絵の具」(作詞作曲 EPO)1曲目は、スリーグレイセスのアルバム「Tripping Triplets」1994が最初で、オリジナルが井上鑑によるジャズボーカルのアレンジだったのに対し、ここではクロスオーバー風のサウンドになっている。それにしても伊東のボーカルの上手さが引き立っているね。なおEPOはもう1曲「想い」3曲目を提供している。「ラブ・レター」(作詞 松本一起 作曲 鴨宮涼)4曲目は伊東にピッタリの大人のバラード。来生たかおとえつこの姉弟による「そこからとこれからの季節」5曲もぐっとくる佳曲だ。「あなたの隣に」(作詞 荒木とよひさ 作曲 馬飼野康二)8曲目は1978年にシングル盤およびアルバム「YUKARI あなたの隣に」に収録された曲の再録音。最後の曲「明日、めぐり逢い」(作詞 松原史明 作曲編曲 森田公一)9曲目のみ日本録音で別の編曲者によるもの。そのため他の曲とかなり異なり歌謡曲的な雰囲気になっている。この曲は1994年8月にシングル盤が発売されていて、明記されてはいないがボーナス・トラック的な位置づけなんだろう。 チェロを思わせる落ち着いた大人の歌声で、斬新なアレンジによる「突然の贈り物」を聴くことができる。 [2024年11月作成] |
|
| Smoochy 坂本龍一 (1995) gut (For Life) | |
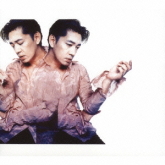 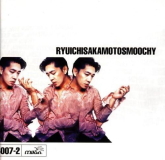 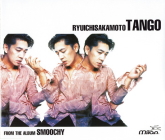 |
1. 愛してる、愛してない [作詞 大貫妙子 作曲編曲 坂本龍一] 2曲目 2. Tango [作詞 大貫妙子 スペイン語文 Fernando Aponte 作曲編曲 坂本龍一] 5曲目 3. Tango (Version Castellano) [作詞 大貫妙子 スペイン語詞 Raul Carnota 作曲編曲 坂本龍一] 13曲目(海外盤のみ) 坂本龍一: Vocal (1,2), Keyboards, Computer Programming, Producer 中谷美紀: Vocal (1) Soraya Lamilla Cuevas: Vocal (3) Gil Goldstein: Accordion (2,3) 佐橋佳幸, Amedeo Pace: Guitar (1) Vinicius Cantuaria: Guitar (2,3) Jaques Morelenbaum: Cello Everton Nelson: Violin (1) Alexander Sipiagin: Trumpet (1) Lawrence Feldman: Flute (2,3) バカボン鈴木: Bass 森俊彦: Drums Programming, Additional Production (2,3) 写真上: 国内盤 (1995年10月20日発売) 写真中: 海外盤 (ボーナス・トラックとして「Tango (Version Castellano)」を含む) 写真下: 海外盤 「Tango」 Promotional Single (「Tango (Version Castellano)」、「Tango (Version Castellano) Radio Edit」収録) 1. Aishiteru, Aishitenai (I Love, I Don't Love) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] 2nd Track 2. Tango [Words: Taeko Onuki, Spanish Text: Fernando Aponte, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] 5th Track 3. Tango (Spanish Version) [Words: Taeko Onuki, Spanish Lyrics: Raul Carnota, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] 13th Track (Overseas Issue Only) by Ryuchi Sakamoto from the album "Smoochy" Octber 20, 1995 |
「Smoochy」は坂本龍一11枚目のアルバムで、タイトルは英語のスラングで「キスしたくなる気分になる」という意味。当時の批評は彼が自ら歌ってJ-Popに挑戦したというものが多かったが、今聴くと、彼が大きな影響を受けたブラジル音楽のスパイスで日本のポップスに味付けしたという印象を持った。ここでの「ブラジル音楽」とはボサノバやサンバに限らない広義の音楽であり、アントニオ・カルロス・ジョビン、デオダード、ミルトン・ナシメント等の音楽をじっくり聴くとわかるものだ。 前作「Sweet Revenge」2004との大きな違いは、ブラジルのチェロ奏者ジャキス・モレレンバウムが参加していることだ。彼とは1990年代初めにカタエーノ・ヴェローゾを通じて知り合ったそうで、1993年の映画「Little Buddha」サウンドトラックが録音上の初顔合わせ。晩年のアントニオ・カルロス・ジョビンのバンドで演奏した彼のチェロは坂本の音楽に大きな深みを与えている。両者の共演はその後も続き、チェロ、バイオリンとの3重奏による「1996」やジャキスの奥さんパウラ(ボーカル)と3人でジョビンが生前使っていたピアノを使用して録音した「Casa」2001などの名作を生み出した。私はアントニオ・カルロス・ジョビンをこよなく愛する者であり、彼がCTIレーベルから出した「Wave」1967、「Tide」1970、「Stone Flower」1970は大傑作だと思うし、晩年の作品も味わい深い。改めて坂本龍一の音楽を聴いていると、発せられる音は違ってもその底に流れている魂は両者相通じるものがあるようで、本アルバムの音楽はそれを如実に感じさせるものだ。 1.「愛してる、愛してない」は、森俊彦がプログラミングした急速調の打ち込みドラムのリズムに乗って坂本と中谷美紀がユニゾンで歌う。本曲が坂本と中谷の初共演で、よほど相性が良かったのか、以降彼女の名義で3枚のアルバムをプロデュースすることになる。大貫さんとしては異色の退廃を漂わせる歌詞が印象的。2.「Tango」は坂本の代表作といえる曲で、タイトルはアルゼンチン・タンゴのことではなく、その音楽の内面の激しさを表したもの。地球の裏側である南米の地への思いが色濃くにじむ大貫さんの歌詞が素晴らしい。坂本のボーカルは「下手」といったほうが適切な表現で、歌詞カードを見ながらでないと意味が伝わってこないほどであるが、この曲に関しては、その歌声が歌詞の持つ切迫した心情を効果的に表している。これらのボーカルを聴いていると、彼が得意でないにも拘わらずあえて歌ったのは、J-Popで売ろうとしたわけではなく、ジョビンと同じように曲の作者が歌うことの意味に拘ったのではないかと思う。なお2.「Tango」について、本アルバムの海外発売分にはソラヤという女性歌手が歌うスペイン語歌詞による「Version Castellano」がボーナス・トラックとして収録されていた。大貫さんは1997年のアルバム「Lucy」で坂本の編曲でセルフカバーし、2010年の「Utau」では坂本のピアノのみの伴奏で歌っている。1.「愛してる、愛してない」については、1997年に発売された中谷のビデオ作品「Butterfish」(1997年2月26日・27日渋谷クラブ・クアトロでのステージ模様を撮影したもの)でライブ映像を観ることができる。 他の曲について(以下 作曲編曲はすべて坂本龍一)。「美貌の青空」(作詞 売野雅勇)1曲目は、1996年の「1996」と2004年の「/04」のアルバムにバイオリンとチェロとの三重奏によるインストルメンタル・バージョンが、2010年の「Utau」で大貫さんのボーカル・バージョンが録音されている。「Bring Them Home」3曲目、「青猫のトルソ」4曲目はピアノ(エレキピアノ)、チェロ、バイオリンとの3重奏で、1996年のアルバム「1996」で再録音されている。「電脳戯話」(作詞 高野寛)8曲目は、当時可能になりつつあったインターネットでのサーフィンのイメージ歌詞にしたもので、現在では当たり前になったネット世界がファンタジックに描かれているのが興味深い。「Hamisphere」(作詞 宮沢和史)9曲目は「半球」という意味のタイトルで、地球の裏側(南米)の地への想いを描いたもの。パウラ・モレレンバウムのバックボーカル、バカボン鈴木ベースと佐橋佳幸のギターが入っている。 最後の曲「A Day In The Park」(作詞 Vivian Sessoms)12曲目のみ他の曲と異なり、ニューヨークのニューソウル風の曲で、そういう意味で前作「Sweet Revenge」の雰囲気に近い曲だ。作詞・ボーカルも前作でフォーチャーされていた女性ヴィヴィアン・セソムズが担当している。 一般的には坂本がポップな曲を目指したアルバムと捉えられているが、実際はブラジル音楽の香りが色濃く出た深みのある作品と言ったほうがよい作品。 [2024年12月作成] [2026年1月追記] 本記事を書いた時は、「Tango (Version Castellano )」は大貫さんの作詞ではないとして、本ディスコグラフィーの対象外としていましたが、その後「Tango」の外国詞がいろいろあり、大貫さんの歌詞の精神がその源として残っていることから、方針を変更して対象とすることにしました。よって以下の通り追記します。 2. 「Tango」については、アルバムの海外発売分のみ最後の13曲目に3.「Tango (Version Castellano )」が収められている(「Castellano」はスペイン語という意味)。同じバッキング・トラックのリミックスにスペイン語のボーカルを載せたもので、スペイン系アメリカ人の歌手ソラヤ(1969-2006)が歌っている。インターネット上の一部の記事に「イタリア語」というものがあるが、それは誤り。 彼女はアメリカ・ニュージャージー州に生まれ、両親はコロンビアからの移住者で、「Soraya」は「プレアデス星団」 の意味。幼い頃から音楽に興味を持ち、ギターやバイオリンを弾き、高校時代から曲を書き始めた。才能を認められて1994年にレコード会社と契約し、1996年に「On Night Like This」でアルバム・デビュー。セカンド・アルバム「Wall Of Smiles/Torre de Marfil」1997にはキャロル・キングがゲスト出演している。 彼女の曲は全米100位以内にランクインすることはなかったが、アダルト・ポップ、ラテン・ポップ部門で評価が高く、特に後者ではグラミー賞を受賞する等、大変な人気を誇った。ただし、サウンド的には過度なラテン臭さはなく、ロックとアコースティックを使い分ける当時の先進的なシンガー・アンド・ソングライターの音作りだった。2000年のサードアルバム発売後、31歳の時にステージ3の乳がんと診断され、闘病しながら音楽活動を続け、2枚のアルバムを出したが、2006年に37歳の若さで亡くなった。母、祖母、母方の叔母も乳がんで亡くなったそうで、生前は乳がんに関する教育、注意喚起、支援運動にも力を注ぎ、「No One Else/Por ser quien soy」という病魔と戦う決意を歌った曲も書いている。 本曲はそんな彼女がデビューアルバム発表前に録音したもので、彼女のファンにとっては貴重なトラックになるだろう。彼女の声には透明感があり、中音域から高音域に移る際の声の裏返りの美しさが際立っている(シャキーラもこの手の裏声を使っていて、これはコロンビアの歌手、ラテン歌手の特技か?)。 スペイン語の歌詞を書いたラウル・カルノタ(1947-2014)はアルゼンチン・ブエノスアイレス生まれで、同国の民族音楽に大きな足跡を残したシンガー・ソングライターだった。本作の歌詞は彼がアメリカに移住していた時期に書かれたもので、1997年の本国帰国後にキャリアの黄金時代を迎えることになる。歌詞の和訳は以下のとおり(翻訳ソフトを使っているので、一部不正確な部分があるかもしれません)。 [Verse 1] 疲れを知らない太陽のように 私は叫ぶ 乾ききった冷たい砂漠を貫く道のように 私は感じる 情熱的に 狂乱するような方法で 私は探す この決定的な 障壁のない瞬間を そして あなたの不在と 空虚の厳しさに 私は苦しむ 世界をこの手につかみ そして失う あれはまるで空高く踊るタンゴのよう それはあなたにとって 別の束の間の愛の嘲笑に過ぎない [Pre-Chorus 1] 非現実的な旅 あなたのいない人生 [Chorus 1] なぜかわからない あなたを失っていることを知りながら 慰めを見つけることができない 待つことはどれほど難しいことか [Verse 2] そして私の視線は名もなき壁に迷い込む そしてあなたの姿は想像上の線 私を侵すエロチックな記憶 私の体は太陽に捧げる赤いバラの情熱 [Pre-Chorus 2] 夢は消え去った 愛の絵葉書 [Chorus 2] なぜかわからない あなたを失っていることを知りながら 慰めを見つけることができない 待つことはどれほど難しいことか この終わりのない旅路の中で [Bridge] 大切な色と香りを 私の体に留めている それらは私の体に残る そして私は私の川を 優しさの翼で あなたのがいた場所へ 温かい紙の船 [Verse 3] そして私の視線は名もなき壁に消え去る あなたの姿は想像上の線 私を侵すエロチックな記憶 私の体は太陽に捧げる赤いバラの情熱に開かれる [Pre-Chorus 3] 昨日の記憶 ついに美しく [Chorus 3] あなたの声は消え去った そして残響が私を悩ませる あなたの姿の隣で それは壁に溶けてゆく 新たな夜明けのきらめき 大貫さんの歌詞と比較すると、一部の語句を除き独自の言葉になっているが、原詞の精神はしっかり受け継がれている。そしてその内容から、1999年にオルネラ・ヴァノーニが歌った同曲のイタリア語版(サミュエル・ベルサーニ作詞)は、このスペイン語版を改変して書かれたものであることがわかる。このイタリア語版には作詞者によるセルフカバー(2000)の他に2017年のフランチェスカ・デ・モリのカバーがある。またモレレンバウム夫妻と坂本龍一によるユニット「Morelenbaum2/Sakamoto」のライブアルバム「Live In Tokyo」2001 およびスタジオ録音「A Day In New York」2003には奥様のパウラ・モレレンバウムが作詞したポルトガル語版があり、それもこのスペイン語版が基となっている。 ちなみに本曲については宣伝・ラジオ放送用のシングルが製作されていて、そこには3分24秒の「Radio Edit」と4分38秒のふたつのトラックが収められている。両者の違いは、Radio Editは「Pre-Chorus 1」、「Chorus 1」、「Verse 2」が編集でカットされている点だ。 後にブレイクする女性が歌った「Tango」のスペイン語版で、素晴らしい出来上がりだ。 |
|
| Piano Nightly 矢野顕子 (1995) Epic (Sony) | |
 |
2. 星の王子さま [作詞 大貫妙子 作曲編曲 矢野顕子] 2曲目 13. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子 編曲 矢野顕子] 13曲目 矢野顕子: Vocal, Piano 1995年10月21日発売 2. Hoshi No Oji Sama (Little Prince) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Akiko Yano] 2nd Track 13. Totsuzen No Okurimono (The Sudden Gift) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Akiko Yano] 13th Track by Akiko Yano from the album "Piano Nightly" on October 21, 1995 |
| 「Super Folk Song」1992に続く、矢野顕子ピアノ弾き語りシリーズの第2弾。彼女が大好きな曲のカバーとオリジナル1曲からなる。オーストリアの古城とロンドンのアビーロード・スタジオの2ヵ所で録音され、前作に増してピアノの音にこだわり、微妙なタッチや音の強弱のニュアンスが最高。かつボーカルも前作のような気負った感じがなくなって、ごく自然に自由に歌っている。その背景にはアルバム発表と出前コンサートで世間に認められたという裏付けがあるようだ。 2.「星の王子さま」は、1991年の朗読CD「音楽物語 星の王子さま」、同年の薬師丸ひろ子のアルバム「Primavera」収録曲のセルフカバー。ここでは「王さまも、うぬぼれも、実業屋も」という前者の歌詞で歌われている。しなやかで変幻自在のピアノと繊細なボーカルは曲の良さを一層際立たせている。13.「突然の贈りもの」は大貫さんのアルバム「Mignonne」1978収録曲のカバー。とても自由なピアノ演奏と歌唱で、彼女がこの曲を完全に自分のものにしていることがよくわかる。 ライナーノーツになる上記2曲についての本人コメント。 星の王子さま 「薬師丸ひろ子さんが歌った。しぶる大貫妙子に頼み込んで詞をつくってもらった。なぜなら矢野は「星の王子さま」を読んだことがなかったから。」 単に知らないから頼んだというよりも、この作品について詞を書くのが如何に大変かを知らずに頼んだというニュアンスだろう。 突然の贈り物 「大貫妙子の曲を歌うということは、彼女から彼女が一番気に入っている毛布を貸してもらうようなものだ。私にとって。よだれやにおいがついてしまうことがわかっていても貸してくれる。いつ歌ってもなつかしく、心があたたかくなる。」素晴らしい紹介文ですね.......。 他の曲について。どれも曲・演奏ともに素晴らしいので個別に書き難く、曲のオリジナルについてのみ述べます。 1. 虹が出たなら [作詞作曲 宮沢和史] The Boomの初アルバム「A Peacetime Boom」1989 2. 星の王子さま 3. 夏のまぼろし [作詞作曲 鈴木祥子] 鈴木祥子 「Long Long Way Home」1990 4. 思い出の散歩道 [作詞 松本隆 作曲 馬飼野俊一] アグネス・チャン「小さな日記」1974 5. What I Meant To Say [作詞 矢野顕子 作曲 Mike Stern] マイク・スターン「Is What It Is」1994収録のインスト曲に歌詞をつけたもの 6. フォロッタージュ氏の怪物狩り [作詞 友部正人 作曲 坂本龍一] 石川セリ 「Rakuen」1985 7. 椰子の実 [作詞 島崎藤村 作曲 大中寅二] 1900年発表の詞に1936年曲を付けたもの。初演・初録音は東海林太郎。 8. 愛について [作詞作曲 友部正人] 友部正人 「6月の雨の夜、チルチルミチルは」1987 9. 機関車 [作詞作曲 小坂忠] 小坂忠(2002年没) 「ありがとう」1971 10. 恋は桃色 [作詞作曲 細野晴臣] 細野晴臣 「Hosono House」1973 11. Daddy's Baby [作詞作曲 James Taylor] James Taylor 「Walking Man」1974 12. ニューヨーク・コンフィデンシャル [作詞 安井かずみ 作曲 加藤和彦] 加藤和彦(2009年没)「あの頃、マリー・ローランサン」1983 13. 突然の贈りもの 14. いつのまにか晴れ [作詞作曲 高野寛] 高野寛 「Ring」1989 15. New Song [作詞作曲 矢野顕子] オリジナル。本人コメント「広告の仕事のために書いたのだが、当初はある人のために最初のところが書きはじめられていた。そして今や、私のための曲となった。あなたに歌うために。」 タイトルの通り、夜部屋を暗くして聴くと心に浸みこんでくる音楽。「Super Folk Songs」に勝るとも劣らない名盤。 [2025年1月作成] |
|
| 1996年 「Tchou」 (1995/4/19発売) Lucy (1997/6/6) の頃 | |
| NHKみんなのうた 星空のオルゴール Various Kuko (1996) 日本コロンビア | |
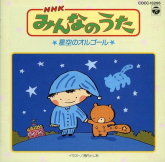 |
1. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 淡海悟郎] 16曲目 Kuko (野口郁子): Vocal 1996年4月20日発売 1. Metropolitan Museum [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Goro Omi] 16th Track sung by Kuko (Ikuko Nogchi) in various artists from the album "NHK Minna No Uta Hoshizora No Orugoal" (NHK Songs For Everybody Music Box Under The Starry Sky" on April 20, 1996 |
| 大貫さんの「メトロポリタン美術館」は 1984年4月〜5月にNHKテレビ「みんなのうた」で初回放送された。清水信之編曲による大貫さんの録音は、1984年5月21日発売のシングル「宇宙みつけた」のB面としてディアハート(RVC)
レーベルから発売され、1986年3月21日発売のアルバム「Comin' Soon」に収められた。「みんなのうた」の中でも特に人気がある曲で、映像はその後も現在に至るまで頻繁に再放送され、各レコード会社が発売した「みんなのうた」曲集にも収められている。その際契約の関係で大貫さんのオリジナルを使えない場合、別の歌い手により録音したものを使うのが通例で、そのため本曲は他のアーティストによるカバーに加えてこの手の別録音が多く存在することとなった。 いままでポニーキャニオン(吉田美智子)、東芝EMI(新居昭乃)、アポロン音楽工業(井上美哉子)、キング(新倉芳美)による録音を紹介してきたが、今回は日本コロンビアからのもの。本作は1996年と他に比べて発売年が遅めであるが、「NHKみんなのうた」のアルバムは当初録音したものをずっと使い回すのが普通なため、私が調べた限りでは同社からは本作が一番古かったが、本作より古いものが出ているかもしれない。 歌い手のKukoの本名は野口郁子で作詞家でもある。アニメ、ゲーム、CMでの作品が多く、特に「ドラゴンボールZ」における一連の歌が有名。また本人名義および Waffle、Liraというグループで活動していて、アルバムも出している。 1.「メトロポリタン美術館」のボーカルは、この手の音楽に最適な癖のない声。シンセサイザーによる演奏は原曲のアレンジに忠実な感じ。編曲者の淡海悟朗は大変幅広い分野をカバーした作曲家・編曲家、キーボード奏者で、日本のシンセサイザー・プログレの草分けと言われる人。 .「メトロポリタン美術館」の「NHKみんなのうた」選集用の録音は、これでひととおり出揃った感じ。これ以降のカバーは独自アレンジによるものになってゆく。 [2025年1月作成] |
|
| 食物連鎖 中谷美紀 (1996) gut (For Life) | |
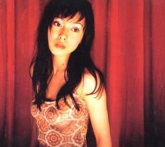 |
1. My Best Of Love [作詞作曲 大貫妙子 編曲 坂本龍一] 5曲目 中谷美紀: Vocal 坂本龍一: Keyboards, Programming, Producer 小倉博和: Guitar 広谷順子: Back Vocal 1996年9月4日発売 1. My Best Of Love [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Ryuichi Sakamoto] 5th Track by Miki Nakatani from the album "Shokumotsu Rensa (Food Chain)" on September 4, 1996 |
| アイドル・グループを卒業した中谷美紀(1976- 当時20歳)が、フォーライフ・レコード内の坂本龍一のレーベルGut(グート)から出した初アルバムで、坂本がプロデュースと半分の作曲・大半の編曲を担当している。坂本のアルバム「Smoochy」1995の「愛してる、愛してない」(大貫さん作詞)でゲストで歌った事がきっかけだったのだろうか?相性の良い歌手を得て「Smoochy」で目指したポップ路線を前に推し進めている。通常この手のアルバムは制作者が前面に出て、歌い手は意思のない操り人形のようになってしまうのだが、本作での中谷には強い自我が感じられる。ただしそれは坂本の創造を阻害するものではなく、同志として共鳴しているようだ。そして彼女は単なる歌い手ではなく、坂本の音楽上のパートナーとなり、その関係は本作を含む3枚のアルバムに昇華してゆく。後に女優として歩んでゆくキャリアをみても、彼女が理知的で強靭な精神の持ち主であることがわかる
(発売当時でなく、現在の視点からみた印象だからかもしれないけど.....)。 坂本のダークでミステリアスな音楽のなかで、大貫さんが作詞作曲した 1.「My Best Of Love」は比較的ポップな曲で、アルバムに彩りを添えている。サウンドの大半は坂本による打ち込みで、バックボーカルは自己のアルバムやシングルを出しながらスタジオ・ミュージシャンとして鳴らした広谷順子(1956-2020)。なお本曲は1997年に発売された中谷のライブ映像作品「Butterfish」でも歌われている。 他の曲について。全10曲中5曲で売野雅勇が作詞を担当していて、「Mind Circus」、「Strange Paradise」、「汚れた脚 The Silence Of Innocence」、「Where The River Flows」(いずれも作曲編曲 坂本龍一)1・2・4・6曲目 での鋭い言葉が並ぶ歌詞は坂本のメロディーと互角に対峙している。そして森俊彦の打ち込みによるヒップポップ風のリズムが内向的な曲・歌詞と歌唱に不思議にマッチしていて、深みが感じられる出来上がりになっている。なお「Mind Circus」は同年中谷が主役の一人を演じたテレビドラマ「俺たちに気をつけろ」の挿入歌、「Strange Paradise」は伊藤園「おーいお茶」のCMで使用された。 「逢びきの森で」(作詞作曲編曲 小西康陽)3曲目はアルバム中異色の曲で、いかにもピチカート・ファイブが好みそうな洒落たジャズ・チューンに仕上がった。「色彩の中へ」(作詞 高野寛 作曲 ヴィニシウス・カントゥアリア 編曲 坂本龍一)8曲目は、ムーディーなボサボヴァで、作曲者は大貫さんのアルバム「Lucy」1997や「東京日和」1997に坂本と一緒に参加している人。「Lunar Fever」 (作詞 高野寛 作曲編曲 森俊彦)は本作唯一のR&Bっぽい曲。中谷のクールなボーカルはとても雰囲気が出ていて、こんな曲も歌えるなんて意外だ。最後の曲「Sorriso Escuro」(作詞作曲 アート・リンゼイ、ヴィニシウス・カントゥアリア 日本語歌詞 売野雅勇)は、英訳すると「Dark Smile」という意味で、アート・リンゼイも坂本と親しく、大貫さんの「Lucy」1997に参加した人。ブラジル風の漂うような音楽を背景にわざと聴き取りにくくしたポルトガル語と日本語の語りが入った曲で、聴いた後に不思議な余韻が残る。 中谷・坂本コラボ3部作の1作目で、坂本がやりかった音楽を伸び伸びと展開している。 [2024年12月作成] |
|
| イレイザーヘッド 竹中直人 (1996) Consipio | |
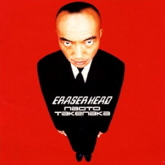 |
1. 二人の星をさがそう [作詞作曲 大貫妙子 編曲 ] 7曲目 竹中直人: Vocal 高橋幸宏: Back Vocal 岸利至: Synthesizer 高橋幸宏: Producer 1996年10月18日発売 1. Futari No Hoshi Wo Sagasou (Let's Search For Our Star) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Toshiyuki Kishi] 7th track by Naoto Takenaka from the album "Eraser Head" on Ocober 18, 1996 |
| 「Eraser Head」は鉛筆の頭についている消しゴムの意味で、デビッド・リンチ監督の1977年の映画タイトルでもある。ここでは表紙写真から竹中の頭部の恰好を揶揄したタイトルのようだ。竹中が主役に抜擢され大評判をとった大河ドラマ「秀吉」放送中の人気絶頂期に制作・発売されたアルバムで、前作「Merci-Boku」1995と同様、コントやギャグが入っているが、前回よりも音楽の割合が多くなっていて、真面目に歌っている曲もある。 大貫さんは前回に続き楽曲を提供。1.「二人の星をさがそう」は歌詞の中に多くの星座が散りばめられたファンタスティックな歌で、アルバムの中で郡を抜いて良い出来。「僕の好きなおひざ 君の好きなピザ ビールにらっかせい もっと ぎょうざ」という言葉の遊びが楽しい。シンセ演奏と編曲を担当した岸利至(1969- )は坂本龍一のシンセサイザー・オペレーターとしてデビューし、YMOやピチカート・ファイブをはじめとする数多くのミュージシャンの作品の演奏、作曲・編曲、リミックス、プロデュースに関わった人。大貫さんはずっと後の2022年にこの曲をセルフカバーしている。彼女にとって「One Fine Day」2005年 以来久々の新曲録音で、「朝のパレット」とのカップリングで2月25日に発売された。録音に際して大貫は高橋幸宏の参加を希望し、2020年の脳腫瘍の手術後の静養が十分になるまで1年半待ったという。そして2021年10月27日の収録におけるドラム演奏が彼の最後のレコーディング参加となった(2023年1月11日没)。 その他の曲では「国分寺1976」が素晴らしい。竹中は曲名の年に当地に住んでいたようで、当時同じ中央沿線に住んだ経験から「中央線」という名曲を書いたThe Boomの宮沢和史に頼んでこの曲を作ってもらったらしい(このことは東京経済大学地域連携センターが制作した記事「『国分時1976』をめぐって」という素晴らしい記事があるので、一読をお勧めします)。曲を聴いているとアコースティックなサウンドの中に70年代当時の空気感が見事に再現されていて、当時大活躍した駒沢裕城のペダルスティールが心に染みる。竹中はいつもふざけているけど、こんな風にも歌えるんだ......。余談であるが、先日六角精児のコンサートを観るために国分寺を訪れたが、再開発された駅前は妙に洒落た感じになっていて、当時の面影を偲ぶ余地もないようだ。 あとハードロック調の「心配御無用」(作詞 竹中直人 作曲編曲 岸利至)2曲目、ボサノヴァの「おいしい水」(といってもジョビンの曲ではない)(作詞 竹中直人 作曲編曲 高橋幸宏)3曲目、ハワイアンの「ピカケに口づけ」(「ピカケ」はハワイの花)(作詞 竹中直人 作曲 竹中直人、岸利至 編曲 岸利至)4曲目、玉置浩二が作曲した「くれない東京」(作詞 森雪之丞 編曲 川中茂則)5曲目。コミカルな歌では「ヘルレイザー (低音三兄弟)」(作詞 竹中直人 作曲編曲 岸利至)9曲目の竹中、細野晴臣、青木達之(スカパラダイスオーケストラ)の低音ボーカルが最高。そして最後の曲不吉(作詞 竹中直人 作曲 竹中直人、岸利至 編曲 岸利至)11曲目が終わった後、前作でお馴染み流しのチャーリ・ボブ彦が出てきてさらっと歌ってアルバムを終える。 音楽アルバムとして十分に面白い作品。「ふたりの星をさがそう」大貫さんがセルフカバーしたけど、原曲もとてもいいよ! [2025年1月作成] |
|
| Living With Joy 高橋洋子 (1996) Kitty | |
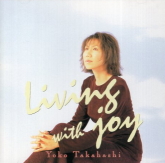  |
1. 新しいシャツ [作詞作曲 大貫妙子 編曲 森俊之] 1曲目 高橋洋子: Vocal 森俊之: Keyboards, Programming 古川昌義: Guitar 細木隆宏: Bass 百々政幸: Manipulation 1996年10月25日発売 アルバム「Living With Joy」 1996年10月2日発売 シングル 1. Atarashii Shatsu (New Shirt) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Toshiyuki Mori] 1st Track by Yoko Takahashi from the album "Living With Joy" on October 25, 1996 |
高橋洋子(1966- )は東京都出身。1987年久保田利伸のバックコーラスとしてプロデビューし、CMソングやサウンドトラックなどのセッション・シンガーとして活躍、1991年にテレビ番組主題歌・挿入歌でソロデビューを果たしている。大変歌が上手い人で、特にバラードにおける繊細な表現力は抜群。そんな彼女が一躍有名になったのは、1995年のテレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のエンディングテーマ「Fly Me To The Moon」、および主題歌「残酷な天使のテーゼ」を歌ってからで、特に後者はこの分野で高い人気を誇る名曲となった。「Living With Joy」はその1年後に発表された彼女5枚目のアルバムで、本人による作詞作曲はなく、11曲中書き下ろしが4曲、残りが既存曲のカバーという構成。 1.「新しいシャツ」(アルバム「Romantique」1980 収録)は名曲と思うが、他のアーティストが取り上げたケースは意外と少ない。大貫さんの歌唱と坂本龍一のアレンジによるイメージがあまりに鮮烈で、それに新しい風を吹き込むことが難しいからだろう。本曲は原曲から16年後に制作された初めてのカバーとなる。オリジナルがスローなバラードだったのに対し、ここでは森俊之のアレンジによってリズミカルでよりポップなサウンドとなっている。特にグルーヴィーなベースラインはみっけものだ。それでも曲が持つしっとりした雰囲気を失っていないのは、ひとえに高橋のニュアンスに富んだ歌唱力にあると思う。ちなみに本曲はTBS系テレビ番組「山田邦子の幸せにしてよ」のエンディング・テーマとして使用され、アルバムに先行してシングルでも発売された。 他のカバー曲について。「Ooo Baby Baby」(作詞作曲 Smokey Robinson, Warren Moore 日本語歌詞 田久保真見 編曲 森 俊之)3曲目は、スモーキー・ロビンソンが在籍したザ・ミラクルズ1965年のヒット(全米16位)、リンダ・ロンシュタットのカバー(1978年 同7位)に日本語の歌詞を付けたもので、高橋はソウルフルに歌い上げていて、様々なスタイルに適用できる器用さを示している。「Hello Winter〜Do Space Men Pass Dead Souls On Their Way To Thr Moon?」(作詞 Traditional, Linda Grossman, 日本語歌詞 並河祥太 作曲 Traditional, John Sebastian Bach 編曲 大森俊之)4曲目は、アート・ガーファンクルの初ソロアルバム「Angel Clair」1973収録曲のカバーで、ハイチ民謡の「Hello Winter(原曲タイトルは「Feuilles-oh (葉っぱ)」)はもとはフランス語(厳密にはハイチ・クリオール語)の歌詞に日本語歌詞を付けている。「Do Space Men Pass Dead Souls On Their Way To Thr Moon?」は当時アートの奥さんだったリンダ・グロスマンがバッハ作「クリスマス・オラトリオ」のなかの1曲に歌詞をつけたもの。中米音楽とバロックのメドレーという面白い構成の曲だ。「つめたい部屋の世界地図」(作詞作曲 井上陽水 編曲 大森俊之)5曲目は井上陽水1972年(アルバム「陽水II センチメンタル」収録)のカバー。「めぐり逢い」(作詞 並河祥太 作曲 Andre Gagnon 編曲 大森俊之)7曲目はカナダ人アンドレ・ギャニオンの1983年インストルメンタル曲に日本語歌詞をつけたもの。フジテレビ系TVドラマ「Age, 35 恋しくて」のテーマソングに採用された。「シャンプー」(作詞 康珍化 作曲 山下達郎 編曲 森俊之)9曲目は、アン・ルイス1979年(アルバム「Pink Pussy Cat」収録)がオリジナル。山下達郎編曲・プロデュースの原曲も最高だったけど、ここでのカバーも凄いね。ボーナス・トラック「Fly Me To The Moon〜Night In Indigo Blue Version」(作詞作曲 Bart Howard 編曲 大森俊之)はアメリカン・スタンダードソング(私はジュリー・ロンドンの1963年バージョンが好き)のカバーであるが、上述の「新世紀エヴァンゲリオン」とは別録音のニューウェイブ風アレンジだ。 オリジナル曲では「ウェンディーの瞳」(作詞 並河祥太 作曲 松本俊明 編曲 鳥山雄司)6曲目が一番。テレビ東京系テレビ番組「情報レストラン」エンディングテーマに使用された曲で、幼い頃の純な心を失わないでという歌詞とメロディーがファンタスティックで、彼女の声質・キャラクターにピッタリ。「ウェンディー」は「ピーターパン」に出てくる女の子のことなんだろうな〜。その他のオリジナル曲も前向きな内容で、聴いていると心が洗われる感じがする。 カバー曲とオリジナル曲がうまく噛み合って、彼女の持ち味がとても生かされた作品になっていると思う。新鮮なアレンジによる大貫さんの「新しいシャツ」も聴きもの。 [2024年11月作成] |
|
| 1997年 Lucy (1997/6/6) の頃 | |
| Butterfish 中谷美紀 (1997) For Life | |
 |
1. My Best Of Love [作詞作曲 大貫妙子] 4曲目(映像) 2. 愛してる、愛してない [作詞 大貫妙子 作曲 坂本龍一] 7曲目(映像) 中谷美紀: Vocal 小森茂生, 大島俊一: Keyboards Ebby: Guitar 宇多川博史: Bass 小島徹也: Drums 録音: 1997年2月26日・27日 渋谷 Club Quattro 発売: 1997年5月21日(VHSビデオテープ)、2000年10月18日(DVD) 1. My Best Of Love [Words & Music: Taeko Onuki] 4th Track 2. Aishiteru, Aishitenai (I Love, I Don't Love) [Words: Taeko Onuki, Music: Ryuichi Sakamoto] 7th Track by Miki Nakatani from the video "Butterfish" recorded on Febuary 2 and 27,1997 at Qlub Quattro Shibuya Tokyo, released on May 21,1997 |
アルバム「食物連鎖」1996 リリースの約半年後に行われたライブの映像作品。タイトル「Butterfish」は北西大西洋にいるマナガツオ科の魚のことで、日本でとれるエボダイ、ハワイの銀鱈の英語名でもある。VHSビデオテープと(恐らく)レーザーディスクは1997年5月、DVDは2000年10月に発売された。会場のクラブ・クアトロは、渋谷のセンター街近くにあるパルコが運営する収容人員800人のライブハウス。イントロは「食物連鎖」1996 収録の「sorrio escuro」が使用され、ジャケットにある目の超アップから始まり、中谷の全身・身体の一部をサーモグラフィー、X線、CT・MRIなど様々な方法で撮影した映像が写る。その映像の中にはオーディエンスの頭部が写り込んでいるものもあるので、ライブ当日に会場でも映し出されたもののようだ。 イントロが終わると、画面がステージに切り替わって「Strange Paradise」が始まる。バックを務めるミュージシャンは当時中堅クラスの人たちで、ソロパートを除き坂本龍一の編曲に忠実な演奏になっている。コーラス・パートで中谷と一緒に歌うハーモニーが聞こえるが、コーラス担当の人はステージにいないので、どうやっているのかな? ① 自動でコーラスを付けるエフェクターを使用(当時そんな機材があった?) ② 予め録音したコーラスパートを演奏に合わせて流す ③ ステージでは単独だったが、ビデオ製作時にオーバーダビングした のいずれかだね。間奏でのエレキピアノ・ソロは大島俊一。ギターのEbbyはファンク・ロック・バンド、ジャガタラのオリジナル・メンバーだった人で、ステージではアコギ・エレキともにグレッチのギターのみで決めているのが印象的。曲後のオーディエンスの拍手・歓声や中谷のアナウンスは最低限で、曲間は前述の中谷の姿、波や水、植物組織や細胞などのイメージ映像が流れる構成。「汚れた脚 The Silence Of Innnocence」と坂本作品が続く。照明やカメラのカット割りなどかなり凝った造りだ。中谷はショートカット・ヘアーで現在とはイメージが異なるが、自信に満ちた眼差しは変わらずエレガントな雰囲気を漂わせている。 1.「My Best Of Love」は照明が明るくなり、中谷もにこやかに歌っている。一転して「Whrere The River Flows」は意図的な白黒画像処理になっていて、モノクロームの良さが感じられる。 「逢びきの森で」のみ坂本の作ではないジャズ曲で、間奏のアルトサックス・ソロは大島俊一。彼はキーボード奏者でありながら、サックスも吹けるマルチ・プレイヤーとして有名な人だ。かなり達者なピアノ・ソロを聞かせる小森茂生は、後に作曲・編曲家、プロデューサーとしても大成する人。ここからの曲間の映像は単語の羅列とそれを素早く読み上げる中谷のモノローグとなる。「安心 無色 男の子 水色 女の子 ピンク色 色分けされた性別 不思議 誘導される ジェンダー」という語りの後の 2.「愛してる、愛してない」はきりっとした演奏・歌唱。「Mind Circus」はコンサートの山場的なパフォーマンス。 これまでの曲はすべて「食物連鎖」からだったが、最後の曲「砂の果実」のみコンサートの時点では未発表の新曲で、約1ヵ月後の3月21日に発売されたシングル曲(その後アルバム「cure」に収録)、本ビデオが発売された5月にはヒット中だったはず。本曲のみ中谷の衣装が異なっていて、撮影も異なる感じになっている。しかしステージのセッティングは同じで、曲が終わった後に拍手が起きるので、本ライブが同じ場所で2日間に渡り行われたという記録から、本曲は他とは異なる日に撮影されたものだろう。 中谷の若々しい姿が拝めるが、現在の凛とした佇まいは当時から変わっていないようだ。 [2025年1月作成] |
|
| 不意打ち 宮村優子 (1997) Victor | |
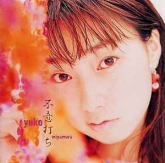 |
1. 彼と彼女のソネット [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 Taeko Onuki 編曲 保刈久明] 9曲目 宮村優子: Vocal 保刈久明: Computer Programming, Guitar 坂元俊介: Computer Operation 宗秀治: Bass 堀越信泰: Chorus 1997年9月22日発売 1. Kare To Kanojo No Sonnet (His And Her Sonnet) [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Creole] 9th Track by Yuko Miyamura from the album "Fuiuchi" (Sucker Punch) September 22, 1997 |
| 宮村優子(1972- )は兵庫県出身の声優、女優、歌手。当初演劇を志したが、大学の頃からゲーム、アニメーション声優の仕事を始める。1995年「新世紀エヴァンゲリオン」惣流・アスカ・ラングレー役、1996年「名探偵コナン」遠山和葉役が有名。そんな彼女が1995年から1999年までの4年間、歌手として4枚のアルバムを出していて、本作はその2枚目にあたる。音程が不安定になる箇所があるなど決して上手くはないけど、声優としてのヴォイス・コントロール能力や声質の魅力を最大限に発揮している。 1.「彼と彼女のソネット」は打ち込み主体のサウンドをバックに、他の曲に比べてより神妙に歌っている。「こんなに近くにいて あなたが遠のいて行く 足音を聞いている」というパートが入っているので、原田知世版の歌詞だ。 他の曲について。「Pi・Pi・Pi」(作詞 高井健 作曲 Love Palette 編曲 米光亮)1曲目は、ファンタスティックな歌詞とメロディーの曲で、彼女のアニメ・ヴォイスの魅力炸裂の佳曲。ユーモラスな「平成偉人伝」(作詞 青島雪男 作曲 関口和之 編曲 高浪啓太郎)2曲目の作詞者は、サザンオールスターズのベース奏者関口和之の変名。英語歌「Skindo-Le-Le」(作詞 C. Amaral 作曲 J. Wagner 編曲 保刈久明)3曲目は、ブラジルのフュージョン・グループViva Brasil 1980年がオリジナルで、日本では1981年の阿川泰子(アルバム「Sunlight」収録)が有名。アメリカでは1983年Aliveのカバーが1990年代のクラブで人気が出た曲だ。宮村はこの難しい曲をちょっとエキセントリック(本人はいたって真面目だけど)に歌っており、それなりに魅力がある。 「Un Nicodeme II〜まぬけなおじさん」(作詞 北田かおる)7曲目は鈴木慶一が作曲編曲、コンピューター・プログラミングで参加。「ハワイ旅情」(作詞 みやむらゆうこ 作曲編曲 周防義和)12曲目、「だいじょうぶの笑顔」(作詞作曲 Love Palette 編曲 安部隆雄)13曲目は打ち込み主体のアルバムの中でのアコースティックな演奏が新鮮。後者では駒沢裕城のペダル・スティール・ギターを楽しめる。その他ここでは紹介しなかったが、彼女のキャラに合ったマンガタッチの面白い曲が多く入っている。 彼女は現在も活躍中。2019年配信のトヨタホームWEB CMのYouTube動画で、6秒以内に長文の宣伝文を読み切るという超難関の早口言葉に挑戦しており、その神業は圧巻! 声優のコケティッシュ・ヴォイスによる.「彼と彼女のソネット」。 [2024年12月作成] |
|
| Cure 中谷美紀 (1997) gut (For Life) | |
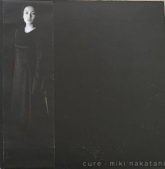 |
1. corpo e alma [作詞 大貫妙子 ポルトガル語訳詩 加々美ヘレナ 作曲編曲 坂本龍一] 8曲目 中谷美紀: Vocal 坂本龍一: Keyboards, Computer Programming, Producer 佐橋佳幸: Guitar 加々美淳 Samba Project II, Fumi Miyagi : Percussion, Back Vocal 1997年9月26日発売 1. corpo e alma (Body And Soul) [Words: Taeko Onuki, Portuguese Translation: Helena Kagami, Music & Arr: Ryuichi Sakamoto] 8th Track by Miki Nakatani from the album "Cure"on September 26, 1997 |
| 中谷と坂本のコラボ3部作の2番目のアルバム。前作では一部の曲で他人による作曲・編曲があったが、本作では1曲を除くすべての作曲と全部の編曲を坂本が担当している。自己レーベルでの制作かつ自身のプロデュースということで、彼が自分の裁量で自由に創ったという感じの作品だ。だからと言って中谷は坂本のアバターではなく、しっかり自分を出しており、両者の一体感が前作よりも深化しているようだ。 全体的にダークなムードが強いアルバムの中で、大貫さんが歌詞を書いた最後の曲 1.「corpo e alma」(ポルトガル語で「身も心も」という意味)は解放感があるサンバ・チューン。坂本のブラジル音楽嗜好が全開で、彼が作ったブラジル音楽風楽曲の中でベストの出来上がりになっている。大貫さんの歌詞も素晴らしく、彼女にしては珍しい官能的な内容であるが、それでも彼女らしい清冽さがしっかり保たれているのはさすが。パーカッションを担当している加々美淳は、現在ブラジル音楽のギタリスト、シンガーとして活躍、Fumi Miyagi はインターネットで資料が見つからなかったので、オリジナルの英語表記のままとした。なおクレジットには訳詞者の名前が載っているが、聴いた限りポル語の歌詞は聞き取れなかった。なお同年11月に発売されたリミックス・アルバム「Vague」に同曲の「Snooze Mix」が収められていて、そこでは大貫さんの歌詞は歌われていないけど、熱帯地方に降るスコールのようなサウンドになっていて面白い。 他の曲について。「いばらの冠」(作詞 松本隆)1曲目は、9月3日に先行発売された中谷5枚目のシングル。バッファリン(薬)のCMとフジテレビ系のバラエティ深夜番組「未来圏」で使用された。松本隆としては暗い感じの歌詞を歌う中谷の表現力が前作より増した感じがする。なお曲名に「Album Version」と付されているが、シングルと録音は同じで、アルバムのエンディングの演奏が30秒ほど長くなっているのが相違点。「天国より野蛮 〜Wilder Than Heaven〜」(作詞 売野雅勇)2曲目は5月21日発売の4枚目のシングルで、伊藤園「お〜いお茶」のCMに使用された。「砂の果実」(作詞 売野雅勇) 3曲目は3月21日に発売されたシングルで「中谷美紀 With 坂本龍一」の名義で発売された。この曲は約2ヵ月前の1月29日「坂本龍一 With Sister M」 (後にSister M は娘の坂本美雨と判明)の名義で発売されたシングル「The Other Side Of Love」(日本テレビ系ドラマ「ストーカー 逃げきれぬ愛」主題歌)の英語歌詞を別内容の日本語にしたもの。メランコリックな歌詞とメロディーの曲であるが、中谷にとって最大のヒット(オリコン10位)となった。坂本が挑戦したポップソングの到達点といえよう。「鳥籠の宇宙」 5曲目は中谷本人の作詞で、「いばらの冠」シングルのカップリングだった曲。「Superstar」(作詞 Bonnie Bramlett 作曲 Leon Russell)はカーペンターズ1969年のヒット曲(全米2位)のカバーであるが、原曲のコード進行を無視して、著しくダークな編曲を施している。 なお本CDは2枚組になっていて、2枚目は坂本作曲によるアンビエント・ミュージックのインストルメンタル「Aromascape」が収められていて、聴くとリラックスできるような音楽になっている。女性歌手のアルバムに、このようなCDを付けることが、このアルバムにおける坂本の立ち位置を象徴している。 「corpo e alma」は坂本流サンバの傑作といえる。 [2025年1月作成] |
|
| 君の住む街にとんで行きたい/街 比屋定篤子 (1997) Mint Age (Sony) | |
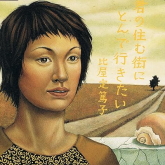 |
1. 街 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 菅原弘明] シングル・カップリング 比屋定篤子:Vocal 菅原弘明: Guitar, Keyboards, Synthesizer, Percussion 名村武: Bass 寺谷誠一: Drums 浜口茂外也: Percussion 菅原弘明、小林治郎: Sound Producer 1977年10月22日発売 |
| 比屋定篤子(1971- ) は沖縄県那覇市出身。ブラジル音楽に傾倒し、東京の美術大学在学中にラテン・アメリカ研究会でボサノヴァを演奏。1994年に音楽上のパートナーとなる小林治郎と出会い、オリジナル作品による本格的な音楽活動を始め、ソニーの新人育成部門に認められて1997年6月「今宵このまま」のシングルでデビューした。「君の住む街にとんでゆきたい」(作詞
比屋定篤子 作曲 小林治郎 編曲 菅原弘明、小林治郎)はその4ヵ月後に発売された2枚目のシングルになる。彼女のディスコグラフィー(https://www.artenia.co.jp/sspe/sub44.html)
で、彼女は本曲につき「小林との共作出発曲。初めて私の詞にメロディーがついて、とても嬉しかった。オリジナルを作る喜びを教えてくれた歌なのです」とコメントしている。デビュー曲がサンバ風だったのに対し本曲は3拍子のスローな曲。しかし「沖縄のサウダージ・ヴォイス」(サウダージ
= 郷愁、憧憬、思慕、切なさ)と呼ばれるブラジル風なノンヴィブラートのクールな歌唱は、他の日本のフォーク歌手とは趣が異なるのが魅力。駒沢裕城のペダルスティールもいい感じで鳴っている。またシングルの3曲目に入っている「君の住む街にとんでゆきたい パラディゾ・バージョン」のバンジョ−を主体とした演奏もなかなか良い。
カップリングとして選ばれたのが、彼女が好きな大貫妙子の1.「街」 (大貫さんのアルバム「Grey Skies」1976収録)。オリジナルは細野晴臣のアレンジだったが、ここで編曲を担当した菅原弘明(1960- )は、坂本龍一や高橋幸宏のシンセイザー・プログラマーとしてキャリアをスタートし、その後キーボード奏者、作曲家、編曲家として活躍した人で、細野とは異なる独自のボサノヴァ・サウンドに仕立て上げている。 その後もアルバムやシングルを出したが、当時はあまり売れず、2001年の結婚を機会に沖縄に移り、当地で音楽活動を続ける。そして2000年代後半にクニモンド滝口に招かれて、1998年の名曲「まわれまわれ」の再録音を含む「流線形と比屋定篤子」名義でアルバム「Natural Woman」2009が発売され、再評価の機運が高まって新作の発表および 2016年には本シングル曲を含むベスト盤「昨日と違う今日〜比屋定篤子ベスト&レア」が発売された。 なお比屋定による大貫さん作品のカバーは、他にアルバム「Sunshower」1977 収録の「何もいらない」がある(前述の「Natural Woman」2009に収録)。 ブラジル音楽を愛するシンガーによる「街」のカバー。 [2025年1月作成] |
|
| 1998年 Lucy (1997/6/6) 、 Attraction (1999/2/24) の頃 | |
| 恋人達の明日/昨日、今日、明日 大石恵 (1998) Ki/oon (Sony) | |
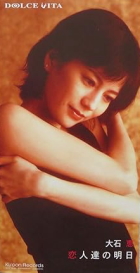 |
1. 恋人たちの明日 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 長谷川智樹] シングル曲 2. 昨日、今日、明日 [作詞 大貫妙子 作曲 Johannes Brahms 編曲 長谷川智樹] カップリング 大石恵: Vocal 1998年7月1日発売 1. Koibito Tachi No Ashita (Lover's Tomorrow) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Tomoki Hasegawa] Single 2. Kinou, Kyou, Ashita (Yesterday, Today, Tomorrow) [Words: Taeko Onuki, Music: Johannes Brahms, Arr: omoki Hasegawa] Coupling by Megumi Oishi from the single on July 1, 1998 |
| 大石恵(1973- 東京都出身)は、高校生はフィギュアスケートの選手で、短大在学中にスカウトされ芸能界に入る。1994年にテレビ朝日「ニュースステーション」のお天気お姉さんとしてデビューしその美貌が評判となる。番組卒業後は女優、タレントとしてテレビドラマ、バラエティ番組、CM等で活躍したが、2000年にL'Arc〜en〜Cielのhydeと結婚して活動休止。2006年〜2007年にキャスターとして復帰したがその後は引退状態となった。 彼女は1998年に歌手デビューして3枚のシングル・ミニアルバムを出していて、本作はその1枚目になる(レーベル名「Ki/oon」は「キューン」と発音するそうだ)。1.「恋人たちの明日」は大貫さんのアルバム「Aventure」1981のカバー。過去に増田恵子(1982)、白石まるみ(1983)、堀江美都子(1984)がカバーしているが、本作はオリジナルのテクノポップと全く異なるボサノバアレンジになっている。アイデア自体は悪くないし、白石の綺麗な声を生かそうとする意図もわかるし、聴いててそれなりに気持ちが良いんだけど、ちょっと線が細いかなという気もする。 それに対してカップリングの 2.「昨日、今日、明日」は彼女のささやき系ヴォイスが上手くはまっていて、いい感じに仕上がっている。原曲はクラシックのブラームス作曲交響曲第3盤第3楽章ポコ・アレグレットのメロディーだ。それをポピュラー音楽にアレンジした最初は、1959年のフランス映画「Aimez-vous Brahms? (邦題 さよならをもう一度)」(フランソワーズ・サガンの小説を映画化したもの)で、主演のイブ・モンタンが「Quand Tu Dors Pres De Moi」(日本語で「貴女が眠るとき」)のタイトルで歌ったもの。同映画に出演していたアンソニー・パーキンス(ヒチコックの名画「サイコ」1960で有名な俳優)や歌手のダリダも歌っている。同曲はその後多くの人にカバーされたが、特筆すべきはセルジュ・ゲンスブールのプロデュースによるジェーン・バーキンの「Baby Alone In Babylone (バビロンの妖精)」1983で、新しい歌詞による独自の世界を築いている。本作も独自の日本語歌詞になっているが、このヴァージョンからインスピレーションを受けているのは明らか。大貫さんは1999年のアルバム「Attraction」でセルフカバーしている。 なおヴィジュアルで売り出した人だけあって、本シングルの発売前の5月21日に上記2曲のミュージック・ビデオを収めたDVDも発売されている。その後本人名義のアルバムは制作されなかたため、当該シングルのみで入手可能な曲となった。 [2025年1月作成] |
|
| Rain -陽のあたる場所- /秋はひとりぼっち/月の舟 大石恵 (1998) Ki/oon (Sony) | |
 |
1. Rain −陽のあたる場所- [作詞作曲 大貫妙子 編曲 長谷川智樹] シングル 大石恵: Vocal 1998年10月21日発売 1. Rain (A Olace In The Sun) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Tomoki Hasegawa] by Megumi Oishi from the single on October 21, 1998 |
| 前作の3ヵ月後に発売された2枚目のシングルで、前作が8cm盤だったのに対し、本作は12cm盤で発売された。1.「Rain −陽のあたる場所-
」は大貫さんの書き下ろし。シャッフルのリズムによる明るい曲で、大石のムードにぴったりの佳曲に仕上がった。大貫さんがアルバム「Lucy」1997年に収めた曲とは同名異曲。誰かがカバーしてもよさそうなんだけど、本曲を聴くことができるのは当該シングルのみだ。 その他の曲が面白い。秋はひとぼっち[作詞作曲 G. Osborne, P.Vigrass, J. Wayne 日本語訳 山上路夫 編曲 長谷川智樹] 2曲目は、イギリスのヴィグラスとオズボーンの二人組が出したシングル「Forever Autumn (秋はひとりぼっち)」1972が原曲。ただし彼らのシングルは英米いずれもチャートインせず、日本でのみのヒットとなった。そして英米では、そのかわりにムーディー・ブルースのジャズティン・ヘイワードが歌ったカバー1978年が全米47位 全英5位の大ヒットとなった。大石のカバーはその20年後ということで、シンセサイザーで埋め尽くされたサウンドとリズムはいかにも1990年代といった感じだ。この曲を持ってきて大石に歌わせたプロデューサーのセンスに敬意を表したい。「月の舟」(作詞 長谷川智樹、大津美紀 作曲編曲 長谷川智樹)3曲目はアコースティックなサウンドが素敵な曲だ。 大石はその後1999年にもう1枚シングル(4曲入りミニアルバム)を出していて、大貫さんとの関わりはないけど、ムーンライダースのかしぶち哲郎がプロデュースしているだけあって、これも面白い作品になっている。 大貫さんの知られざる佳曲。 [2025年1月作成] |
|
| Listen To The Music 槇原敬之 (1998) Sony Music | |
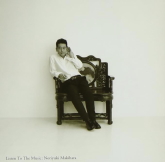  |
2. 海と少年 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 槇原敬之] 2曲目 槇原敬之: Vocal, Back Vocal, Keyboards 橋本茂樹: Synthesist 小倉博和: Guitar 槇原敬之: Producer 1998年10月28日発売 写真下: 初回発売分に付いたCDケース・カバー 2. Umi To Shonen (The Sea And The Boy) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Noriyuki Makihara] 2nd Track by Noriyuki Makihara from the album "Listen To The Music" on October 28, 1998 |
| 槇原敬之(1969- 大阪府出身)が1998年に出した9枚目のアルバムで、初のカバー作品集。ジャンルや知名度などおかまいなしに、好きな曲を選んで、自らのプロデュース・編曲で作りあげ、持前のハイトーン・ヴォイスで女性歌手やオフコースの曲を歌いこなしている。 2.「海と少年」は大貫さんのアルバム「Mignonne」1978収録曲からで、1986年の矢野顕子に次ぐ2番目のカバー。原曲よりもグルーヴを効かせた槇原らしいポップなサウンドが心地良い。 ちなみに翌年1999年6月20日放送の音楽番組「ミュージック・フェア」で槇原敬之、矢野顕子、大貫さんの共演が実現し、本曲、「ピーターラビットと私」、矢野の「David」(本アルバム収録)を3人で代わる代わる歌う映像が残っている(当該番組では、その他に各自ソロで槇原「Hungry Spider」、矢野「ひとりぼっちはやめた」、大貫さん「四季」を歌ったそうだ)。 その他の曲について。 全曲につき編曲 槇原敬之 1. 蒼い月の夜〜Lady In Blue〜[作詞作曲 Lou] 1994: 1991年〜1992年に活動したバンド「Lazy Lou's Boogie」のボーカリスト Louが出した3枚目のシングル「泣いたり笑ったり忙しい君に」のB面曲。 2. 海と少年 3. 秋の気配 [作詞作曲 小田和正] 1977: オフコース11枚目のシングルで、アルバム「Junktion」収録。 4. Rain [作詞作曲 大江千里] 1988: 7枚目のアルバム「1234」収録。槇原はこの曲について「男性シンガーソングライターの祖として尊敬している気持ちと、この曲の構成の素晴らしさに敬服」と述べている。 5. ミス・ブランニュー・デイ [作詞作曲 桑田佳祐] 1984: サザンオールスターズ20枚目のシングル。 6. 君に、胸キュン [作詞 松本隆 作曲 Y.M.O.] 1983:イエローマジック・オーケストラ7枚目のシングルで、アルバム「浮気なぼくら」に収録。カネボウ化粧品のCMソングに採用されヒットした。 7. David [作詞作曲 矢野顕子] 1986: 矢野顕子のアルバム「峠の我が家」から。フジテレビ系列ドラマ「やっぱり猫が好き」のテーマソング。ここでのブラジル音楽風アレンジは素晴らしい。 8. 朧月夜 [作詞 高野辰之 作曲 岡野貞一] 1914: 文部省唱歌。アイリッシュ・チューン風の編曲が曲に合っている。 9. 春よ来い [作詞作曲 松任谷由美] 1994: 松任谷由美 26枚目のシングル。アルバム「The Dancing Sun」収録で、同名のNHK連続テレビ小説の主題歌となり大ヒットした。 10. Monkey Magic [作詞 奈良橋洋子 作曲 タケカワユキヒデ] 1978: ゴダイゴ8枚目のシングル。日本テレビ系ドラマ「西遊記の」テーマ曲。本アルバム唯一の英語曲で、意外と英語が上手い。 11. 空と君のあいだに [作詞作曲 中島みゆき] 1994: 中島みゆき 31枚目のシングル(アルバム「予感」に収録)。日本テレビ系ドラマ「家なき子」の主題歌で、彼女最大のヒット曲。 12. 月の舟 [作詞 森雪之丞 作曲 中崎英也] 1988: 三貴「ブティックJoy」 CMソングに採用。オリエンタル調のメロディーが魅力的な佳曲。 素晴らしい曲を理屈抜きで楽しめるアルバムだ。 [2025年1月作成] |
|
| 1999年 Attraction (1999/2/24) の頃 | |
| ...Adesso Live Album Ornella Vanoni (1999) CGD East West | |
 |
1. Isola (Tango) [作詞 大貫妙子 イタリア語詞 Samuele Bersani 作曲 坂本龍一 編曲 Stefano Melone] 1曲目 Ornella Vanoni: Vocal Rita Marcotulli: Piano Stefano Melone: Keyboards, Programming, Conductor Saverio Porciello: C. Guitar Beppe Quirici: Bass, Producer Elio Rivagli: Drums Fulvio Renzi: Violin, Viola Alessandro Branca: Cello Samuele Bersani: Producer 2025年7月7日発売 1. Isola (Tango) [Words: Taeko Onuki, Italian Words: Samuele Bersani, Music: Ryuichi Sakamoto, Arr: Stefano Melone] 1st track by Ornella Vanoni from the album "...Adesso Live Album" on July 7, 1999 |
| 坂本龍一と大貫妙子の名作「Tango」は、坂本のアルバム「Smoochy」1995、大貫の「Lucy」1997が各初出で、「Utau」2010が共演作となる。本曲は海外においてカバーされ、本作はイタリア語詞によるもの。 オルネラ・ヴァノーニ(1934-2025)はイタリアのロンバルディア州ミラノ出身の歌手、女優。1950年代から活動を始め、1960年代にヒット曲を連発してイタリアを代表する歌手となった。代表作は1970年の「L'Appuntamento」(逢いびき)。また女優として舞台、映画、テレビで活躍した人だ。 本作はそんな彼女が65歳の時に発表したアルバムで、「Adesso」は「今」という意味。最初と最後の曲のみスタジオ録音であとはライブになっている。その最初の曲が1.「Isola」 (Tango)で、タイトルはイタリア語で「島」のこと。シンガー・ソングライターのサミュエル・ベルサーニが書いたイタリア語の歌詞は、1995年の坂本龍一のアルバム「Smoochy」の海外盤に収録された「Tango (Version Castellano)」のスペイン語歌詞(ラオル・カルノタ作詞)を改変したもの。彼は翌2000年にセルフカバーしている。大貫さんの歌詞と比較すると、大半は独自の言葉になっているが、原詞の精神はしっかり引き継がれている。歌詞の和訳は以下のとおり(翻訳ソフトによる日本語訳なので、一部不正確な部分があると思いますが、ご了承ください)。 私は島 星々が私を囲む 黙して歩けば 道をみつけるだろう 君を置いて行った道を 話の中 一瞬一瞬が決定的になる 誰もいない教会の階段で眠りに落ちる 砂のように両手で顔を覆い 目をあければ 心配はなくなる 楽園とは そこに行かない者たちの目的地 なんという間違いなのか 君とこんな人生を送るなんて なぜなら 君を失いつつあることを理解し その意味もわかっている そしてそれがどれほどの痛みをもたらすかも知っている 君が電話をかけてくるのは孤独のため でも 私も孤独から君にかけ直した 私を襲うエロチックな記憶のため 突然 太陽の下のバラのような情熱が芽生える 君と過ごす時間に敬意などない なぜなら 君を失ったことを知りながら 安らぎを求めている でも それがどれほどの痛みをもたらすかも知っている 心と魂を切り離すことが もし私が君の目を見つめるなら 私はこの口元に与え 君は私のものだと伝えられる それは君に影響を与える言葉であると 君は知っている 君は私のものではないと 君が電話をかけてくるのは孤独のため でも 私も孤独から君にかけ直した 私を襲うエロチックな記憶のため 突然 太陽の下のバラのような情熱が芽生える 君と過ごす時間に敬意などない なぜなら 君を失ったことを知りながら 安らぎを求めている でも それがどれほどの痛みをもたらすかも知っている 心と魂を切り離すことが 「Isola」は「島」の意味。オルネラは、男女の張り詰めた関係を貫禄たっぷりに歌いあげていて、ラテン音楽の濃密な雰囲気に満ちた素晴らしい作品に仕上がっている。 他の曲については、イタリア語の歌詞なので意味がわからないが、彼女の前向きなパーソナリティーが反映された曲が多くなっていて、聴いていて気持ちがよい。 「Tango」のイタリア語歌詞によるカバー。 [2025年11月作成] [2025年11月追記] オルネラ・ヴァノーニ氏は、2025年11月お亡くなりになりました(享年91)。ご冥福をお祈りいたします。 [2026年1月追記] イタリア語詞の経緯につき追記しました。 |
|
| Dawn Pink 坂本美雨 (1999) WEA Japan | |
 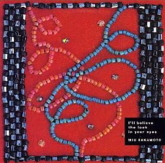 |
1. I'll Believe The Look In Your Eyes [作詞 大貫妙子 作曲 川村結花 編曲 坂本龍一 コーラス・アレンジ 大貫妙子] 3曲目 2. The Letter After The Wound [作詞 坂本美雨 作曲編曲 坂本龍一 コーラス・アレンジ 大貫妙子] 2曲目 坂本美雨: Vocal 坂本龍一: Keyoboards, Computer Programming Jeff Galub: Guitar (1) 大貫妙子: Chorus 写真上: アルバム 1999年9月29日発売 写真下: シングル 2000年2月9日発売 1. I'll Believe The Look In Your Eyes [Words: Taeko Onuki, Music: Yuka Kawamura, Arr: Ryuichi Sakamorto, Chorus Arr: Taeko Onuki] 3rd Track 2. The Letter After The Wond [Words: Miu Sakamoto, Music & Arr: Ryuchi Sakamorto, Chorus Arr: Taeko Onuki] 2nd Track by Miu Sakamoto from the album "Dawn Pink" on September 29, 1999 |
坂本美雨(1980- 以下「美雨」) は坂本龍一(以下「教授」)、矢野顕子(以下「矢野」)の間に生まれた娘。 9歳で家族とニューヨークに移住し現地の高校を卒業する。1997年16歳で教授の「The Other Side Of Love」1997でデビュー(Sister M という覆面名だったが後に美雨と判明)。東京とニューヨークを行き来しながら音楽活動し、1998年11月にミニアルバム「Aquascape」を発表。その後1999年5月に映画鉄道員(ぽっぽや)」(高倉健主演)の同名の主題歌を出し、4ヵ月後の9月(本人19歳の時)に発売されたアルバムが本作だ。そこには「Aquascape」に収められた曲4曲のリミックス(うち2曲の歌の録り直し)が収められている。超有名・有能な親の元に生まれたため、彼らのサポートを受けたアルバムの制作などのメリットを享受したが、「親の七光り」とみなされる苦労も多かっただろう。 そんな彼女が持って生まれた素質として挙げられるのは「声」だ。とても素直で綺麗な声で、ヨーロッパのトラディショナルに合う神秘的な深みがある。声量はないのでシャウトする場面はなく、呟き系の歌声になるけど、日本語、英語の発音、ヴォイス・プロダクションが大変美しいので、じっくり聴く込むと心が洗われるような気がする。その半面、声質や歌い回しに矢野のような癖がなく、そのためインパクトに欠ける点もある。 全11曲のうち6曲につき美雨が作詞していて、その歌詞は抽象的で教授やLune Sea (後にX Japanに加入)のSugizoが作る音楽の作風に合っている。大貫さんが歌詞を提供した1.「I'll Believe The Look In Your Eyes」は、それらのなかでは比較的具体的な内容で、教授がつけたメロディーと編曲もわかりやすく聴きやすい曲になっている。彼女のホームページのディスコグラフィーで、本アルバムの各曲につき本人がコメントしており、本曲について以下引用する。 「大貫さんに、人類愛のような大きなものでなくもっと個人的な愛をテーマに、と言われてメールで自分の体験を大まかにつたえ、それを元に大貫さんが書いてくださった詞です。恋愛に関する詞は自分で書くのはまだ未知の域なのでまだ自分が歌うとは思っていなく、大貫さんの詩を最初に読んだ時は戸惑いもありましたが、実際こういう気持ちはあるんだし飛び込んでみような、と思えた途端歌に勢いが出ておもしろかったです」 作曲の川村結花は当時は主にシンガー・アンド・ソングライターとして活動、後にスマップの「夜空ノムコウ」1998で作曲家としてブレイクした。なお本曲は翌年2月に同アルバム収録の「in aquascape」(作詞 坂本美雨 作曲編曲 坂本龍一)11曲目とカップリングでシングルカットされた。 他の曲について。「ひとりごと」(作詞作曲 矢野顕子 編曲 坂本龍一)1曲目 は矢野がアグネス・チャンに提供した曲(アルバム「美しい日々」1979収録)で、「ごはんができたよ」1980でセルフカバー、その後何度も再録音され彼女の代表曲となった作品だ。ここでは矢野が曲の提供とサイドボーカル(これが素晴らしい)、教授が編曲と演奏で彼女をやさしく包み込んでいて、当時すでに別居していた二人が一人娘のために注いだ家族愛がひしひしと感じられる名曲にして名演。この曲の数ある録音(カバーを含む)のなかで、これが一番好きだ。コメントで坂本のことを「教授」、矢野のことを「矢野さん」と言っている彼女のコメントが面白い。「awakening」(作詞 Arto Linsay 作曲編曲 坂本龍一)4曲目は教授の音楽仲間アート・リンゼイが美雨の日本語詞を基に英語で作詞したもの。現地育ちという事で、英語の発音と表現力は完璧で、曲の雰囲気にもぴったり合っている。「Child Of Snow」(作詞 Jeffrey Cohen 作曲編曲 坂本龍一)5曲目は上述の「鉄道員(ぽっぽや)」の英語バージョン。アイリッシュ・チューンを想起させるひんやりとした感触が最高。「Internal」(作詞 坂本美雨 作曲 Sugizo) 6曲目は、素直な歌声と演奏が気持ち良い佳曲。「Dawn」(作詞 矢野顕子、坂本美雨 作曲 矢野顕子 編曲 Jeff Bova)10曲目は矢野らしいメロディーが面白い曲で、教授や矢野のニューヨークの音楽仲間ジェフ・ボヴァが担当しているため、少し毛色が違ったサウンドになっている。 当時教授のもとでアルバムを制作した中谷美紀は自我を感じさせる歌唱だったのに対し、美雨は教授やSugizoが創り出した音の海の中でのびのびと漂っているような趣がある。アルバムのクレジットを見る限り、教授と矢野の威光に隠れて本人の存在感が霞んでいるように見えるが、実際聴いてみると本人の持ち味がそれなりに発揮されていて、なかなか良い仕上がりになっていると思う。 [2025年1月作成] |
|
| 私生活 中谷美紀 (1999) WEA Japan | |
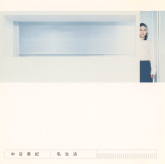 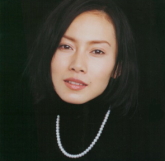 |
1. 夏に恋する女たち [作詞作曲 大貫妙子 編曲 前田和彦 星野英和 坂本龍一] 7曲目 中谷美紀: Vocal 坂本龍一: Keyboards, Producer 写真上: 「私生活」 1999年11月10日発売 写真下: 「MIKI」 2001年11月12日発売 1. Natsu Ni Koisuru Onna Tachi (Women In Love In Summer) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Kazuhiko Maeda, Hidekazu Hoshino, Ryuichi Sakamoto] 7th Track by Miki Nakatani from the album "Shiseikatsu" (Private Life) on November 10, 1999 |
| 中谷美紀と坂本龍一による3部作最後のアルバムで、その後2000年と2001年に2枚のシングルを出した後にコラボは終了し、その彼女は音楽活動から身を引いて女優業に専念する。前作に比べて中谷の作詞が4曲に増えた一方、音楽面では坂本カラーがより前面に出るなど、両者ともやり切った感がある。彼女が歌を止めたのは、これ以上の作品は出来ないと思ったからではないかな。 いままでのアルバムと異なり、書き下ろしは少なく、前作からの2年間に発売されたシングル2枚のリミックス、別バージョンや既発表曲のカバー、そしてアンビエント(環境音楽)風なサウンドをバックにしたモノローグなどの作品が多くを占めている。また編曲面でも坂本以外に、彼のチルドレンとも呼べる若手のクリエイター達が参加している点もあげられる。 大貫さんのカバー 1.「夏に恋する女たち」は1983年に発売されたシングル(アルバム「Signifie」収録)で、同名のTBS系テレビドラマの主題曲だった曲。ここでは打ち込みのシンセサイザー主体の思い切ったアレンジが施されていて、そのチープなサウンドをバックにしたボーカルが意外なほどいい感じで、とても面白い出来上がりとなった。坂本と一緒にアレンジを担当している前田和彦は、坂本のラジオ番組にデモを投稿して認められた人で、大貫さんの曲も入っている長谷川恵里のアルバム「Flavor」2002の全編でアレンジを担当している。なおアルバムのクレジットには明記されていないが、彼もシンセサイザーなどで演奏に加わっているものと思われる。もう一人の星野英和についてはインターネットで資料がみつからなかった。ちなみに2001年11月にワーナーから出たベスト盤「MIKI」には、ドラムスを強調した同曲の「Drum Mix」が収録されている。 他の曲について。「フロンティア」 (作詞 中谷美紀 作曲編曲 坂本龍一)1曲目は、1998年11月に発売された坂本美雨のアルバム「Aquascape」に収録された英語歌詞の「awakening」に新たな日本語歌詞をつけたもので、バックトラックもリミックスしたものを使用している。本曲は7月にシングルで発売されているが、エンディングにおけるギターソロなどでリミックス違いがある。本曲は中谷が主演した日本テレビ系ドラマ「女医」の主題歌となった。なお「all this time」 (作詞 jcfs 作曲編曲 坂本龍一)12曲目は、同曲に英語歌詞(坂本美雨のものとは異なる)を付けたもので、アレンジも異なる別バージョン。「雨だれ」(作詞 中谷美紀 作曲編曲 坂本龍一)2曲目は、坂本のアルバム「BTTB」1998に収録された「Opus」に歌詞を付けたもの。「Temptation」(作詞 中谷美紀 作曲 Gabriel Faure 編曲 鷲見音右衛門文宏、星野英和、坂本龍一)3曲目は、私にとって子供の頃観たアパレル・メーカーのCMが印象的だったフォーレの「ペレアスとメイザンド」に中谷が詩を付けたもので、シンセの編曲によりクラシック曲のイメージがかなり変わっている。 「クロニック・ラブ」(作詞 中谷美紀 作曲編曲 坂本龍一)5曲目は、坂本の「Bellet Mecanique」(アルバム「未来派野郎」1986収録)に歌詞をつけたもので、これも中谷主演のTBS系ドラマ「ケイゾク」の主題歌。1990年2月に発売されたシングルとはシンセの音が異なるリミックスになっている。「フェティッシュ」(作詞 売野雅勇 作曲編曲 坂本龍一)9曲目は本作唯一の売野の作詞で、シングル「クロニック・ラブ」のカップリングと異なり、メロディー楽器を少なくして主にリズムを強調したリミックスになっている。 過去2作品と同様、歌唱から感じられる中谷の自我は健在で、歌詞を多く書いている分、より強く出ているように思える。その分、より自分の好みを押し出した坂本とのバランスがとれているようだ。そんなアルバムの中で、大貫さんの「夏に恋する女たち」は、他の抽象的な内容の曲とは異なる光を放っている。 [2025年2月作成] |
|
| Watermelon Sugar Flim-Flam (1999) Low Blow | |
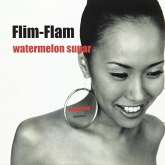 |
1. 都会 [作詞作曲 大貫妙子] 1曲目 ハル(井川春): Vocal 加藤ゆうじ: Electric Piano, Organ 星克典: Bass, Other Instruments S-KEN, Flim-Flam: Producer 1999年11月21日発売 1. City [Words & Music: Taeko Onuki] 3rd track by Flim-Flam from the album "Watermelon Sugar" on November 21, 1999 |
| 大貫さんの「都会」は今はCity-Popの名曲として、20以上のアーティストにカバーされているが、その初回は1977年のオリジナル(「Sunshower」収録)の22年後、1999年だった。この曲が認められるまでに、これほどの時間がかかったということだね。以前本ディスコグラフィーで、最初のカバーは黒沢律子(「Melody」2001収録)と書いたが、その後本アルバムを発見し、訂正のうえ本記事を書いている次第。もしかすると、これよりも古いカバーが私が知らないところで存在しているかもしれないね.........。そうであれば人生の楽しみがまだ残っているというもんだ。 「Flim Flam」の意味は「でたらめ、たわごと、ごまかし、ペテン」という意味で、この言葉からローラ・ニーロの曲「Flim Flam Man」(彼女の最初のアルバム「More Than A New Discovery」1967収録 → 1973年に表紙デザイン・曲順を変えて「First Songs」として再発。また1971年にバーブラ・ストレイサンドがカバー)を思い出す。どのような意図でこの名前を付けたのかは不明であるが、ここでのFlim-Flamは、ボーカリスト井川春(ハル、Haru、後にTiger)とサウンド・クリエイターの星克典(Katz)からなるユニットだ。本アルバムは1990年代の後半頃からクラブで活動を始めた彼ら3枚目かつ最後のアルバムで、1999年11月21日にまずレコード、翌2000年1月21日にCDで発売された。 「都会」はクラブでかかりそうなヒップポップ・アレンジで、シンプルなサウンドのバックとソウルフルなハルのボーカルが聴きもの。キーボードを弾く加藤ゆうじは、アルバム・クレジットでは英語で表記され、インターネットに情報がなかったため、ここでは名前をひらがなで表示した。 他の曲では6曲中4曲がHaru作詞、星克典作曲のオリジナルで、グルーヴ感あふれる黒っぽいR&B曲。うち「まばたきをする間に」2曲目では、作詞の共作者とラップで林亜門が参加している。そしてもう1曲のカバーはプリンスの「Little Red Corvette」 (1983全米6位)。これもヒップポップ調の面白いアレンジ。 Hanaはその後2000年にTigerという名前でソロデビューし、シンガー、ラッパーとして活動しながら、サザンオールスターズやMISHA等のバックボーカルをやったり、安室奈美恵やMISHAなどに楽曲を提供している。星克典も主にインディーズの世界でサウンドクリエイターとして活躍し、MISHAの作品などに参加している。 「都会」の最初のカバーで、ゴキゲンなヒップポップ・アレンジ、ソウルフル・ボーカルを聴くことができる。 [2025年8月作成] |
|
| 2000年 ensemble (2000/6/21) の頃 | |
| L'oroscopo speciale Samuele Bersani (2000) Pressing | |
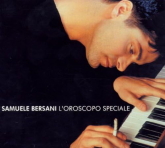 |
1. Isola (Tango) [作詞 大貫妙子 イタリア語詞 Samuele Bersani 作曲 坂本龍一 編曲 Beppe D'Onghia] 8曲目 Samuele Bersani: Piano, Vocal Beppe D'Onghia: Piano, Keyboards, Producer Roberto Guarino, Marco Formentini: Guitar Paolo Costa: Bass Alfredo Golino: Drums Gionata Colaprisca: Percussion Arke String Quartet: Strings 2000年7月11日発売 1. Isola (Tango) [Words: Taeko Onuki, Italian Words: Samuele Bersani, Music: Ryuichi Sakamoto, Arr: Beppe D'Onghia] 8th track by Samueke Bersani from the album "L'oroscopo speciale" on July 11, 2000 |
| 1999年イタリアの歌手オルネラ・ヴァノーニが大貫妙子・坂本龍一作「Tango」を歌ったが、翌年イタリア語詞の作者サミュエル・ベルサリ(1970-
)がセルフカバー、彼の4枚目のアルバム「L'oroscopo speciale」(「Oroscope」はホロスコープ= 星占いに使われる天宮図のこと)に収録された。 オルネラのバージョンが歌手としてのアプローチだったのに対し、本曲は理知的なシンガー・ソングライターとしての視点によるオーラに満ちたパフォーマンス。アルバムの中でも突出した存在で、曲の持つ魔力が最大限に発揮されている。このイタリア語詞(歌詞の内容については同曲のオルネラの記事を参照ください)によるカバーは後に歌い継がれてゆくことから、イタリアで高い評価を受けたに違いない。 切れ味抜群の「Tango」のカバーだ。 [2025年11月作成] |
|
| Home Girl Journey 矢野顕子 (2000) Epic | |
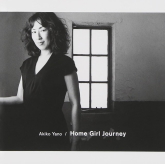 |
2. 会いたい気持ち [作詞作曲 大貫妙子 編曲 矢野顕子] 2曲目 矢野顕子: Vocal, Piano, Producer 2000年11月1日発売 2. Aitai Kimochi (I Want To Meet You) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Akiko Yano] 2nd track by Akiko Yano from the album "Home Girl Journey" on November 1, 2000 |
| 矢野顕子弾き語りシリーズの第3作。ニューヨーク郊外にある矢野のプライベート・スタジオでの録音で、前2作よりもピアノの音が自宅の部屋で録音したかのような親しみやすい音だ。内容的には従来に増して幅広い選曲で楽しませてくれる。 2.「会いたい気持ち」は大貫さんのアルバム「Shooting Star In The Blue Sky」1983からで、本曲につき矢野はライナーノーツに以下のとおり書いている。 静かなター坊(大貫妙子)もいいが、かわいいター坊もすごく好き。そうか、ブレーキこわれちゃう時もあるんだね。 別れなどクールな内容の歌が多い大貫さんなだけど、ここでは思い切りはっちゃけていて、聴いていてウキウキする曲。矢野のピアノ・アレンジもそういう気分になっていて、明るく解放感に満ちた演奏が誠に魅力的。他の曲が原曲のリズム、アレンジを根底から変えているのに対し、この曲は比較的同じ乗りで取り組んでいる。 他の曲について(編曲はすべて矢野顕子) 1. Paper Doll [作詞作曲 山下達郎] 1978 「Go Ahead」。ビートが効いた曲を矢野流に料理し切っていて凄い! 2. 会いたい気持ち 3. 赤いクーペ [作詞 谷川俊太郎 作曲 小室等] 1996 「時間のパスポート」。谷川の歌詞が本当に素晴らしい。 4. 夜明けのワインディング・ロード [作詞作曲 忌野清志郎] 1985 RCサクセション 「Heart Ace」 5. 雷が鳴る前に [作詞作曲 槇原敬之] 1992 「君は僕の宝物」 6. しようよ [作詞 森浩美 作曲 Jimmy Johnson] 1995 SMAP シングル 7. ニットキャップマン [作詞 糸井重里 作曲 岡田徹] 1996 ムーンライダース 「Bizarre Music For You」。原曲と比べると面白い。 8. 夢を見る人 [作詞作曲 田島貴男] 1995 Original Love 「Rainbow Race」 1995 9. Photograph [作詞作曲 辻睦詞] 1995 Oh! Penelope 「Photograph」 10. 世界はゴー・ネクスト [作詞 サエキけんぞう 作曲 窪田晴夫] 1987 パール兄弟 「パールトロン」 11. 遠い町で [作曲作詞 宮沢和史] 1998 「Sixteenth Moon」 12. Home Girl Journey [作曲 矢野顕子] オリジナルのインストルメンタル。資生堂のCMのために作った曲とのこと。 13. さようなら [作詞 谷川俊太郎 作曲 谷川賢作] 1998 DiVa 「そらをとぶ」 谷川賢作は俊太郎の息子。 14. 在広東少年 [作詞作曲 矢野顕子] セルフカバー 1980 「ごはんができたよ」。原曲からあっと驚く変貌を遂げている。 15. さすらい [奥田民生] 1998 「股旅」 どの曲も素晴らしく、彼女でしかできない唯一無二の音楽だ。 [2025年5月作成] |
|
| 2001年 ensemble (2000/6/21) note (2002/2/20) の頃 | |
| Amii-Phonic 尾崎亜美 (2001) For Life | |
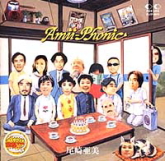 |
1. Sweet Breath [作詞 尾崎亜美 作曲 大貫妙子 編曲 尾崎亜美] 9曲目 尾崎亜美: Vocal, Keyboards 是永巧一: Electric Guitar, Acoustic Guitar 小原礼: Bass 山本秀夫: Drums 浜口茂外也: Percussion 橋本茂昭: Programming 大貫妙子: Chorus 2001年8月22日発売 1. Sweet Breath [Words: Ami Ozaki, Music: Taeko Onuki, Arr: Ami Ozaki] 9th track by Ami Ozaki from the album "Amii-Phonic" on August 22, 2001 |
| 私にとっての尾崎亜美(1957- )は、松任谷正隆が編曲を担当したデビュー作「Shady」1976と「Mind Drops」1977そしてシングル盤の「マイ・ピュア・レディ」1977だった。その陰影の濃い音楽が好きだったのだが、実際の彼女はもっと明るい人だという記事を読んだ記憶が当時ある。その後の彼女の作品は聴いていなかったので、デビュー25周年を記念して豪華なゲストを招いて制作された本アルバムを聴いた時は、予想していたとはいえ、力強いロックな歌唱に驚かされた。 大貫さんが作曲した1.「Sweet Breath」は10ccの「I'm Not In Love」1975 のようなイントロから始まる。しっとりした内容の歌詞で、大貫さんのメロディーもそれにそったものになっているが、アルバムの中では地味な感じになった。曲中とエンディングで大貫さんのバックボーカルが聞こえる。曲自体は決して悪くないんだけど、歌い手と曲にミスマッチがある印象は否めない。初期の尾崎亜美のイメージだったらしっくりきたんじゃないかな。この曲の出来については両者とも満足しなかったようで、ゲストの写真がコラージュされたアルバム表紙のイラストに大貫さんの姿がないのはそのためなんだろう。 他のゲストは、細野晴臣、奥田民生、福山雅治、Sing Like Talking、宇崎竜童、鈴木茂、真矢、デーモン小暮、杏里、高橋幸宏という豪華な面々で、プロデュースは尾崎本人と旦那の小原礼。1.「北京ダック」(作詞作曲 細野晴臣 編曲 尾崎亜美、小原礼)1曲目は「Tropical Dandy」1975のカバーで、細野とのデュエットが最高。細野にとっても25年後のセルフカバーということだね。ちなみに本曲はアルバム最後に「おまけバージョン」として尾崎一人の歌唱による別録音が収められているが、昔のSP盤をラジオで聞いているようなノイズ処理が施されていて、スウィングジャズ・ギター主体の古風なサウンドによく合っている。2.「Melody Junk」 (作詞 尾崎亜美、作曲 奥田民生、編曲 Amigos) 2曲目は、ギターに奥田、ドラムスに沼澤尚を迎えたゴキゲンなロックで、奥田のサイドボーカルが入る。「風のライオン」(作詞作曲編曲 尾崎亜美)3曲目は「Natural Agency」1991収録曲のセルフカバーで、福山は歌以外にハーモニカを吹いている。4.「Friendship 自然の法則」(作詞 藤田千章 作曲編曲 尾崎亜美)4曲目は前向きで明るい曲で、佐藤竹善(Sing Like Talking) とのデュエットが素晴らしい。 「Camping Boogie-Woogie」(作詞 尾崎亜美 作曲 宇崎竜童 編曲 小原礼)5曲目はブギウギ・ロックで、宇崎とのデュエットがユーモラスで楽しい。「ゆっくり踊るベアーのような夜を往く」(作詞 鈴木慶一 作曲編曲 小原礼)6曲目はLuna Seaのドラマー、真矢の乾いたドラムサウンドが最高のロック。逆回転エフェクトによるヘンテコなギターソロは鈴木茂だ。「Window Of Nature」(作詞作曲編曲 尾崎亜美)8曲目はブラジル音楽風のサウンドで、デーモン閣下とのデュエット・ボーカルがかっこいい。「Forgive Yourself」(作詞作曲編曲 尾崎亜美)9曲目の杏里とのデュエットは、二人の声質の相性の良さが際立っている。「New Life」(作詞 高橋幸宏 作曲 尾崎亜美 編曲 小原礼)10曲目は高橋のボーカルとドラムスが堪能できる。「手をつないでいて」(作詞作曲編曲 尾崎亜美)11曲目は本アルバムの中で唯一ゲストなしの曲。 要するに、大貫さんの「Sweet Breath」が悪いんじゃなくで、他の曲が良すぎたということだね。 [2025年3月作成] |
|
| brew 村松崇継 (2001) MIDI | |
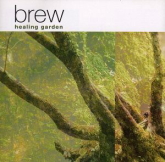 |
9. ひまわり [作曲 大貫妙子 編曲 村松崇継] (Instrumental) 9曲目 村松崇継: Piano, Keyboards, Programming 2001年9月12日発売 9. Himawari (Sunflower) [Music: Taeko Onuki, Arr: Takatsugu Muramatsu] (Instrumental) 9th track by Takatsugu Muramatsu from the album "brew" on September 12, 2001 |
| 村松崇継(1978- 静岡県出身)は作曲家で、映画・テレビドラマ、舞台・ミュージカル、各種イベント、コマーシャル等の音楽を数多く手掛ける他に、アーティストへの楽曲提供や編曲・プロデュースやピアニストとしての録音やコンサートで活躍している。本作は彼が坂東眞砂子原作のホラー映画「狗神」(原田眞人監督)の音楽を担当した際に作ったテーマ曲を含む日本映画音楽集。彼のピアノと打ち込みによるインストルメンタルで、独自アレンジによるヒーリング音楽的な音作りになっている。いかにも打ち込みっぽい音が気になるが、彼が弾くピアノの生音の粒立ちの素晴らしさがそれを上回っている。 大貫さんの9.「ひまわり」は、写真家荒木経惟夫妻のフォトエッセイを映画化した「東京日和」(1997年 竹中直人監督、竹中直人、中山美穂主演)の主題歌。大貫さんは1曲(モーツァルトの「トルコ行進曲」)を除き、映画の音楽全般を作曲(編曲者は坂本龍一、フェビアン・レザ・パネ、小倉博和)していて、本曲は唯一歌が入る曲だった。エレキピアノ、シンセサイザー、ナイロン弦ギター、パーカッションによるブラジル音楽風の坂本のオリジナルの編曲に対し、ここでは村松のゆったりとして透明感のある生ピアノが前面に出て、途中から打ち込みによるオケが加わり、おだやかなサウンドに終始する。 他の曲について (編曲は全て村松崇継、表示順は 映画 公開年 監督 [作詞作曲] オリジナルの歌手 曲の発表年→映画と異なる場合のみ。 特記) 1. 愛は花、君は種子 「おもいでぽろぽろ」1991 高畑勲 [原曲「The Rose」 作詞作曲 Amanda McBroom 日本語詞 高畑勲] 都はるみ。 原曲はベット・ミドラーによる同タイトルの映画1980の主題歌で全米3位。 2. 君をのせて 「天空の城ラピュタ」1986 宮崎駿 [作詞 宮崎駿 作曲 久石譲] 井上あずみ 3. やさしさに包まれたなら 「魔女の宅急便」1989 宮崎駿 [作詞作曲 荒井由美] 荒井由美 1974。シングルおよびアルバム 「Misslim」に収録された名曲。ここではギターのコードカッティングのないスローなアレンジになっている。 4. となりのトトロ 「となりのトトロ」 1988 宮崎駿 [作詞 宮崎駿 作曲 久石譲] 井上あずみ 5. 時には昔の話を 「紅の豚」 1992 宮崎駿 [作詞作曲 加藤登紀子] 加藤登紀子1987。ただし映画で採用されたのは、1992年のライブ・バージョン。 6. 風の谷のナウシカ 「風の谷のナウシカ」 1984 宮崎駿 [作詞 松本隆 作曲 細野晴臣] 安田成美。宮崎監督が気に入らなかったため、本曲は映画には採用されず、イメージソングという位置付けになった。 7. Swallow Tail Butterfly 〜あいのうた〜 「スワロウテイル」1996 岩井俊二 [作詞 岩井俊二 CHARA 小林武史 作曲 小林武史] Yen Town Band。 Yen Town BandはCHARA (Vocal)、小林武史(Keyboards, Guitar, Producer)、名越由貴夫(Guitar)からなる映画のために結成されたバンド。 8. カントリーロード 「耳をすませば」1995 近藤喜文 [原曲 「Take Me Home, Country Roads」作詞作曲 John Denver, Bill Danoff, Taffy Nivert 日本語訳詞 鈴木麻実子 補作 宮崎駿] 本名陽子。原曲はジョン・デンバー 1971 全米2位。映画のオープニングで使われた英語版は1973年のオリビア・ニュートン・ジョンのカバー。本名陽子は当時16歳で映画の主人公の声も担当した。訳詞を書いた鈴木麻実子はプロデューサー鈴木敏夫の娘。 9. ひまわり 10. 電話線 「ホーホケキョとなりの山田くん」1999 高畑勲 [作詞作曲 矢野顕子] 矢野顕子 1976。矢野顕子のデビュー作「日本少女」収録でアメリカ録音。リトルフィートがバックを担当したことで話題となった。本アルバムの中では珍しいアップテンポのリズムが付いていて、ここでは村松のピアノとアレンジが曲の浮遊感を上手く表現している。主題歌「ひとりぼっちはやめた」も矢野顕子で本曲は挿入歌。映画はいしいひさいちの4コマ漫画が原作。 11. 「狗神」のテーマ 「狗神」2001 原田眞人 [作曲 村松崇継] 村松崇継。制約の多い映画のサウンドトラックに対し、ここでは自分の曲を思いのままに編曲した感じで、5分50秒の力が籠った大作に仕上げられている。 12. はにゅうの宿 「火垂るの墓」 1988 [作詞 John Howard Payne 作曲 Henry Bishop] アメリータ・ガリ=クルチ(Amelita Galli-Curci) 「Home Sweet Home」1917。1823年作曲のイングランド民謡として親しまれていて、里見義訳による日本語版はで1989年に唱歌として出版された。映画ではエンディングでイタリアのオペラ歌手アメリータ・ガリ-クルチ(1882-1963)が歌った英語版が使われている。 以上のとおり、曲の3分の2がスタジオジブリによるアニメ作品の音楽となっている。 「ひまわり」のヒーリング・ミュージック的アレンジ。 [2025年12月作成] |
|
| 夢 /風の道 /この広い空の下 岩崎宏美 (2001) テイチク | |
 |
1. 風の道 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 古川昌義] シングル「夢」 2曲目 岩崎宏美: Vocal 2001年9月21日発売 1. Kaze No Michi (The Wind Road) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Masayoshi Furukawa] 2nd Track by Hiromi Iwasaki from the single "Yume" (Dream) on September 21, 2001 |
| 岩崎宏美(1958- 東京都出身)が2001年に出したシングル「夢」の2曲目に大貫さんの「風の道」(オリジナルはラジのアルバム「Quatre」1979、大貫さんのセルフカバーは「Cliche」1982に収録)が入っている。坂本龍一編曲によるラジと大貫さんのひんやりとした透明感のあるサウンドに比べて、素直で暖かい感じの音作り・歌唱になっている。なお本曲はアルバム未収録。 その他の曲について タイトル曲の「夢」(作詞作曲 さだまさし 編曲 古川昌義)1曲目は、もとはさだの「第2回まさしんぐWorldコンサート」(1985/1/31〜2/23 東京・大阪・名古屋で計6回公演)の「軽井沢ホテル」という劇中の曲として作られたもので、主演女優は岩崎と十勝花子のダブルキャストで、前者の場合は岩崎、後者の場合さだが歌った(YouTubeで十勝花子が演じる舞台の映像を観ることができる)。なお同曲はさだ本人により「軽井沢ホテル」とのカップリングで同年3月にシングル盤が発売された。岩崎の録音はその16年後のカバーにあたり、2003年のアルバム「Dear Friends」にはボーカルを録り直したものが収録された。「この広い空の下」(作詞 阿久悠 作曲 馬飼野講康二 編曲 古川昌義)3曲目は、岩崎のファースト・アルバム「あおぞら」1975収録曲の新録音。 当時は喉のポリープや他の難病に悩まされ活動を抑えていた時期にあたり、本作には彼女の回復と再生を願う気持ちが込められているようだ。 [2025年1月作成] |
|
| Melody RIZCO (黒沢律子) (2001) WEA JAPAN | |
 |
1. 都会 [作詞作曲 大貫妙子] 1曲目 黒沢律子: Vocal 2001年11月21日発売 1. City [Words & Music: Taeko Onuki] 1st track by RIZCO (Ritsuko Kurosawa) from the album "Melody" on November 21, 2001 |
| すみません。このアルバム持っていないので多くは語れませんが、知っている範囲内で書きます。 黒沢律子(1972- 東京都出身)は小学生で歌手オーディションに応募し、高校生の1990年にデビューする。1993年までにシングル5枚、アルバム5枚を出し、その後「b'Rouge」という女子二人組のユニットでNHKの音楽番組「ポップジャム」に出演し、シングルを6枚出す。1998年からソロ歌手「RIZCO」として再デビューし、シングル5枚、アルバム2枚、またレベッカのメンバーとのユニット「R.P.R」でアルバム1枚を出したが、2002年の途中で音楽活動を止めている。全体的にダンサブルな曲が多いようだ。 「Melody」は彼女最後のアルバムで、J-Popの名曲8曲とオリジナル1曲からなっている。1.「都会」(アルバム「Sunshower」1977収録)は数多くの人がカバーしている名曲。アレンジは坂本龍一のオリジナルに近く、グルーヴも同じ感じ。イントロのメロディーはシンセサイザーが奏で、間奏ソロはエレキギター、原曲では大貫さんが歌っていたコーラス・パートはシンセが担当、エンディングでエレキピアノのソロが入る。黒沢は都会的なセンスで軽やかに歌っているが、ちょっと大人しいかな?原曲のアレンジ・演奏の偉大さに敬意を表して、あまりいじらなかったのだろう。それに対し、この後に続くカバー群にはいろいろなアイデアがつぎ込まれるようになってゆく。 他の曲は資料によると、「月下美人」1981(門あさ美)、「白いページの中に」1978 (柴田まゆみ)、「Midnight Love Call」1977 (石川セリ) 1980 (南佳孝)、「Destiny」 1979 (松任谷由美)、「駅」1986 (中森明菜) 1987 (竹内まりや)、「夏の恋人」 1978 (竹内まりや)、「みずいろの雨」1978 (八神純子)、「15分だけのタイムマシン」(オリジナル)。山下達郎作詞作曲の隠れた名曲「夏の恋人」を黒沢がどんなふうに歌っているのか、聴いてみたい! [2025年5月作成] [2025年8月追記] 「これが「都会」の最初のカバーだった」と書きましたが誤りでした。最初のカバーは1999年発売の「Flim-Flam」のミニアルバム「Watermelon Sugar」でした。ということで、書き直しました。 |
|
| Live In Tokyo 2001 Morelenbaum2 & Sakamoto (2001) WEA Japan | |
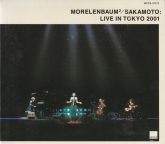 |
4. Tango [作詞 大貫妙子 ポルトガル語歌詞 Paula Morelenbaum 作曲 坂本龍一] 4曲目 Paula Morelenbaum: Vocal 坂本龍一: Piano Jaques Morelenbaum: Cello Luiz Brazil: Guitar Morelenbaum2, 坂本龍一: Producer 録音: 2001年8月21, 22日 赤坂ACTシアター 発売: 2001年11月21日 1. Tango [Words: Taeko Onuki, Portuguese Lyrics: Paula Morelenbaum, Music: Ryuichi Sakamoto] 8th Track by Morelenbaum2 & Sakamoto from the album "Live In Tokyo" on November 21, 2001 |
| 私にとってのブラジル音楽との出会いは、クラシックのレコードばかり聴いていた父親がたまにかけるラテン音楽のなかの1枚、映画「黒いオルフェ」1959
のサウンドトラックだった。強烈なサンバのリズム、「A Felicidade(哀しみよさようなら)」と「Manha De Carnival (オルフェの歌)」の哀愁は幼時体験として私の心に刻まれ、その後の音楽愛好の基礎となった。アントニオ・カルロス・ジョビンを意識したのは、大学1年生の時にアルバム「Wave」1967を買ってからで、以降すかっりはまって彼のアルバムを買いそろえた。また「Tide」1970の編曲をしていたデオダードにも入れ込んだ。ということで私にとってブラジル音楽、特にジョビンは特別な存在だ。 坂本龍一にとってもブラジル音楽とジョビンは、クラシックと並んで自己の音楽のルーツのひとつとなっている(私とレベルが違うので「にとっても」というのが恥ずかしい)。そんな彼が1990年代にブラジル人のチェロ奏者ジャキス・モレレンバウム(1954- ) と知り合い、コンサートや映画「Little Buddah」1993のサウンドトラック、坂本の「Sweet Revenge」1994、「1996」1996などのレコーディングで親交を深めてゆく。そんな彼らが1995年にリオでコンサートをした際に、ジョビンの生前に彼と演奏活動をしていたジャキスの計らいで、坂本が1994年に亡くなったジョビンの家に招待され、ジョビンのピアノに触れた感動から、この場所でジョビンの作品集を録音する企画が生まれた(そのエピソードはラテン音楽のe-マガジン「月刊ラティーナ」2023年4月7日の坂本龍一追悼記事「ジョビンへの募る想い.....-モレレンバウム夫妻と坂本龍一の友情が構築させた、扉に鍵のない家、『CASA』 」に詳しく述べれている)。そして坂本(ピアノ)、ジャキス(チェロ)、奥さんのパウラ(1962- ボーカル)のプロデュースで、2001年1月から同地およびリオのスタジオで名作「Casa」が録音され、それは作曲家の坂本にとって唯一の他人の作品集となった。そして9月の発売にむけて、プロモーションのためのコンサートが各地で行われた。本アルバムは、8月の日本でのコンサートの模様を録音したもので、同年11月に日本のみで発売された(当時同内容のものが「DVDオーディオ」として別途出たが、それは高音質をうたう音源方式であって映像ではない)。 コンサートは上記3人と、「Guest Performer」というクレジットで、歌伴で有名なギタリスト、ルイス・ブラジル(1954- )の4人編成。15曲のうち演奏曲は「Casa」収録曲が6曲で、同アルバムは静かで瞑想的な曲が多かったためか、ステージ用として軽快または知名度のある曲が加えられた。オーディエンスの拍手の大半はカットされているため、臨場感に欠けるが、その分音楽に集中できる。 坂本作の4.「Tango」はその中でカエタノ・ヴェローゾの5.「Coracao Vagabundo」とともに非ジョビン作品で、「Casa」に入っていなかった曲。パウラによるポルトガル語歌詞の訳は以下のとおり。 灼き続ける太陽のように 飽くことなく燃え 砂漠の道のように 冷たく乾いた感じ 情熱的に 狂おしいほどに 私は求める 阻むもののない時を あなたの不在が私を苦しめる 空虚の重み 世界は私の手の中に そしてそれを失うことは 華麗なタンゴの舞のよう でもあなたにとって これはただの 束の間の恋でしかない 現実感のない旅 あなたなしで生きることは なぜかわからない 苦しみながらも まだあなたを求めている どうしていいかわからない 希望を捨てて生きるられないのか 私の視界は迷う あなたの名前のもとに あなたの姿は架空の線 私を侵す誤りの記憶 私の体は情熱で開かれる 太陽に向かうバラのように 夢は消えた 残ったのは絵ハガキのよう想い出 なぜかわからない 苦しみながらも まだあなたを求めている どうしていいかわからない 待つことなく生きる術が 終わりのない旅路の中で 愛しさを胸に留めて 感じる痛み 私が下る川はすべてあなたのもの あなたがいた場所にあったのは 壊れやすい紙の船 私の視界は迷う あなたの名前のもとに あなたの姿は架空の線 私を侵す誤りの記憶 私の体は情熱で開かれる 太陽に向かうバラのように 募る思い出 私にとって美しい なぜかわからない 苦しみながらも まだあなたを求めている どうしていいかわからない 待つことなく生きる方法が あるいは あらたな明日か この歌詞は、坂本龍一のアルバム「Smoochy」1995の海外盤に収められた「Tango (Version Castellano)」のスペイン語歌詞(ラオル・カルノタ作詞)を改変したもの。大貫さんの歌詞と比較すると、大半は独自の言葉になっているが、原詞の精神はしっかり引き継がれている。そしてこれが他のジョビン作品の中にあっても、全く違和感を感じないというのは驚異的。二人の音楽の根幹にある魂が同じだからだろう。 その他の曲について: 曲名(和訳または「日本語・英語名」))[作詞作曲] 初出アーティストと発表年。特記 「*」は「Casa」収録曲 「☆」は下記の映像に収められた曲 1. As Praias Desertas (ひと気のないビーチ)[Jobim] Elizeth Cardoso 1958。初期作品で彼が歌詞も書いている。* 2. Amor Em Paz (平和の中の愛 「Once I Loved」)[Vinicius de Moraes, Jobim] Antonio Carlos Jobim 1963。アルバム「The Compser of Desafinado, Plays....」にインストルメンタルで収録(本アルバムは本曲でなく「Dreamer」を収めているほうが多い)。Ray Gilbertによる英語詞で歌われたAstrud Gilbert 1965、Frank Sinatra 1967が有名。ここではポルトガル語詞による歌唱。* ☆ 3. O Grande Amour(大いなる愛)[Vinicius de Moraes, Jobim] Mario Reis 1960。Stan Getz & Joao Gilberto 1963が決定版。* ☆ 4. Tango ☆ 5. Coracao Vagabundo (さまよう心)[Caetano Veloso] Caetano Veloso 1967。オリジナルはGal Costaのデュエット。☆ 6. Sabia (ツグミ)[Chico Buarque, Jobim] Antonio Carlos Jobim 1970。アルバム「Stone Flower」収録。「Terra Brasilis」1980にも入っている。* ☆ 7. Tema Para Ana (アナのテーマ)[Jobim] Antonio Carlos Jobim 1995. 亡くなる数か月前、奥さんのアナのために書いたワルツ。デモ音源が死後に発売されたアルバム「Songbook Antonio Carlos Jobim Instrumental」に収められた。とてもとても美しく愛らしいワルツ。* ☆ 8. Sem Voce (あなたなしで)[Vinicius de Moraes, Jobim] Sylvia Telles 1959。ジョビンのバージョンはNana Caymmi との共演盤「Caymmi Visita Tom」1965に収録。* ☆ 9. Insensatez (愚かさ 「How Insensitive」) [Vinicius de Moraes, Jobim] Joao Gilberto 1961。ジョビンのインストはアルバム「The Compser of Desafinado, Plays....」1963に、英語版はAstrud Gilbert 1965、Frank Sinatra 1967が有名。☆ 10. Falando De Amor (愛について語る)[Jobim] Tom Jobim & Miucha 1979。 ジョビン単独の歌唱はアルバム「Terra Brasilis」1980 収録。 11. Desafinado (調子はずれ) [Newton Mendonca, Jobim] Joao Gilberto 1959。Stan GetzとJoao の「Getz/Gilbeto」1963も有名。セルフカバーは「Stone Flower」1970収録。☆ 12. So Tinha De Ser Com Voce (それはあなたに起こるべくして起こった)[Aloysio de Oliveira, Jobim] Antonio Carlos Jobim 「The Wondeful World...」1965。「Elis & Tom」 1974における Elis Reginaのボーカルが最高。☆ 13. A Felicidade (幸せ「哀しみよさようなら」)[Vinicius de Moraes, Jobim] Orfeu Negro (黒いオルフェ)Sound Track 1959。Joao Gilberto 1959が定番。ジョビン自身は「The Wondeful World...」1965で。☆ 14. Ela E Carioka (彼女はカリオカ)[Vinicius de Moraes, Jobim] Sergio Mendes 1963。ジョビンのバージョンは「The Wondeful World...」1965。カリオカは「リオっ娘」の意味。☆ 15. Chega De Saudade (憧れは十分だ「想いあふれて」)[Vinicius de Moraes, Jobim] Elizeth Cardoso 1958。カルドーゾの歌は旧来の古風なスタイルだったが、その少し後に発売されたJoao Gilberto の新しい感覚の演奏が大評判となり、ここに「世界最初のボサノヴァ」が誕生した。ジョビンのインストバージョンは「The Compser of Desafinado, Plays....」1963。☆ ここでの坂本の演奏は無駄を極限までに省いた音数で、一部のファンにとっては物足りなく思うかもしれないが、ジョビンのプレイスタイルにショパン、サティ、ドビッシーなどの現代クラシックの香り付けをしたもので、ひとつひとつの音の粒の美しさは例えようがない。こんな風に弾ける人って、いるようでいないんだよね。ジャキスのチェロの厳格なクラシックの素養と自由でしなやかな精神が調和したプレイが素晴らしい。チェロの艶やかな音がジョビンの音楽にとても良く合っている。もっともアップテンポの曲では、弓を置いてピチカートによるベースの役割に専念しているけどね。ルイスのギターは控え目なプレイに終始するが、13.「A Felicidade」で唯一のギターソロを入れている。そしてパウラの透明感あふれるヴォイスはリオの空気を感じさせるものだ。ポルトガル語の原詩と日本語の訳詞を前に聴くと、豊穣な歌の世界が限りなく広がってゆく。本当に美しい音楽だ。 ちなみにNHK衛星放送による当該コンサート、アルバム「CASA」録音風景、3人のインタビューからなる映像がある。CDについては、8月28日の大阪フェスティバルホールでのコンサートのセットリストから当日のコンサートと同じ曲順と思われるのに対し、映像では編集により曲順は変更され、曲間に録音風景やインタビューが挿入されている。 ① Amor Em Paz ② Insensatez ③ Estrada Branca アルバム「Live In Tokyo」 未収録曲 (「Casa」に入っていた曲) ③ Sem Voce ④ Sabia ⑤ Caracao Vagabundo ⑥ Tema Para Ana ⑦ Tango ⑧ Desafinado ⑨ So Tinha De Ser Com Voce パウラはシェイカーを振りながら歌っている。 ⑩ A Felicidade ⑪ Ela E Carioca ⑫ Chega De Saudade ⑬ Samba Do Avidao アルバム「Live In Tokyo」 未収録曲 (「Casa」CDのボーナストラック)。パウラは歌いながらシェイカーを振り、曲の最後では坂本が左手でシェイカーを振りながら右手でピアノを弾き、ジャキスが弓を使ってクィーカーのような音を出しているのが面白い。最後に全員が並んでお別れの挨拶をしているので、アンコールで演奏された曲と思われる。 ③ Estrada Branca (白い道「This Happy Maddness」) [Vinicius de Moraes, Jobim] Elizeth Cardoso 1958。フランク・シナトラの英語歌 1971、ジョビンのセルフカバ(英語)は「Terra Brasilis」1980。 ⑬ Samba Do Avidao(ジェット機のサンバ) [Jobim] 映画「Copacabana Palceのサウンドトラック」1962。ジョビン自身では「The Wondeful World...」1965、「Miucha & Tom Jobim Vol.1」 1977など。歌詞のモデルとなった国際空港は、現在「アントニオ・カルロス・ジョビン空港」という名前になっている。 「Casa」録音風景は、2004年に発売された3人の録音・ツアー風景を日記風に記録した映像作品「Morekenbaum2/Sakamoto 3 Years」からの抜粋。 パウラが曲後に「Tango」について「龍一のボサノヴァよ」と語っているのが印象的。 これで「Tango」の歌詞は、日本語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語の4つあることになるね。 [2025年12月作成] [2026年1月追記] ポルトガル語歌詞の背景について追記しました。 |
|
| Mood 八代亜紀 (2001) 日本コロムビア | |
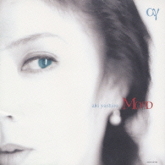 |
1. あなたとふたり [作詞 大貫妙子 作曲 平沢敦士 編曲 平沢敦士、佐々木康綱] 6曲目 八代亜紀: Vocal 進藤陽悟: Piano 里見紀子、高橋亜聖: Violin 蒲谷克典: Cello 成谷仁志: Viola 八代亜紀、川村昌司: Producer 2001年11月21日発売 1. Anata To Futari (Two With You) [Words: Taeko Onuki, Music: Atsushi Hirasawa, Arr: Atsushi Hirasawa, Yasutsuna Sasaki] 6th Track by Aki Yashior from the album "Mood" on Novemebrt 21, 2001 |
| 八代亜紀(1950-2023)に関する私の最初の記憶は、日本テレビ系列の歌謡番組「全日本歌謡選手権」だ。1970年代は歌手への登竜門としてのオーディション番組が流行っていたが、この番組はアイドル歌手向けではなく、下積みのプロ歌手が人生を賭けて背水の陣で挑戦する厳しいものだった。作曲家や歌手などの審査員の目に叶って10週勝ち抜いてグランドチャンピオンになった人が、メジャーデビューのチャンスを得ることができ、彼女の他に五木ひろし、中条きよし、山本譲二、天童よしみなどが本番組から世に出た。彼女の出演は1972年で、テレビを観ていた私は無名だった彼女の歌声・表情をはっきり覚えていて、それほど強烈な印象だったということだ。私は演歌は聴かないので、その後の彼女についてはテレビ番組やCM等で見聞きする程度となったが、2010年代以降に出されたジャズのアルバムを聴いて「上手い人だな」という印象は持っていた。 そんな彼女がCMの仕事で知り合った音楽プロデューサーの川村昌司と組んで制作したアルバムが本作「Mood」だ。彼の奥さんが八代の付き人だった関係もあって、家族的な付き合いの中で好きなように制作したようだ。当時の彼女は演歌がメインで、本格的なジャズのアルバムも出していない頃であり、そんな時期にソウル、クラブ・ミュージック、ボサノバ、ジャズ、クラシックなどに挑戦し、その過激な内容に彼女のファンは違和感を感じたはずで、キワモノと見做され売れなかったものと思われる。その後2010年にオンディマンドCDの発売、2013年のネット配信開始を経て再評価が進み、2024年11月の「レコードの日」に2枚組LPとして再発された。なおCDは稀少盤として中古市場で高値を呼んでいる。 1.「あなたとふたり」はストリング・カルテットとピアノをバックにした演奏。大貫さんの歌詞とこの編成での演奏ということで、ピュア・アコースティックを連想するが、作曲者の平沢敦士(アルバム・クレジットの「厚士」は漢字の間違い)のニューウェイブ的音楽性により、かなり趣が異なる感じになっているが、情感溢れる素晴らしい歌唱が新しい魅力を生み出している。なお本曲は2013年に出たジャズ、ポップス曲を集めたコンピレーション・アルバム「Mr. Something Blue 〜Aki's Jazzy Selection〜」に収められた。 その他の曲について。「愛を信じたい (MOOD Ver.)」(作詞 秋元康 作曲 中崎英也 編曲 佐々木康綱)1曲目は1991年発売のシングルの再録音で、ここではシンセサイザーと打ち込みを中心としたソウルフルなアレンジをバックにした八代のボーカルが素晴らしい。プロデューサーよると、レコーディングは目黒区の自宅近辺にあるスタジオ(世田谷区深沢)で、通常の仕事の帰りに立ち寄って行ったとのことなので、於日本として、一方バックコーラスは別途ニューヨークで録音されたもの。「イン・ザ・スターライト」(作詞 森雪之丞 作曲 南佳孝 編曲 Be The Voice) 2曲目は南得意のラテン調シティ・ポップで、鈴木茂がリズムギターで参加している。「Fly Me To The Moon」(作詞作曲 Bert Howard)3曲目、「Sweet Love」(作詞作曲 Ray Haden) 9曲目のアレンジを担当したレイ・ヘイドンは当時イギリスのソウル、アシッド・ジャズ界で活躍していた人で、これらのバックトラックはロンドンでの録音だ。前者は八代が好きなジュリー・ロンドンの歌唱で迫りながら、アレンジはヒップポップ、ラップという斬新な内容で、良く出来ていると思う。後者はクラブ・ミュージックそのもので、エフェクト処理がされた八代の歌声は現地のものとしか思えないグルーヴがある。 「おいしい水」(作詞 藤井千夏 作曲 平沢敦士 編曲 Singha's) 4曲目は、シンセと打ち込みによるジャパニーズ・ソウル。「Fusigi」(作詞 一倉宏 作曲編曲 鈴木智文)5曲目はクールなボサノバで、八代さんはこんな風にも歌えるんだ....うーん凄い。「Unchained Melody」(作詞 Hy Zaret 作曲 Alex North 編曲 長谷川智樹)7曲目は1955年の古い曲で、ライチャス・ブラザース1965年が定番。ここでは古風なサウンドとシンセをミックスしたアレンジで、本アルバムのなかでは比較的おとなしい感じ。「舟歌」(作詞 阿久悠 作曲 浜圭介 編曲 D.J. Boca-Parma, Kenn Nagai) 8曲目はご存知の名曲を外人DJがクラブ風にアレンジしたもの。一聴して「何これ?」と思う人が多いと思うが、私はとても良く出来ていると思う。 「Don't Cry」(作詞作曲編曲 EBBY)11曲目はファンクロック・バンド、ジャガタラのギタリストだったEBBYの曲で、J-Pop ソウルの佳曲。「生まれ変わる朝」(作詞 Aki Yashiro 作曲編曲 長谷川智樹)12曲目は本人が書いた本音じみた歌詞と彼女の歌を優しく包むクラシカルなサウンドが心に浸みる。最後の「Aki's Holy Night」(作詞 かの香織 作曲編曲 大沢誉志幸)13曲目は、その後八代さんのクリスマス・コンサートで必ず歌われたというジャズ・チューン。大沢本人がギター、佐山雅弘がピアノ、村上秀一がドラムスで参加している。 すべての曲において八代さんのボーカルが本当に素晴らしく、多様性が認められる前の時代に出た早過ぎた名作といえよう。当時この作品がもっと認められて、その結果いろんなスタイルで歌ってくれていたらよかったのに心から思う。ちなみにプロデューサーの川村昌司のインスタグラムに、レコード会社から配布された見本盤を関係者に渡す模様を記した「八代亜紀さんMOOD行脚」というシリーズ投稿があって、とても面白い内容なのでお勧め。 [2025年2月作成] |
|
| 2002年 note (2002/2/20) の頃 | |
| Smooth Le Gout Avec Piano Smooth Ace (2002) Toshiba EMI | |
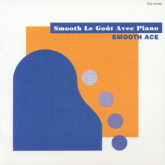 |
3. 新しいシャツ [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Team Smooth Ace コーラス・アレンジ Smooth Ace] 3曲目 重住ひろこ: Vocal 岡村玄、平慎也、李眞姫: Chorus 富樫春生: Piano 2002年5月22日発売 3. Atarashii Shatsu (The New Shirt) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Team Smooth Ace, Chorus Arr: Smooth Ace] 3rd Track by Smooth Ace from the album "Smooth Le Gout Avec Piano" on May 22, 2002 |
| スムースエースは岡村玄と重住ひろこを中心としたア・カペラ・ヴォーカル・グループで、1990年の大学サークルから始まり、平慎也、李眞姫を加えた4人組で
2001年に東芝EMIからCDデビューを果たし、佐藤博、小曽根真(ピアノ)、渡邊香津美、鈴木茂、徳武弘文(ギター)、小原礼、岡沢章、細野晴臣、高水健司(ベース)、林立夫(ドラムス)、浜口茂外也(パーカッション)などの豪華なバック陣でアルバムを制作した。本作はカバー作品集で、色違いのジャケット、オリジナル作品からなる「Smooth
La Musique Avec Piano」と同じ日に発売された。ベースが入った1曲を除きすべて富樫春生(ジャズ・ピアニスト、セッション・ミュージシャン)のピアノのみによる演奏。しかも間奏ソロなしの伴奏に徹して、それ以外の音をコーラスがカバーしているのが特徴。重住がひろこが大半のリードボーカルを担当しており、一部で李眞姫の声が聞こえる。男性は主にコーラスの役割を担い、女性ボーカルとデュエットで2曲歌っている。富樫の無駄のない美しいピアノをバックとした歌唱はシンプルかつストレートで、原曲の魅力を余すところなく伝え、コーラスはハミング、日本語の他に原曲にない英語のフレーズを歌って曲に彩りを与えている。 3.「新しいシャツ」は2回目のカバーで、大貫さんの「Romatique」1980がオリジナル。澄み切った空気の中で透明感に満ちたピアノとコーラスをバックとしたボーカルが若々しい(発売当時重住は30歳)。原曲の間奏部分の大村憲司のギターソロでは、コーラス隊が英語のフレーズを歌っている。しかしその意味がわかるようにはせず、器楽的に聞こえるようミキシング処理をしているところがミソ。 他の曲について (全曲につき 編曲 Team Smooth Ace コーラス・アレンジ Smooth Ace)。 1. 卒業写真 (作詞作曲 荒井由美) ハイファイセットの「卒業写真」1975、同年に作者のセルフカバー「Cobalt Hour」。 2. 未来予想図 II (作詞作曲 吉田美和) Dream Come Trueの「Love Goes On...」1989、吉田が高校生の時に作曲したもの。 3. 新しいシャツ 4. You Go Your Way (作詞 小山内舞 作曲 豊島吉宏) Chemistry シングル 2001。 ケミストリーは川畑要、堂珍嘉邦からなるヴォーカルデュオ。 5. もう恋なんてしない (作詞作曲 槇原敬之) 槇原敬之5枚目のシングル 1992で、日本テレビ系「子供が寝たあとで」主題歌。 6. Ride On Time (作詞作曲 山下達郎) 山下達郎 1980年のシングル、アルバムで、日立マクセル・カセットテープのCM曲。この曲のみグルーヴ感を強調するため、小原礼のベースを加えている。凝りに凝ったコーラス・アレンジが素晴らしい。 7. Tsunami (作詞作曲 桑田佳祐) サザンオールスターズ44枚目のシングル。 8. 抱きしめたい (作詞作曲 桜井和寿) Mr.Children 2枚目のシングル、アルバム「Kind Of Love」1992収録。 9. Anniversary〜無限にCalling You (作詞作曲 松任谷由美) ユーミン23枚目のシングル、アルバム「Love Wars」1989。KDD企業イメージソングとして使用。 10. 長い間(作詞作曲 玉城千春) Kiroroのデビューシングル(インディーズは1996、メジャーは1998)。 11. 駅(作詞作曲 竹内まりや) 中森明菜のアルバム「Crimson」1986が初出で、1987年のシングルでセルフカバー。 12. X'mas Day In The Next Life (作詞 鈴木慶一 作曲 高橋幸宏)高橋幸宏 1990年のシングル。 4人組によるグループは2004年に平、李の二人が脱退。その後は、2006年に結婚した岡村と重住の夫婦デュオ、および重住のソロで活動を続けている。 静かな夜に聴くと、心に染みこんでくるアルバム。大貫さんの曲の数あるカバーのなかでも出色の出来だと思う。. [2025年2月作成] |
|
| Hawaiian Munch 山弦 (2002) Universal | |
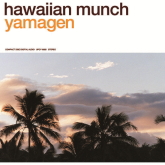 |
1. 蜃気楼の街 [作曲 大貫妙子 編曲 山弦] (Instrumental) 5曲目 佐橋佳幸: Nylon String Guitar 小倉博和: Nylon String Guitar 2002年6月21日発売 1. Shinkiro No Machi (The Mirage City) [Music: Taeko Onuki, Arr: Yamagen] (Instrumental) 5th track by Yamagen from the album "Hawaian Munch" on June 21, 2002 |
| 山弦は佐橋佳幸(1961- )と小倉博和(1960- )の二人のスーパーギタリストによるユニットで、1990年セッションで出会い、1998年に初めてのアルバム「Joy
Ride」を出した。エレクトリック、アコースティックの両方をこなす人達で、ふたりと大貫さんとのセッションワークは1990年の「New Moon」を最初として、その後もコンサート、レコーディングに頻繁に参加している。そして2001年に山弦の曲「祇園の恋」と「Harvest」(上述の「Joy
Ride」収録)に大貫さんが歌詞を付けて各「あなたを思うと」、「シアワセを探して」という曲名で2001年にシングルを発売し、その直後に「大貫山弦妙子
tabo 2001tour」を行った。その際にアンコールとして演奏されたのが「蜃気楼の街」のインストルメンタルで、それは翌年ハワイ・オアフ島でレコーディングされたカバー曲アルバム「Hawaiian
Munch」に収録された。ナイロン弦ギター2台による繊細な演奏で、歌無しながら聴いていてじ〜んと心に響く。 本アルバムはウクレレによる1曲を除き、全曲アコースティック・ギター2本のみによる演奏で、オルタネイト・ベースによるフィンガースタイルを使わないスタイルで他のフィンガースタイル・ギタリスト達のデュエットと一線を画している。歌伴で使われるリズム、オブリガード、ソロを発展させてインストルメンタルに仕上げた感じだ。以下曲目・作曲者・オリジナル・アーティスト(または主要アーティスト)と発表年および注記。 1. Moon River [Henry Manchini] Henry Manchini & Orchestra 1961: 映画「Breakfast At Tiffany's (ティファニーで朝食を)」のサウンドトラックで、映画では主演のオードリー・ヘップバーンが歌い、アンディ・ウィリアムス1962のカバーが有名。ナイロン弦ギターによる演奏。 2. Yeh Yeh [Roger Grant, Pat Patrick, Jon Hendricks] ①Mongo Sabtamaria 1963: もとはラテンのインスト曲だったが、②ボーカリーズのジョン・ヘンドリックスが歌詞を付けてランバート・ヘンドリックス&ロスによるジャズ・カバー1963 、③さらにイギリスのジョージ・フェイムのロック・カバー1964 で全英1位、全米21位の大ヒットを記録した。ここでの演奏の乗りは②に近い。 3. On Broadway [Barry Mann, Cynthia Weil, Jerry Leber, Mike Stoller] The Drifters 1963: バリー・マンとシンシア・ウェイルが作った曲にリーバー・アンド・ストーラーが改良を加えて完成させたもので、ザ・ドリフターズで全米9位のヒットとなった。ちなみに改良以前のザ・クッキーズによるデモ・バージョンを聴くことができ、両者を比較するとおもしろい。またジョージ・ベンソンによるカバー1978 全米7位も必聴。 4. Kona [山弦] 山弦2000: アルバム「High Life」収録曲のセルフカバーで、ウクレレ2台による演奏。 5. 蜃気楼の街 6. Never My Love [Don Addrisi, Dick Addrisi] The Association 1967: アドリシ・ブラザースの作曲で、全米2位の大ヒットを記録。ギターの胴を叩いてパーカッションのような音を出している。 7. Jeux Interdits [Unknown] Romance Anonimo (愛のロマンス)というスペインのギター曲: ルネ・クレマン監督の映画「Jeux Interdits (禁じられた遊び)」1952で使用されたナルシソ・イエペスのギター演奏が有名。ここでは2台のギターでブラジル音楽の味付けがされていて、とても面白い出来あがり。 8. Don't Give Up On Us [Tony Macaulay] David Soul 1976: 日本でも放送されたテレビ番組「刑事スタスキー・アンド・ハッチ」のハッチ役、またはクリント・イーストウッド主演の映画「Magnum Force (ダーティー・ハリー2)」の悪い警官役で有名なデビッド・ソウルのヒット曲(全米1位) 好きな曲への敬意を払いながら楽しんで演奏しているのがわかる。なかでも大貫さんの「蜃気楼の街」への思い入れたっぷりの演奏は素晴らしい。 [2025年3月作成] |
|
| Clarify Soul MIO (2002) SME (Sony) | |
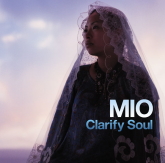 |
1. 好きのかたち [作詞 大貫妙子 作曲編曲 佐橋佳幸] 7曲目 MIO: Vocal 佐橋佳幸: Acoustic Guitar, Sound Produce 2002年10月23日発売 1. Suki No Katachi (Shape Of Love) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Yoshiyuki Sahashi] 7th track by MIO ftom the album "Clarify Soul" on October 23, 2002 |
| MIOについては、同名のシンガーが複数いてインターネットの情報が錯綜しているため、調査が難しかった。まずソニーミュージックのオフィシャルサイトに1999年から2001年までのディスコグラフィーがあったが、プロフィールやニュースはブランクだった。次にWikipediaの「MIO(シンガーソングライター)」を見ると、「R&Bシンガーソングライター、東京都原宿出身」とあり、アルバム3枚、シングル9枚とDVD1枚が載っていたが、それ以上の情報はなし。「MIO 原宿出身」で検索すると「井上ミオ (@mio3034)」のインスタグラムに行き当たり、そこには「メジャーアーティストを経て経営者へ (中略) 2011年から自由な音楽会社経営と、2017年から目黒近郊で発酵系朝挽き焼き鳥店(朝挽き鶏炭火焼き牡丹)を経営」とあった。そしてそのお店が目黒線の不動前駅にあり、クリエイティブな内容で高評価を受けていることがわかった。さらにそのインスタグラムにはYouTubeの「QOL channel」のアドレスが付いていて、彼女が家族や仲間たちとYouTube、FMラジオ番組をやっていた。さらに「MIO 牡丹 ブログ」の検索で「MIO〜リスペクトワールド」というブログを見つけることができた。そこには彼女が1973年生まれであること、自作の詩の発表や、バリ島ウブドにおにぎり屋をオープンしたこと、音楽活動について 2022年に21年振りにワンマンライブをやったことなどが書かれていた。ということで、アルバム・シングルの発表は2001年までだけど、現在は焼き鳥屋を経営しながらブログ、ラジオ、YouTubeなどで発信を続けていることがわかった。 本アルバムのタイトル「Clarify Soul」は「魂を明らかにする」という意味で、3枚目で最後のアルバムになる。ソウルフルなボーカルが魅力的な人で、ボーナストラック2曲を除く全10曲のうち6曲で河野圭、2曲で佐橋佳幸が編曲を担当している。1.「好きのかたち」は佐橋のアコギのみの伴奏によるシンプルなサウンド。大貫さんのピュアな歌詞を歌うMIOの歌はスローテンポでありながらもしっかりグルーヴしていて、アルバムの真ん中に配置されて変化と彩りを与える存在になっている。 その他の曲では佐橋編曲のもうひとつ「ひとりの歌」(作詞 朝水彼方 作曲編曲 佐橋佳幸)3曲目が良いね。シュガーベイブを彷彿させるサウンドで、聴いてるとニヤニヤしてしまう。「Seeds 〜ひまわりの種」(作詞 Shifo 作曲 Shifo, HIBINO GEnKI 編曲 河野圭」1曲目と「あなたに会いたい」(作詞 森浩美 作曲 長部正和 編曲 河野圭)5曲目は各シングルカットされ、「全国のFMチャートを賑わせた」と帯にある。「Clarify Soul」(作詞 MIO 作曲 森俊之 編曲 河野圭)は当時29歳だった本人の思いが籠められた歌詞と寄り添うソウルフルなサウンドが印象的な佳曲。「琥珀色の地球」(作詞 松本隆 作曲 平井夏美 編曲 阿部潤)9曲目は松田聖子1986年の作品(アルバム「Supreme」収録)のカバーで、ピアノとウッドベースのみによる伴奏。「Mother's Eternity」(作詞 町田俊行 作曲 亀井登志夫 編曲 河野圭)10曲目は、フジテレビ系ドラマ「怪談百物語」(竹中直人主演)のテーマ曲になった。最後の2曲は以前に出したシングル曲のリミッックスで、ボーナス・トラックとして収められている。 大貫さんの歌詞を佐橋佳幸の作曲とアコギ一本の伴奏で楽しめる。 [2015年2月作成] |
|
| ア・カペラ・ウィンターカヴァーソング集〜うぶごえ音泉 Baby Boo (2002) Waner Music Japan | |
 |
7. 春の手紙 [作詞作曲 大貫妙子 ア・カペラ・アレンジ 瀬川忍, Aqua] 7曲目 瀬川忍(シノブ): Vocal (Top Tenor) 水野裕介(ユースケ): Vocal (Tenor) 櫻井貴之 (チェリー): Vocal (Leed Tenor) 若松健治 (ケン): Vocal (Baritone) 藤森祐輔 (ユウ): Vocal (Bass) 桝田和宏 (Kazz): Vocal (Voice Percussion) 西垣哲二(Aquanotes), Baby Boo: Sound Producer 2002年11月13日発売 7. Haru No Tegami (The Letter On Spring) [Words & Music: Taeko Onuki, A Cappella Arr: Shinobu, Aqua] 7th track by Baby Boo from the album "A Cappella Winter Song Covers Ubugoe Onsen (Birth Voice of Sound Fountain) "on November 13, 2002 |
| ベイビー・ブーは1996年結成のコーラスグループで、2002年にメジャーCDデビュー。当初6人組でスタートし現在は5人で活動を続けている。本アルバムは2枚目(カバーアルバムとしては最初)の作品で、冬にちなんだ曲をカバーしたもの。翌年12月に第2弾として「ア・カペラ・ウィンターカヴァーソング集〜うぶごえ音泉2」を出している。アルバムの資料にはメンバーの名前がなく、CDジャケットのクレジット欄にも記載がないが、その代わりに男性6人の写真があるため、上記のメンバーであることが特定できた。それは2004年のヴォイス・パーカッション担当KAZZの脱退(グループがパーカッションやシンセサイザーを伴奏に付けることの選択を迫られたための脱退で、その後の彼はヴォイス・パーカッションの世界を追及し続けている)を除いてメンバー交替がないことからわかるように、彼らが一体であることを表しているようだ。 本アルバムはボーナス・トラックを除きすべて冬にまつわる曲で、楽器を使わず人の声だけで作られている。冷たい空気に包まれた静かな夜に聴いていると、ア・カペラのピュアな歌声が浸み入ってきて、心が透明になるような気がする音楽だ。7.「春の手紙」のオリジナルは、大貫さんが1993年に出したシングルで、TBS系ドラマ「家裁の人」の主題歌として使用され、2005年のアルバム「One Fine Day」に山弦の伴奏による新録音で収録された。ここでは来る春に向けての心情が素晴らしいコーラス・アレンジで歌われている。バックのリズムはどう聞いてもパーカッションか打ち込みにしか思えないけど、これはKAZZ(桝田和宏)のヴォイス・パーカッション。彼のパフォーマンスをYouTubeで観たが正に超人的だった。なお後年彼らがこの曲を歌う映像がYouTubeに投稿され、そこからリードボーカルはチェリー(櫻井貴之)であることがわかった。アレンジはメンバーの瀬川忍とAquaとあるが、後者は当時ベイビー・ブーをサポートしていたAquanotesという西垣哲二を筆頭とする集団のようだ。 他の曲について(特記ない場合は 編曲 瀬川忍, Aqua) 1.「Merry Christmas Mr. Lawrence」 [作曲 坂本龍一] 映画「戦場のメリークリスマス」1983のために作曲された超名曲をハミングとスキャットのみでアレンジした。クリエイティブなアレンジが最高で、オリジナルがもつ精神を見事に伝えている。 2. 「めぐる季節」[作詞作曲 小田和正] オフコース1976年9枚目のシングルで。同年のアルバム「Song Of Love」収録。 3. 「氷の世界」[作詞作曲 井上陽水] 1973年のアルバム・タイトル曲で、ヴォイス・バーカッションとベースでファンキーなリズムを表現している。 4.「クリームシチュー (The Stew)」 [作詞 糸井重里 作曲 矢野顕子] 矢野のアルバム「Oui Oui」1997収録。ここでは軽快な曲のリズムを変更する大胆なアレンジを施している。 5.「風」 [作詞 北山修 作曲 端田宣彦 編曲 浅田祐介, Aqua] はしだのりひことシューベルツによる1969年のフォークブームの名曲。本作のなかでは最もア・カペラらしいアレンジ。 6.「さらばシベリア鉄道」 [作詞 松本隆 作曲 大瀧詠一] 太田裕美1980年がオリジナルで、大瀧のセルフカバーは「A Long Vacation」1981に収められた。 7.「春の手紙」 8.「Little Christmas」 [作詞作曲 若松健治 編曲 瀬川忍] この曲のみメンバーが作曲したオリジナル。ア・カペラ・コーラスがぴったりはまった佳曲。 9.「歩いて帰ろう」初回限定盤のみに収められたボーナス・トラックで、斉藤和義1994年の代表曲のカバーでフジテレビ系の子供番組「ポンキッキーズ」のテーマ曲に使用された。この曲のみ明るい感じのドゥワップで冬っぽくないけど、ボーナス・トラックということで......。 クリエイティブなア・カペラが堪能できる逸品。素晴らしいアレンジによる「春の手紙」が楽しめる。 [2025年3月作成] |
|
| Livre norinha (2002) On The Decki | |
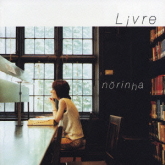 |
1. 海と少年 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 佐藤五魚] 6曲目 norinha: Vocal, Fender Rhodes 佐藤五魚: Programming, Keyboards 2002年11月20日発売 1. Umi To Shonen (The Sea And The Boy) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Go Sato] 6th track by norinha from the album "Livre" on November 20, 2002 |
| norinha (ノリーニャ、本名 五十嵐典子)は東京生まれ。ホテルのラウンジや結婚式でピアノを弾きながらデモテープを作成し、2002年にインディ・レーベルからCDデビューを果たし、3枚のミニアルバムを制作した。その後はライブ活動を行いながら他アーティストのアルバムやライブにピアニスト、ボーカリストとして参加したり、ヒップポップ・バンドのキーボード奏者として活動した。現在は演奏活動以外に目黒区祐天寺でピアノ教室を開催している。 本作は彼女のデビュー作で、帯のキャッチフレーズ「ボサノバ発、クラブジャズ経由、J-Pop行」にあるとおり、ブラジル音楽にジャズとJ-ポップを取り入れたサウンドを展開している。ブラジル音楽への傾倒が強く、7曲中2曲は英語、2曲は日本語とポルトガル語が混じった歌詞。アルバムタイトルはポルトガル語で「自由」という意味で、彼女の芸名も南米風だ。バンドが参加した本格的なサンバリズムの2曲を除き、キーボードと打ち込みによる音作りで、編曲と演奏担当の佐藤五魚は村上秀一との仕事が多かった人。 1.「海と少年」は大貫さんのアルバム「Mignonne」1978収録曲のカバーで、矢野顕子1986年、槇原敬之1998年に次ぐ3番目となる。打ち込みによる軽快なリズムのアレンジであるが、アルバムの中ではブラジル臭さが薄めで、J-ポップというかクラブ寄りのサウンドを意識した作りになっている。 他の曲について(以下 編曲はnorinha、佐藤五魚)。「ラジオの恋人」(作詞 こだまかおり 作曲 norinha) 2曲目、「O meu Brasil」 (作詞 norinha, こだまさおり 作曲 norinha) 5曲目は、ギター、ベース、パーカッションが加わったバンド編成による本格的なブラジリアン・ジャズの曲で、彼女のボーカルやピアノソロが活き活きしていて本来の音楽性が発揮されていると思う。私はカルロス・ジョビン、デオダード、ナラ・レオン等のブラジル音楽が大好きなんだけど、そんな私が聴いても良い出来だと思う。ただしこれらが日本で受けるか否かは別問題だけどね。「Tea For Two」(作詞 Irving Caesar 作曲 Vincent Youmans)3曲目は1924年の曲で、ドリスデイ1950年のカバーが有名なスタンダード・ソングのボサノバ・カバー。 「毎日がパーティーみたい」(作詞 norinha, こだまさおり 作曲 norinha) 4曲目は J-ポップ寄りの曲だ。「citrus」(作詞作曲 norinha 補作詞 深井由美子)は英語歌詞による落ち着いた感じのボサノバ。 日本人によるブラジル音楽としてかなりの出来だと思うが、今は忘れ去られてしまったのが残念だ。 [2025年2月作成] |
|
| ウサギチャンスーパースター !! Vol. 0001 Various Artists (2002) USAGI-CHANG | |
 |
1. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 エイプリルズ] 14曲目 [エイプリルズ] イグチミホ: Vocal, Synthesizer イマイケンタロウ: Vocal, Performer (All Sound Works) ナカムラタツヤ: Guitar シミズケイスケ: Bass ショトクジュウキ: Drums 鈴木アキラ: Producer 2002年11月21日発売 1. Metropolitan Museum [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Aprils] 14th track by Aprils from the album "Usagi-Chan Superstar !! Vol. 0001" (Various Artists) on November 21, 2002 |
| 大貫さんの「メトロポリタン美術館」は 1984年4月〜5月にNHKテレビ「みんなのうた」で初回放送された。清水信之編曲による大貫さんの録音は、1984年5月21日発売のシングル「宇宙みつけた」のB面としてディアハート(RVC)
レーベルから発売され、1986年3月21日発売のアルバム「Comin' Soon」に収められた。「みんなのうた」の中でも特に人気がある曲で、映像はその後も現在に至るまで頻繁に再放送され、各レコード会社が発売した「みんなのうた」曲集にも収められている。その際契約の関係で大貫さんのオリジナルを使えない場合、別の歌い手により録音したものを使うのが通例で、そのため本曲は他のアーティストによるカバーに加えてこの手の別録音が多く存在することとなった。 本作は上記のような原曲の再現でなく、独自のアレンジを施したバージョンの最初にあたる。渋谷系アーティストの鈴木アキラが設立したインディ・レーベルUSAGI-CHANG RECORDSが制作したエレクトロ・ガールズ・ポップのコンピレーション・アルバムで、全17曲打ち込みによるシンセサイザーをメインとしたサウンドをバックに女の子達が歌う。初期のテレビゲームにあったようなシンセのチープなサウンドを逆手にとったような音作りで、超高速の派手な曲やフランス語で歌うコケティッシュな曲など、いろいろ入っている。 そのなかで「メトロポリタン美術館」はシンセサイザーと生楽器を組み合わせた演奏。ザ・エイプリルズはイマイケンタロウとイグチミホによる男女のボーカルが主体のバンドで、アルバム制作とコンサートの他にゲームやテレビ番組、CM音楽なども手掛け、現在も元気に活動している。イントロは同じメロディーであるが、すぐに打ち込みのシンセサイザーの細かなリズム音が鳴り始め、イマイケンタロウの声が「M E T R O P O L I T A N」のスペルを語り、独自の世界が広がってゆく。イグチミホのボーカルもサウンドエフェクトを効かせた部分もあり少しニューウェイブな感じ。 エレクトロポップによる「メトロポリタン美術館」のカバーのはしり。 [2025年2月作成] |
|
| flavor 長谷川恵里 (2002) Inter | |
 |
1. 彼と彼女のソネット [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 大貫妙子 編曲 前田和彦] 11曲目 長谷川恵里: Vocal, Chorus 前田和彦: All Instruments, Edits 前田和彦: Producer 2002年12月11日発売 1. Kare To Kanojyo No Sonnet (His And Her Sonnet) [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Kazuhiko Maeda] 11th Track by Eri Hasegawa from the album "flavor" December 11, 2002 |
| 長谷川恵里についてはインターネットに資料がなくプロフィールは不明。2001年にインディ・レーベルからシングル3枚を出し、翌年本アルバムを発売後に表舞台から姿を消したという事だけしかわからない。プロデュースと全16曲の編曲および大半の演奏を担当した前田和彦は、1996年に坂本龍一のラジオ番組に投稿した楽曲が評価され、その後インディーの世界で活躍する作曲・編曲家、プロデューサー、エンジニアになった人。 アルバムは ①Active Side (7曲) ②Pops Side (3曲) ③ Relaxing Side (6曲)の3部構成からなり、ラッパーをフューチャーした曲もあるヒップポップ・サウンドのアクティブ・サイドのイメージが強烈で、後の部がかすんでしまっている。個人的にはヒップポップ系は得手ではないので、それらの打ち込み主体のサウンドを聴くのはつらいところがあるが、ポップスとリラクシングの部になるとソウルフルで聴き易く面白い曲が出てくるので、最後まで聴かずに途中で止めちゃう人がいることを考えると、ちょっと損な構成だなと思う。要するに彼女はソウル音楽をベースに何でも歌える人だったけど、いろいろ詰め込み過ぎたため、イメージを絞りきれず、結果売れなかったのではないかと思う。 本人作詞、前田和彦作曲による曲が大半を占める中で、1.「彼と彼女のソネット」は「Relaxing Side」の冒頭を飾るカバー曲。アレンジが凝っていて、本来のコード進行を無視した音使いにより一風変わったサウンドになっている。本人は真面目に綺麗に歌っているので、聴いていてちょっと不思議な感じになる。でもその試みはあまり成功したとは思えず、同曲のカバーのなかでは最も異質な感じになった。 他の曲では、ポップスの部の「とどけ君の空色へ」(作詞 長谷川恵里 作曲 小東義典 編曲 小東義典 前田和彦)8曲目が読売テレビ「あさリラ!」のオープニング・テーマ、「Growin' UP」(作詞 瀬田千恵子、長谷川恵里 作曲 前田和彦 編曲 前田和彦 小東義典)9曲目が日本テレビ「ウェークアップ!」のエンディング・テーマに採用されたそうだ。比較的アコースティックなサウンドのリラクシング・サイドにも「空白の時」(作詞 政谷剛史 作曲 政谷剛史、前田和彦 編曲 前田和彦、小東義典)12曲目などいい曲がある。そして最後の曲は、坂本九1963年の大ヒット曲のカバー「見上げてごらん夜の星を」(作詞 永六輔 作曲 いずみたく 編曲 前田和彦)16曲目。 今では忘れ去られた存在の歌手による、最も変わったサウンドの「彼と彼女のソネット」。 [2025年1月作成] |
|
| 2003年 note (2002/2/20) One Fine Day (2005/2/16)の頃 | |
| 君の音 松本英子 (2002) BMGファンハウス | |
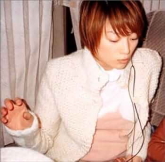 |
7. いつも通り [作詞作曲 大貫妙子 編曲 武部聡志] 7曲目 松本英子: Vocal, Chorus 武部聡志: Piano, Keyboards, Producer 小倉博和: Electric, Acoustic Guitar 美紅月千春: Wood Base 河村智康: Drums 三沢またろう: Percussion 山中雅文: Synthesizer Program 弦一徹ストリングス: Strings 2003年2月26日発売 7. Itsumo Dori (As Usual) [Words & Music: Takeo Onuki, Arr: Satoshi Takebe] 7th track by Eiko Matsumoto from the album "Kimi No Oto (The Note Of You)" on Febuary 26, 2003 |
| 松本英子(1979- 秋田県出身)は1999年6月19歳でシングル・デビューし、20歳になった同年9月の2枚目シングル「Squall」(福山雅治作詞作曲、プロデュース)が大ヒットして一躍有名になった。ファースト・アルバム「From
The First Touch」は10月の発売で、大半につき、作詞は川村真澄、只野菜摘(1曲のみ松本本人が只野と共作)が、作曲・編曲はスウェーデン人のダグラス・カーが担当している。本作は4枚目のアルバムで、全9曲中カバー6曲、セルフカバー1曲、オリジナル2曲という構成。武部聡志がプロデュースと全曲のキーボード、1曲を除く全ての編曲を担当している。 7.「いつも通り」は大貫さんのシュガーベイブ時代の曲(「Songs」1975収録)で、「蜃気楼の街」のカバーは数あれど、この曲についてはこれだけという珍しい存在だ。原曲よりもテンポをあげてソリッドなボサノバのアレンジになっている。ストリングスの一部はオリジナルに沿ったメロディーを奏で、原曲のサックスソロはピアノソロに置き換わっている。シュガーベイブ時代の大貫さんは、かなり声を張って歌っていたので、両者を比べると松本のほうが優しいように感じるのが面白い。 他の曲について(以下特記ない場合は 編曲 武部聡志)。 1.「今年の冬」 [作詞作曲 槇原敬之] 槇原敬之 1994 アルバム「Pharmacy」収録。槇原がハーモニー・ボーカルで参加、シングル・カットされた。 2.「思いの花束」 [作詞 松本英子、川江美奈子 作曲 川江美奈子] オリジナル、他のカバー曲に引けを取らない良い出来。 3.「ワインの匂い」 [作詞作曲 小田和正] オフコース 1975の名曲。 同タイトルのアルバムに収録。 4.「花」 [作詞作曲 喜納昌吉 編曲 Smile & Tears] 喜納昌吉とチャンプルーズ 1980、 アルバム「Blood Line」収録。友人のシンガー・アンド・ソングライター、加藤いずみがハーモニー・ボーカルで参加。 5.「日常」 [作詞 松本英子 作曲 武部聡志] オリジナル、これもなかなかいい出来。 6.「Forever Friends」 [作詞作曲 竹内まりや] 竹内まりや、 1992 アルバム「Quiet Life」収録。ホンダ・トゥデイのCMソング。 7.「いつも通り」 8.「Squall」 [作詞作曲 福山雅治] 1999年シングルのセルフカバー。ここでの彼女は武部のピアノとストリングスのみのバックで、しっとりと歌っている。 9.「夢見るシャンソン人形 (Additional Track)」 [作詞作曲 Serge Gainsbourg] France Gall 1965年の名曲シャンソン。彼女が歌う日本語バージョンもある。ここでは松本がフランス語で頑張って歌っている。 松本の爽やかな声の魅力が生かされている。彼女はその後も息の長い音楽活動を展開。その他として福山雅治のライブへのコーラス参加やラジオ番組のDJなどでも活躍している。 「いつも通り」の珍しいカバーを聴ける。 [2025年4月作成] |
|
| Treasure The World 有里知花 (2003) Virgin (東芝EMI) | |
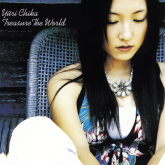  |
10. あなたに会いに行こう [作詞 大貫妙子 作曲 宮沢和史 編曲 高野寛] 10曲目 有里知花: Vocal 斉藤哲也: Acoustic Piano 高野寛: Guitars, Chorus, Producer 鈴木正人: Bass, Organ 沢田周一: Drums 柳田謙二: Percussion 写真上: アルバム 2003年9月3日発売 写真下: シングル 2003年6月25日発売 10. Anatani Ai Ni Yukou (I'll Come To see You) [Words: Taeko Onuki, Music: Kazufumi Miyazawa, Arr: Hiroshi Takano] 10th track by Chika Yuri from the album "Treasure The World" on September 3, 2003 |
| 有里知花(1981- )は神奈川県生まれ。母親の宮前ユキ(2014年没)はカントリー歌手として有名だったが、日本におけるハワイアン音楽の浸透に貢献した人でもあった。そんな親の元で育った彼女はハワイとの縁が深く、2001年同地で出したシングル「I
Cry」がローカル・ヒットし、その後「hana」のシングル、アルバムで日本デビューした。英語の歌唱が大変上手い人で、英語の歌詞による曲、英語の歌詞が混じった日本語の曲が多く、無国籍な雰囲気がある。 彼女が2003年の日本ASEAN交流年(1967年設立の東南アジア諸国連合と日本の交流30周年を記念して当時の小泉首相の提唱により行われ、日本側は国際交流基金が企画担当を務めた)のイベントひとつとして開催された「J ASEAN Pops」のイメージソングとして歌ったのが10.「あなたに会いに行こう」だ。大貫さんによる国境を超えた出会いを描いた歌詞、宮沢和史による特定の国でないアジアを感じさせるメロディーによるスケールの大きな曲、高野寛の編曲と有里知花の歌唱により融和と協力を象徴する名曲となった。 まずシングルが先行発売され、次いで曲が収められたアルバム「Treaure The World」が発売された。さらに同曲はASEAN各国で母国語の歌詞が付けられて、その国の著名シンガーによって歌われた。さらに10月22日ジャカルタ、26日バンコク、そして12月21日横浜で各国の歌手が参加したジョイントコンサートが開催され、そのフィナーレで同曲が歌われた。そのうちNHK衛星放送による12月21日横浜パシフィコでの映像を観ることができた。それは約10分にわたり各国の歌手達がこの歌を母国語で歌い継ぐ素晴らしいパフォーマンスだった。以下参加歌手を登場順にリストアップした。 ① 有理知花(日本): イントロダクション(語り) ② 宮沢和史(日本): スキャット (ガットギターを弾きながら) ③ Dick Lee (ディック・リー、 シンガポール): 英語(ピアノを弾きながら) ④ 有理知花(日本): 「あなたに会いに行こう」 ⑤ Briohny Smyth (ブライオニー、タイ) ⑥ Tanya Chua 蔡健雅(タニア・チェア、シンガポール): 中国語 ⑦ Alexandra Bounxouei (アレクサンドラ・ブンスアイ、ラオス) ⑧ Jolina Magdangal (ジョリーナ・マグダンガル、フィリピン) ⑨ Koh Mr. Saxman (コウ・ミスター・サックスマン、 タイ) :アルトサックス・ソロ ⑩ Preap Sovath (プリアップ・ソヴァット、 カンボジア) ⑪ Lay Phyu (レービュー、 ミャンマー): Iron Cross のボーカリスト ⑫ Lam Truong (ラムチューン、ベトナム) ⑬ Lo Ryder (ローライダー、ブルネイ) ⑭ Hans Anwar (ハンス・アンワル、ブルネイ) ⑮ AB Three (AB スリー、インドネシア) ⑯ Siti Nurhaliza (シティ・ヌルハリザ、 マレーシア) ⑩⑪でR&B調、⑫⑬⑭でラップ調になるなど、高野寛による柔軟でしなやかで飽きさせることのないアレンジ、その後も各国で代表的な歌手であり続けた人達の思いが籠った歌唱は感動的。ちなみに上記以外にブライオニー④とアレクサンドラ⑦が、それぞれ別のコンサートで有里と歌った映像も残っている。 なお宮沢のメロディーも日本語以外の歌詞を載せた公式録音が少なくても二つ存在する。シンガポールの鬼才ディック・リー③が作詞した英語と中国語のバージョンで、前者は有里知花の上記シングル「Treasure The World」に同じタイトルで収録された(アルバムには入っていない)。歌われている歌詞の内容は大貫さんの歌詞の訳ではなく、同じ精神で書かれた別のものになっている。後者は同じく有里の歌で「珍愛這世界」というサブタイトルの配信で聴くことができるが、当初どういう形でリリースされたかについての情報は見つからなかった。また本曲は2004年の台湾のテレビドラマ「100% Senorita (千金百分百)」で日本語バージョンが挿入歌として使用されたので、同地でも知られた曲になっている。 その他の曲について。 1.砂浜ラブレター [作詞 Kenneth Makuakane 徳田憲治 作曲 Kenneth Makuakane 編曲 Tsukada] 2. Such A Beautiful Feeling [作詞作曲 Eric Justin Kaz 編曲 黒沢秀樹] 3. Thank You -Oceans Of Love- [作詞作曲 Kenneth Makuakane 編曲 山本隆二] 4. 懐かしのキャシィ・ブラウン [作詞作曲 荒木一郎 編曲 小倉博和] 5. If Not For You [作詞 Dick Lee 作曲 宮沢和史 編曲 冨田恵一] 6. 浜辺(skit) 7. それぞれの浜辺で同じ月を見ている [作詞 GAKU-MC 有里知花 作曲 高野寛 有里知花 編曲 高野寛] 8. 風にたくして [作詞作曲 有里知花 編曲 高野寛] 9. 地平線の向こうへ [作詞 有里知花 作曲 佐藤竹善 編曲 黒沢秀樹] 10. あなたに会いに行こう 11. TSUNAMI [作詞作曲 桑田佳祐 編曲 小倉博和] 英語の曲は2, 3, 5の3曲で、1,9は歌詞のなかに英語の部分がある。1, 3 の作者は上記のハワイでヒットした「I Cry」を手掛けた人。2の作者はアメリカ人のシンガー・ソングライターで、リンダ・リンシュタットやボニー・レイットが歌った「Love Has No Pride」が代表作。本曲は彼がメンバーだったグループ、アメリカン・フライヤーのセルフタイトル・アルバム1976に入っていた。4は荒木一郎1976年のカバーで、ハワイの香りが漂うアメリカン・ポップス。5は冨田ラボの冨田恵一が編曲と演奏を担当した極上の音楽。6はウクレレと本人のスキャットによる45秒の断片。7, 8は本人による作詞作曲で高野寛が制作に関わり、7に入っているGAKU-MCのラップが面白い。9.の佐藤竹善はSing Like Talkingのフロントマン。ボーナストラックの11は、山弦の小倉博和による南国風のアレンジが面白いサザンの曲。ということで、どの曲も良い出来だと思う。 有里はその後少ないながらもアルバム発表とコンサート活動を続けていたが、2015年以降の記録は見つからなかった。海外と日本の市場の狭間のなかで無国籍な持ち味を生かしきれず、歌手としてのステータスを固めきれなかったのではないかと思う。近年のYouTubeへの投稿から海外(アジア)のファンが今もいるようだ。 埋もれさせるにはもったいない名曲・名作。 [2025年3月作成] |
|
| 2004年 note (2002/2/20) One Fine Day (2005/2/16)の頃 | |
| 空に星があるように 井上芳雄 (2004) ビクターエンタテイメント | |
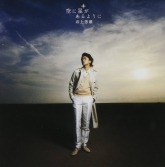 |
1. 黒のクレール [作詞作曲 大貫妙子 編曲 羽岡佳] 1曲目 井上芳雄: Vocal 2004年8月11日発売 1, Kuro No Claire (Black Claire) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Kei Haneoka] 1st Track by Yoshio Inoue from the album "Sora Ni Hoshi Ga Aru Yoni" (Like There Are Stars In The Sky) on Augst 11, 2004 |
| ミュージカル界の頂点に立つ井上芳雄(1979- 福岡県出身)25歳の時の作品。彼のデビューは東京藝術大学声楽科在学中の2000年で本作はアルバムとしては2枚目。数多くの舞台、コンサート、映画、テレビに出演し、声優や司会などマルチな活躍をしている彼であるが、当時は「ミュージカル界のプリンス」と言われながらメディアへの露出はまだ少なかった頃。2曲のオリジナル以外は、日本のポップスの名曲を男女・時代に関係なく選んでいて、自分が好きな曲を歌っているのがよくわかる。女性受けする甘い顔と声のため、私は少し斜に構えて聴いてみたが、曲に対する敬意に満ちた誠実な歌唱が心に響いてきて実に良いのだ。 冒頭曲1.「黒のクレール」は大貫さんのアルバム「Cliche」1981のカバー。羽岡佳の編曲はストリングスとピアノを中心としたクラシカルなサウンドで、井上は素直に伸びやかに歌っている。この人は男女を超越した声色を持っていて、聴いていて歌の内容が目に浮かぶのは、ミュージカル・シンガーとしての特質だろう。ミュージシャンのクレジットはなし。 他の曲は以下のとおり(曲名 作詞 作曲 編曲、オリジナルと発表年) 1. 黒のクレール 2. 木綿のハンカチーフ: 松本隆 筒美京平 羽岡佳、 太田裕美 1975 3. 花鳥風月: Satomi 服部隆之 服部隆之 (オリジナル) 4. 空に星があるように: 荒木一郎 荒木一郎 服部隆之、 荒木一郎 1966 5. 上を向いて歩こう: 永六輔 中村八大 羽岡佳、 坂本九 1961 6. 胸の振り子:サトウハチロー 服部良一 服部隆之、 霧島昇 1947 7. 琥珀色の地球: 松本隆 平井夏美 花岡佳、 松田聖子 1986 8. 恋のバカンス: 岩谷時子 宮川泰 服部隆之、ザ・ピーナッツ 1963 9. You Are The Top: 三谷幸喜 井上陽水/平井夏美 上柴はじめ、 舞台劇 「You Are The Top 〜 今宵の君」 2002 10. 伝えたい・・・ありがとう: 井上芳雄 羽岡佳 羽岡佳 (オリジナル) 2.「木綿のハンカチーフ」は「エー?」という選曲だけど、意外にいい感じ。3.「花鳥風月」は軽やかなボサノヴァ曲。彼の声は聴く人の心を癒す魅力があるね。4.「空に星があるように」、5.「上を向いて歩こう」は彼のパーソナリティーにぴったり。6.「胸の振り子」は日本のポップスの父、服部良一の名曲で編曲者の隆之は彼の孫。7.「琥珀色の地球」は松田聖子の代表曲で、本アルバムにはボーナスとして当曲のライブ映像を収めたDVDが付いていて、井上の若々しい姿を観ることができる。 8.「恋のバカンス」も面白い選曲で、ここではザ・ピーナッツのハーモニーを多重録音でこなしている。9.「You Are The Top」は三谷幸喜作・演出のロマンティック・コメディーの劇中歌。市村正親、浅野和之、戸田恵子主演によるDVDが発売されている。陽水本人のヴァージョンは2002年のアルバム「カシス」に収録。本アルバムの中では最もミュージカル風の曲だ。10.「伝えたい・・・ありがとう」は井上本人の作詞によるオリジナル。 [2025年4月作成] |
|
| 沿志奏逢 Bank Band (2004) Toys Factory | |
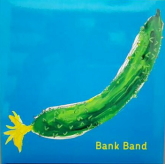 |
4. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Bank Band] 4曲目 櫻井和寿: Vocal 小林武史: Keyboards 古川昌義: Guitar 山本拓夫: Soprano Sax 美紅月千晴: Bass 山木秀夫: Drums 2004年10月20日発売 4. Totsuzen No Okurimono (The Sudden Gift) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Bank Band] 4th Track by Bank Band from the album "Soshi Soai" on October 20, 2004 |
| 2003年設立の社団法人 ap bankは、小林武史、櫻井和寿(Mr. Children)、坂本龍一が拠出した資金を環境保護、自然エネルギー促進、省エネルギーなどの環境保全に関する個人や団体へ低金利で融資する非営利団体。その資金集めおよび同団体の活動周知のために小林と桜井はBank
Bandを結成し、2004年から現在に至るまでライブ活動を行っている。第1回目は2004年1月に六本木で行われたが、それ自体は赤字だったこと、ライブの手応えが良かったことからCDが制作され、同年10月に30万枚限定で発売されその収益はap
bankの運営資金に充当された。そこにはライブで演奏されたカバー曲が収められ、選曲した櫻井は「単に自分が好きだった曲を選曲したのではなくて、自分なりにメッセージを感じ取って、なおかつ演奏するとき、それを込めてやってみました」、小林は「自分たちのごく身近にあった過去の楽曲のなかのメッセージを紡いでいくことで、新しいメッセージをつくる、そのことにこそ、意義があると思っています」と語っている。収録された12曲(Secret
Track含む)の構成は10曲が1972年〜1998年のカバーで 2曲がMr.Childrenのセルフカバー。いろんなタイプの曲があるが、一貫しているのはメッセージ性の強さで、櫻井のボーカルからこれらの曲を歌いたい、伝えたいという強い思いが伝わってくる。 小林と彼の音楽仲間であるスタジオ・ミュージシャンによるバックであるが、ライブを前提としているため、シンセサイザーの打ち込みのないシンプルでストレートなバンド・サウンドになっている。山本のソプラノ・サックス・ソロ以外は派手な演奏はなく、皆櫻井の歌を引き立ている役に徹している。曲に対する新解釈や奇をてらったアレンジはなく、原曲に対する敬意が籠っていて、歌と演奏によって如何に思いを伝えるかということに注力しているようだ。 4.「突然の贈りもの」は、社会性のあるメッセージ・ソングが多い中で、男女の関係を描いた異質の存在であるが、女性の思いをしっかり伝える歌詞により、アルバムの中にしっくり収まっている。「Mignonne」1978の原曲の坂本龍一に対し、ここでは小林武史のアレンジが楽しめる。彼が大貫さんのバックをやっていた時のライブアルバム「Live '93 Shooting Star In The Blue Sky」1996にはこの曲が入っていないので、そういう意味でも面白い一曲。櫻井は素直な感じで真正面からの歌唱に取り組んでいる。オリジナルでは松木恒秀のギターだった間奏ソロは、ここでは山本のソプラノ・サックスが担当している。 他の曲について(全曲につき編曲 Bank Band、弦編曲 小林武史、四家卯大) オリジナル・アーティスト、初出作品「アルバム」、発表年 1. 僕たちの将来 [作詞作曲 中島みゆき] 中島みゆき「はじめまして」1984 2. カルアミルク [作詞作曲 岡村靖幸] 岡村靖幸 シングル、「家庭教師」1990 3. トーキョー・シティー・ヒエラルキー [作詞作曲 山口洋] ヒートウェイブ 「Tokyo City Man」 1997 4. 突然の贈りもの 5. 限りない欲望 [作詞作曲 井上陽水] 井上陽水「断絶」 1972 6. マイ・ホーム・タウン [作詞作曲 浜田省吾] 浜田省吾 シングル、「Promised Land 〜約束の地」 1982 7. 糸 [作詞作曲 中島みゆき] 中島みゆき 「East Asia」 1992 8. Hero [作詞作曲 櫻井和寿] Mr. Children シングル2002 9. 幸福のカノン[作詞作曲 さねよしいさ子] さねよしいさ子 「ペクレナトルポポワ」 1990 10. 優しい歌 [作詞作曲 櫻井和寿] Mr. Children シングル 2001 11. 歓喜の歌 [作詞 遠藤賢司、岩佐東一郎、作曲 Ludwig van Beethoven] 遠藤賢司 「嘆きのウクレレ」 1972 以下Secret Track (12か13のいずれかが収録。ジャケットに表示がないので、実際に聴かないとどちらか分からないようになっている) 12. 僕と彼女と週末に [作詞作曲 浜田省吾] 浜田省吾 「Promised Land 〜約束の地」 1982 13. イメージの詩 [作詞作曲 吉田拓郎] 吉田拓郎] 吉田拓郎 シングル、 「青春の詩」 1970 中島みゆきの 7. 「糸」は、現在は名曲・傑作の評価が確立しているが、1992年の発表時はアルバムの中の1曲に過ぎなかった。その後テレビドラマ「聖者の行進」1998の主題歌に採用されてシングルCDが発売されたが、世間に認知されたのは、2004年の本アルバムでのBank Bandのカバーが住友生命のCMに使用されてから。その後2010年以降多くのアーティストがカバーするようになって、その地位を不動のものにした。セルフカバーの8.「Hero」、10.「優しい歌」は、Mr.Childrenではバンドサウンドだったの対し、ここでは前者が小林のピアノ、山本のソプラノ・サックス、後者は櫻井のギター、小林のキーボードを中心としたシンプルなアレンジで、櫻井のストレートな歌唱が印象的。9.「幸福のカノン」は一風変わった感じの面白い曲で、アルバム中の気分転換的な存在。 営利目的、オリジナル曲制作の苦労から解放された自由でピュアなメッセージ・ソングがここにある。「突然の贈りもの」のシンプルかつストレートなカバー。 [2025年6月作成] |
|
| Calore 鈴木慶江 (2004) EMI Classic | |
 |
1. 美しい人よ La Violetera [作詞 Eduardo Montesinos 日本語歌詞 大貫妙子 作曲 Jose Padilla Sanchez 編曲 三宅一徳] 4曲目 鈴木慶江: Vocal 三宅一徳: Keyboards 田代耕一郎: Guitar 篠崎正嗣: Strings 三沢またろう: Percussion 2004年11月10日発売 1. Utsukushii Hito Yo La Violetera (The Beautiful One) [Words: Eduardo Montesinos, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Music: Jose Padilla Sanchez] 4th track by Norie Suzuki from the album "Calore" on November 10, 2004 |
| 鈴木慶江(1973- )は神奈川県出身のソプラノ歌手。東京藝術大学やイタリアの大学で声楽を学び、2007年以降は日本で活動する。ソロリサイタルを主にテレビやラジオへの出演、CM、社会貢献活動など幅広い活動をしている。「Calore」(イタリア語で「情熱」という意味)は3枚目のアルバムで、クラシックにとどまらず、ポピュラー、トラディショナルにも取り組んだ意欲作で、大貫さんの「美しい人よ」のカバーが入っている。 「美しい人よ」はスペインの古い歌に大貫さんが日本語の歌詞をつけたもの。原曲の「La Violetera」(邦題「花売り娘」)は1914年ホセ・パディラの作曲。エデュアルド・モンテシノスの歌詞は春のマドリードでスミレを売る娘たちを描いたもの。1920年代のハバネラのリズムによるラケル・メラのバージョンが最初のヒットで、チャップリンが映画「City Lights」1931で取り上げて有名になった。その後多くの人がカバーしたが、1987年のナナ・ムスクーリの録音が絶妙なアレンジと透き通る歌声で曲の美しさを最大限に引き出し決定版となった。それは本当に惚れ惚れする素晴らしさだ。 大貫さんは1994年にシングル盤で発売。日本語歌詞は原曲の春のイメージのみを引き継いだ全く異なる内容であるが、彼女らしい気品が香り立つ逸品になっている。ハープ奏者の浅川朋之のアレンジによる、ナナのヴァージョンに磨きをかけた感じのハープやストリングスの調べと、大貫さんの凛とした歌声が本当に最高。なお本曲はJR東海のCMに使用され、1995年のアルバム「Tchou」には別録音が収められた。 本作はこの曲の最初のカバーになる。鈴木のソプラノ・ヴォイスがいい味を出している。一般的にソプラノ歌手の歌声は頭にキンキンくるケースが多いけど、彼女の声には優しい丸みがあって、高い声には珍しい癒しがあるのだ。確かにクラシック風なんだけど堅苦しさはなく、歌う人の思いが豊かな声に乗せて広がってゆくような感覚があって、聴いていてそれなりに心地良い。自由な精神を持っている人なんじゃないかなと思う。アレンジを担当した三宅一徳は多様なジャンルの音楽をこなす作曲家、編曲家、キーボード奏者で、大貫さんのシングル・バージョンをベースとした音作りになっている。なおライナーノーツで鈴木は本曲につき以下のようにコメントしている。 偶然に出会った心地よいメロディー 歌っていた時 ニースの青い海 モナコの爽やかな空 あるいはポジターノの海岸線の風が 私の周りに広がっていました 他の曲について(特記ない場合: 編曲 三宅一徳) 「Mal di Luna 月光(ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第14番より)」(作詞 Rinaldi Giuseppe 作曲 Ludiwig van Beethoven) 1曲目 歌詞がついたバージョンがあるとは知らなかった。何か聴いていて不思議な感じ。 「Reverie 夢」(作曲 Debussy) 2曲目はハミングによる歌唱。本当に美しいメロディーで、神々しい感じ。 「Air on G String - Du bist wie eine Blume G線上のアリア〜君は花のごとく」(作詞 Heinrich Heine 作曲 J.S. Bach 編曲 奥居史生) 3曲目 ハイネによるこの詩は通常シューマン作曲で歌われるが、ここではバッハの曲に合わせている。他に例がないようで、本作のためのアレンジかな? 「Scarborough Fair」(Traditional) 6曲目 ポール・サイモンがアレンジしたアルペジオとケルト音楽調の伴奏を合わせたアレンジ、そして透き通った歌唱が美しい。 「Traumerrei from "Kinderszenen" Op.15 トロイメライ〜「子供の情景」作品15より」 (作詞 伊藤美佐子 作曲 Robert Shumann) 7曲目 シューマンの名曲にドイツ語の歌詞をつけたもの。 「Winter from "Four Seasons" 冬〜「四季」より」(作詞 鈴木慶江 作曲 Antonio Lucio Vicaldi) 8曲目 鈴木本人がイタリア語の歌詞をつけている。 「星めぐりの歌」(作詞作曲 宮沢賢治)9曲目 賢治の作品「双子の星」や「銀河鉄道の夜」に出てくる歌。他の作品に比べて異質な印象があるが、聴いてみるとアルバムの世界観にしっくり合っている。 「Ave Maria アヴェ・マリア」(作詞 Walter Scott ドイツ語訳 Adam Storck) 10曲目 心が洗われる曲。 ソプラノ歌手による美しい「美しい人よ」。 [2025年2月作成] |
|
| Three Different Tones 畠山美由紀 (2004) Tone&Co | |
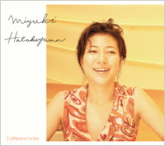 |
4. 新しいシャツ [作詞作曲 大貫妙子] 4曲目 畠山美由紀: Vocal 笹子重治: Guitar 録音: 2004年9月12日 原宿 Blue Jay Way 発売: 2004年11月22日 1. Atarashii Shirts (The New Shirts) [Words & Music Taeko Onuki] 4th track by Miyuki Hatakeyama from the album "Three Different Tones" on November 22, 2004 |
| Port Of Notes(本ディスコグラフィー2009年のアルバム「Luminous Helo」参照)のボーカリスト畠山美由紀が、ソロで3人の異なるスタイルのギタリストと各1対1で開いた「Three
Different Tones」という企画コンサートのライブ盤。原宿にあったライブハウス「Blue Jay Way」(2006年閉店)が会場で、1回目が7月11日(小沼ようすけ
= ジャズ)、2回目が8月4日(福原将宣=フォーク、ロック)、3回目が9月12日(笹子重治=クラシック、ブラジリアン)だった。 4. 「新しいシャツ」は笹子重治のナイロン弦ギターによる伴奏。彼はブラジリアン・スタイルのギタリストで、ショーロ・クラブというグループのリーダーでもある。彼と同じくブラジル音楽を愛する畠山とは、現在に至るまでCD制作やコンサートで共演する仲。畠山のインタビューの中で、インタビューアーが「笹子さんのギターが奏でられると、瞬間、そのギターの音色に恋に落ちるように畠山さんが歌に入り込んでゆくのがわかります」と語っている通り、ギター1本、しかも持続音の少ないナイロン弦でのミニマムな音の間が静寂の世界を作り出し、畠山もそれに応えて奥深い情感の籠った歌唱をみせている。まさに大貫さんのストイックさが際立ったこの曲にぴったりのパフォーマンスで、もともとピアノの弾き語りのアレンジが多いなかで、特異な存在感を発揮している。 その他の曲について(曲名、歌詞の言語、作詞作曲者、オリジナルと発表年、本作におけるギター伴奏者、特記) 1. Summertime 英語[作詞 DeBose Heyward, Ira Gershwin 作曲 George Gershwin] Porgy And Bess (Musical) 1935 小沼ようすけ。ビリー・ホリデイ1936, エラ・フィッツジェラルドとルイ・アームストロング1959のカバーが有名。フィンガスタイルによるジャズギターの伴奏による畠山の歌唱には少しモダンな渋みがあって、私はフィービー・スノウを思い出した。 2. Diving Into Your Mind 英語[作詞作曲 畠山美由紀] 畠山美由紀 2002 福原将宣。 オリジナルは彼女のソロデビューとなるシングル盤で、アコースティック・ギター、ベース、キーボードによる伴奏。 3. 真夏の草原 日本語 [作詞作曲 畠山美由紀] 畠山美由紀 2003 福原将宣。アルバム「Wild And Gentle」2003収録。釧路湿原を走る汽車のイメージで作った曲とのことで、歌詞・メロディー、歌唱・演奏すべてにおいて素晴らしい出来。 4. 新しいシャツ 5. ロマンスをもう一度 日本語 [作詞 上野泰明 作曲 葛谷葉子] 葛谷葉子 2007 笹子重治。小田急ロマンスカーのCMソング。 6. Time After Time 英語 [作詞作曲 Cyndi Lauper, Rob Hyman] Cyndi Lauper 1984 福原将宣。全米1位の名曲。この曲のみコーラス部分で福原がハーモニー・ボーカルをつけている。 7. 蘇州夜曲 日本語 [作詞 西條八十 作曲 服部良一] 渡辺はま子、霧島昇 1940 小沼ようすけ。同年の李香蘭の映画「支那の夜」で使用された名曲で、彼女の歌によるレコードは1953年に発売された。 8. Cantador 英語 [作詞作曲 Dorival Caymmi, Nelson Motta 英語詩 Alan and Marilyn Bergman] Dori Caymmi 1972 笹子重治。オリジナルはブラジル人ドリ・カイミによるポルトガル語の歌(タイトルは「歌手」の意味)だったが、ここではサラ・ヴォーンが彼の伴奏で録音した英語歌詞のバージョン「Like A Lover」1977のカバー。サラの壮大な歌唱が素晴らしかったが、ここでの畠山のピュアで透明感ある歌いっぷりもとても良いね。 9. ほんの少し 日本語 [作詞 畠山美由紀 作曲 小島大介、畠山美由紀] Port Of Notes 1999 福原将宣。Port Of Notesのミニアルバム「More Than Paradise」1999に収録され、2021年に「Two」でセルフカバーされた曲。 10. あなたの街へ 日本語 [作詞作曲 畠山美由紀] 畠山美由紀 2003 笹子重治。アルバム「Wild And Gentle」2003収録。 以上のとおり、全10曲中カバーが6曲、オリジナルのセルフカバーが4曲、日本語の歌が6曲、英語の歌が4曲という構成。3人のギタリストのスタイルの違いの面白さ、歌い手と伴奏者の心の交流が強く感じられる作品で、静謐な「新しいシャツ」としてピカイチの存在。 [2025年10月作成] |
|
| 2005年 One Fine Day (2005/2/16)の頃 | |
| The Note Of My Nineteen Years 竹井詩織里 (2005) Tent House | |
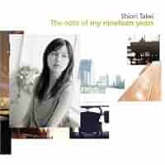 |
2. 蜃気楼の街 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Dr. Terauchi, Pierrot Le Fou] 2曲目 竹井詩織里: Vocal 増崎孝司: Guitar 小野塚晃: Keyboards 勝田一樹: Sax 村田浩一: Back Vocal 2005年1月9日発売 2. Shin-Kiro No Machi (The Mirage Town) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Dr. Terauchi, Pierrot Le Fou] 2nd track by Shiori Takei from the album "The Note Of Nineteen Years" on January 9, 2005 |
| 竹井詩織里(1985- )は大阪府生まれで兵庫県育ち。立命館大学在学中の2003年にCDデビューし、アルバム3枚、ミニアルバム4枚、シングル9枚、ベストアルバム1枚を出したが、卒業して一般企業に就職した2008年に引退した。一部の曲での作詞、ルックスと声の良さと安定した歌唱力により熱心なファンがついたようだが、大々的には売れなかった。代表曲は「名探偵コナン」のエンディング・テーマに採用された「世界
止めて」2005。 彼女はメジャーから作品を発表しながら、マイナー・レーベルからもアルバムを出していて、「私がxx歳のうちに残しておきたいもの」というコンセプトで制作したカバーソング・ミニアルバムのシリーズで、18歳から20歳まで3作のうちの2作目にあたり、彼女の20歳の誕生日(2月6日)の少し前に発売された。バックを務めるミュージシャンは、ディメンションというフュージョン・バンドで、自己名義のアルバムの他にいろんな歌手のバックを担当していた人達だ。編曲者は変名になっていて、うち「Pierrot Le Fou」はジャン・リュック・ゴダール監督の「気狂いピエロ」1965 のことかな。 2.「蜃気楼の街」はオリジナルよりもテンポが速く、ダンサブルなフュージョン・サウンドになっていて、サックスやギターソロが入るとても面白いアレンジ。ドラムスのクレジットがないが打ち込みのようだ。 他の曲について (特記ない場合は 編曲 Dr. Terauchi, Pierrot Le Fou) 1.「Honesty」 (作詞作曲 Billy Joel 編曲 小林哲) ビリー・ジョエル 1979年の名作。これは意表をつくボサノバ・アレンジ 3.「My Favorite Things」 (作詞 Oscar Hammerstein II 作曲 Rochard Rogers) 1959年のミュージカル「Sound Of Music」からで、1965年の映画ではジュリー・アンドリュースが歌った。ここではピリッとしたジャズ・ワルツのアレンジ。 4.「Baby One More Time」(作詞作曲 Max Martin) ご存知ブリトニー・スピアーズ1998年のデビュー曲。アコギ一本のみのバックがユニーク。 5.「My Happy Ending」(作詞作曲 Clif Magness, Avril Lavigne) アヴリル・ラヴィーン 2004年のヒット曲で、ロック調のアレンジ。 6.「Baby It's You」(作詞 Mack David, Luther Dixson 作曲 Burt Bacharach) オリジナルはザ・シュレルズ1961だが、ザ・ビートルズ1963、スミス 1969のカバーも名高い。ここではスミスでのアレンジを発展させてガレージ・ロック風に仕上げた。この曲のみベース、ドラム奏者が入った生バンド・サウンドになっている。 洋楽カバーのアルバムは一般にはあまり受けないと思うけど、彼女の英語はとてもきれいで、凝ったアレンジも面白い。生活感が感じられるライナーの写真と一緒に本人の思い入れがたくさん入っていて、自分自身とコアなファンを対象にしたものと推測される。その中で唯一の日本語曲「蜃気楼の街」が違和感なく溶け込んでいるのは、この曲がもつ無国籍な味わいからくるのだろう。 [2025年3月作成] |
|
| 蜃気楼の街 Reggae Disco Rockers (2004) Flower | |
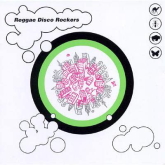  |
1. 蜃気楼の街 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Reggae Disco Rockers] 1曲目 2. 蜃気楼の街 (Inst.) [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Reggae Disco Rockers] 6曲目 有坂美香: Vocal 高宮紀徹: DJ, Programming 小林洋太: Bass 西内徹: Sax 太田靖雄: Trumpet 写真上: シングル CD (2005年3月30日発売) 写真下: シングル Record 1. Shin-Kiro No Machi (The Mirage Town) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Raggae Disco Rockers] 1st track 2. Shin-Kiro No Machi (The Mirage Town) (Instrumental) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Raggae Disco Rockers] 6th track by Raggae Disco Rockers from the single "Shin-Kiro No Machi (The Mirage Twon)" on March 30, 2005 |
レゲエ・ディスコ・ロッカーズは、1994年DJの高宮紀徹を中心に結成されたレゲエ・ユニット。オリジナルや古今東西の名曲のレゲエ・カバーで日本におけるラヴァーズ・ロックの代表的存在。本作は5作目のシングルCD(ミニアルバム)で、オリジナルの他に以前に出した曲のセルフカバーやインストルメンタル・バージョンなどは入っている。 1.「蜃気楼の街」はシュガーベイブのアルバム「Songs」1975に入っている大貫さん初期の名曲のカバー。ここでのブラスをフィーチャーしたレゲエ・アレンジはとても自然な感じで、大貫さんの楽曲カバーの中でもオリジナリティーと出来の良さで上位に位置するものだ。ふくよかな声で歌う有坂美香(1974- 神奈川県出身)は米国でボーカルを学び、帰国後アニメソング等を歌っていたが、2004年にレゲエ・ディスコ・ロッカーズに加入。また「機動戦士ガンダム Seed Destiny」第2期のエンディングテーマ「Life Goes On」2005の大ヒットで有名になる。また様々なアーティストのアルバムにボーカリストとしてフィーチャーされ、自己名義のアルバムも出している。2.「蜃気楼の街 (Inst.)」はボーカル抜きのカラオケ・バージョンであるが、聴くだけでも十分心地良く、曲として十分鑑賞可能な内容になっている。 CDシングルには全7曲収録で、インストルメンタルの「Bond Street」3曲目は1997年、「Bless You」5曲目は1999年のシングルのセルフカバーで、「Rainbow」3曲目は少し前に出したシングル・レコードのバージョンからYOYO-Cのラップを抜いた有坂のソロバージョン。「Wedding」6曲目は川崎のクラブ・チッタにおけるライブ録音。どれもレゲエを耳に心地良く発展させたラヴァーズ・ロックのサウンドになっている。 なお同時期に45回転のシングル・レコードも発売されていて、A面が「蜃気楼の街」、B面が「蜃気楼の街 (version) 」となっているが、B面はCDシングル6曲目のインスト・バージョンと同じものだ。 「蜃気楼の街」の気持ち良いレゲエ・アレンジ。 [2025年3月作成] |
|
| BGM Vol.2〜沿志奏逢 Bank Band (2005) DVD Toys Factory | |
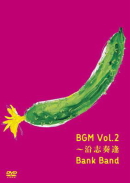 |
1. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Bank Band] 8th track (映像) 櫻井和寿: Vocal 小林武史: Keyboards 古川昌義: Guitar 山本拓夫: Soprano Sax 美紅月千晴: Bass 山木秀夫: Drums 録音: 2004年11月17日 ブルーノート大阪 2005年3月30日発売 4. Totsuzen No Okurimono (The Sudden Gift) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Bank Band] 8th Track by Bank Band from the DVD "BGM Vol.2 Soshi Soai" on March 30, 2005 |
| 環境保護、自然エネルギー促進、省エネルギーなどの環境保全に関する個人や団体へ低金利で融資する非営利団体 ap bank の資金調達のため、また同団体の活動や考えを知ってもらうために、櫻井和寿(Mr.
Children)と小林武史は音楽仲間とBank Bandを結成し、2004年1月にカバーソングのコンサート「BGM〜Bank With Gift
of Music for ap bank」を開催した。その後10月20日にスタジオ録音によるアルバム「沿志奏逢」を発表し、11月11日恵比寿ガーデンホール、17日大阪ブルーノートで食事・飲物付きのコンサートを実施した。翌年3月に発売された本DVDは両者のライブとインタビュー映像からなり、収益はap
bankの活動資金に充てられた。ちなみにタイトルが「BGM Vol.2」になっているのは、1月に続く2回目のコンサートになるため。 添付されたブックレットに掲載された作家の月本裕(1960-2008)によるエコロジー、エネルギーについての寄稿、ap bankについての解説、融資先についてのレポート、および曲間に挿入されたインタビュー映像から、このDVDが単なる音楽鑑賞のためでなく、ap bankの活動状況の宣伝および環境問題を視聴者に問うために制作されたことがわかる。バンドのメンバーはアルバムと同じで、クレジットに「Second Keyboards」として安達練の名前があるが、映像には映っておらずメンバー紹介にも含まれていない。彼はMr. Childrenと仕事をしている人で、推測するに作品の制作段階で、修正・追加作業のオーバーダビングを担当したものと思われる。 1.「突然の贈りもの」で櫻井はギター(独自のピックガードを付けたマーチンD-28)を置いて、椅子に座って歌う。その際の表情がとても豊かで、全身全霊を込めて歌っている様が伝わってくる。スタジオ録音よりも本人の個性というか、歌い回しの癖が強調されて、曲が持つニュアンスもよりはっきり表現されている。最初の伴奏はピアノとギターだけで、セカンド・ヴァースからウッドベースとドラムスが加わる構成。 他の曲について。アルバム収録曲は隠しトラックも含めて全部やっていて、CDに入っていなかった3曲は以下の通り。表示は曲名 [作詞作曲] オリジナル・アーティスト、年、特記 (編曲はすべて Bank Band) ① 空席 [作詞作曲 真島昌利] 真島昌利 1994。ザ・クロマニヨンズ、The Blue Hearts、The High-Lowsなどのバンドのギタリストで、ソロアルバム「人にはそれぞれ事情がある」に収録。 ② 昨日のNO、明日のYES [作詞 GAKU-MC 作曲 森俊之] GAKU-MC 2002。ラッパーで櫻井とウカスカジーというユニットを結成した人。自然環境問題に関心が高く、東日本大震災復興活動、ボランティアで活躍。なお同曲は後にスタジオ録音され、2008年発表のアルバム「沿志奏逢2」に二人によるデュエットが収められた。 ③ ストレンジ・カメレオン [作詞作曲 Sawao Yamanaka] the pillows 1996。山中さわおは同グループのボーカル、ギター担当。この曲は、売れるために制作した作品の失敗による疎外感に悩む自身を「まわりの色に合わせられない出来損ないのカメレオン」に例えたもので、同グループの代表曲となった。グループは2025年に解散。 本作の一番最後には、太陽が昇る都市の遠景をバックに、「あなたがイメージする未来はどんなものですか?」という字幕が現れ、本作が提起した問題について視聴者が各自考えることを促している。 櫻井の渾身の歌唱による「突然の贈りもの」の映像。 [2025年12作成] |
|
| Rembrandt Sky 藤田恵美 With 森亀橋 (2005) Leafage(ポニーキャニオン) | |
 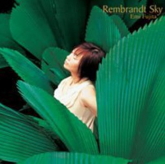 |
5. スプマンテの恋 [作詞 大貫妙子 作曲 佐橋佳幸 編曲 森亀橋] 5曲目 藤田恵美: Vocal 森俊之: E. Piano, Cemballo 佐橋佳幸: E. Guitar, E. Sitar 亀田誠治: E. Bass 河村 カースケ 智康: Drums 山本拓夫: A. Flute 数原晋: Flugelhone 写真上: 日本盤 2005年11月2日発売 写真下: アジア各国盤 (英語版) 2005年発売 5. Spumante No Koi (Spumante Love) [Words: Taeko Onuki, Music: Yoshiyuki Sahashi, Arr: Mori-Kame-Bashi] 5th track by Emi Fujita with Mori-Kame-Bashi (Emi With MKB) from the album "Rembrandt Sky" on November 2, 2005 |
| 森亀橋は、プレイヤー、作曲・編曲家、プロデューサーの森俊之、亀田誠治、佐橋佳幸からなるユニットで、ドラムスの川村カースケ智康を加えて不定期にコンサート等を行っている。彼らが2005年に藤田恵美とタイアップして制作したアルバム。 藤田恵美(1963- 東京都出身)は、子役から始めて13歳で演歌歌手としてデビューしたがすぐに辞めて、しばらくアマチュア歌手としてカントリーを歌っていた。1991年にギタリストの藤田隆二と結婚して二人で「Le Couple」を結成しアルバムとシングルを出す。最大のヒット曲は1997年の「ひだまりの詩」。グループは2005年に活動休止して、2007年の離婚後はソロとして活動。2001年が最初のアコースティックなサウンドによる欧米曲のカバーアルバム「camomile」シリーズが日本・東南アジア各国で好評を博し、その延長線上で制作されたのが本作だ。森・亀田・佐橋が各4曲づつ作曲を担当(ただし亀田については1曲のみ奥さんの下成佐登子が作曲)し、藤田は3曲作詞している。シンセサイザーやプログラミングを最低限にしたバンドサウンドと藤田の暖かみのあるボーカルとがうまく噛み合い、生み出された爽やかな感じのラブソングは聴いていて心地よい。 大貫さんが作詞した5.「スプマンテの恋」はなかでも飛び切りお洒落な感じの曲で、トリコロールの服(3つの色の組み合わせ)、コクトーの猫、スプマンテ(発泡性ワイン)、ガウディーの椅子といった言葉がポンポン飛び出してくる。大貫さんの数多い歌詞の中でもその軽やかさで、筆頭に挙げられる作品だと思う。藤田のボーカルはこんな感じの曲にぴったりで、佐橋が弾くエレクトリック・シタールの音色もいいね。 他の曲も、みなとても良い出来であるが、あえてひとつといえば1.「風のくちぶえ」かな。作詞者のAlvin Woodstockはリリー・フランキーの変名(彼はアルバム帯に「私は彼女の歌声に、音楽という言葉を超えたはるか、美しいものを感じる」という賛辞を送っている)。俳優、文筆家(脚本、小説、エッセイ)、画家(イラスト、絵本)、音楽(作詞、作曲、演奏)などマルチな才能を発揮する才人が書いた歌詞が素晴らしい。 なお本作は、アジア各国での販売のために、同じバッキングトラックを使用した英語盤が同時並行で制作された。訳詞でなく英語詩で、欧米の著名作詞家に依頼したもの。日本盤と曲順が異なるので、対照表は以下のとおり。 1. 風のくちぶえ[作詞 Elvis Woodstock 作曲 森俊之] → 7. More Than Ever Before [作詞 Marica Aderwall] 2. 海よりも虹よりも[作詞 宮沢和史 作曲 亀田誠治] → 5. Unbelievable [作詞 Samuel Waermo] 3. eternity [作詞 佐藤純子、下成佐登子、作曲 下成佐登子] → 1. Somewhere [作詞 Terry Cox] 4. 秋のスイカ [作詞 藤田恵美 作曲 森俊之] → 3. Every Single Day [作詞 Mark Goldenberg] 5. スプマンテの恋 → 6. Lucky Day [作詞 Mark Goldenberg] 6. Rembrandt Sky [作詞 藤田恵美 作曲 佐橋佳幸] → 2. Love Let Go [作詞 Randy Goodrum] 7. 東京で会いましょう [作詞 宮原芽映 作曲 佐橋佳幸] → 9. Tokyo Lover [作詞 Esther Suganuma] 8. 200x [作詞 藤田恵美 作曲 森俊之] → 10. 200x [作詞 Esther Suganuma] 9. 真夜中のペットショップ [作詞 谷口崇 作曲 亀田誠治] → 8. Window Shopping [作詞 Alan O'Day] 10. 今がよければ [作詞 宮原芽映 作曲 佐橋佳幸] → 4. To Daydream With You [Chris Farren] 11. 夏のリクイエム [作詞 湯川れい子 作曲 佐橋佳幸] → 11. My Summer Love [作詞 Alan O'Day] 12. 影法師 [作詞 伊藤俊吾 作曲 亀田誠治] → 12. Ten Million Tears [作詞 Randy Goodrum] 藤田の英語の歌唱はとても自然な感じで、それでいて西洋人にはない繊細さがあって、とてもいい感じ。東南アジア諸国で受けたのも道理で、香港でゴールドディスク、マレーシアでダブル・プラティナディスクを獲得したという。 大貫さんの歌詞のなかでも、洗練された軽やかさにおいて筆頭に挙げられる作品。 [2025年4月作成] |
|
| Never Ending Story/彼と彼女のソネット 坂本美雨 (2005) Yamaha Music Communications | |
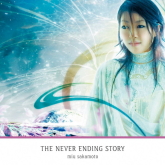 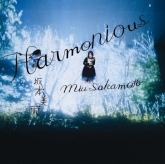 |
1. 彼と彼女のソネット [作詞 C. Cohen, R. Wargnier 作曲 R. Musumarra 日本語詞 大貫妙子 編曲 徳澤青弦 from anonymass] single coupling 徳澤青弦: Cello, Programming, Producer 江草啓太: Acoustic Piano 写真上: シングル (2005年11月16日発売) 写真下: アルバム「Harmonious」(2006年5月24日発売) 1. Kare To Kanojo No Sonnet (His And Her Sonnet) [Words: C. Cohen, R. Wargnier, Music: R. Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki, Arr: Seigen Tokuzawa] single coupling by Miu Sakamoto from the single "Never Ending Story" November 16, 2005 |
| 「Never Ending Story」はドイツ人ミヒャエル・エンデの小説「Die unendliche Geschichte (はてしない物語)」1979を映画化したもので、1984年公開。いじめられっ子の少年が読むと物語の主人公になれる不思議な本と出会い、ファンタジーのなかでの冒険を通じて実生活で生きる勇気を得る話で、英語版にキース・フォーシー(Keith
Forsey)作詞、ジョルジオ・モロダー(Giorgio Moroder)作曲のタイトル曲が使われ、カジャグーグーを脱退してソロに転向したリマール(Limahl)が歌って各国でヒットした(全米17位、全英4位)。 坂本のカバーは2005年シングルで発売され、ホンダ車のCMに使われた。チェロ奏者で作曲・編曲家の徳澤駙弦(「anoymass」は彼が所属する音楽ユニット)のチェロとプログラミング、江草啓太のピアノとシンセサイザーの二人による演奏。打ち込みによるエレクトロ・ポップとチェロとピアノのアコースティックな響きがうまくブレンドした透明感あるサウンドが素晴らしく、ボーカルについてもオリジナルのリマールよりも坂本のほうがこの曲に合っている。彼女の声はこの手のファンタジーものに向いているからね。 カップリングで収められたのが「彼と彼女のソネット」で、同じ二人による伴奏だ。ここではリズムセクションなしで、打ち込みによる最低限の効果音とピアノとチェロのみというシンプルなサウンドにすることで、坂本の透き通った声の魅力が生かされている。 シングル発売から6ヵ月後の翌年5月に上記2曲が収められたアルバム「Hamonious」が発売された(2曲は2番目、4番目に収録)。上記の2人の他に、神田朋樹、成田忍、半野喜弘、森俊之、佐橋佳幸等、多くの人がプロデュース、編曲、演奏に携わっているが、特記事項として父親の坂本龍一の名前がないことがあげられ、本作より父の庇護を離れて一人歩きを始めたということだ。半分が英語の歌詞の曲になっているが、アメリカ育ちの彼女にとって自然なのだろう。3.「オキナワソバのネエさんへ」(作詞作曲 柴草玲 編曲 成田忍)はタイトル通り沖縄風の曲だけど、作者の柴草玲(ピアニスト、シンガーアンド・ソングライター)は埼玉県出身だった。6.「風花-remix ver.」(作詞 坂本美雨 作曲編曲 森俊之)は 2024年に出した限定版シングルがオリジナルで、本作収録はそのリミックス版。エコーを効かせた坂本の声が天女のようで、最初は漂い、最後は疾走する音楽も素晴らしい。7.「Paths Of Desire」(作詞作曲 Asler Emil, Julie C Flanders 編曲 徳澤青弦)はアメリカのグループ October Project 1993年のカバー。オリジナルよりも良い出来と思う。8.「One More Second」(作詞 Rufus Miller 作曲 Dominic Miller 編曲 佐橋佳幸)作者のギタリスト、ドミニク・ミラーは2006年のアルバム「Forth Wall」でインストルメンタルとしてセルフカバーしている。10.「遠くへゆきたい」(作詞 永六輔 作曲 中村八大 編曲 森俊之)は1962年NHKテレビ番組「夢で逢いましょう」のために作曲され、ジェリー藤尾の歌が最初。その後1970年の番組「遠くへ行きたい」で再使用され、多くの人が歌った。ここでは、当時この曲を歌っていたデューク・エイセスのコーラスをバックに坂本が歌っている。 清浄、静謐な雰囲気のなかで歌われる「彼と彼女のソネット」もいいね。 [2025年5月作成] |
|
| 2006年 One Fine Day (2005/2/16) UTAU (2010/11/10) の頃 | |
| Shiplaunching 冨田ラボ (2006) Sony Music Direst (Japan) | |
 |
1. プラシーボ・セシボン feat.高橋幸宏+大貫妙子 [作詞 堀込高樹 作曲編曲 冨田恵一] 2曲目 2. しあわせのBlue feat. Yoshika [作詞 大貫妙子 作曲編曲 冨田恵一] 8曲目 高橋幸宏、大貫妙子:Vocal (1) Yoshika: Vocal (2) 冨田恵一: All Instruments, Producer 2006年2月22日発売 1. Placebo C'est si bon feat. Yukihiro Takahashi + Taeko Onuki [Words: Takaki Horigome, Music & Arr: Keiichi Tomita] 2nd Track 2. Shiawase No Blue (Blue Of Happiness) feat. Yoshika [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Keiichi Tomita] 8th Track |
| 冨田恵一(1962- 北海道出身)は1988年にKEDGE名義の「Complete Samples」でアルバム・デビューし、その後は作曲・編曲家・プロデューサーとして売り出す。そして2003年に「冨田ラボ」名義でソロアルバム「Shipbuilding」を発表、作曲、アレンジ、演奏、プロデュースを一人でこなしてゲストに歌わせるスタイルを確立した。本作はその2枚目で、次作の「Shipahead」2010を含めて「Shipシリーズ3部作」といわれている。スタジオに籠って、打ち込みによるドラムスを除くほぼすべての楽器を自身で演奏。完璧主義のプロダクションは本人が影響を受けたというスティーリー・ダンに通じるものがある。 大貫さんが高橋幸宏と参加した1.「プラシーボ・セシボン」は「すてきな偽薬」という意味のタイトルで、作詞担当の堀米高樹は兄弟ユニットKIRINJIの兄。「目眩、偏頭痛、胃潰瘍、タブレット、処方箋、副作用」という医療用語が出てくるクセのあるラブソングであるが、大貫さんと高橋の存在感がそれを凌駕している。サウンド的にはスティーリー・ダンそのものと言った感じで、グルーヴ感が何とも心地よい。本曲についてはヨーロッパ風のレストランを舞台に二人が(口パクで)歌うオフィシャル・ミュージック・ビデオがある。大貫さんが作詞した 2.「しあわせのBlue」を歌うYoshika(1983- )は2000年代初めにインディ・レーベルでデビューし、2005年にメジャー・デビュー。結婚と出産による活動休止後 2008年に音楽活動を再開したが、2014年以後の記録はインターネットになかった。少し憂いを帯びた囁き系ヴォイスはなかなか魅力的で、クールでありながらどこか暖かさも感じる曲とサウンドにぴったり合っている。 他の曲について(作曲・編曲はすべて冨田恵一)。ゲストシンガーは Soulhead、田中拡邦(Mamalaid Rag)、Chemistry、山本領平といった面々。作詞者は吉田美奈子、糸井重里、鈴木慶一、高野寛という豪華メンバー。それとインストルメンタルが3曲ある。「Like A Queen」(作詞 吉田美奈子)3曲目を歌うSoulhead(2.「しあわせのBlue」のYoshikaと妹のTsugumiによる姉妹ヒップポップ・デュオ)によるゴキゲンなナンバー。「ずっと読みかけの夏」(作詞 糸井重里)はChemistryの歌によるメロウなソウルナンバー。特にお気に入りの曲についてコメントしたが、インストを含む残りの曲もみなゴキゲンな出来で、冨田の底知れぬ才能とオタク度を感じさせるものになっている。 [2025年4月作成] |
|
| かざうた 藤原道山 (2006) 日本コロムビア | |
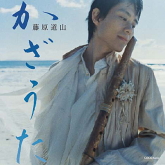 |
8. 四季 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 武部聡志] Instrumental 8曲目 藤原道山: 尺八 (一尺八寸/永廣真山銘、一尺七寸/藍空銘) 武部聡志: Piano, Producer 小倉博和: Acoustic Guitar 2006年3月22日発売 1. Shiki (Four Seasons) [Music: Taeko Onuki, Arr: Satoshi Takebe] 8th track by Dozan Fujiwara form the album "Kazauta" (The Wind Song) on March 22, 2006 |
| 藤原道山(1972- 東京生まれ)は尺八奏者。箏曲家の祖母の影響のもと10歳で尺八を始める。東京芸術大学在学中に頭角を表し、邦楽に限らず西洋楽器との共演など幅広い音楽に取り組み、2001年にアルバム・デビューを果たす。本アルバムは34歳時の6枚目のアルバムで、作曲家・編曲家の武部聡志(1957-
)と組んでポップなサウンドのオリジナル作品や既存曲のカバーに取り組んでいる。 大貫さんの「四季」は松嶋奈々子が出演したMax Factor「ななこなでしこ」のCMに使われ、アルバム「Attraction」1999 に収録され、後年坂本龍一とのアルバム「Utau」2010でセルフカバーされた曲。YouTubeなどに投稿されたカバーはあるが、正式録音としては意外にも本作が唯一の存在。歌無しのインストルメンタルで、尺八の艶やかで哀愁あふれる音色が曲にマッチしている。ピアノとアコースティック・ギターによるシンプルな伴奏も良い。使用した一尺八寸は最低音がD、一尺七寸はE♭のタイプで、2種類使ったのは音程の関係からかな? 他の曲について(特記ない場合はインストルメンタル、編曲 武部聡志) 1. 月の鏡 [作曲 藤原道山] 2.はじまりの音 [作曲 川江美奈子] 3. もらい泣き [作詞 一青窈 作曲 武部聡志、溝渕大智] 一青窈のデビュー・シングル(アルバム「月天心」収録)2002のカバー 4. かざうた [作詞作曲 川江美奈子] 歌: 川江美奈子 5. 水の影 [作詞作曲 松任谷由美] シモンズのシングル(ドラマ「幸福の断章」主題歌)1978のカバー。松任谷はアルバム「時のないホテル」1980でセルフカバーしている。 6. 光 [作曲 藤原道山] 7. 東風(こち)[作曲 藤原道山] 8. 四季 9. 島唄 [作詞作曲 宮沢和史] The Boom 1992のカバー。 10. 花 [作詞作曲 喜納昌吉] 歌と三味線: RIKKI 喜納昌吉 1980のカバー 11. 春告鳥(はるつげどり)[作曲 マシコタツロウ] 曲を提供し歌も入れているシンガー・ソングライターの川江美奈子がブックレットに寄せた賛辞「音色が語っているから... いい音楽には詞(ことば)はいらないと気づきました」にあるように、2曲を除きすべてインストルメンタルで、心に染み入る音色と圧倒的な表現力で迫ってくる。J-Popのカバーは尺八の音色に合った憂いのある曲が選ばれ、1.「月の鏡」、4.「かざうた」、11.「春告鳥」はおだやかで透明感のあるアンサンブル、6.「光」は現代的な雰囲気の独奏、そして 9.「島唄」、10.「花」は沖縄サウンドだ。なお後者で三味線を弾いて歌っているRIKKI(1975- 本名 中野律紀)は奄美大島出身の歌手。一方 3.「もらい泣き」のエンディングのソロや 7.「東風(こち)」では、クロスオーバー風の躍動的なプレイで驚かせてくれる。 尺八による「四季」のインストルメンタルが楽しめる。 [2025年11月作成] |
|
| Listen Or Love jenny01 (2006) インペリアル(テイチクエンタテインメント) | |
 |
1. 都会 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 太宰百合] 1曲目 NAOKO: Vocal 太宰百合: Acoustic Piano, Electric Piano 西嶋徹: Bass 藤井摂: Drums 藤田明夫: Soprano Sax Arvin Homa Aya: Chorus 須永辰緒 (Sunaga t experience): Producer 2006年10月4日発売 1. Tokai (City) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Yuri Dazai] 1st Track by jenny01 form the album "Listen Or Love" on October 4, 2006 |
| jenny01はNAOKO(ボーカル 浅草出身)をメインとしたユニットで、着せ替えフランス人形の製造番号01というコンセプトで命名された。彼女のフランス訛り風のウィスパリング・ヴォイスがチャーム・ポイントで、ライブでは人形のように頻繁に服を着替えたという。1999年に結成し、インディーズから4枚のミニアルバムを出した後にメジャーデビューした。本作はメジャー3枚目のミニアルバムで、その後活動が途絶えるが、2023年にNAOKOがjenny01を復活させ、ライブを行ってシングルを出した。彼女は現在浅草で宝飾業に従事しているとのこと。ウィキペディアによると、jenny01はロックバンドでギター、ベース、ドラムスのサポートメンバーがいると書かれているが、本アルバムに関しては曲毎に異なるミュージシャンがバックをやっていて、グループ的な要素はなく "jenny01 = NAOKO"となっている。 1.「都会」(大貫さんのアルバム「Sunshower」1977収録曲のカバー)は、「レコード番長」と呼ばれ「Sunaga t experence」の名義でアルバムを出しているDJ、音楽プロデューサーの須永辰緒が制作に携わり、ジャズをベースに幅広い音楽性をもつピアニストの太宰百合が編曲し若手のジャズプレイヤーと演奏することで、当時流行りの打ち込みに頼らないライブなサウンドに仕上がっている。NAOKOのコケティッシュなボーカルは、大貫さんの少し退廃的なボーカルとは異なる面で都会の雰囲気を醸し出していて、個性的でとてもいい感じだ。 「都会」とブラジリアン・ジャズの「New Season」(作詞 NAOKO, inco saito 作曲編曲 尾方伯朗)5曲目以外は打ち込み中心のポップ・サウンド。ダンスミュージック音楽ユニット Studio Apartmentの作曲家・編曲家の阿部登がプロデュースした「rain, rain」(作詞 NAOKO 作曲編曲 阿部登)2曲目はブラジル、「Melody」(作詞 NAOKO 作曲編曲 阿部登)3曲目はハウス・ナンバー。「砂漠の絨毯」(作詞 NAOKO 作曲 奥山みなこ 編曲 高宮永徹、中村新史)4曲目の編曲者は、Reggae Disco Rockersの高宮紀徹の兄だ。 なお最後の2曲「My First Recipe」と「Monologue」は2005年発表のアルバム「Ladymade」に収録された曲のリミックス。 数ある「都会」のカバーの中でも筆頭に挙げられる存在。 [2025年3月作成] |
|
| NapsaQ〜青春ソングリクエストアルバム〜 NapsaQ (2006) Ponny Canyon | |
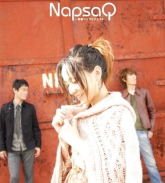 |
8. 突然の贈りもの [作詞作曲 大貫妙子 編曲 NapsaQ] 8曲目 下川みくに: Vocal 松ケ下宏之: Piano 伊藤多賀之: Guitar 2006年12月20日発売 8. Totsuzen No Okurimono (The Sudden Gift) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: NapsaQ] 8th track by NapsaQ from the album "NapsaQ-Seishun Song Request Album" (NapsaQ- The Request Album For Songs Of Youth) on December 20, 2006 |
| NapsaQは、アイドル歌手出身で歌手・女優・声優の下川みくに(1980- 北海道出身) が、歌手、マルチ奏者、作・編曲家、プロデューサーの松ケ下宏之(1973-
)、シンガーアンド・ソングライターの伊藤多賀之(1976- ) と結成したユニットで、発表作品は本作のみ。インターネット、ラジオ番組などで募集したファンからのリクエストに基づいて選曲された、スウィートでサワーな「青春」をテーマとしたカバーソング集であるが、全13曲中最後の3曲はボーナス・トラックまたは隠しトラックでのオリジナルまたはセルフカバーになっている。 シンセサイザーなどの電子楽器は使っていないようで、エレキギターが入ったロックな曲もあるが、アコースティックなサウンド中心の手作り感にあふれたアレンジが魅力的。下川の声色はアイドル系であるが、声優ということもあり滑舌・音程が正確でかつ情感が籠っていて、とても上手い人だと思う。アニソンを多く歌っているのもむべなるかな。ただこの手のシンガーにありがちなんだけど、どの歌も自分の色に染め切って曲の個性を凌駕してしまう傾向があるようで、その結果どの歌も同じように聞こえるけらいもある。 そのなかで大貫さんの名曲 8.「突然の贈りもの」(オリジナルは「Mignonne」1978収録)はピアノとギターだけのシンプルなバックで、切々と歌い上げる下川のボーカルが素晴らしい。曲が持つ情感の豊かさが本人の歌唱とうまくバランスしていて、自然な感じで聴いていてホロリとさせられる。間奏のギターソロも原曲の松木恒秀のプレイの向こうを張って頑張っているね。 他の曲について(編曲は全てNapsaQ) 1. カンナ8号線 [作詞作曲 松任谷由美] 松任谷由美 1981 アルバム「昨晩お会いしましょう」 2. 愛を止めないで [作詞作曲 小田和正] オフコース 1979 15枚目のシングル、 アルバム「Three And Two」 3. M [作詞 富田京子 作曲 奥居香] プリンセスプリンセス 1989 7枚目のシングル「Diamonds」のB面、アルバム「Let's Get Crazy」 4. 駅 [作詞作曲 竹内まりや] 中森明菜 1986 アルバム「Crimson」。竹内まりや 1987 シングル、 アルバム「Request」。ここでのリズミカルなアレンジは面白い。 5. 青春の影 [作詞作曲 財津和夫] チューリップ 1974 6枚目のシングル、アルバム「Take Off (離陸)」 6. 悲しくてやりきれない [作詞 サトウハチロー 作曲 加藤和彦] ザ・フォーク・クルセイダーズ 1968 2枚目のシングル、アルバム「紀元貳阡年」 7. あなたに会えてよかった [作詞 小泉今日子 作曲 小林武史] 小泉今日子 1991 32枚目のシングル、アルバム「afropia」 8. 突然の贈りもの 9. フレンズ [作詞 Nokko 作曲 土橋安騎夫] レベッカ 1985 4枚目のシングル、アルバム「Rebecca IV〜Maybe Tomorrow〜」 10. 想い出がいっぱい [作詞 阿木燿子 作曲 鈴木キサブロー] H2O 1983 5枚目のシングル、 アルバム「Emotion」 11. PicniQ (Bonus Track) [作詞 下川みくに 作曲 松ケ下宏之、伊藤多賀之] オリジナル 12. おやすみ (Bonus Track) [作詞 下川みくに 作曲 松ケ下宏之、伊藤多賀之] オリジナル 13. 石焼イモ(NapsaQ Version) (Hidden Track) [作詞 マリモラッコ 作曲 マリモラッコ、伊藤多賀之] ブリーフ & トランクス (伊藤がメンバーのユニット) 2000 7枚目のシングル、アルバム「ボクらのエキス」1999。この曲のみ3人が交替でリードボーカルを担当している。 オリジナルになると伸び伸びと歌っている感じが面白い。 ここでの「突然の贈りもの」はなかなかの出来だと思う。 [2025年4月作成] |
|
| 2007年 One Fine Day (2005/2/16) UTAU (2010/11/10) の頃 | |
| Tomta Lab Concert at SHIBUYA-AX 2006.3.19 冨田ラボ (2007) Sony Music Associates | |
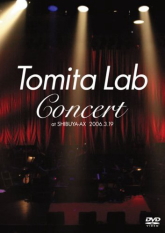  |
5. しあわせのBlue feat. 武田カオリ (Tica) [作詞 大貫妙子 作曲編曲 冨田恵一] 5曲目(映像) 8. プラシーボ・セシボン feat.高橋幸宏+大貫妙子 [作詞 堀込高樹 作曲編曲 冨田恵一] 8曲目(映像) 武田カオリ: Voca; (1) 高橋幸宏、大貫妙子: Vocal (2) 冨田恵一: Keyboards (1), Guitar (2) 松本圭司: Kayboards 桜井芳樹: Guitar 鈴木正人: Bass (2), Synthesizer Bass (1) 村石雅行: Drums 三沢またろう: Percussion 山本拓夫、近藤和彦: Sax, Flute 西村浩二: Trumpet, Flugelhorn 村田陽一: Trombone 金原千恵子ストリングス(5, 8には参加していない) 金原千恵子、矢野晴子: 1st Violin 栄田嘉彦、桐山なぎさ: 2nd Violin 徳高真奈美、渡部安見子: Viola 堀沢真己、笠原あやの:Cello 2007年1月24日発売 録音: SHIBUYA-AX, Tokyo on March 19, 2006 1. Shiawase No Blue (Blue Of Happiness) feat. Kaori Takeda (Tica) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Keiichi Tomita] 4th Track 2. Placebo C'est si bon feat. Yukihiro Takahashi + Taeko Onuki [Words: Takaki Horigome, Music & Arr: Keiichi Tomita] 8th Track |
| 冨田恵一は2006年2月22日にアルバム「Shiplauching」を発表し、その翌月に1回限りのコンサートを行った。会場は国立代々木競技場の駐車場にあったSHIBUYA-AX
(渋谷アックス、仮設施設として2000年にオープンし2014年に閉館・解体)。これまでアルバムの楽曲では打ち込みのドラムス以外の全てを自分で演奏してきた彼にとって、バンドとの生演奏という大きな挑戦となり、腕利きのリズムセクション5人、ホーンセクション4人、そしてストリングス8人を集めて、バンドのスコアも全部自分で書いて臨んだという。リズムセクションとのリハーサルは入念におこなったが、さすがにホーンやストリングス、そしてゲストボーカリストとは最小限にしかできなかったようだ。1回だけの公演としては全く採算がとれない内容であるが、アルバム・プロモーションに加えてテレビ放送、DVD化による収入も見込んでいたはずで、完全主義者の彼の希望をかなえるためにこれだけの投資をしたという事は、当時の彼が如何に評価され、かつ人気があったかを示している。本コンサートの一部は同年6月〜7月に4回(各30分)に分けてMTVで放送され、翌2007年1月に完全版としてDVDが発売された。そこには当日の演奏曲と冨田および出演者のアナウンスのすべてが2時間4分にわたり収録されている。途中で冨田のフェンダー・スーツケース・ピアノが壊れて修理をしたそうだが、さすがにその場面はカットだね.....。 大貫さんが作詞した1. 「しあわせのBlue」 は「Shiplaunching」ではYoshikaが歌っていたが、コンサートでは冨田のアルバムには参加していない武田カオリが歌った。彼女は宮城県出身で、2000年代にギタリストの石井マサユキとのユニットTICAでアルバムを出し、以降はソロで活動している。なお彼女は2015年のコンピレーション・アルバム「Peaceful」で「色彩都市」を歌っている。観ていると、歌の中のサイドボーカル、およびサビのハーモニーを誰が歌っているかが気になる。ステージにはバックボーカリストの姿は見えないので、ゲストボーカルの一人がステージの袖で歌っているのかな?前のインスト曲から切れ目なく始まる8.「プラシーボ・セシボン」でも、コーラス部分で誰かが大貫さんにハーモニーを付けている。ここでは冨田はエレキギターを演奏(彼は19曲中7曲でギターを弾いているが、リズム、ソロともバツグンに上手い)。高橋、大貫二人とも貫禄十分で他のアーティストとは次元が異なる存在感を放っている。 他の曲について (全曲につき 作曲・編曲 冨田恵一) [Set 1] 1. Waltz (Instruental) コンサートの序曲。 2. 罌粟 feat. 畠山美由紀 [作詞 松本隆] 畠山美由紀は男女ユニットPort Of Notesのボーカリスト。曲名は「けし」と読む。 3. 耐え難くも甘い季節 feat. 畠山美由紀 [作詞 畠山美由紀] 4. ずっと読みかけの夏 feat. Chemistry [作詞 糸井重里] 川畑要、堂珍嘉邦からなるボーカルデュオ。 5. しあわせのBlue 6. 道 feat. 武田カオリ [作詞 bird] 「Shipbuilding」で歌っていた作詞者のbirdが妊娠・出産で休業のため、この曲も武田が歌った。 7. Shiplaunching (Instrumental) 8. プラシーボ・セシボン [Set2] 9. Blue II ジャズとプログレッシブ・ロックを合わせたような曲・演奏。 10. Like A Queen feat. Soulhead [作詞 吉田美奈子] Yoshika(姉)とTsugumi (妹)の姉妹デュオ。本コンサートの中では最もソウルフルな曲。冨田のギターソロがかっこいい。 11. アタタカイ雨 feat. 田中拡邦(Mamalaid Rag) [作詞 高橋幸宏] エレキギターを弾きながら歌う田中拡邦は、2007年の「Sunshine Days Of 70's Tribute Album Sunny Rock」にも参加していた人。 12. 香りと影 feat. キリンジ [作詞 堀込高樹] 堀込高樹(兄)と泰行(弟)の兄弟デュオ。 13. 乳房の勾配 feat. キリンジ [作詞 堀込高樹] 1998年に発売されたオムニバス盤に入っていた曲で、後2004年のキリンジのシングル「You And Me」 にカップリングとして収録された。エロチックな歌詞が何ともたまらない。 14. Shipyard (edition 1) feat. Saigenji (Instrumental) Saigenjiがアル・ジャロウばりのスキャットを聞かせる。 15. 太陽の顔 feat. Saigenji [作詞 Saigenji] 16. 恋は傘の中で愛に feat. Ryohei (山本領平) [作詞 鈴木慶一] [Encore] 17. 眠りの森 feat. ハナレグミ [作詞 松本隆] ボーカリスト永積タカシのソロユニットで、ソウルフルなボーカルが素晴らしい。 18. Prayer On The Air [作詞 高野寛] この曲のみ冨田本人が歌っている。 19. Waltz 〜Reprise〜 (Instrumental) 最後にもう一度バンドおよび本日出演のシンガー達を紹介して幕を閉じる。 当日の演奏曲19曲の初出は以下のとおり。 Pro-File of 11 Peoducers Vol.1 (Various Artists) 1998: 13 Shipbuilding 2003: 3, 6, 12, 14, 15, 17 Wild And Gentle (畠山美由紀)2003: 2 Shiplaunching 2006: 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 18 なし: 1, 9, 19 10.「Like A Queen」の後でストリングスとホーンセクションが紹介される。冨田は「金原千恵子ストリングス」のみの紹介だったが、コンサート当日のプログラムには全員のフルネームが載っており、各人につき、紹介時に写った顔とインターネットの写真を突き合わせることにより以下のとおり特定できた。向かって左から前列: 矢野晴子、金原千恵子、栄田嘉彦、桐山なぎさ(Violin)、後列:渡部安見子、徳高真奈美(Viola)、笠原あやの、堀沢真己(Cello)。ホーンは向かって左から近藤和彦、山本拓夫、西村浩二、村田陽一。 各曲のアレンジの完成度が凄く、演奏から生まれるグルーヴ感が尋常じゃない。コンサートの模様を捉えたカメラワーク・編集や音響も最高で、全てにおいて完璧といえる出来栄えになっている。 なおDVDには特典として「プラシーボ・セシボン」、「ずっと読みかけの夏」、「アタタカイ雨」、「Like A Queen」のMusic Clipが収められている。 コンサート映像作品の傑作。 [2025年7月作成] |
|
| nami The Good Day's J-Pop 高田なみ (2007) プリズム(コロムビア) | |
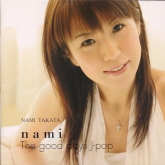 |
6. 小さなワルツ [作詞作曲 大貫妙子 編曲 木住野佳子] 6曲目 高田なみ: Vocal 木住野佳子: Piano Chris Silverstain: Bass 藤井摂: Drums 2007年4月18日発売 1. Chisana Waltz (The Little Waltz) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Yoshiko Kishino] 6th track by Nami Takata from the album "nami The Good Day's J-Pop" on Arril 18, 2007 |
| 高田なみは富山県出身。2002年にStep To Heavenのボーカリストとしてアルバム「Wish You Were Here」を出した後の2007年に発表した初ソロアルバムが本作で、1970年代〜1990年代のJ-ポップの名曲をカバーしたもの。ブラジリアン・ジャズ風のサウンドをバックに歌う彼女のボーカルは素直で優しく、理屈抜きに聴くことで心を和ませてくれる。編曲担当は、ジャズ・ピアニストの木住野佳子と幅広い音楽をカバーするギタリストの竹中俊二。 6.「小さなワルツ」はブラジルで録音された大貫さんのアルバム「Tchou」1995からのカバーで、大貫さんにはボサノバ調の名曲がたくさんあるのに地味な曲を選んだね。オリジナルのオスカール・カストロ・ネヴィスの編曲があまりに素晴らしいので、カバーするのは不利かなと思ったが、ピアノトリオによるシンプルなジャズワルツのアレンジで、それなりの味を出している。高田さんのボーカルは、大貫さんのようなクールさはなく、ブラジル音楽を歌う歌手のなかでは暖かみが感じられる。ベーシストは1985年から日本で活躍するアメリカ人で、ドラムスはjenny01のアルバムにも参加していた若手ミュージシャンだ。 他の曲について(曲名、作詞作曲編曲、オリジナル・アーティスト、オリジナル発表年の順番で表示)。もともとボサノバ調の曲が多いが、斬新なアレンジのものもある。 1. 夏の恋人(作詞作曲 山下達郎 編曲 木住野佳子) 竹内まりや 1978: デビューアルバム「Beginnings」に入っていた曲で、当初から山下が竹内に入れ込んでいたことがわかる作品。山下の編曲と竹内のボーカルが最高だったが、ここでのサロン・ジャズ風の演奏もなかなかいいね。 2. あの日に帰りたい(作詞作曲 荒井由美 編曲 竹中俊二)荒井由美 1975: 説明不要の名曲。オリジナルではハイファイセットの山本潤子によるスキャットから始まるが、ここではブラスによるアレンジになっており、その代わりにエンディングのダブルテンポでスキャットが再現され、そのバックに流れるピアノソロがいかしている。 3. Down Town (作詞 伊藤銀次 作曲 山下達郎 編曲 木住野佳子) シュガーベイブ 1975:これも名曲。ここではストリングス付きのワルツ・アレンジが施されていて、そのアイデアを楽しみながら聴くべし。 4. 友だち (作詞 岩里祐穂 作曲 上田知華 編曲 竹中俊二) 今井美樹 1995:アルバム「Love Of Life」収録。本カバーのほうがより大人っぽくていい感じ。 5. 水色の雨(作詞作曲 八神純子 編曲 竹中俊二) 八神純子 1978: 大ヒット曲のサンバ・アレンジ。八神の伸びのあるボーカルとは異なる優しい感じの歌声。 6. 小さなワルツ 7. あなたに出逢えてよかった(作詞作曲 平松愛理 編曲 木住野佳子) 平松愛理 1991: アルバム「redeem」収録。OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)「三毛猫ホームズの幽霊城主」(原作: 赤川次郎)の主題歌に採用された曲。ここでも落ち着いた感じのアレンジで高田の声質・キャラによく合っている。木住野のエレキピアノが心地よい。 8. マイ・ピュア・レディ (作詞作曲 尾崎亜美 編曲 竹中俊二) 尾崎亜美 1977: 資生堂CMに採用された尾崎最大のヒット曲。ここでは原曲にほぼ近いアレンジと歌唱。 9. 少女 (作詞作曲 五輪真弓 編曲 木住野佳子)五輪眞弓 1972: 同タイトルのアルバム収録された初期の名曲のカバーで、ブラジル臭さはなく、ピアノとストリングスをバックにしっとりと歌っている。 10. 夢で逢えたら (作詞作曲 大瀧詠一 編曲 竹中俊二)吉田美奈子1976: アルバム「Flapper」1976収録。大変面白いボサノバ・アレンジで本アルバム発売当時話題になった。エレキギターの演奏が洒落ている。 高田はその後もシンガー・アンド・ソングライターとしてマイペースで音楽活動を続けている。変わった仕事としては教養ネット番組の解説者に対する聞き手役というものもある。 カバーアルバムと言って侮ることなかれ! いい曲をいい演奏で楽しめる。大貫さんの珍しい曲のカバーも聴けるぞ。 [2025年3月作成] |
|
| Lovers Metro Trip (2007) Brill Build. (Geneon) | |
 |
1. 都会 (Instrumental) [作詞作曲 大貫妙子 編曲 青木多果] Instrumental 10曲目 山中淳子: Organ トリ音: Theremin 渡辺雅美: Vibraphone 青木多果: Producer 2007年7月4日発売 1. Tokai (City) Instrumental [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Taka Aoki] 10th track by Metro Trip from the album "Lovers" on July 4, 2007 |
| メトロ・トリップはプロデューサー、ギターの青木多果とボーカルの日野友香からなる音楽ユニットで、2000年に結成、2004年から2007年までの間に4枚のアルバム、ミニアルバムを出した。本作は彼ら最後の作品で、コーサ・ノストラの桜井鉄太郎が主宰するブリル・ビルディング・レーベルから発売された。渋谷系らしく、良い音楽なら何でも取り込もうという節操の無さ(褒め言葉で使っています)が持ち味で、レゲエ・リズムのラヴァーズ・ロック、ソウル、クラブ、ラテン、シティ・ポップ、フォーク何でもござれだ。 全11曲中インストルメンタルが2曲で、そのひとつが1.「都会」。ラヴァーズ・ロックのサウンドで、面白いのはテルミンを使っていること。1920年にロシアで発明された世界初の電子楽器で、本体に手を触れずに、その上で手を動かすことで音量と音色をコントロールするのが特徴。演奏者のトリ音(とりね 本名 櫻井えり子、トリ音は無類の鳥好きからついた「鳥姉=とりねえ」がなまったもの)は、ゲーム会社に所属する作曲家、サウンドクリエイターで、サガの「ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド」やバンダイナムコの「アイドルマスター」が主要作。またテルミン奏者としてライブ活動を行っている。聴いていると、音程を正確に保つのが難しそうな楽器だね。ヴィブラフォンの渡辺雅美は有名なマリンバ、ビブラフォン奏者の長男で、クラブ・ジャズ・バンドを率いて活躍中。 他の曲では、ラッパーのBaquerattah(バケラッタ)がゲスト参加したラヴァーズ・ロックの「Lovers」 (作詞 日野友香、Bawuerattah 作曲編曲 青木多果) 1曲目、松原秀樹(2016年没)のギターソロがかっこいいJ-Pop 「Weekend」 (作詞作曲編曲 青木多果) 2曲目と「Driving」 (作詞作曲編曲 青木多果) 5曲目、 ニューソウルっぽい「In The Friday」(作詞 日野友香 作曲編曲 青木多果) 6曲目、こてこてのR&B「フランキー」 (作詞 さえきけんぞう 作曲編曲 青木多果) 8曲目、ノラ・ジョーンズそっくりの 「幸せの涙」 (作詞 日野友香 作曲編曲 青木多果) 9曲目、田ノ岡三郎のアコーディオンと青木のアコースティックギターのみの伴奏によるフォーク風の.「朝日のあたる道」(作詞作曲 田島貴男 編曲 青木多果) 11曲目(Original Love 1994のカバー)など、面白い曲が盛りだくさんだ。 テルミンとヴィブラフォンという一風変わった楽器による「都会」。 [2025年9月作成] |
|
| Life Cosa Nostra (2007) Geneon | |
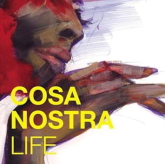 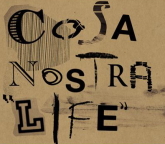 |
1. 都会 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 佐橋佳幸] 6曲目 小田玲子: Vocal 佐橋佳幸: Gut Guitar, Celesta 2007年9月5日発売 写真下: 初回発売分に付けられた紙製スリーブケース 1. Tokai (City) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Yoshiyuki Sahashi] 6th track by Cosa Nostra from the album "Life" on September 5, 2007 |
| コーサノストラはマフィアの別名であるが、本来はイタリア語で「我らのもの」という意味。1991年クラブシーンにおけるDJとミュージシャンから派生したユニットで、メンバー交代を繰り返し、本アルバム製作時は桜井鉄太郎(ギター、キーボード、プログラミング)、長田定男(Osadasadao、パーカッション、ブログラミング)、小田玲子(ボーカル)の3人。ごった煮または幕の内弁当のように種々の音楽が詰まっているが、各曲に漲るグルーヴ感が全体に統一感を与えている。 大人数またはプログラミングによる音数の多い曲が多いなかで、大貫さんの作品カバー「都会」は、佐橋佳幸のナイロン弦ギターとチェレスタ(鈴のような音色の鍵盤楽器)のみによるシンプル伴奏になっていて、アルバムの息抜き、気分転換的な存在といえる。佐橋は以前から桜井の友人だったそうで、本曲以外にも4曲ギターで参加している。大貫さんと縁の深い佐橋によるブラジル音楽風のギターアレンジが光っていて、憂いを帯びた小田のボーカルも曲に合っている。クールな演奏なんだけど、確かなグルーヴを感じさせるパフォーマンスだ。 その他の曲 「Cherry/Redのルーレット」(作詞 サエキけんぞう 作曲編曲 桜井鉄太郎)1曲目はロック賑やかなロック曲で、元ピチカート・ファイブの歌姫野宮真貴がゲストで歌っている。「光と風」(作詩 小田玲子 作曲編曲 Osadasadao) 2曲目はブラスをフォーチャーしたラテン調の曲で、Baquerattahのラップが入る。「果てしない恋〜I Always Love You」(作詩 小田玲子 作曲編曲 桜井鉄太郎)3曲目はソウル風J-Popサウンド。「Life」(作詞 小田玲子、Osadasadao 作曲 Cosa Nostra、青木多果)4曲目はインスト部分が長いファンク調の曲。「Border Dub」(作曲編曲 Osadasadao) 7曲目はレゲエ調のインストルメンタルで、ラップ調のヴォイスが聞こえる。「明るい未来計画」(作詞 Osadasadao 作曲 nanase、Osadasadao 編曲 Osadasado 青木多果)8曲目はビックバンド・ジャズの乗りが面白い。「Come Inside Me」(作詞 Pig The Ryo、小田玲子、Osadasadao 作曲編曲 Osadasadao、青木多果)9曲目は、小田のボーカルとPig The Ryoのラップによるファンク。「Beware Boyfriend」(作詞作曲 Teddy Johns、Robert Taylor 編曲 佐々木淳、桜井鉄太郎)10曲目はイギリスの歌手マリ・ウィルソン 1982のカバー。 最後の曲「Iko Iko」(作詞作曲 Barbara Hawkins, James Crawford, Joan Johnson, Rosa Hawkins 編曲 Osadasadao, ヤマカミヒトミ)12曲目は ニューオリンズのジェイムス "シュガーボーイ" クロフォードの「Jock-A-Mo」1953がオリジナルであるが、女性コーラス・グループのザ・ディキシー・カップスが録音の合間に戯れで歌ったものがたまたま録音され、それに手を加えて「Iko Iko」のタイトルでシングル発売(1964年)され全米20位のヒットになったことにより有名になった。その後もドクター・ジョン、グレイトフル・デッド、シンディー・ローパなど多くのカバーがある。ここではニューオリンズということで、元ボ・ガンボスのDr. Kyonのピアノが大活躍。小田玲子の他にユニット前任者の鈴木桃子のボーカルも加わった賑やかで楽しい演奏。曲の終盤で聞こえる野太い声は、あの和田アキ子とのこと。 「都会」はアルバムの中では異色の曲なんだけど、佐橋の編曲・演奏と小田のボーカルにより素敵な感じに仕上がっている。 [2025年6月作成] |
|
| Lingkaran For Baby Various Artists (2007) Ki/oon (Sony) | |
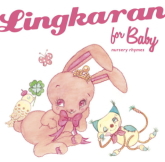 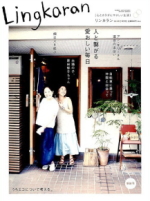 |
4. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 ビューティフル・ハミングバード] 4曲目 ビューティフル・ハミングバード 小池光子: Vocal 田畑伸明: Acoustic Guitar (Guild F-30 '67) 藤原マヒト: Piano, Accordion 武嶋聡: Clarinet Piro: Percussion 写真上: CD (2007年9月26日発売) 写真下: 雑誌 Lingkaran Vol. 26 (2007年10月) 1. Metropolitan Bijutsu-Kan (Metropolitan Museum) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Beautiful Hummingbird] by Beautiful Hummingbird from the album "Lingkaran For Baby" (Various Artists) on September 26, 2007 |
| Lingkaran (リンカラン= インドネシア語で「輪」、「円」の意味)は2003年4月創刊、2009年1月の40号で休刊となった月刊・隔月刊雑誌で、出版社はソニー・ミュージックソリューションズ。「ヒトとカラダにやさしい生活」をコンセプトに、エコ、スロー、手作りの衣食住に係る紹介記事と写真が長期保存可の上質紙に印刷されていた。 本作は雑誌Lingkaranとソニー系のレーベル Ki/oon(キューン)がタイアップして、「パパとママと子ども達を結ぶ、楽しくておしゃれな童謡」をテーマとして、個性的なアーティスト達が既存の童謡に創造的なアレンジを施すことにより大人でも十分楽しめるクォリティーの作品に仕上げている。本作は「for baby」シリーズの第1作として発表され、その1ヵ月後に第2弾としてロックなサウンドによる「Rock for Baby」が発売された。なおポップな表紙は板橋よしえが主宰するファッション・ブランド、Candy Stripperのデザイナーが担当している。 「メトロポリタン美術館」は小池光子(ボーカル)と田畑伸明(アコースティック・ギター)の二人からなるビューティフル・ハミングバードによる演奏。2002年の結成で2003年に初アルバムを発表、現在も元気に活動を続けている。ここでは藤原マヒトのアコーディオンとクラリネットを中心とした電気楽器を使わないアコースティックなバックと芯の強い小池のボーカルにより、個性あふれるサウンドになっている。 全19曲について。 1. 大きな栗の木の下で [イギリス民謡 日本語詞 寺島尚彦 編曲 黒沢薫、北山陽一] ゴスペラーズのアカペラによる歌唱。NHKテレビ「うたのおじさん」で友竹正則が歌って広まった。 2. うたえバンバン [作詞 阪田寛夫 作曲 山本直純 編曲 大嶽香子] ナチュラル・ハイ 女性デュオ。1971年のNHK特番のテーマソングとして作られ、その後繰り返しカバーされて合唱曲や教科書にも採用されてスタンダードになった。 3. 黒ネコのタンゴ [作詞 Francesco Pagano, Francesco Saverio Maresca, Armando Soricillo 作曲 Francesco Pagano 日本語詩 みおたみずほ 編曲 so-to] wyolica 男女二人組。原曲はイタリアの「Volevo un gatto nero (黒ネコが欲しかったのに)」で、1969年当時6歳の皆川おさむが歌って大ヒットした。リズムを変えた面白いアレンジ。 4. メトロポリタン美術館 ビューティフル・ハミングバード 5. くまんばちがとんできた [作詞 糸井重里 作曲 矢野顕子] 矢野顕子 & 坂本美雨の親子共演。「NHKみんなのうた」で2002年10月〜11月に放送されたものと同じ演奏で、当時シングルでリリースされた。ロック調のアレンジ。 6. きらきらぼし [フランス民謡 日本語詞 武鹿悦子] フルカワミキ エレクトロポップのアレンジ。 7. 五木の子守唄 [日本民謡] 東田トモヒロ、エレキピアノとドラムス主体のニューソウル風サウンドの奇抜なアレンジ。 8. 赤い花白い花 [作詞作曲 中林三恵 編曲 宮田まこと] 湯川瀬音 作者不明で世に広まり、1970年赤い鳥が歌った後に作者が判明した。 9. 浜辺の歌 [作詞 林古渓 作曲 成田為三 編曲 ビューティフル・ハミングバード] 大正時代に書かれ、昭和16年に李香蘭が録音、その後教科書に掲載されるようになった。ビューティフル・ハミングバードのアレンジ、演奏は西洋のトラッドのよう。 10. 勇気一つを友にして [作詞 片岡輝 作曲 越部信義] 紗希。イカロスの飛翔と墜落のギリシア神話の歌で、1975年10月〜11月「NHKみんなのうた」で放送。ピアノ弾き語りによるストレートな歌唱。 11. おはなしゆびさん [作詞 香山美子 作曲 湯山昭] 野宮真貴。 香山美子1976年の詩集が初出で、後に「おかあさんといっしょ」で歌われて有名に。渋谷系サウンド風のおもしろいアレンジ。 12. 真赤な秋 [作詞 薩摩忠 作曲 小林秀雄] 鈴木祥子。ボニージャックスの歌で 「NHKみんなのうた」1965年10月〜11月に放送。ここでは独唱から始まり12弦ギター演奏、効果音をバックに多重録音による合唱・輪唱に発展する6分41秒におよぶアヴァンギャルドな世界で、サウンド・メイキングの大友良英は後に「あまちゃん」2013の音楽で広く有名になる。 13. 遠き山に陽は落ちて [日本語詞 堀内敬三 作曲 Antonin Dvorak 編曲 オオヤユウスケ] オオヤユウスケ。ドボルザークの交響曲第9番「新世界より」第2章の主旋律に歌詞をつけたもので、日本では「家路」というタイトルになった。ギター、ピアノのみによるシンプルなアレンジ。 14. アイスクリームの唄 [作詞 佐藤義美 作曲 服部公一] 土岐麻子。ラジオ放送の「ABC子どもの歌」のために書かれ、1962年の「NHKみんなのうた」(旗照夫、天地総子歌)で放送された。変拍子のアレンジが面白い。 15. 永良部の子守唄〜Where Is Your Mammy?〜いったーあんまーまーかいが [沖永良部民謡〜作詞 U-Dou & Platy, B.P. 作曲 朝本浩文〜八重山地方のわらべ歌] 大山小百合 feat. U-Dou & Platy。沖縄歌謡とラップの融合という本作で最も過激なアレンジ。サウンドメイキングは朝本浩文(2016年没) 16. てるてる坊主 [作詞 浅原鏡村 作曲 中山晋平] フルカワミキ 17. ドナドナ [作詞 Arthur Kevess, Sheldon Secunda, Teddi Schwartz, Aaron Zeitlin 作曲 Sholem Secunda 日本語詞 安井かずみ 編曲 Choclat & Akito with the band] Choclat & Akito。渋谷系のChocolatと夫の片寄明人からなるユニット。イディッシュ語の歌に英語の詩をつけた1960年のジョーン・バエズの録音が定番。1966年安井かずみが日本語詞をつけて「NHKみんなのうた」で岸洋子が歌った。面白いアレンジで、同じ録音が本作と同じ年に出た彼らのアルバム「Tropical」に入っている。 18. おぼろ月夜 [作詞 高野辰之 作曲 岡野貞一 編曲 so-to] wyolica ギターの演奏が面白いアレンジ 19. Over The Rainbow 虹の彼方に [作詞 E.Y. Harburg 作曲 Harold Arlen 日本語詞 水島哲] かの香織。映画 「オズの魔法使い」1939でジュディー・ガーランドが歌った。水島哲の日本語歌詞は1961年美空ひばりが録音している。 以上、情報が多すぎて書くのが大変! ちなみに雑誌Lingkaranの26号(2007年10月)と27号(同11月)の裏表紙の裏面に本作と「Rock for baby」の全面広告があり、さらに後者の音楽コーナーに1.「大きな栗の木の下で」を歌うゴスペラーズの記事が掲載された。 どの曲も個性的なアレンジとアーティストの歌唱によるもので、捨て曲がなく創造性とクオリティーの高さが凄い。「メトロポリタン美術館」とてもいいよ。 [2025年5月作成] |
|
| Little Girl Blue 北浪良佳 (2007) One Voice (Video Arts Music) | |
 |
1. 色彩都市 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 石井彰] 9曲目 北浪良佳: Vocal 石井彰: Piano, Producer 天野清継: Guitar 井上陽介: Bass 外山明: Drums Eric-Maria Couturier: Cello 2007年10月24日発売 1. Shikisai Toshi (The Colored City) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Akira Ishii] 9th track by Yoshika Kitanami from the album "Little Girl Blue" on October 24, 2007 |
| 北浪良佳は兵庫県神戸市出身。大学・大学院で声楽を習うかたわら、モデルとして活動。卒業後はオペラ・シンガーとしてデビューしたが、直ぐにジャズに転向。2004年「神戸・ジャズ・クィーン・コンテスト」で優勝し、2007年に本作でアルバム・デビューした。クラシックで鍛えた豊かな声とジャンルにこだわらない音楽性が持ち味で、本アルバムはガーシュイン、コール・ポーター、ロジャース・アンド・ハートといったジャズのスタンダード曲をメインとして、武満徹、スペインの歌、シューベルトの歌曲なども取り上げている。 大貫さんの1.「色彩都市」(アルバム「Cliche」1982収録) もそんな1曲で、ここでのアレンジは他のカバーと大きく異なり、ワルツのリズムになっていて、最初は違和感を感じたが聴き込むと(特にアルバムを通して聴くと)気持ち良く聴けるようになった。ジャズのカルテットをバックにした歌唱で、面白いのはギターがスライド奏法で弾いていること。自身ソロアルバムを出している天野清継はジャズ、クロスオーバー、ロックなど幅広い音楽性を持つ人であるが、彼がスライド・ギターを弾いているのは驚きだね。でもそれがとても良い味を出していて、北浪の少しねっとり気味の歌声によく合っている。間奏におけるベースソロとそれに続くハミングとスライドギター、ピアノによるジャズっぽいコード進行も新鮮で、石井彰のアレンジのセンスが光っている。そしてエンディングで加わるチェロはフランス人のエリック・マリア・クチュリエで、彼は欧州のクラシック、ジャズ音楽界で活躍するチェロ奏者だ。ジャズ・スタンダード曲や武満徹などの錚々たる曲目のなかにあって、大貫さんの「色彩都市」が全く引けをとらずに堂々と輝きを放っているのは凄い。 他の曲について(編曲はすべて石井彰)。 バックを担当する日野皓正のグループにいた石井彰(ピアノ)、前述の天野清継(ギター)、そしてリズムセクションの2人はいずれも現在も現役で活躍している人達で、特にスタンダード・ジャズ曲でのサポートは鉄壁。北浪もそれに応えて安定した歌唱をみせていて、個人的にはナット・キング・コール1950年の「Mina Lisa」が特に好き。しかし私が特に注目するのはジャズ以外の曲についてだ。 「小さな空」4曲目、「燃える秋」5曲目は、現代音楽の作曲家武満徹(1930-1996)の作品(作詞は前者が本人、後者が五木寛之)。「小さな空」は1962年の連続ラジオドラマ「ガン・キング」のために書かれたもので、その後合唱曲として広まった。「燃える秋」は1978年公開の同名の映画の主題歌で、ハイファイセットが歌ったシングルが出ている。この映画は三越の岡田茂社長の企画で制作されたが、彼の会社私物化が問題となり解任されるという事件が発生したため、それを象徴するいわくつきの作品として映画は黒歴史化されてしまったが、歌はスタンダードとして残った。武満の音楽の素晴らしさを気付かせてくれた北浪のカバーに感謝したい。ちなみにこの2曲については本作よりも以前に録音された、武満のお気に入りだったという石川セリのバージョンも最高(前者が「翼〜武満徹ポップ・ソングス」1995、後者が彼の死後制作された「MI・Yo・TA」1997に収録)。 「Amapola」6曲目はスペインのホセ・ラカジュが1924年に発表した曲で、題名は「ひなげし」の意味。1939年にディアナ・ダービンが自身の映画「銀の靴(First Love)」で、また1941年ジミー・ドーシー・オーケストラによるバージョンが大ヒットした。日本では1937年の淡谷のり子による日本語の録音が最初、近年ではCMで使用されたナナ・ムスクーリのバージョンが決定版。また山下達郎によるアカペラ・バージョン(「On The Street Corner 2」1986収録)もある。大変美しい曲で、フランス人のアコーディオン奏者リシャール・ガリアーノの五重奏団が加わり、クラシックの素養がある北浪の歌唱の魅力が最大限に発揮され、リシャールのアコーディオン・ソロも最高の名演になった。「Ave Maria」はご存知シューベルトの歌曲。ここでの彼女はクラシックの型にはまらないソウルフルな熱唱で、間奏で天野のロックなエレキギター・ソロが入るなど、自由奔放な演奏になっている。 ジャズ・ワルツによる「色彩都市」が聴けるよ! [2025年5月作成] |
|
| Sunshine Days of 70's Tribute Album Sunny Rock ! Various Artists (2007) Image Quest Interactive | |
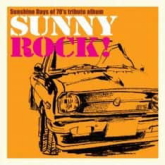 |
9. 海と少年 [作詞作曲 大貫妙子] 9曲目 櫛引彩香: Vocal YANCY: Keyboards 田中拡邦: Guitar 戸田吉則: Bass 棚沢雅樹: Drums 黒沢秀樹: Producer 2007年11月21日発売 9. Umi To Shonen (The Sea And The Boy) [Words & Music: Taeko Onuki] 9th track by Sayaka Kushibiki from the album "Sunshine Days of 70's Tribute Album Sunny Rock !" on November 21, 2007 |
| 「Sunshine Days」は2007年神奈川テレビ等で放送されたテレビドラマ(放送期間 2007/8/26 - 12/9 全12話)。西原亜希、斉藤慶太、初芝崇史主演で、1978年夏の茅ケ崎を舞台に売れない兄弟デュオが女性と出会い、カフェを始めて仲間を増やしキャリアを切り開いてゆくドラマだった。茅ケ崎と音楽とカフェということは、当時地元のホテルでアルバイトをしながら音楽を志し、カフェを開いて音楽を中心とした湘南カルチャーを作りあげた岩沢兄弟のブレッド
& バターがモデルになっているのは明らかで、本ドラマにおける兄弟デュオの名前も「BB」という確信犯なんだけど、彼らは内容的にも音楽的にも一切関わっていない。YouTubeで総集編やメイキングを観た限り、元気な若者たちが騒いでいる青春ドラマのようだ。 主人公の二人が演っている音楽とは別に、ドラマの背景に流れる音楽につき、黒沢秀樹がプロデューサーとなって1970年代のニュー・ミュージック(当時はそう呼ばれていたが、現在は「シティ・ポップ」と言われているね)の名曲のトリビュート集が制作され、番組に先駆けて発売された。そこではシンセサイザー、コンピューターなど当時存在しなかった楽器・機材を使わず、ギター、キーボード、ベース、ドラムスというシンプルでストレートなバンド・サウンドで録音され、主にインディ系で活躍する人たちがボーカルを担当している。 大貫さんの作品からは 9.「海と少年」が選ばれた。歌っている櫛引彩香(1975- 青森県出身)は1999年にメジャーデビュー。2004年からはインディーで現在も音楽活動を続けている。ちなみに彼女は翌年1月に発売されたコンピレーション・アルバム「Pure Voice〜J-Cover」(一十三十一が歌う大貫さんの「彼と彼女のソネット」収録)で、今井美樹1988年の「彼女とTop On Duo」を歌っているね。ここでは原曲に比較的忠実なアレンジ。演奏はよりライブな感じで彼女も素直な感じで歌っている。 他の曲について。曲名 [作詞 作曲] ここで歌っている人、オリジナル・アーティストと発表年 「収録アルバム」、特記 注:編曲者のクレジットがないが、原曲をベースとしたバンドによるヘッドアレンジと思われる。 1. Pink Shadow [作詞作曲 岩沢幸矢 & 二弓] 河原崎亙/ポメラニアンズ/quinka with a yawn、ブレッド&バター 1974 「バーベキュー」。ティンパン・アレイが参加した傑作アルバムだったが、当時は全く売れなかった。この曲は山下達郎がステージで演奏することでも有名。河原崎はポメラニアンズのリーダー。キンカ・ウィズアヨオンは青木美智子のソロユニット。本アルバム中ベストの出来栄え。 2. ソバカスのある少女 [作詞 松本隆 作曲 鈴木茂] ママレイドラグ、ティン・パン・アレイ 1975 「キャラメル・ママ」。アルバムでは鈴木茂と南佳孝のデュエットだった。後の1977年に南がソロでシングルを出している。ママレイドラグは「海と少年」でギターを弾いている田中拡邦(1979- 佐賀県出身)のユニット。 3. オリビアを聴きながら [作詞作曲 尾崎亜美] 有里千花、杏里 1978 シングル、「杏里-apricot jam」。杏里のデビュー曲。当初発売時はヒットしなかったが、時を経て有名になり、現在は名曲と評価されている。有里知花(1981- 神奈川県出身)は2003年に大貫さん作詞の「あなたに会いに行こう」を歌っている。 4. Let's Dance Baby [作詞 吉岡治 作曲 山下達郎] 平泉光司、山下達郎 1978 「Go Ahead」。翌年シングル・カットされた。もともとはザ・キングトーンズのために書かれた曲で、山下のバックで歌っている女性は吉田美奈子。平泉光司は benzo、Couchのボーカリスト。Couchは2008年の大貫さんのトリビュート・アルバム「音のブーケ」で「都会」をカバーしている。 5. 天気雨 [作詞作曲 荒井由美] 柳田久美子、荒井由美 1976 「14番目の月」。荒井由美が結婚して松任谷に改姓する前の最後のアルバムに収録。仕事で湘南を訪れた際に書いた曲ということで、ドラマにぴったりの内容。柳田久美子(1983- 岩手県出身)は現在もインディーで活動中。 6. Magic [作詞 岩沢幸矢 & 二弓、及川恒平 作曲 岩沢幸矢 & 二弓] 黒沢秀樹、ブレッド&バター 1974 「バーベキュー」(「魔術」という日本語タイトルで収録)。同アルバムから2曲目の選曲。ソウルっぽいフォーク・サウンドが何ともいい感じの曲。プロデューサーの黒沢秀樹が自ら歌っている。 7. ラストステップ [作詞 吉田美奈子 作曲 山下達郎] ハミングキッチン、吉田美奈子「Flapper」 1976。山下達郎も 「Circus Town」 1976で歌っている。湘南エリアを本拠地とするハミングキッチンはイシイモモコ(ボーカル)、眞中やす(A.Guitar)のユニット。原曲のボーカルが凄すぎて、ここでのカバーは分が悪い感じがするが、肩の力が抜けたボーカルもそれなりに良し。 8. ありがとう [作詞作曲 細野晴臣] 黒沢健一、小坂忠 「ありがとう」1971、細野と小坂のユニゾンボーカルになっているが、細野の声が断然目立っていた。ここでは黒沢秀樹の兄健一が歌っている。 9. 海と少年 10. プールサイド [作詞 来生えつこ 作曲 南佳孝] sowan song、南佳孝 「South Of Border」1978。南佳孝の傑作。 sowan songは2022年に本名のマエソワヒロユキに改名。黒沢秀樹と活動を共にすることが多い人。 11. ハリケーン・ドロシー [作詞作曲 細野晴臣] Yancy、細野晴臣 「Tropical Dandy」 1975。「ドロシー」は1937年のジョン・フォード監督の映画「Hurricane」に主演したエキゾチックな雰囲気が印象的だったドロシー・ラムーアのこと。50年前にこの曲を聴いたときは本当に衝撃的だった。私の音楽観に大きな影響を与えた曲で、これ以降様々なジャンルの音楽を先入観無く聴けるようになった。この曲のカバーとはとても果敢な挑戦だと思うけど、細野のボーカルとベース、佐藤宏のピアノ、鈴木茂のギター、林立夫のドラムスがあまりに凄すぎて、原曲の偉大さを改めて思い知った次第。Yancyはピアニストとして本アルバムの他の曲にも参加している人で、ここでは低音のボーカルで頑張っているけど、やはり細野さんの声がいかに魅力であるかを痛感してしまう。 12. スノー・エクスプレス [作曲 鈴木茂] サンシャインデイズバンド、鈴木茂 1975 「Band Wagon」。アルバムのクレジットにはオリジナルとして「ティンパンアレイ」と表示されているが、「Bando Wagon」は鈴木にソロアルバムなので正しくは「鈴木茂」。オリジナルはアメリカ録音で、ローエル・ジョージを除くリトル・フィートの連中がバックを担当しており、彼らのようなミュージシャンが日本人のバックをした事は当時画期的だった。ここではアルバム録音用に集められたミュージシャン達によるインストルメンタルになっている。 全体的な印象として、原曲に沿ったアレンジになっていて、特に中条卓(前述のCouchのベーシスト)、戸田吉則のベースを目立たせたミキシングが特徴的。シンセの重低音がなかった1970年代において、演奏にグルーブ感を生み出すためのベースの役割が強調されている。そういう意味でも、懐かしさを覚えるサウンドだ。 [2025年6月作成] |
|
| Music & Me 原田知世 (2007) For Life | |
 |
1. 色彩都市 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 伊藤ゴロー] 2曲目 原田知世: Vocal 吉野友加: Irish Harp 伊勢三木子: Violin 三木祥子: Viola 徳澤青弦: Cello 鈴木正人: Contrabass 2007年11月28日発売 1. Shikisai Toshi (The Colored City) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Goro Ito] 2nd track by Tomoyo Harada from the album "Music & Me" on Novbembr 28, 2007) |
女優業に専念していた原田知世が5年振りに出したアルバムで、デビュー25周年を記念して彼女の誕生日に発売された。ライナーの彼女の言葉によると、2004年にプロデューサーの伊藤ゴローと知り合い、2006年に彼のソロプロジェクト「Moose Hill」のアルバム「Desert House」にゲスト・ボーカルで2曲参加したことが本作のきっかけになったという。新旧の知り合いからの作品提供と演奏参加により、40歳になった彼女の世界観・人生観が色濃く反映された作品になった。アルバム・タイトルがそのことを如実に示している。 大貫さんの名曲 1.「色彩都市」は、原田の感性・声質にぴったり。40という年輪を重ねた落ち着きのある声で、とても気持ちよさそうに歌っている。伊藤ゴローの編曲は、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、アイリッシュ・ハープというアコースティックな編成による演奏で、大貫さんのピュア・アコースティックの弦楽四重奏とはバイオリン1台が抜けてコントラバスによるベースが入っている点で異なる。アイリッシュ・ハープを弾く吉野由香はもともとグランドハープの奏者で、自分の音楽を表現するためにティコ・ムーンというギターとのユニット等で活動し、伊藤ゴローの作品にもよく参加している人。弦楽器のみによるクリスタルな響きが曲に新たな魅力を付け加えている。 他の曲について。 「君とぼく」(作詞 原田知世 作詞編曲 伊藤ゴロー)3曲目は、「色彩都市」と同じストリングスと中島ノブユキのピアノ、菅原雄太のドラムスによるブラジルの香り漂う演奏。原田が書いた歌詞の世界観が素晴らしい。「Are You There?」(作詞 Hal David 作曲 Burt Bachlach 編曲 高橋幸宏) 4曲目はディオンヌ・ワーウィック1965年のヒット曲(全米39位)のカバーで、高橋の編曲がこの曲に新鮮な彩りを与えている。本アルバムの中でも見っけものの逸品。「I Will」(作詞作曲 Lennon McCartney 編曲 伊藤ゴロー)5曲目はビ-トルズ「White Album」1968から。「Wonderful Life」(作詞作曲編曲 オニキユウジ)6曲目はアメリカ日系人のシンガーソングライターの作品で、本人がドラムス以外の演奏を担当している。原田は全12曲中5曲につき英語で歌っているが、違和感を感じないのは、彼女のライフスタイルのなかに英語が自然にあるからだろう。「菩提樹の家」(作詞作曲編曲 鈴木慶一)は以前のアルバムのプロデュースを担当した鈴木慶一が参加。「ノスタルジア」(作詞 樽湖夫 作曲編曲 伊藤ゴロー)は、前述の伊藤のアルバム「Desert House」2006で原田が歌っていた曲の再録音で、文語調の古風な歌詞とトラッドのような演奏が印象的。「くちなしの丘」(作詞作曲 辻村豪文 編曲 伊藤ゴロー)11曲目は兄弟ユニット、キセルの辻村兄弟がギターとベースを弾いている(彼らは前述の「I Will」にも参加)。 そしてハイライトは2曲のセルフカバーだ。「シンシア」(作詞 原田知世 作曲 Ulf Turesson 1997年発売シングル) 8曲目は伊藤のギター、中島のピアノとリズムセクション、「時をかける少女」(作詞作曲 松任谷由美 編曲 伊藤ゴロー 1983年発売シングル)は伊藤のギターのみによるボサノバ・アレンジ。特に後者における原田のボーカルは24年前とは雲泥の差と言い切れる成長を感じさせるものだ。両曲とも最初からボサノバ曲だったと錯覚させるような自然な仕上がりになっているところが凄い。 薬師丸ひろ子 1988年、松任谷由美 2013年とならぶ、「色彩都市」 3大カバーのひとつ。 [2025年6月作成] |
|
| 2008年 One Fine Day (2005/2/16) UTAU (2010/11/10) の頃 | |
| Pure Voice 〜 J-Cover Various Artists (2008) Yoshimoto R And C Co. | |
 |
8. 彼と彼女のソネット (Studio Session) [作詞 Catherine Cohen, Regis Wargnier 作曲 Romano Musumarra 日本語詞 大貫妙子] 8曲目 一十三十一: Vocal 秋山浩徳: Acoustic Guitar 高野康弘: Sound Producer 2008年1月16日発売 1. Kare To Kanojyo No Sonnet (His And Her Sonnet) [Words: Catherine Cohen, Regis Wargnier, Music: Romano Musumarra, Japanese Lyrics: Taeko Onuki] 8th Track by Hitomitoi from the album "Pure Voice〜J-Cocer" Various Artists on January 16, 2008 |
| 1980年代のJ-Popをピュアな声をもつ女性シンガー達がカバーしたオムニバス盤。帯のキャッチ・フレーズは「7人のティンカーベルヴォイスの持ち主が好きなアーティストの70'sから80'sのJポップをカバー」。80年代特有のシンセポップはアコースティックに、そうでなかった曲は逆に2000年代のエレクロトロ・ポップにと、原曲と異なる2000年代のアレンジにより曲の新たな魅力を引き出している。 特に8.「彼と彼女のソネット」は原曲および多くのカバーにあるようなリズミカルなシンセポップではなく、アコースティック・ギター一本のみの伴奏という意表をついた作りになっていて、「Studio Session」というサブタイトルがスタジオでさっと制作されたことを示唆している。一十三十一(ひとみとい、1978- 本名 天野一十三、旧姓 下村 北海道出身)は2002年CDデビュー。グルーヴ感溢れる音楽を得意とする人で、ここではギターのアルペジオとボーカルのみの演奏であるが、それでも聴いていると確かなビートが感じられる歌唱だ。彼女は大貫さんフォロワーの一人で、2005年のテレビ番組で「いつも通り」を大貫さんと二人で歌ったり、本作以降も大貫さんの曲を多くカバーしている。 他の曲について 曲名 [作詞 作曲 サウンドプロデューサー] 歌い手、オリジナルと発表年、特記 1. You Were Mine [作詞 川村真澄 作曲 久保田利伸 Sound Producer 御供信弘] 一十三十一、久保田利伸 1988、 スリーフィンガーのアコースティックギターのドラムスがメインの演奏(原曲はシンセポップ)。 2. Diamonds [作詞 中山加奈子 作曲 奥居香 Sound Producer 御供信弘] 名嘉真祈子、プリンセス・プリンセス1989、ブラジル音楽風アレンジ。名嘉真祈子はトルネード竜巻のボーカリスト。 3. 想い出がいっぱい [作詞 阿木燿子 作曲 鈴木キサブロー Sound Producer 塚田耕司] Chocolat & Akito、H2O 1983、Chocolat & Akitoは、モデル・歌手のchocolatと片寄明人による夫婦デュオ。エレピ、ベース、ドラムス主体のシンプルな演奏が新鮮。 4. 彼女とTip On Duo [作詞 秋元康 作曲 上田知華 Sound Producer 塚田耕司] 櫛引彩香、今井美樹 1988、レゲエ調のアレンジ。 5. やさしさにさようなら [作詞作曲 小田和正 Sound Producer 大久保友裕] chiiko、オフコ−ス 1978、唯一の1970年代の曲。chiikoは沖縄を活動拠点とするシンガーで、ボイストレ−ナー平田千恵としても有名。ピコピコしたシンセとガットギターのコンビーネション、ソウルフルなボーカルとオフコースの組み合わせが面白い。 6. ダンデライオン〜遅咲きのタンポポ [作詞作曲 松任谷由美 Sound Producer 塚田耕司] bice、松任谷由美 1988、原田知世 1988、シンセサイザーが印象的なアレンジ。bice (ビーチェ)は本名木嶋(旧姓 中島)優子で、1972年埼玉県出身。2010年に心筋梗塞により急死(享年38)。 7. まつわ [作詞作曲 岡村孝子 Sound Producer 清水ヒロタカ] Chocolat、あみん 1982、原曲は歌謡曲風のアレンジだったが、ここではグランジ・ロック風J-Popのサウンドとピュアな女性ボーカルとの対比が面白い。 8. 彼と彼女のソネット 9. between the words & the heart -言葉と心- [作詞作曲 小田和正 Sound Producer Aiko & 高野康裕] Aiko、小田和正 1988、アコースティックなボサノバアレンジ。Aikoはadvantage Lucyというギターポップ・バンドのボーカリスト。 10. そして僕は途方に暮れる [作詞 銀色夏生 作曲 大沢誉志幸 Sound Producer 塚田耕司] 櫛引彩香、大沢誉志幸 1984、ピアノとアコースティック・ギターが入ったシンセポップ。 11. 悲しいくらいほんとの話 [作詞 来生えつこ 作曲 来生たかお Sound Producer 塚田耕司] bice、原田知世 1982、エレクトロポップのアレンジ。 女性シンガーの透明感溢れるピュアな歌声が、創意工夫に富んだアレンジによって引き立っている。 ギター一本のみの伴奏による「彼と彼女のソネット」。 [2025年5月作成] |
|
| 一緒にうたおう! NHKみんなのうた (2008) Bad News | |
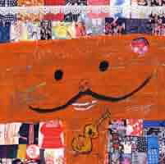  |
1-3. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子] 3曲目 (おとなVer.) ヒダリ 太田ヒロシ: Vocal, Guitar Justin Bacon: Mecha 上月大介: Bass 2-3. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 miwacho] 3曲目 (こどもVer.) ランドセルズ 大内亮介(10才): Recorder, Vocal, Chorus 大山未悠(8才): Vocal, Chorus シーナ(10才): Pianica, Vocal, Chorus ナユ(12才): 木琴, Vocal, Chorus 田野ソウタ(10才): Guitar, Vocal, Chorus 田野ヒビカ(13才): Pianica, Vocal, Chorus 写真上: おとなVer. (2008年2月6日発売) 写真下: こどもVer. (2008年2月6日発売) 1-3. Metropolitan Bijutsu-Kan (Metropolitan Museum) [Words & Music: Taeko Onuki] by Hidari from the album "Issho Ni Utao! NHK Minna No Uta - Otona Ver." (Let's Sing Together MHK Everbody's Songs - Adult Ver.) (Various Artists) on Febuary6, 2008 2-3. Metropolitan Bijutsu-Kan (Metropolitan Museum) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: miwacho] by Randsels from the album "Issho Ni Utao! NHK Minna No Uta- Kodomo Ver." (Let's Sing Together MHK Everbody's Songs - Child Ver.) (Various Artists) on Febuary6, 2008 |
| Bad News Recordsというインディー・レーベルの企画・制作によるもので、主にJ-Popのアーティストが関わった「NHKみんなのうた」の名曲カバー集。面白いのは同じ曲目・曲順で、アーティストが自分流にアレンジした「おとなVer.」と一般公募で募った子供達が歌う「子供Ver.」の2枚のCDが同時発売されたことだ。前者について編曲者のクレジットがないのは、アーティストが自分達でアレンジしたものだからと推測される。後者については「伴奏」、「ミックス」、「All
Instruments」として音作りを担当した大人の名前がクレジットされている。、 おとなVer.の1-3「メトロポリタン美術館」を演奏したヒダリ(「左」の意味)は、神戸を本拠地とするロックバンドで、結成後にメカがメンバーに加わって、打ち込みによるテクノロック的傾向が強くなった。2014年に活動休止。数ある同曲のカバーの中で、最もテクノ色が強いアレンジ。 こどもVer.の2-3「メトロポリタン美術館」は、収録曲の中は例外的に、打ち込みによるエンディングのドラムスを除いて子供たちが自ら演奏している。アレンジャー「miwacho」の本名は藤村みわ子で、ランドセル・レコードというレーベルを立ち上げて、子供達によるバンド「ランドセルズ」のプロデュースを行っている人。従って本作は、他の曲と異なり公募によるシンガーではなく、彼女のマネジメントに所属する子供達がレコーダー、ピアニカ、ギター、木琴などを演奏して歌ったものだ。ボーカルの音程には子供らしい不安定さはあるが、「へたうま」の範疇に入るレベルで、演奏も含めて他の曲と一線を画している。 以下おとなVer.の他の曲について (作詞作曲 オリジナル・アーティスト 初回放送年月 本作のアーティスト 特記) 1. 切手のないおくりもの [作詞作曲 財津和夫] 財津和夫、チューリップ 1978/6 アナ(大久保潤也と大内篤による音楽ユニット) 2. バナナ村に雨がふる [作詞 銀色夏生 作曲 乾裕樹] EPO 1987/8 toddle (田淵ひさ子のバンド) 3. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子] 大貫妙子 1984/10 ヒダリ 4. 山口さんちのツトム君 [作詞作曲 みなみらんぼう] 川橋啓史 1976/4 Harco (2018年以降は本名の青木慶則で活動) 5. 南の島のハメハメハ大王 [作詞 伊藤アキラ 作曲 森田公一] 水森亜土、トップギャラン 1976/4 ヒックスヴィルと堂島孝平 (ヒックスヴィルは3人組のバンド) 6. くまんばちがとんできた [作詞 糸井重里 作曲 矢野顕子] 矢野顕子&坂本美雨 2002/10 スムルース (徳田憲治を中心とするグループ) 7. むかしトイレがこわかった![作詞作曲 楳図かずお] 楳図かずお 2000/8 石橋英子(シンガーソングライター) 8. ビューティフル・ネーム [作詞 奈良橋陽子 作曲 タケカワユキヒデ] ゴダイゴ 1979/4 Cubismo Grafico feat. Yuuki (松田岳二のソロプロジェクト、ボーカルは女性っぽく聞こえるけどエフェクトを効かせた Tani Yuuki かな?) 9. コンピュータおばあちゃん [作詞作曲 伊藤良一] 東京放送児童合唱団(酒井司優子) 1981/12 ハックルベリーフィン (3人組のバンド。オリジナルの坂本龍一編曲はYMOそのもの。当時はコンピューターを操るおばあちゃんは歌になるほど珍しかった?) 10. 私のニャンコ [作詞作曲 矢野顕子] 矢野顕子、ひばり児童合唱団 1983/4 高野寛 (オリジナルの編曲は坂本龍一) 11. メッセージソング [作詞作曲 小西康陽] ピチカート・ファイブ 1996/12 堂島孝平 12. 青天井のクラウン [作詞 中川敬 作曲 中川敬, 河村博司] ソウル・フラワー・ユニオン 1998/12 荒井良二 (音楽活動もする絵本作家) 13. クラリネットをこわしちゃった[フランス民謡] ダークダックス 1963/2 エビタイガー (3人組のパンクバンド) 14. へんな家 ! [作詞 S.バルドッティ 訳詞 木下忠司 作曲 V. モラエス] レミー・ブリッカ、東京放送児童合唱団 1983/2 つじあやの with 堀下さゆり & 小西透太 (原曲はブラジル音楽の「La Casa」。つじと堀下はシンガーソングライター、小西はサクラメリーメンのボーカル、ギター担当) 15. おしりかじり虫 [作詞 うるまでるび 作曲 松前公高、うるまでるび] おしりかじり虫 2007/6 スケルトンズ (男性のうるまと女性のでるびの夫婦ユニットで、松前公高のサポートを得て作詞・作曲・歌・映像を手がけている) おとなVer.は原曲の良さと奇抜なアレンジにより、オリジナルと比較してニヤニヤしながら楽しんで聴くことができる。一方こどもVer.は、歌っている子供達の歌唱力にバラツキがあるため、聴く人によって評価が分かれるだろう。「メトロポリタン美術館」はそれなりに良いと思うけど.....。 「メトロポリタン美術館」のカバーをおとなVer.とこどもVer.の2通りで聴くことができる。 [2025年5月作成] |
|
| 音のブーケ Various Artists (2008) MIDI Creative | |
 |
以下 特記ない場合は作詞作曲 大貫妙子、 編曲 各アーティスト(正確にはクレジット表示なし) 1. 突然の贈りもの ari (Mignonne 1978) ari: Vocal, Piano 2. 横顔 Water Water Camel (Mignonne 1978) 齋藤キャメル (Water Water Camel): Vocal, Acoustic Guitar 田辺玄 (Water Water Camel): Acoustic Guitar, Electric Guitar, Ukulele, Sound Effects 須藤剛志 (Water Water Camel): Electric Bass ゆうずぃ: Drums, Vibraphone 吉原キサト: Backing Vocal 3. メトロポリタン美術館 永山マキ meets hitme&miggy (HNKみんなのうた 1984、Single B-Side 1984、 Comin' Soon 1986) 永山マキ: Vocal, Clarinet, Shaker ヤマカミヒトミ (hitme&miggy): Flute, Malodion, Whistle 宮嶋みぎわ (hitme&miggy): Piano, Wind Chime, Xylophone 高井亮士: Wood Bass 4. 海と少年 犬塚彩子 (Mignonne 1978) 犬塚彩子: Vocal, Guitar 菅沼雄太: Percussions 5. MOMO 寺尾紗穂 (Comin' Soon 1986) 寺尾紗穂: Vocal, Piano 只熊良介: Percussions 6. 若き日の望楼 casa (Romantique 1980) 古賀夕紀子: Vocal 古賀美宏: Guitar 守屋拓之: Bass 7. コロは屋根の上 marasica (HNKみんなのうた 1986、Pure Drops 1991) 上机さくら (marasica): Vocal 白山詠美子 (marasica): Piano, Synthesizer 村尾祐介: Bass 矢野秀平: Percussions 8. 街 Quiet Village (Grey Skies 1976) 八田裕之: Guitars, Programmings 生松秀之: Keyboards, Programmings 原川マコト: Keyboards 銭天牛: Bass 菅田直人: Drums 佐藤直子: Percussions ミトモタカコ: Guest Vocal 9. Rain Dance [作詞 大貫妙子 作曲 中西俊博] 蛇腹姉妹 Instrumental (Purissima 1988) 佐々木絵実: Accordion 藤野由佳: Accordion 10. 夏色の服 山田庵巳 (Cliche 1982) 山田庵巳: Vocal, 8strings guitar 11. 新しいシャツ Dois Mapas (Romantique 1980) 木下ときわ: Vocal 新美博允: Guitar 冨田謙: Electric Piano, Programming 橋本歩: Cello 千ヶ崎学: Bass 12. 都会 Couch (Sunshower 1977) 平泉光司: Vocal, Guitars 中條卓: Bass 小島徹也: Drums 13. ひまわり ううじん (東京日和 1997) ううじん: Vocal, Guitar 14. メトロポリタン美術館 omu-tone Instrumental (HNKみんなのうた 1984、Single B-Side 1984、 Comin' Soon 1986) 澤口希: Marimba, Glocken 佐藤貴子: Percussion, Pianica 高橋若菜: Marimba, Vibraphone 15. 黒のクレール ネグリータ Instrumental (Cliche 1982) 須藤信一郎: Piano 伊沢陽一: Steel Pan 羽場達彦 (Oyasumi-Records) : Producer 小池アミイゴ: Jacket Design 2008年3月2日発売 All songs written by Taeko Onuki except noted, amd arranged by aritists 1. Totsuzen No Okurimono (The Sudden Gift) by ari 2. Yokogao (Face In Profile) by Water Water Camel 3. Metropolitan Museum by Maki Nagayama meets with hitme&miggy 4. Umi To Shonen (The Sea And The Boy) by Ayako Inuzuka 5. MOMO by Saho Terao 6. Wakaki Hi No Boro (The Lookout Of The Yonger Days) by casa 7. Koro Wa Yane No Ue (Koro's On The Roof) by Marasica 8. Machi (City) by Quiet Village 9. Rain Dance [Words: Taeko Onuki, Music: Toshihiro Nakanishi] by Jabara Shimai (Instrumental) 10. Natsuiro No Fuku (The Dress Of Summer Color) by Anmi Yamada 11. Atarashii Shatsu (The New Shirts) by Dois Mapas 12. Tokai (City) by Couch 13. Himawari (Sunflower) by Uujin 14. Metropolitan Museum by omu-tone (Instrumental) 15. Kuro No Claire (The Black Claire) by Negurita (Instrumental) from the album "Oto No Bouquet (The Bouquet Of Sound)" Various Artists on March 2, 2008 |
| 羽場達彦(1965-2010) は熊本県出身のミュージシャン、文筆家。小学校の頃から音楽に目覚め、青山学院在学時は打ち込みによる音楽制作に熱中する。中退後は会社員やジャズバーのマスターなどを経て井の頭線の池ノ上駅前にあるbobtailというライブバーのオーナーとなり、ミュージシャンとの人脈を築き、自らも「池ノ上陽水」という名前でアルバムを自主制作したが、2010年に永眠。 そんな彼がbobtailに出演したアーティスト等に声をかけて制作(注*)したのが、大貫妙子のトリビュート・アルバム「音のブーケ」だ。2013年発表の同種のアルバム「大貫妙子トリビュート」と異なり、ここではインディ系のアーティストが参加していて、費用の関係もあってか、シンプルでストレートかつ自由な雰囲気に満ちた作品に仕上がった。 1. 突然の贈りもの ari ari(シンガーソングライター)の代表作はJR九州のCMソング「雨上がり」2003。その名前での2010年代以降の活動記録はなかったが、この曲の作詞者のクレジットから本名は山里亜理沙で、森英臣(ギター)とMount Sugarというユニットを組んだり、近年は山里ありさという名前で出身地の沖縄で活動していることがわかった。ピアノ弾き語り(ギターソロが入る間奏部分がなく、すぐに歌が始まるので、聴いていて少しびっくりする)で淡々と歌っており、透明感溢れる感じが何とも良い感じ。 2. 横顔 Water Water Camel 山梨県の中学の同級生で結成されたバンドで、現在は個々で仕事(齋藤は佐賀県で精肉店兼カフェ、田辺はCM・WEBの音楽制作、須藤はセッションプレイヤーなど)をしながら、現在に至るまでグループとしての活動を続けている。原曲と異なるコード進行かつピアノレスの演奏で、欧州のトラッドを聴いているかのような気分になる不思議なサウンド。 3. メトロポリタン美術館 永山マキ meets hitme&miggy 永山マキ(シンガーソングライター)はユニット、モダーン今夜やiimaのボーカリストを務め、cmや子供向けのイベントを行っている。hitme&miggyは、ホーン奏者hitme(ヤマカミヒトミ)とピアニストmiggy(宮嶋みぎわ)の二人で、ジャズ、ブラジル、クラシック音楽を演奏するデュオ。4分を超えるこの曲にしては長い演奏で、ピアノとフルート、鍵盤ハーモニカ、ホイッスルによる独自の編曲およびアコースティックな伴奏で、途中で転調したり独自のメロディーが流れるなどの展開が魅力的。 4. 海と少年 犬塚彩子 愛知県出身の犬塚彩子は、ボサノヴァ・サンバのギタリスト、ボーカリスト。9枚のアルバムを発表し、現在も活動中。「海と少年」はギターとパーカッションによる完全なボサノヴァ・アレンジによる伴奏で、ノンヴィブラートのクールなボーカルもいかにもそれらしい。 5. MOMO 寺尾紗穂 寺尾紗穂(1981- 東京都出身)はシュガーベイブのベーシスト寺尾次郎(1955-2018 フランス映画字幕翻訳家)の娘で、2007年にメジャーデビューし、本作のアーティストの中で唯一、2013年メジャー・レーベルから出た「大貫妙子トリビュート」にも「Rain」で名を連ねている。アルバム、シングル、ゲスト参加の他にCMの仕事も多い。また2010年代よりエッセイストとしての活動も活発。「MOMO」はパーカッションとピアノのみの伴奏で、声質が大貫さんに似ている(大貫さんよりも少しだけ強めの声かな)。 6. 若き日の望楼 casa casaは古賀夕紀子と古賀美宏の姉弟によるデュオで2002年結成。ブラジル音楽をコアにジャズ、ソウルを取り入れたスタイルで、2010年代以降は(恐らく有紀子の海外渡航のため)活動を休止したが、2018年にアルバムを出している。ナイロン弦ギターとウッドベース(ピッチカートと弓を使ったアルコ奏法)のみによる演奏で、ブラジル音楽の香りが強く漂う。間奏のハミングなどストイックな感じの歌声、プレイが曲にマッチしている。 7. コロは屋根の上 marasica マラーシカは「大人の童謡」をコンセプトとした女性二人組。2006年〜2007年の間に2枚アルバムを出している。ピアノを中心に軽めのリズムセクションやシンセサイザーによる犬の鳴き声などを加えた演奏で、使用楽器は異なるが雰囲気的には原曲に近い。 8. 街 Quiet Village (Grey Skies 1976) 本作の中では例外的な大人数のバンド編成によるエレクトリック・サウンド。YMOに影響を受けた矢田と池松が始めたバンドが母体で、2000年代-2010年代に活躍。ライブやレコーディング時は仲間のミュージシャンが参加するのが恒例。ベースの銭天牛の本業は西洋占星術師。ミトモタカコはソウル好きなボーカリストとのことで、奇抜なリフと原曲無視の和音によるユニークなサウンドとエレキギター・ソロ、ソウルフルなボーカルによる摩訶不思議なサウンド。本アルバムの中では最も過激なアレンジだ。 9. Rain Dance [作詞 大貫妙子 作曲 中西俊博] 蛇腹姉妹 Instrumental (Purissima 1988) 本職が校正校閲の自営業という佐々木(姉)と、民族音楽好きのアコーディオン奏者藤野(妹)による偽装姉妹デュオ。アコーディオン2台のみによるブカブカしたインストルメンタル。この曲に関して大貫さんは作詞だけなので、インストルメンタルにしてしまうと厳密には彼女の曲ではない? ということになるが、ここでは細かいことは言いっこなしだね。 10. 夏色の服 山田庵巳 (Cliche 1982) ベース弦付きの8弦クラシックギターによる長尺な語りと歌唱という独自の世界を築いたシンガー・ソングライターで、代表作は「機械仕掛乃宇宙」2012。彼は青葉市子に音楽を志す動機を与えた師でもある。本作の時点ではデビューアルバム発表前で知名度は低かったはず。クラシック・ギターによる伴奏が精緻で厳かな響き。それにしても歌声を聴いたとき、てっきり女性と思ってしまった!? 11. 新しいシャツ Dois Mapas (Romantique 1980) Dois Mapasはポルトガル語で「二枚の地図」という意味。木下ときわ(ボーカル)と新美博允(ギター、本アルバムのクレジットでは「博允」と表示されているが他の資料では「広允」となっている)のプラジリアン・ユニット。2002年から活動記録があり、現在も二人で演奏している。橋本歩はクラシック、ジャズ、ポップスなど幅広いジャンルで活躍するチェロ奏者。打ち込みによるパーカッションやシンセサイザーの無機的な音と、ギターとチェロのアコースティックな音が絡み合って独特な浮揚感があるサウンドを創り出している。きりっとした感じの木下のボーカルも良いが、特に長いエンディングでのチェロの解放感溢れるプレイが素晴らしい。 12. 都会 Couch (Sunshower 1977) Couchはギター、ベース、ドラムスの3人組グループで2002年結成。ギターの多重録音はあるが、ピアノレスという弦楽器の響きに満ちたサウンドが個性的で、オリジナルとは異なるグルーヴ感が新鮮。本人達も相当気に入っていたようで、9年後の2017年に発売された彼らのアルバム「リトルダンサー」に同じ録音が収められ、同時にシングルEPレコードも発売された。 13. ひまわり ううじん (東京日和 1997) 「ううじん」は「植う人(=植える人)」の意味の造語。2000年代の後半に活動記録がある。アルバム「おめでとう ありがとう」2007は羽場達彦のレーベル、オヤスミレコードから発表。多重録音による自身のコーラス入りで、本人の持ち味に合った選曲だ。 14. メトロポリタン美術館 omu-tone Instrumental (HNKみんなのうた 1984、Single B-Side 1984、 Comin' Soon 1986) オムトンは打楽器奏者3人組によるインストルメンタル・グループで2003年結成、現在も活動中。メンバーのあだ名は、Chang-Nong、わかめーる、tko。この曲はアルバムにふたつ入っていて、こちらもアイデアに富んだ楽しい演奏。 15. 黒のクレール ネグリータ Instrumental (Cliche 1982) ネグリータはピアニスト須藤信一郎とスティール・ドラム奏者伊沢陽一のユニット。この曲をスティール・ドラムの演奏で聴くという不思議な体験........。 以上、アーティストの個性を最大に生かした作りながらも自己満足に陥っていないのは、プロデューサー、アーティスト達の大貫さんに対する愛着と敬意があるから。小池アミイゴによるジャケット・イラスト、歌詞ページに載せられた各アーティストの似顔絵も秀逸で、プロデューサー羽場達彦の渾身の作品となった。 注* ・成瀬さんという方のブログ「geopolitical critique」の2010年5月末の投稿 「追悼, bobtail 羽場達彦」に、彼が同所に通った50回のコンサートの出演者一覧が掲載されており、その中に本アルバム参加者の名前が多くある。 ・蛇腹姉妹の藤野由佳のオフィシャルサイトの2008年2月14日付投稿に、ライブバーBobtailのマスター、羽場さんに声をかけられて参加した旨の記述がある。 [2025年5月作成] |
|
| Summerin' 土岐麻子 (2008) Rhythm Zone (Avex) | |
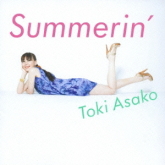 |
7. 都会 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 渡辺シュンスケ] 7曲目 土岐麻子: Vocal 渡辺シュンスケ: Piano, Programming 沖祥子、伊勢三木子: Violin 萩原薫: Viola 橋本歩: Cello 2008年6月25日発売 7. Tokai (City) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Shunsuke Watanabe] 7th track by Asako Toki from the album "Summerin'" on June 25, 2008 |
| 土岐麻子(1976- 東京都出身)はジャズサックス奏者土岐英史の娘。2004年インディーズでのソロアルバム・デビュー当初はジャズのスタンダード曲を歌っていたが、2006年の「Weekend
Shuffle」でJ-ポップのカバー、さらにメジャー第1作目の「Talkin'」で自らの作詞によるオリジナルに挑戦した。本作はそれに続くミニアルバム(全7曲)でカバー5曲、オリジナル2曲からなる。 大貫さんの「都会」(アルバム「Sunshower」1977収録)のカバーはピアノ、ベースと弦楽四重奏による演奏。編曲とピアノはSchroeder-Headz (シュローダー・ヘッズ)というソロプロジェクト名でも活躍する渡辺シュンスケで、聞こえるフィンガー・スナップ(指パッチン)のような音は打ち込みによるもの。原曲のようなリズムはなく、ピアノと弦楽器による静かな演奏をバックに土岐がしっとりと歌っている。ただし間奏におけるピアノソロはジャズそのものだ。渡辺シュンスケとはその後もコラボが続いていて、2015年のアルバム「Bittersweet」に添付されたDVDのライブではSchroeder-Headzをバックに土岐が「都会」を歌っている。 その他の曲について。 1. Libertine [作詞 土岐麻子 作曲 松本良喜 編曲 奥田健介] オリジナル 2. サマーヌード [作詞 桜井秀俊、倉持陽一 作曲 桜井秀俊 編曲 川口大輔] 真心ブラザース 1995 3. 小麦色のマーメイド [作詞 松本隆 作曲 呉田軽穂 編曲 川口大輔] 松田聖子 1982 4. Reach Our I'll Be There [作詞作曲 Holland, Dozier, Holland 編曲 奥田健介] Four Tops 1966 (全米1位) 5. La Isla Bonita [作詞作曲 Bruce Gaitsch, Madonna Louise Ciccone, Patrick Keonard 編曲 伊藤ゴロー] Madonna 1987 (全米4位) 6. Smilin' [作詞 土岐麻子 作曲編曲 川口大輔] オリジナル 7. 都会 ジャズを歌っていた人だけあって、フュージョン・ジャズっぽいサウンドをバックに軽やかに歌っている。声質が重々しくないため、リズミカルな歌い方が向いているようだ。5.「La Isla Bonita」はサックスをフィーチャーしたジャズっぽいアレンジで一風変わった出来栄え。 [2025年4月作成] [2025年5月追記] 後で気がつきました。2021年WOWWOWで放送されたドラマ「ペンションメッツァ」(主演 小林聡美)のエンディング・テーマ曲「空飛び猫」(2021年2月3日配信)は、渡辺シュンスケ氏の作詞作曲編曲で大貫さんが歌っています。 |
|
| 懐かしい未来 alan (2008) avex trax | |
   |
1. 懐かしい未来〜longing future〜[作詞 大貫妙子 作曲 菊池一仁 編曲 中野雄太] Single 2. 合唱 懐かしい未来〜longing future〜 [作詞 大貫妙子 作曲 菊池一仁 編曲 中野雄太] Single Coupling alan: Vocal (1), 二胡 (1) 杉並児童合唱団: Children's Chorus (2) 坂本龍一: Piano (1), Producer (1) 中野雄太: Keyboards (1), Programming (1), Piano (2) 伊平友樹: Acoustic Guitar (1) フレーベル少年合唱団/MCキッズ: Children's Chorus (1) 菊池一仁: Sound Producer 写真上: Single 2008年7月2日発売 (1, 2収録) 写真中: Album 「Voice Of Earth」 (DVD付 特別盤)2009年3月4日発売 (1収録) 写真下: Album 「Voice Of Earth」 (DVD無 通常盤)2009年3月4日発売 (1収録) 1. Longing Future [Words: Taeko Onuki, Music: Kazuhito Kikuchi, Arr: Yuta Nakano] 2. Chorus: Longing Future [Words: Taeko Onuki, Music: Kazuhito Kikuchi, Arr: Yuta Nakano] by Alan from the single "Longing Future" on July 2, 2008 |
alan (阿蘭 本名 アラン・ダワジュオマ 1987- )は中国四川省カンゼ・チベット族自治州(甘孜州)丹巴県(通称:美人谷)出身。元歌手の母のもとで二胡と歌を習い、音楽学校を卒業してインディーズ・レーベルからレコードを出したり、音楽祭で入賞していたが、2006年エイベックスが北京で開催した新人発掘オーディションに出て、安室奈美恵と夏川りみを歌って審査員に衝撃を与え、当時浜崎あゆみ、倖田來未などを担当していた菊池一仁が作曲・プロデュースを手掛けて、2007年「明日への讃歌」で日本でのメジャー・デビューを果たした。 そしてニューヨーク在住の坂本龍一が彼女が出演したテレビ番組を観て感銘を受け、プロデュースを申し出たことにより、3枚目のシングルである1.「懐かしい未来〜longing future〜」の企画がスタートし、本曲はNHKが推進する地球エコプロジェクト「Save The Future」のイメージソングとなった。同プロジェクトは「大きな問題となっている地球温暖化を防止するために、私たちは何ができるか」をテーマとした多数の特別番組の制作、専用YouTubeチャンネルの創設、NHK放送センターでのイベント開催などを実施。alanは2008年6月8日に新宿御苑で行われた「エコうた」という番組に出演し、坂本龍一のピアノ演奏のビデオと本人の屋外での歌唱の合成パフォーマンスが放送された(当該映像はYouTubeで観ることができる)。ちなみに同曲は翌2009年のプロジェクトでも使用され、そこでは彼女が日本各地を回って同曲を現地の人々と合唱したという。 歌詞・メロディーともに雄大なスケールの「懐かしい未来〜longing future〜」は、神がかった彼女の声にピッタリだった。彼女の場合、日常会話では中国なまりがあるけど、歌での日本語の発音は完璧で、それ以上の表現力・説得力を感じさせるところが凄い。そして坂本が奏でるピアノの音、彼女による艶やかな二胡のソロに加えて、チィベットフェイクと言われる独特なコブシが効いた歌声を聴くことができる。この地声による凄い高音を彼女は最初から訓練なしにできたとかで、民族的に恵まれた特質によるものとしかいいようがない。本曲は約半年後にそれまでに出したシングルをまとめたアルバム「Voice Of Earth」に収録されたが、そこでは子供達の声が入ったイントロがシングルよりも少し長くなっている。またアルバムの特別盤には同曲のプロモーション・ビデオを収めたDVDが付いていて、その映像の最後には撮影地につき以下の字幕があった。 「東京湾、中央防波堤内側埋め立て地の東側に位置する。その大部分は、昭和48年から昭和62年にかけて区部で発生したごみ1,230万トンで埋められた土地。都心部におけるヒート・アイランド現象の改善を目標とした"緑の東京10年プロジェクト"の一環として、東京湾に浮かぶ東京ドーム19個分の大きな緑の森の整備を計画している。」 「区部」とは江東区のことで、17年後の2025年3月、この場所は「海の森公園」としてオープンし、少し遅れたもののプロジェクトは無事実現している。 またシングルには同曲の合唱版 2.「合唱 懐かしい未来〜longing future〜」も収められていて、そこではピアノのみの伴奏で子供たちが歌っている。なおこのバージョンについてもプロモ・ビデオがあり、特別盤アルバムのDVDに収められている。そこでは小学校を訪れたalanが子供達の合唱を聴き、一緒に歌うシーンがあるが、実際には彼女の声は聞きとれない。合唱版はこの曲が子供達に歌い継がれてゆくことを期待して作ったものと思われるが、現在は森山直太朗作詞作曲で上白石萌音が歌い、全国高校サッカー選手権大会の応援歌となった同名異曲(2022年)が合唱曲として広く認知されていて、こちらのほうは忘れ去られてしまったようだ。 alanは2011年以降活動拠点を中国に移したため、日本でこの曲を歌う人がいなくなってしまった。しかるに大貫さんは2009年から2012年まで放送されたNHK FMのラジオ番組「大貫妙子 懐かしい未来」のテーマ曲としてこの曲のセルフカバーを使用、放送開始時の2009年4月29日に発売されたベストアルバム「Palette」に収録された。(坂本龍一を除く)他の人が作曲した曲を大貫さんがセルフカバーした珍しいケース。 ちなみにalanはその後中国において確固たる地位を築き活躍しているが、頻度は少ないものの、たまに来日してコンサートを開き、そこで本曲を歌っている。 [2025年7月作成] |
|
| Sunshine Days Live Sunny Rock ! Various Artists (2008) Pony Canyon | |
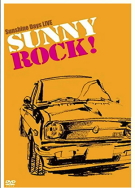 |
9. 海と少年 [作詞作曲 大貫妙子] 9曲目(映像) 櫛引彩香: Vocal YANCY: Keyboards 田中拡邦: Guitar 中條卓: Bass 辻凡人: Drums 黒沢秀樹: Producer 2008年7月25日発売 9. Umi To Shonen (The Sea And The Boy) [Words & Music: Taeko Onuki] 9th track by Sayaka Kushibiki from the DVD "Sunshine Days Live Sunny Rock !" on July 25, 2008 |
テレビドラマ「Sunshine Days」(放送期間 2007/8/26 - 12/9 全12話)の背景音楽として制作されたサウンドトラック・アルバム「Sunshine Days Of 70's Tribute Album Sunny Rock !」の2007年11月21日発売をうけて、翌2008年2月1日渋谷道玄坂にあるDuo Music Exchange にてコンサート「Sunshine Days Live Sunny Rock !」が行われ、その模様を収めたDVDが7月25日に発売された。 DVDの曲目・曲順および各曲の歌い手はCDと同じ。バンド・メンバーについて、DVDのジャケットのクレジット表示はベース、ドラムスで複数の奏者が参加していたCD(スタジオ録音)のものになっているが、コンサートでは最後におけるバンドメンバー紹介で、中條卓(ベース)、辻凡人(ドラムス)の二人が担当していることがわかる。また冒頭の曲「Pink Shadow」で河原崎亙が「コンサートの後半戦の終盤」と言っているので、コンサートでの曲順を編集によってCDと同じに並び変えていることがわかる。そしてDVDの収録時間(1時間9分)はコンサートとして短か過ぎ、実際はもっと多くの曲を演っていたようで、そのためコンサートの予告映像にはnote、初芝崇史などCD、DVDに登場しない人物の名前も載っている。さらに曲が始まる前にジャケット写真に曲名を表示した画像が毎回挿入される構成になっているなど、DVD制作にあたり多くの手が加えられている。 それでも田中拡邦(ギター、ママレイドラグ)、YANCY (キーボード)、中条卓(ベース、Couch)、辻凡人(ドラムス、bonobos)といった当時インディーズで活躍中のバンドから選りすぐったメンバーによるSunshine Days Bandのライブ演奏が、スタジオ録音よりも遥かに素晴らしく、CDとは別に本映像を楽しむ価値は十分にあると断言できる。 櫛引彩香が歌う大貫さんの 9.「海と少年」はベースとドラムスがCDとは異なる人による演奏。間奏のエレキギター・ソロ、終盤のエレキピアノ・ソロいずれもスタジオ録音よりも活き活きしている。 他の曲について 1. Pink Shadow [作詞作曲 岩沢幸矢 & 二弓] 河原崎亙/ポメラニアンズ/quinka with a yawn。終盤で河原崎が「Pink Shadow」というコーラスへの参加をオーディエンスに頼むというライブならではの趣向付き。 2. ソバカスのある少女 [作詞 松本隆 作曲 鈴木茂] ママレイドラグの田中拡邦が歌う。その横でアコースティック・ギターを弾いているのはプロデューサーの黒沢秀樹。 3. オリビアを聴きながら [作詞作曲 尾崎亜美] 有里千花。ここでも黒沢秀樹がアコギを弾く。 4. Let's Dance Baby [作詞 吉岡治 作曲 山下達郎] Couchの平泉光司がエレキギターを弾きながら歌い、バックコーラスは有里千花。 5. 天気雨 [作詞作曲 荒井由美] 柳田久美子 6. Magic [作詞 岩沢幸矢 & 二弓、及川恒平 作曲 岩沢幸矢 & 二弓] 黒沢秀樹がアコースティック・ギターを弾きながら歌う。 7. ラストステップ [作詞 吉田美奈子 作曲 山下達郎] イシイモモコのボーカルはスタジオ録音ではイマイチと言ったが、ここでは伸び伸びと歌っていて、その出来栄えは天と地ほどの違い。眞中やすのアコースティック・ギターもいいプレイをしている。 8. ありがとう [作詞作曲 細野晴臣] 黒沢健一のリードボーカルに秀樹がアコースティック・ギターを弾きながらハーモニーをつけている。 9. 海と少年 10. プールサイド [作詞 来生えつこ 作曲 南佳孝] sowan song (本名マエソワヒロユキ) 11. ハリケーン・ドロシー [作詞作曲 細野晴臣] Yancy。この曲のみプログラミングによるパーカッションが入る。スタジオ録音よりも自然な感じの演奏で、Yancyのボーカルもまあ悪くない。 12. スノー・エクスプレス [作曲 鈴木茂] サンシャインデイズ・バンド。アンコールでの演奏で、黒沢秀樹、平泉光司、田中拡邦の3台のエレキギターが各ソロをとって大活躍するスリリングな熱演。曲のエンディングで、バンドメンバーの紹介と本日の出演者の再登場があってフィナーレとなる。 なおDVDにはテレビドラマの出演者達による当該Live告知の映像(15秒、30秒の2通り)が特典として収められている。 若いミュージシャン達による70年代の音楽に対する敬意が気持ち良く、かつシンセサイザーがなかった時代のライブのグルーヴの再現が見事で、血が躍る素晴らしいパフォーマンスが楽しめる。 [2025年7月作成] |
|
| Downtown YMCK & DE DE Mouse (2008) avex trax | |
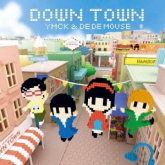  |
4. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子] 4曲目 コトリンゴ: Vocal De De Mouse: Sound Production 写真上: 6曲入りミニアルバム(2008年9月24日発売) 写真下: 7インチ・シングルレコード Downtown / メトロポリタン美術館 by DE DE Mouse (2017年3月29日発売 avex - jet set) 1. Metropolitan Bijutsu-Kan (Metropolitan Museum) [Words & Music: Taeko Onuki] by DE DE Mouse feat. Kotoringo from the album "Downtown" on September 24, 2008 |
| YMCKとDe De Mouseが70〜80年代のシティーポップスをカバーした6曲入りミニアルバム。帯のキャッチフレース 「現代のオルタナティブ・シーンを代表する2つの才能が、シティポップスの名曲達を見事にリアレンジ!ハッピーかつクールなそのセンスとパワーに乾杯!!」や、「"8bitサウンド"と"泣きのインスト"とのバトルが実現」という宣伝文句がふるっている。内容的には各アーティストがそれぞれ3曲の制作を担当していて、両者による共演はない。 1.「メトロポリタン美術館」の音作りをしたDE DE Mouseは、作曲家、編曲家、プロデューサー、キーボード奏者、DJの遠藤大輔によるソロ・プロジェクト。「DE」は彼の氏名のイニシャル、「Mouse」は小柄な身体から付けたものとのこと。現在も元気に活躍している彼の音楽活動開始は2005年頃とのことなので、本作は初期の作品となる。キーボード演奏と打ち込みによるアレンジは大変ユニークで、本曲の数多いカバーの中でも独創性で群を抜いている。特にボーカルのサンプリングによる効果音作りが得意なようだ。ボーカルのコトリンゴ(本名 三吉里絵子 1978- )はシンガー・ソングライター、ピアニスト(ジャズで培ったピアノの腕も相当なもの)で、2006年に坂本龍一のラジオ番組に送ったデモテープが認められて本格的なプロデビューを果たした人。本作へのゲスト参加は彼女の初期の仕事のひとつで、その後映画「この世界の片隅に」2016 の音楽担当で、一般的な名声を不動のものとすることになる。 DE De Mouseの他の曲について。 DE DE Mouse担当の「ルージュの伝言」(作詞作曲 荒井由美)2曲目は荒井由美1989年のシングル(アルバム「Cobalt Hour」収録)。懐かしいね〜。ここでもボーカル・サンプリングで面白い音を作っている。歌っているYUKAは、音楽ユニットmoumoon (ムームーン)のボーカリスト。「Downtown」(作詞作曲 伊藤銀次、山下達郎)6曲目は、ご存知シュガーベイブ1975年のシングル(アルバム「Songs」収録)。私にとってシティポップ原点となった想いでの作品。曲のウキウキ感を見事に表現したアレンジが素晴らしく、一十三十一(ひとみとい)の軽快なボーカルも最高だね。彼女とDe De Mouseとの音楽的親交はこの後も続き、共演作がいくつかある。ちなみに約10年後の2017年に「Downtown/メトロポリタン美術館」で7インチ・シングル・レコードが発売されている。 YMCKの曲について YMCKはMidori (栗原みどり ボーカル、作曲)、Yokemura (除村武志 作詞、作曲、編曲)、Nakamura (中村智之 映像、作曲 アルバム・ジャケットのイラストにおけるドット絵の部分は彼の担当))からなる音楽ユニットで、ファミコンのような8bitの音とボーカロイドのような歌唱が特徴。2003年結成でavexからのメジャーデビューは2008年1月。「8bitサウンド」とは1980年代のコンピューターや家庭用ゲーム機で使われた音源チップを使用した音楽がおおもとで、性能上の厳しい制約のためピコピコした独特の安っぽい音がする。普通では得られないデフォルメされたような音を逆手にとってひとつの音楽スタイルとして発展させたのが「8bit」で、欧米では「Chiptune」と呼ばれている。編曲担当のYokemuraは、その音を作り出すソフトウェアを開発して、安っぽい音を使ってレベルの高い音楽を生み出すという音作りをしている。「Downtown」(作詞作曲 伊藤銀次、山下達郎)1曲目から、昔楽しんだコンピューター・ゲームのピコピコに懐かしさを覚えてしまう。エフェクト処理した栗原のボーカルもさっぱりした感じで悪くない。同曲については同じアルバムにDE DE Mouseのバージョンも入っているので、同じコンピューター音楽といってもこれだけ違うんだなということの見本みたいな感じになっている。「ビューティフル・ネーム」(作詞 奈良橋陽子(英語詩) 伊藤アキラ(日本語詞) 作曲 タケカワユキヒデ)はゴダイゴ1979年のシングル。よく聴くとここでの音使いはかなり凝ったものになっている。「風をあつめて」(作詞 松本隆 作曲 細野晴臣)5曲目ははっぴいえんど1971年の名曲。しっとりしたアコースティックな曲を8bitのコンピューター・サウンドに置き換えるなんて、魔術のようで個人的にお気に入りの1曲。 とても面白いアレンジ、サウンドによる「メトロポリタン美術館」のカバー。ボーカルが当時知名度が低かったコトリンゴというのも魅力。 [2025年6月作成] |
|
| Time & Space SAWA (2008) Cyclops/sambafree | |
 |
3. メトロポリタン美術館 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 中塚武] 3曲目 SAWA: Vocal 中塚武: Drum Programming, Instruments, Producer 2008年12月10日発売 1. Metropolitan Bijutsu-Kan (Metropolitan Museum) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Takeshi Nakatsuka] by SAWA from the album "Time & Space" on December 11, 2008 |
| SAWA (本名・生年 未公表)がデビューした2008年に出した2枚目のミニアルバム(全5曲)。彼女が自身で作曲や打ち込みを始める前の頃の作品で、各曲毎に異なるプロデューサーがついてファンタスティックなハウス・ミュージックを生み出している。 3. 「メトロポリタン美術館」は中塚武プロデュースによるもので、打ち込みによるアレンジが斬新。 2分ちょっとの原曲に対しインストルメンタル部分を加えて4分弱に仕上げている。SAWAのノン・ヴィヴラートのボーカルは可愛い系の声でありながら、芯の強さと滑舌の良さによって、打ち込みによる音数とリズムの刻みが多いバックに負けることなく、しっかり存在感を発揮している。 他の曲について 1.「Stars」(作詞作曲編曲プロデュース Ram Rider) : ミュージックビデオをYouTubeで観ることができ、彼女の若々しい姿が拝める。 2.「Discovery」(作詞 SAWA 作曲編曲プロデュース 福富幸宏): CDデビュー前にプレイステーションのゲームソフト「ニッポンのあそこで」のテーマソングとして採用された曲で、実質的な彼女のデビュー曲といえる。 3.「メトロポリタン美術館」 4.「Are You Ready For Love ?」(作詞作曲 Casy James. Leroy Bell, Tom Bell 編曲プロデュース A Hundred Birds): エルトン・ジョンがフィラデルフィア・ソウルのスタッフとのセッションで録音した1975年作品のカバー。この曲のみ打ち込みでなく、ア・ハンドレッド・バーズというバンドが伴奏を担当している。 5.「Time & Space」(作詞 SAWA 作曲編曲プロデュース 瀧澤賢太郎): かっこいいスペーシーな佳曲。 彼女は2010年より作曲と打ち込みによるサウンド・メイキングを始めて、アルバム・シングル発表、コンサート、DJ活動、楽曲・映像配信、テレビ・ラジオ出演、CM音楽、他アーティストのプロデュースや楽曲提供など幅広い活動を行っている。 数ある「メトロポリタン美術館」のカバーのなかでも、創造性に長けていて屈指の出来栄えだと思う。 [2025年4月作成] |
|
| 2009年 One Fine Day (2005/2/16) UTAU (2010/11/10) の頃 | |
| 1ミリのキセキ 村上ゆき (2009) Yamaha Music Communications | |
 |
1. 私を連れて帰ろう [作詞 大貫妙子 作曲編曲 村上ゆき] 11曲目 村上ゆき: Vocal, Piano 2009年1月21日発売 1. Watashi Wo Tsurete Kaero (Let's Go Back Taking Myself) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr: Yuki Murakami] by Yuki Murakami from the album '1Mili No Kiseki' (The Miracle Of 1mm)on January 21, 2009 |
| 村上ゆき(1971- 福岡県出身)は、武蔵野音楽大学在学中に弾き語り、ジャズピアノの活動を開始して、2004年にCDデビューした。自己名義アルバム、コンピレーション・アルバムへの参加やピアニストとして他アーティストのサポートの他に、端正な歌声を生かしてCMソングを歌うことが多い。 本作は5作目のアルバムで、作詞に本人、大貫さんとコピーライターの一倉宏、作曲が本人、編曲・プロデュースが本人、ショーロ・クラブの沢田穣治や武部聡志といった内容。大貫さんが歌詞を書いた1.「私を連れて帰ろう」は本人のみによる弾き語りになっている。 思い出の場所に自分を連れて帰ろうという歌詞、ゆったりとしたメロディー、ピアノ、歌唱が素晴らしい曲で、大貫さんの提供曲のなかでも上位にランク付けできる。なお本曲は東武特急スペーシアCMソングに採用された。 他の曲について。 タイトル曲 1.「1ミリのキセキ」(作曲作詞 村上ゆき 編曲 武部聡志)1曲目は、これのみ武部聡志編曲で、ストリングスが入った力強いバラード。2.「To Be Continued」(作詞作曲 村上ゆき 編曲 沢田穣治)2曲目はアコーディオンが入った軽快で前向きな曲。3.「恋+薬」は村上のピアノ、オーストラリア生まれで日本在住のアンディ・ベバンのソプラノ・サックスにブラジル音楽の香りが漂う。本曲はライオン バッファリンAのCM曲となった。本アルバムでは、どうしても7.「TANUKI」(作詞作曲 村上ゆき 編曲 沢田穣治)7曲目のジャジーな曲、ブラジリアンな 8.「7人の私」(作詞 一倉宏 作曲編曲 村上ゆき)8曲目や10.「思い出のつかまえかた」(作詞 一倉宏 作曲 村上ゆき 編曲 沢田穣治)10曲目のグルーヴ感に溢れた歌唱・演奏に興味が行ってしまうが、ピアノだけの弾き語りやピアノ、ベース、ストリングなどの伴奏の曲もそれなりに良い出来。ドラムスが入っていないけど、ピアノやベースだけの演奏でもしっかりグルーヴしているところがいいね。そして何よりも素直で透き通った感じの声質がとても魅力的。 大貫さん作詞の1.「私を連れて帰ろう」、是非聴いてみてください。 [2025年6月作成] |
|
| Seaside Town Vairous Artists (2009) Space Shower Music | |
 |
1. Samba De Mar [作詞作曲 大貫妙子 編曲 Traks Boys] 1曲目 SAWA: Vocal Traks Boys: All Instruments, Producer 2009年8月5日発売 1. Samba De Mar [Words & Music: Takeo Onuki, Arr: Traks Boys] 1st track by SAWA from the album "Seaside Town" (Various Artists) on August 5, 2009 |
| 「海辺」をテーマとしたJ-Popの曲をDJ・トラッカーと女性歌手達がカバーしたコンピレーション・アルバム。全9曲異なる人達がプロデュースとアレンジを担当して、打ち込みによるエレクトロ・ニュージックの世界を創りあげている。 冒頭の1.「Samba De Mar (海のサンバ)」は大貫さんのアルバム「Aventure」1981に入っていた曲。清水信之と加藤和彦による編曲は打ち込みによるエレクトリック・サウンド流行のはしりで、発売当時聴いて「これはスゴイ」と感じた記憶がある。当初演奏者が始めたこの手のメイキングは、機材の進歩によりDJなども参入して、彼らが音楽をかけるクラブを発表の場として独自の発展を遂げてゆくことになる。本作のカバーは、きつめのビート、煌めくようなカラフルなサウンド、そしてSAWAのボーカロイドのような歌声は「18年後にこの曲はこうなったんだよね!」と言わんとしているように思える。間奏のシンセソロも最初は独自の内容であるが、締めくくりは原曲と同じメロディーになったり、エンディングのダブルテンポになるあたりもオリジナルに対するオマージュのようだ。SAWAについては2008年の「Time & Space」で説明済。サウンドメイキング、プロデュースのTraks BoysはK404とXTALの二人によるDJ/プロデューサー・ユニット。 なお本曲は2010年のSAWAのアルバム「あいにゆくよ」(初回限定盤)に中塚武によるリミックス版(ボーカルは同じでバックの演奏が異なっている)が収められている。 他の曲について (表示順は 曲名 [作詞 作曲 編曲(プロデュース)] シンガー オリジナル・アーティスト 発表年 収録アルバム) 特記事項 1. Samba De Mar 2. Sweet Sea Side [作詞 藤井フミヤ 作曲 土屋昌已 編曲 Zecky (Discossession)] AYA (Stoned Green Apples) 藤井フミヤ 1995 「R&R (ロックンロール)」 3. Ride On Time [作詞作曲 山下達郎 編曲 Dorian] 和田純子(The Decorations) 山下達郎 1980 「Ride On Time」 4. 渚 [作詞作曲 草野政宗 編曲 peechboy] 和田純子(The Decorations) スピッツ 1996 「インディゴ地平線」 5. 青い珊瑚礁 [作詞 三浦徳子 作曲 小田裕一郎 編曲 BETA PANAMA (MP2)] 和田純子(The Decorations) 松田聖子 1980 「Squall」 6. 渚・モデラート [作詞 リリカ新里 作曲 高中正義 編曲 ラスベガス(Harley & Quin)] カコイミク 高中正義 1985 「Traumatic 極東探偵団」 7. 波よせて [作詞 武藤さつき、東里起 作曲 東里起 編曲 CHERRYBOY FUNCTION] 和田純子(The Decorations) Small Circle Of Friends 1997 「Platform 5」 クラムボン 2006年のカバーも有名 8. 忘れられたBig Wave [作詞作曲 桑田佳祐 編曲 LUVRAW/Kashif] LUVRAW & BTB (Talk Box) サザン・オール・スターズ 1990 「Southern All Stars」ビーチボーイズそのものの原曲をトーキングボックスで歌う珍品 9. サザエさん一家 [作詞 林春生 作曲 筒美京平] レモン 宇野ゆう子 1969 9.「サザエさん一家」のみ海と関係ない歌なんだけど、「アンコール」ということで入れたのかな?多くの曲でボーカルを担当している和田純子(夫の鈴木俊治とのユニット、Be The Voice、The Decorationsでマイペースの活動を続けている人)がいいね。 1981年の「Samba De Mar」を2009年のサウンドでアレンジ。原曲に対する敬意が込められたカバー。 [2025年5月作成] |
|
| Letters 一十三十一 (2009) Garuru | |
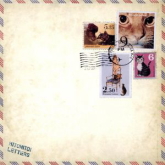 |
7. 蜃気楼の街 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 曽我部恵一] 7曲目 10. 春の手紙 [作詞作曲 大貫妙子 編曲 曽我部恵一] 10曲目 一十三十一: Vocal, Producer 横山裕章: Piano, Synthesizer 曽我部恵一: Acoustic Guitar, Chorus, Producer 長久保寛之: Electric Guitar, Clasical Guitar 木暮晋也: Acoustic Guitar, Electric Guitar 加藤雄一郎: Sax 伊賀航: Bass オータコージ: Drums, Percussion 注: 曲毎のパーソナルがないため、録音に参加したミュージシャン全員を列記しています 編曲についてのクレジットはありませんが「Sound Produce: Keiichi Sogabe」とありますので、 編曲者は彼としました。 2009年9月23日発売 7. Shinkiro No Machi (Mirage City) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Keiichi Sokabe] 7th Track 10. Haru No Tegami (The Letter Of Spring) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Keiichi Sokabe] 10th Track by Hitomitoi from the album "Letters" on September 23, 2009 |
| FM Nack5は埼玉県を対象とする独立系FMラジオ放送局。一十三十一(ひとみとい 1978- アルバム「Pure Voice〜J-Cover」2008で紹介済)はそこで番組「Letters」のパーソナリティーを務め、ゲストを招いてトークやライブ演奏を行っていた。その番組のなかで「手紙」にまつわる曲について、リスナーから届いたリクエストをもとに本作「Letters」が企画された。制作にあたり本人がプロデューサーとなり、サニーデイ・サービスの曽我部恵一が共同プロデューサーおよびサウンド・プロデュースを担当した。以下本人と曽我部のコメント。 郵便受けの前で待つ手紙 ひと夏で終わってしまった文通 引き出しの中にしまったままの手紙 恥ずかしくて破いてしまった手紙 昔好きだった人のくせのある手紙 何度も何度も書き直した手紙 ドアに挟んであった手紙 やっと渡せた最初の手紙、最後の手紙 持ち歩いては読み返した手紙 遠い国から届く絵葉書.... 誰にだってひとつは思い当たるでしょ? たった一行だって手紙はハートがこもってる。 そんな胸キュン☆アルバムです。 (一十三) アコースティックなスタイルで こんな名曲の数々をカバーさせてもらうなんて..... ゾクゾクします。 こんなにメロウでいいんですか? (曽我部) どの曲もオリジナルを十分に尊重したうえで、打ち込み、シンセサイザーの音があまり目立たないバンド・サウンドによる演奏と一十三十一の歌唱により付加価値をつけている。7.「蜃気楼の街」、10.「春の手紙」は本アルバムの中では比較的原曲に近い素直なアレンジで、彼女の大貫さんに対する尊敬の念が滲み出ている。大貫さんのクールな雰囲気とは異なる飾り気のない誠実な感じの声がいいね。 他の曲について(編曲者 曽我部恵一) 1. 返事はいらない[作詞作曲 荒井由美] 荒井由美1972年のデビューシング。翌年発表の初アルバム「ひこうき雲」には別録音が収められた。 シングルは当時全然売れなかったので、中古市場で超高値を呼んでいる。 2. 風立ちぬ [作詞 松本隆 作曲 大瀧詠一] 松本聖子 1981 シングル、同一タイトルのアルバム 3. Love Letter [作詞作曲 甲本ヒロト] The Blue Hearts 1989 シングル アルバム「Train-Train」 1988 原曲とは異なるアコースティックでメロウなアレンジがいい感じ。 4. 青春はいちどだけ(Colour Field) [作詞作曲 Double Knockout Corporation] The Flipper's Guitar 1990 アルバム「Camera Talk」 作詞作曲は小山田圭吾と小沢健二で、ふたりのイニシャルがともに「KO」のためそういうクレジットになった。かなりポップな感じだった原曲をさわやかなアコースティック・サウンドの曲にアレンジした。 5. 左手で書いたラブレター[作詞作曲 浜田省吾] Fairlife 2004 アルバム「Have A Nice Life」 Fairlifeは浜田省吾、水谷公生、春嵐の3人によるユニット。ヴァースのメロディーはポール・アンカの「Puppy Love」1960そのもので、著作権上の問題はなかったのかな? 6. Letters [作詞作曲 宇多田ヒカル] 宇多田ヒカル 2002 シングル アルバム「Deep River」 オリジナルはラテン調だったが、ここでのアレンジと歌唱のほうが曲の良さをよりうまく伝えているように思われる。 7. 蜃気楼の街 8. Storm [作詞 吉田美奈子 作曲 山下達郎] 山下達郎 1979 アルバム「Moonglow」 ソウルっぽい曲で、村上秀一(ドラムス)、岡沢章(ベース)、松木恒秀(ギター)、佐藤宏(キーボード)という最強メンバーによる原曲のグルーヴに負けない演奏。 9. Love Letter [作詞作曲 尾崎亜美] 酒井法子 1989 シングル アルバム「Blue Wind/Noriko Part IV」 本人が出演したライオン汗止めスプレーのCMに使用された。アイドル歌謡の原曲を爽やかなポップソングに仕上げている。 今やEメールやLineに押されて廃れつつある手紙にまつわる曲を集めたコンセプト・アルバムで、大貫さんの作品が2曲も選ばれている。どちらも必聴! [2025年6月作成] |
|
| Eyja 原田知世 (2009) EMI Music Japan | |
 |
1. 夢のゆりかご [作詞作曲 大貫妙子 編曲 伊藤ゴロー] 6曲目 原田知世: Vocal 伊藤ゴロー: Programming Daniel Bjarnason: Piano 吉野友加: Irish Harp Hildur Ingveldardottir Gudnadottir: Cello Steinunn Eva Sveinsdottir: Voice (Sampling) 2009年10月21日発売 1. Yume No Yurikago (Cradle Of Dreams) [Words & Music: Takeo Onuki, Arr: Goro Ito] 6th track by Tomoyo Harada from the album "Eyja" on October 21, 2009 |
| 原田知世18枚目のアルバムで、前作「Music & Me」2007と同じく伊藤ゴローのプロデュース。アイスランド語で「島」という意味のタイトルの「Eyja」(エイヤ)が示すように、本作はアイスランドと日本で録音された。同国は自然に恵まれた人口30万の島国で、他国からの文化的影響を受けにくい環境から独自の音楽が育ち、ビョークなどのアーティストを輩出しているところ。本作は伊藤ゴロー、梅林太郎(近年青葉市子と行動を共にしている人)と、ムームなどアイスランドのミュージシャン達の共同作業により、厳粛で透明感あふれる独自の音楽を創り出している。アルバムのアート・ディレクションとデザインは当時の夫エドツワキによるもの。 大貫さんが作詞作曲した1.「夢のゆりかご」の歌詞は短いけど奥行がある内容で、ひんやりとした感覚のメロディーも本作の音楽にぴったりだ。この曲を単独で聴いた時の印象が、アルバム全体の一曲としての場合とかなり異なってくるのが面白い。ピアノとチェロがアイスランドの人で、特にチェロを弾くヒドゥル・グドナドッティルはムームのメンバーであり、それとは別に映画音楽の世界などで活躍している人。吉野友加は伊藤ゴローと親交があるハープ奏者で、アイリッシュ・ハープの響きがとても美しい。なお効果音的な子供の声が聞こえる。 他の曲について 全11曲中、英語の歌詞は4曲。アイスランドのグループ、ムームは2曲に関与。「Us」 [作詞 原田知世、天辰京子, 作曲プログラミング mum] 3曲目はムームの二人(オリヴァル・スマラソンとグンネル・ティーネス)の二人が原田と一緒に歌っている。「予感」 [作詞 原田知世、天辰京子, 作曲編曲 mum] 7曲目は、アコースティックとエレクトリックが溶け合った独特のサウンド。「ハーモニー」 [作詞原田知世 作曲 梅林太朗] 1曲目は梅林主導、「Giving Tree」 [作詞 いしわたり淳治 作曲編曲 伊藤ゴロー] 2曲目、「Voice」 [作詞 原田知世、天辰京子 作曲編曲 伊藤ゴロー] 8曲目は伊藤主導の曲。「Fine」 [作詞 原田知世 作曲 伊藤ゴロー] 4曲目、「黒い犬」 [作詞 Tarkov 作曲編曲 伊藤ゴロー、梅林太郎] 5曲目、「ソバカス」 [作詞 原田知世 作曲 細野晴臣] 9曲目、 「青い鳥」 [作詞 原田知世 作曲 伊藤ゴロー] 11曲目は二人が関与し、4曲目と11曲目についてはアイスランドのミュージシャン達が加わっている。「ソバカス」には細野がベースで参加。そして「Marmalade」 [作詞 原田知世、天辰京子 作曲編曲 Valgeir Sigudsson] 10曲目はビョークのプロデュースを手掛けたヴァルゲイル・シグルドソンが作曲編曲を担当している。そして原田のボーカルは、常に増して呟き、囁き声に徹している。 ひとつのカラーに統一されたトータル・アルバム。 [2025年7月作成] |
|
| Luminous Halo Port Of Notes (2009) Rhythm Zone (Avex) | |
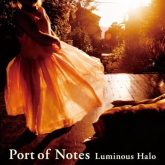 |
1. Fly High [作詞 大貫妙子 作曲 畠山美由紀、小島大介 編曲 Jesse Harris/The Ferdinandos, Port Of Notes] 3曲目 畠山美由紀: Vocal 小島大介: Electric Guitar, Back Vocal Jesse Harris: Acoustic Guitar Rob Burger: Organ Robert Jost: Bass Ron Rieser: Drums Robert Do Pietro: Percussion 2009年11月4日発売 1. Fly High [Words: Taeko Onuki, Music: Miyuki Hatakeyama, Daisuke Kojima, Arr: Jesse Harris/The Ferdinandos, Port Of Notes] 3rd Track by Port Of Notes from the album "Luminous Halo" on November 4, 2009 |
| 2002年のノラ・ジョーンズ「Don't Know Why」(全米1位)は衝撃的だった。ジャズの香りがするフォーキー、ブルージーなサウンドがとても新鮮だったからだ。この曲はグラミー賞の「Best
Female Pop Vocal Performance」を受賞し、作者で伴奏者のジェシー・ハリスは一躍有名になった。彼はシンガー・ソングライターとしてアルバムを発表しながら、多くのアーティストへの曲提供、伴奏、プロデュースを行っているが、その中には日本のアーティストも複数含まれている。畠山美由紀はその一人として、2007年のソロアルバム「Summer
Clouds, Summer Rain」を彼の伴奏・プロデュースで発表し、その後小島大介とのユニットPort Of Notesの本アルバム制作を再び彼の手に委ねた。 タイトル「Luminous Halo」は直訳では「光る光輪」となり、本作の副題「燦然と輝く光彩」を意味している。ニューヨークで6日間という強硬スケジュールでの録音だったそうだが、じっくり作り込まれたような感じがあり、事前の準備に十分な時間をかけたこととミュージシャンのレベルの高さのためだろう。帯のキャッチフレーズ「ナチュラルで芳醇な、日本人ならではのサウダージ感に包み込まれるマスターピース」の通り、「サウダージ=憧憬、思慕、切なさ」を内に秘めたブラジル音楽の雰囲気が漂っている。 大貫さんが作詞した 1.「Fly High」は、飾り気のないアレンジ・演奏をバックに畠山が歌う、聴いていて本当に気持ちが良い曲。ギターのコードストロークとドラムス、パーカッションがメインで、背景に流れるオルガンが効果的。「CDjournal」2009年11月10日インターネット掲載の記事に、本作に係る畠山と小島のライナー・ノーツが掲載されていて、そこでは二人が各曲につき曲作りの背景や録音の様子を詳細に語っており、本曲については以下のとおり(以下抜粋です。全文を読みたい方は、上記の元情報をご参照ください)。 畠山: 大貫さんには曲だけお渡しして、フリーテーマで書いてもらいました。意外性のある書き出しからはじまって、徐々に大貫さんワールドに突入してゆく感じが、やっぱり凄いと思いました。大貫さんのポジティブな歌詞にすごく勇気をもらった気がします 小島: 美由紀ちゃんにはない、大貫さん独自の言葉選びが興味深かったですね。"まだまだ良い曲が作れるんじゃない?"みたいな、僕らに対する大貫さんからの期待が込められいるような気がして。 その他の曲について(編曲 Jesse Harris/The Ferdinandosm Port Of Notes) 突出した曲、ヒットを当て込んだ曲はなく、全体を通しで聴くことで良さを味わうことができるアルバムだと思う。大半の曲について、作詞作曲は畠山と小島の共作で、小池龍平が1曲 「Ancient Breeze」9曲目で共作者に加わっている。そして一部の曲は各人の単独作品。外部に作詞を頼んだ曲は 「私の街」(作詞 曽我部恵一 作曲 畠山美由紀、小島大介)6曲目。唯一の英語曲 「If You Are Coming In The Fall」8曲目は、アメリカの詩人エミリー・ディキンソン(1830-1886)の詩に畠山が曲をつけている。これらの曲についても上記の通り畠山と小島によるライナーノーツがあり、とても面白い内容なので是非参照してほしい。 Port Of Notesのその後について、畠山、小島は本作以降は個別に活動することになるが、2021年に再会してセルフカバー・アルバム「TWO」を発表している。 大貫さんが書いたポジティブ系の曲として、「Fly High」は一聴に値する作品と思う。 [2025年8月作成] |
|
| ナチュラル・ウーマン 流線形と比屋定篤子 (2009) Happiness | |
 |
3. なにもいらない [作詞作曲 大貫妙子 編曲 クニモンド瀧口] 3曲目 比屋定篤子: Vocal 後藤雅宏: Electric Piano, Hammond Organ 山崎陽子(Laranja) : Electric Piano, Keyboards クニモンド瀧口: Keyboards, Producer 山之内俊夫: Electric Guitar 梅原新: Electric Guitar Solo 小山晃一: Bass 北山ゆう子: Drums 平野栄二、的場響子: Percussion 2009年11月4日発売 注: 曲毎のパーソナルがないので、参加ミュージシャン全員を記載しています。 3. Nani Mo Iranai (Don't Need Anything) [Words & Music: Taeko Onuki, Arr: Kunimond Takiguchi] 3rd track by Ryusenkei To Atsuko Hiyajo from the album "Natural Woman" dated on November 4, 2009 |
クニモンド滝口は、広報、アパレル、レコード屋、ライブハウスの仕事を経て、2003年よりグループ「流線形」を結成して活動を開始。アルバム「シティミュージック」で 1980年代のJ-Popのグルーヴを再現して好評価を得た。本作は3枚目の作品で比屋定篤子とのコラボ作品。2009年10月(本作発売前)のインタビューによると、彼は比屋定の大貫さんカバー曲「街」1997を聴いて好きになり、その後両者が同じレーベル所属になって、イベントで一緒になったことがきっかけで本作での共演が実現したとのこと。この時点の流線形は結成時のメンバーが抜けて彼一人のユニットになっていたため、腕利きのセッション・ミュージシャンを集めて制作された。ベーシック・トラック録音からアルバム発売まで1年かけてじっくり作り込んだとのこと。比屋定篤子については1997年作品「君の住む街にとんで行きたい」(大貫さんの「街」収録)の記事を参照ください。 大貫さんの3.「なにもいらない」(「Sunshower」1977収録) はクニモンドのリクエストによるもので、坂本龍一(キーボード、アレンジ)、松木恒秀(リズムギター)、渡辺香津美(ギターソロ)、後藤次利(ベース)、クリストファー・パーカー(ドラムス)、斉藤ノブ(パーカッション)による超名演を自分がやったらどうなるか、と挑戦したそうだ。他の曲と異なり、原曲のアレンジ、グルーヴ感はあまり異なっておらず、スティーリー・ダンを超えようとした野心的なオリジナルに対するオマージュのように聞こえる。それにしてもこの曲のカバーに敢えて挑戦したアレンジャ−、シンガーとプレイヤー達は本当に怖いもの知らずだね。原曲が凄すぎて比較するのは酷なんだけど、歌・演奏ともに彼らの持ち味を出していて、それなりに成功していると思う。 その他の曲について (全曲につき 編曲 クニモンド滝口) 1. ムーンライト・イヴニング [作詞作曲 クニモンド滝口] 1970年代後半の Dr. Buzzard's Original Savannah Bandのノスタルジックなラテン・フュージョンサウンドは、1980年代にサディスティックスの加藤和彦や今井裕が彼らなりに消化して展開したが、本曲はそれらをもとにしたもの。ブラスやスティール・パンを入れた賑やかなサウンド。 2. あたらしい日々 [作詞作曲 クニモンド滝口] さんさんと降り注ぐ日差しのような明るい曲で、比屋定のボーカルがよく合っている。 3. なにもいらない 4. まわれまわれ [作詞 比屋定篤子 作曲 小林治郎] 1999年の比屋定のアルバム「ささやかれた夢の話」に収録された彼女の代表曲のセルフカバー。ここでのアレンジ、演奏、グルーヴはもろToto (David Paich)だね。ヤカマミヒトミのサックスソロがいい。 5. オレンジ色の午後に [作詞 比屋定篤子 作曲 小林治郎] 比屋定の1999年のシングルのセルフカバー。ここではシャッフルのリズムによるきりっとしたサウンドで、マイケル・フランクスを意識したとのこと。 6.サマー・イン・サマー 〜想い出は、素肌に焼いて〜 [作詞 山川啓介 作曲 八神純子] 八神純子 1982年シングル(JAL沖縄キャンペーンソング)のカバー。歌謡曲風の原曲に対し、ここではシティポップのアレンジ。八代と比屋定の声質の違いを聴き比べると面白い。サビのパートで、クニモンドのハーモニー・ボーカルが聴ける。 7. メビウス [作詞 比屋定篤子 作曲 小林治郎] 1999年の比屋定のアルバム「ささやかれた夢の話」収録曲のセルフカバー。ここでのアレンジはデオダードそのもので、彼の「Skyscraper」(1972「Deodato 2」収録)を元にしたとのこと。 8. ナチュラル・ウーマン[作詞作曲 クニモンド滝口] 女性の成長を賛美する前向きなシティ・ポップ。 オリジナル3曲、比屋定のセルフカバー3曲、他アーティストのカバー2曲という構成で、好きなアーティストのスタイルを敬意を込めて取り入れながら、単なる模倣に終わらず、オリジナリティをしっかり出すところにクニモンド滝口の持ち味が発揮されている。比屋定のブラジル音楽風ノンヴィブラート・ヴォイスもぴったりはまっている。 世紀の名演「なにもいらない」に挑んだ大胆不敵なカバー。 [2025年5月作成] |
|