| 1975年 Sugar Babe 「Songs」 (1975/4/25発売)の頃 |
| 家 筒井康隆 山下洋輔 (1976) Frasco (Nippon Phonogram) |
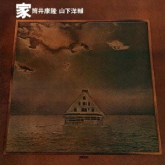
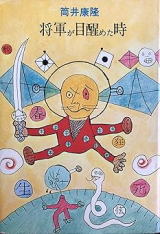
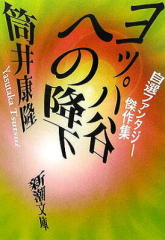
|
1. 海 [語り 筒井康隆 音楽編曲 山下洋輔] A面1曲目
筒井康隆: Narration
山下洋輔: Piano, Electric Piano, Synthesizer, Organ, Celesta, Harpsichord, Glockenspiel, Vibraphone, Marimba, Bells, Gong, Violin, Chorus
タモリ: Narration
大貫妙子: Vocal
鈴木利恵、中沢まゆみ: Chorus
柏原卓: Synthesizer, Organ, Electric Piano, Percussion, Chorus
伊勢昌之: Acoustic Guitar, Electric Guitar, Guitar Synthesizer, Whistle
村松邦夫: Electric Guitar
寺尾次郎: Electric Bass, Percussion, Chorus
望月英明: Bass
北沢康隆、黒川博: Percussion, Chorus
生田朗: Gong Stand, Percussion, Chorus
宮坂剛: Effects
坂田明: Alto Sax
高橋知己: Tenor Sax
近藤俊則(近藤等則): Trumpet
向井滋春: Trombone
国吉征之(国義静治): Flute
山田恵子: Harp
玉野嘉久、森岡美穂子、田中英一、藤米田健生、藤原祥隆、中山誠: 1st Violin
渡辺恭孝、宮内洸、脇精一、大町欽一: 2nd Violin
遠山克彦、横井俊雄、北爪現世、中村由記子: Viola
阿部雅士、井戸聡: Cello
注:曲毎のパーソネルがないため、本作に参加した全員を記載しました。
写真上: 「家」 LP 1976
写真中: 「将軍が目醒めた時」新潮社刊 1972
写真下: 「ヨッパ谷への降下」新潮社文庫 2006
録音: 1975年7月28日~1976年1月24日
1. Umi (Ocean) [Talk: Yasutaka Tsutsui, Music & Arr: Yosuke Yamashita]
A-1 by Yasutaka Tsutsui and Yosuke Yamashita from the album "Ie (House)"
1976
|
小説家の筒井康隆(1934- ) とジャズピアニストの山下洋輔(1942- )のコラボにより、筒井の短編小説「家」を音楽主体でレコード化した作品で、当時シュガーベイブの大貫さん、村松邦夫、寺尾次郎が参加。大貫さんにとっては(コーラスを除く)ボーカルとして他人の作品に参加した初めての作品となった。
[筒井康隆著 短編小説 「家」について]
初出が「将軍が目醒めた時」新潮社刊 1972で、ナンセンスなSF短編を書いていた初期から実験的・前衛的な作品を書くようになった時期にあたる。当時は一般的な人気が出始めた頃で、私も文庫本をたくさん買って読んだ記憶がある。本作は海の中に建つ合掌造りのような屋根を持った巨大な木造の家が舞台で、4階建ての室内は襖で仕切られて多くの家族が住んでいるという設定。食料や木材は住民の男達が乗る伝馬船によって運ばれてくる。話は隆夫という子供の視点で進行する。彼は同じ階に住んでいる茜という少女を気にしているが話したことはない。船を沈め住民を海に落とす暴風雨の日、隆夫は父親に船は何処から食料・木材を取ってくるのかという質問をするが、子供に話せない恐ろしい秘密があるようで、父親から家を追い出され布団をしまう部屋で寝る。そこに嵐で溢れた海水が入ってきて、隆夫は布団に寝たまま、家の周囲に巡らされた縁側を漂流する。
という不思議なストーリーで、家の構造と人々の生活の描写が執拗で、これでもかこれでもかという言葉の洪水に見舞われ、そのパワーに圧倒される。時代設定は不明であるが、ケビン・コスナー主演の映画「Waterworld」1995
(注: 映画は小説から20年以上後に作られたもの)を想起させ未来世界のように感じられるものの、距離の表現に古風な「間」、「尺」を使うことで、時代感覚と切り離されたような感もある。
「家」はLPのライナーノーツに全編がびっしり記載されているが、本としては「ヨッパ谷への降下」新潮社文庫 2006で入手可能。
[筒井康隆・山下洋輔 「家」LPレコードについて]
帯のキャッチフレーズは「日本ジャズの鬼才山下洋輔が彼の敬愛するSF作家筒井康隆の原作を得て、半年余を費やして完成させた文章と音楽の画期的競合!」。筒井と山下はお互いにファンで深い交友関係をもち、作品上多くのコラボがある。本作はそのひとつで、短編小説の抜粋を筒井が朗読し、山下が小説から得られたイメージで自由に音楽を付けている。それは小説の設定や筋に限定されない自由な発想に基づくもので、原作に従属した音楽とは根本的に異なるものだ。当時の山下はフリー・ジャズを演奏しながらエッセイを書いたり、学生運動で封鎖されたバリケード内で演奏するなどの型破りなパフォーマンスを繰り広げていて、本作でも型に嵌らない自由な創造力をいかんなく発揮している。使用楽器面ではシンセサイザーが出始めたばかりの頃で、今の耳で聴くと技術的に未熟な音もあるが、当時の環境の中でこれだけのサウンドを創り出したのは驚異的だ。
[大貫さんの参加について]
当時彼女はシュガーベイブのアルバム「Songs」が出てしばらく経った頃で、一部から熱狂的な支持を得られたが、一般的な知名度はまだ低かった時期。そんな頃に何故同僚の村松、寺尾と一緒に本作に参加したのか、一見謎に思えるが、シュガーベイブのWikiにある詳細極まりない年表を見ると、1974年4月に風都市を辞めた長門芳郎が友人達と設立した「テイク・ワン」という事務所の専属アーティストが山下洋輔トリオとシュガーベイブだったことがルーツであるとわかった。ちなみに前述のWikiに3人が1975年10月27日に本作の録音に参加という記述がある。なお大貫さんは最初の曲「海」に参加している。
[大貫さんが参加した1.「海」について]
14分37秒の曲はシンセサイザーの独奏から始まり「海」と「水」についての筒井の朗読が入る。ピアノによるリフが始まり、筒井の小説の描写のように執拗に続く。それにゆっくりした音で色を置いてゆくエレキギターは村松が弾いているようだ。向井滋春のトロンボーンが聞こえ、リフは他のキーボードが加わって厚みを増し、エレキピアノが和音を散りばめる。
ゴングが鳴り曲調がぱっと明るくなった10分40秒で大貫さんのボーカルが登場。彼女はコーラス付きで「じゃあぱ ねえず じゃあぱ ねえず さいぷ りいす さいぷ りいす」という歌詞を2回歌い、3回目は男性コーラスも加わり彼女の出番は約1分で終わる。この意味不明の言葉は、小説で伝馬船から食料や木材を積み下ろす際に歌われていて、彼らもその意味を知らないと書かれている。本来はもっと賑やかな歌いのように思えるが、ここでは大貫さんのクールな声がむしろシュールな雰囲気を醸し出している。
その直後にフルートによる前衛的な素早いパッセージが入る。それを吹いている国義静治は、後に国吉征之の名前で音楽プロデューサーになる人だ。バックで鳴り続けているリフにエレキベースがユニゾンで加わるが、これは寺尾が弾いているのだろう。終盤に山下のピアノがフリージャズ・スタイルで切り込んできてフルートと絡み合う。
[その他の曲について]
シンセのリフ音(当初とは別のパターン)の中切れ目なく 2.「月」に続き、筒井が隆夫と茜の出会いを短く語る。ここではウッドベースとギターが鳴っている。筒井による変わった形の「月」の話。ストリングスをバックに坂田明によるフリーなサックスソロ。不思議な月が夜空に浮かぶ様が現代音楽的な不協和音の中で表わされている。A面は筒井の「その夜暴風雨がやってきた」という語りで終わり。
B面 3.「嵐」は風の効果音を背景にギターがジャズ・スタンダードの「Stormy Weather」を奏でる。ラジオによる天気予報官のアナウンスと男性群によるお経のような変なコーラスが短く入ったあと、天気予報官がデフォルメして意味不明の言葉を話し出し、なんちゃって中国語も飛び出す。それで話の主がタモリであることがわかる。山下が福岡で彼を発見し、あまりに面白く才能豊かなので、東京に呼び寄せて芸能界デビューさせたという逸話があり、本作はタモリにとって、媒体におけるデビュー作となった(テレビには1975年8月に初出演済。当時はビデオやCD、DVDがない時代で、カセットテープとレコードが一般販売可能な媒体だった)。
吹きすさぶ嵐の効果音を背景にギターと口笛によるボサノヴァが入る。ギターを弾いているのは日本おけるボサノヴァ・ギターの草分けだった伊勢昌之。この後タモリのハナモゲラが再登場し筒井による隆夫の漂流の話の後、何故か赤ちゃんがはしゃぐ声。シンセによるアンニュイな感じのメロディーが流れ、ストリングスとハープ、カモメの鳴き声が加わり、嵐が過ぎ去った様を暗示。
最後の曲 4.「家」は筒井の「次に目覚めた時、あたりは薄明かりの中にあった」という言葉から始まり、複数の男女による会話が続く。次に出てくるのは1.「海」のリフをテープの逆回転録音で再現したもの。ピアノによるリフにガットギターが音を入れ、筒井は隆夫の漂流の様を語り、その合間にブラスセクションが挿入され、最後はリフがテープ回転がゆっくりと停止する感じで止まり、「南の縁側の西端にたどりつくには一週間かかった」という小説の最後の言葉を筒井が語って終わる。
[むすび]
天気予報官とハナモゲラ、ジャズ・スタンダードやボサノヴァ、赤ちゃんの泣き声など、小説の筋とは全く関係ない声や音が出てきて、もうやりたい放題であるが、約40分にわたり、尽きることのないアイデアと創造力で聴く者の感受性を揺さぶり続ける。何度聞いても都度新しい発見がある傑作!ちなみに本作は2008年にCD化されている。
大貫さんのボーカルの使われ方が尋常じゃないけど、大切なシーンでシュールな効果を出すことに成功している。
[2024年9月作成]
|
| 1977年 「Sunshower」 (1977/7/25発売)の頃 |
| 夜の旅人 松任谷正隆 (1977) Panam (Crown) |

|
1. 荒涼 [作詞: 荒井由美、作曲: 松任谷正隆、荒井由美] A面2曲目
松任谷正隆 : Vocal, Keyboards, Producer
大貫妙子 : Vocal
鈴木茂 : Electric Guitar
Ted M. Gibson, 瀬戸龍介 : Acoustic Guitar
林立夫 : Drums
斉藤ノブ : Percussion
1977年11月25日発売
1. Koryo (Desolation) [Words: Yumi Arai, Music: Masataka Matsutoya, Yumi
Arai] A-2
From LP Album "Yoru No Tabibito" (Night Traveler) by Masataka
Matsutoya (November 25, 1977)
|
松任谷正隆の唯一のソロアルバム。発表された1977年は、奥様荒井由美のアルバム発表はなく、「14番目の月」1976/11/20と「孔雀」1978/3/5の狭間の時期にあたる。当時レコード会社の契約でアルバムを作ることになっており、嫌々制作したという。自分が表に出ると作品を客観的にみることが出来なくなるのが耐えられないという理由で、発表後もずっと好きになれなかったとのこと。当時私は発売直後に購入したが、音作りの素晴らしさとボーカルの下手さのアンバランスに違和感を感じた記憶がある。その後聴かなくなって、今回数十年ぶりに全編を聴いてみたが、意外にも結構楽しむことができた。当時は「上手い下手」の定義が画一的で、現在のような多様性の尊重という価値観がなかった時代だったと思う。長い年月の中でいろんな人の様々なスタイルの歌声を聞いて、耳の度量が大きくなったこともあるかな。なお制作にあたり奥さんの松任谷由美が作詞とアルバム・ジャケットのイラスト(彼女は多摩美術大学卒業)で手伝っている。
大貫さんがゲストで参加した1.「荒涼」は、ハイファイセットのアルバム「ファッショナブル・ラヴァー」1976に収められていた録音がオリジナル。作曲者につき、インターネットでは「松任谷正隆」または「荒井由美」とする資料が多いが、正しくは両者の共作。北海道のオホーツク海に面する北の果ての地の景色を描いた歌詞に「鉄道沿いの
海岸線に...... 古びた列車の 窓の隙間で」という部分があるが、その後1980年代に廃線となり、今はない風景。私は稚内から知床までレンタカーで一人旅をしたことがあるが、広大な海・地平とどこまでも続く道は、日本の他の地域にない景色だった。ただし寒いのは苦手なので、夏に行きましたが......。この曲の録音にあたり、北をイメージする歌手として大貫さんを採用したとのこと。両者は、荒井由美の「Misslim」1974、「Cobalt
Hour」1975、「14番目の月」1976へのコーラス参加などの仕事上の付き合いがあった関係。大貫さんはいつに増して硬質な感じで歌っており、一方松任谷の平板な感じのボーカルも、ここでは曲想に似合っていてなかなかの出来。ハイファイセットの山本潤子の暖かみのある歌声よりもいいかもしれない。またハイファイでのアレンジが松任谷のエレキピアノ一本だったのに対し、ここではバンドによる伴奏となっている。冬の情景を見事に描き出したアコースティック・ギターのアルペジオは、その爪弾きのタッチから
Ted M. Gibson (当時吉川忠英が使っていた変名)で間違いないだろう。それとは別に左チャンネルから時折聞こえる生ギターの音は、1972年にEastというグループで米国でアルバムを発表した瀬戸龍介か、吉川忠英のオーバーダビングのいずれか(本アルバムは曲毎のパーソネルの表示がないため)。時折聞こえる鈴木茂のスライドギターのキューンという音が、広大な空間を想起させて効果的だ。
この録音は、後の2007年に大貫さんのアルバム「Sunshower」1977の再発の際にボーナス・トラックとして収録された。また同時期の二人のコラボとして彼女のシングル「明日から、ドラマ」1977/3/5発売
のプロデュース、アレンジ担当があげられる。
他の曲についても簡単に説明しよう。
「沈黙の時間」A面1曲目は、スタジオ・ミュージシャンである自分自身を描いた曲。「煙草を消して」A面3曲目は、ギター抜きのサンタナといった感じのラテンロック。「霧の降りた朝」A面4曲目はフォークっぽく、「もう二度と」B面1曲目、「気づいたときは遅いもの」B面2曲目は当時の荒井由美サウンドに近い。「乗り遅れた男」B面3曲目は本作のなかで異色の存在で、1930~1940年代のスウィンギーなアメリカン・スタンダード風の曲。不貞腐れた歌詞と歌いっぷりが面白い。そして極めつけの「Hong
Kong Night Sight」B面4曲目は、香港への憧れに満ちた名曲。イギリス統治領だった当時の香港は、私にとって「The World of
Suzie Wong (スージー・ウォンの世界)」1960、「Love Is A Many Splendored Thing (慕情)」 1955
(いずれもウィリアム・ホールデン主演)、および「Les Tribulations d'un Chinois en Chine (カトマンズの男)」1965
(ジャン・ポール・ベルモンド主演)のイメージ、すなわち西洋と東洋がごっちゃになった少々妖しげな世界だった。細野晴臣がやっていた音楽と、歌詞に出てくる映画
「スージーウォンの世界」に感化されて作ったというこの曲は、そのエキゾチックな雰囲気を見事に伝えている。私が滞在した返還前の1990年代には、その香りがまだ残っていたが、返還後20年以上過ぎた今すっかり失われてしまったのが残念。ちなみにここでの細野のベース・ランは最高!本当に凄いよ!そしてこの曲は、松任谷由美がミニアルバム「水の中のアジアへ」1981でセルフカバーしていて、こちらも必聴。
制作当時彼らは考えもしなかったと思うが、「荒涼」や「Hong Kong Night Sight」を40年以上経った今聴くと、失われた当時のイメージが懐かしく脳裏に蘇ってくる。そういう意味で、制作当時と異なる意味合いで味わい深い作品に醸成したと思う。
[2024年2月作成]
|
| 1978年 「Mignonne」 (1978/9/21発売)の頃 |
| South Of The Border 南佳孝 (1978) CBS Sony |
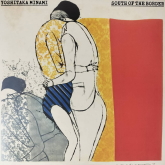
 |
1. 日付変更線 [作詞 松任谷由美 作曲 南佳孝 編曲 坂本龍一] A面4曲目
南佳孝: Vocal
大貫妙子: Duet Vocal, Back Chorus
坂本龍一: Fender Rhodes & Korg PS-3100
鈴木茂: Electric & Acoustic Guitars
細野晴臣: Bass
林立夫: Drums
浜口茂外也: Percussion
斉藤ノブ: Percussion
吉川祐二: Percussion
坂本龍一、南佳孝: Sound Producer
写真上: アルバム・ジャケット 1978年9月21日発売
写真下: シングル盤「日付変更線」ジャケット 1978年7月21日発売
1. Hiduke Henkosen (Date Line) [Words: Yumi Matsutoya, Music: Yoshitaka
Minami, Arr: Ryuichi Sakamoto] A-4 by Yoshitaka Minami from the album "South
Of The Border" September 21, 1978
|
南佳孝(1950~ 東京都出身)の3枚目のアルバム。初アルバム「摩天楼のヒロイン」1973はとても良い出来だったが、プロデューサーの松本隆とアレンジャーの矢野誠のコンセプトが前面に出過ぎたきらいがあったため、2枚目の「忘れられた夏」1976が彼本来の姿での実質デビュー作といえるだろう。その後ティンパンアレーのアルバム「キャラメル・ママ」1975でゲストとして歌った鈴木茂の「ソバカスのある少女」を1977年にシングル盤カバーし、その翌年に出したのが本作で、本人の作曲、坂本龍一のアレンジと共同サウンド・プロデュースによりジャズ、ラテン・フレイバー溢れる名作となった。アルバム・ジャケットの官能的な絵は池田満寿夫(1934-1997)の「愛の瞬間」(リトグラフ、1966年)で、この名作の使用が許可されたという事は、本作が制作段階でいかに高い評価を得ていたかという事実の証といえよう。
1.「日付変更線」は彼女のもとを去って飛行機で日付変更線を超える男の話で、松任谷由美の歌詞は短編小説のような味わいがある。「スコール」、「遠浅サンゴ礁」という南国の言葉が出てくるので、行先は中央アメリカか南米の国なのかな?松任谷の洒落た歌詞、南のクールなメロディーと坂本の絶妙なボサノバ・アレンジにより素晴らしい曲に仕上がった。大貫さんは「Duet
Vocal」としてクレジットされているが、彼女が単独で歌う部分はなく、コーラス・パートで南のボーカルにハーモニーを付けているだけ。しかしそのハーモニーの存在感が強烈で曲の印象をより深いものにしている。またエンディングで彼女のバックコーラスが聞こえるのもいいね。なお本曲はアルバム発売に先行してシングルカットされた。また松任谷由美は25年後の2003年にアルバム「Yuming
Compositions: Faces」で本曲をセルフカバーしているが、両者を聴き比べると南の退廃的でダークな雰囲気のボーカルがいかに曲に合っていたかがよくわかる。
その他の曲について、来生えつこが歌詞を書いた曲が特にいいね。「夏の女優」1曲目(作曲はすべて南なので以降記載省略)、「プールサイド」2曲目、「常夜灯」5曲目のいずれも都会の男女のライフスタイルを切り取ったもので、気怠さと艶っぽさが奇妙に同居している。「夏の女優」はからっとしたラテン・ダンス調のアレンジなんだけど、南が歌い始めた途端さっと影を帯びるところが面白い。「プールサイド」は、南・坂本がブラジルの作曲家アントニオ・カルロス・ジョビン、編曲家デオダードの影響を受けたことがよくわかる。あと最後の「スフィンクスの夢」(作詞
三浦徳子)10曲目、「終末(おわり)のサンバ」(作詞 一條諦輔)11曲目のメドレーが素晴らしい。前者ではエジプトのスフィンクスに自身の孤独を投影させ、後者は「宴のあとの虚しさ」を歌い、聴き終わった後に何とも言えない余韻を残す。
本作は1978年という時代のなかで生まれた最良の作品のひとつと言える。坂本龍一にとって、ブレイクスルーとなるアルバム「千のナイフ」の発売が同年10月25日、イエローマジック・オーケストラのデビューアルバムの発売が11月25日なので、本作はその前夜の仕事として筆頭にあがる存在と位置付けることができる。
[2024年10月作成
|
| 1982年 「Cliche」 (1982/9/21発売)の頃 |
| Dear Heart 大貫妙子 Epo Jake H. Conception (1982) Dear Heart (RVC) |

 |
1. Dear Heart [Jay Livingston, Ray Evans, Henry Mancini] Promotional Single
A Side
大貫妙子、Epo, Jake H. Conception : Vocal
清水信之 : All Instruments、Arrangement
Scot Lowson : Narration
Promotional Single Record (Picture Disk) "Dear Heart" Not For Sale (1982)
写真上: A面
写真下: B面
|
1982年宮田茂樹がRVC(Victor) 内に立ち上げたDear Heart レーベルのプロモーションのために制作、関係者に配布された非売品シングル盤。レーベルのロゴのみが印刷されたシンプルな白紙のカンガルー・ジャケットに収まったピンク色のピクチャー・レコードで、盤上にレーベル・アーティストとスタッフ、関係者の名前が列挙されている。そのA面に大貫さんが参加している。
1. 「Dear Heart」は、1964年の同名の映画(日本非公開)のためにヘンリー・マンシーニが書いた主題曲で、アカデミー主題歌賞にノミネートされた他、アンディ・ウィリアムス、ジャック・ジョーンズで前者が全米24位、後者が全米30位のヒットを記録した。映画はマンハッタンを舞台にした中年男女の恋愛の機微を描いたもので、主演はグレン・フォード、ジェラルディン・ペイジ、アンジェラ・ランズベリー、監督は「Marty」1955
が代表作のデルバート・マン。地味な俳優陣と華やかさに欠ける中年男女の物語ということで日本公開が見送られたこともあり、マンシーニらしい素敵なメロディーの曲なんだけど、日本におけるこの曲の知名度は低い。
ここではマンシーニと彼のオーケストラによる歌付のオリジナル・バージョンに忠実なアレンジで、大貫さん、エポ、そしてサックス奏者のジェイク H.
コンセプション(1936-2017) が丁寧に歌っている。彼はフィリピン出身で、1964年23歳で来日、幅広い分野で数多くのスタジオ・セッションで活躍した他、自己名義のアルバムも発表した人。3人の声は綺麗に混じり合っていて、時折りジェイクが一人で歌う部分があるが、女性二人のソロパートはない。間奏部分ではスコット・ローソンという人の語りが入る。カントリー・スタイルのピアノとストリングス・サウンドのシンセサイザーをバックにした2分半ちょっとの短い曲だ。
なおB面は越美晴(Vocal)、鈴木さえこ(Drums)、Jake H. Conception (Sax)、清水信之(All Instruments)による同曲のセッション。
大貫さんは、このRVC傘下の同レーベルで2枚(「Signifie」1983、「カイエ」1984)、宮田茂樹のRVC退社、ミディ・レコード設立後に5枚(「Copine」1985、「Comin'
Soon」1986、「A Slice Of Life」1987、「Purissima」1988、「New Moon」1990)のアルバムを製作している。
非売品であるが、そこそこの枚数が配られたようで、中古品市場で比較的高値で出回っている。大貫さんの声はエポと溶け合っていて、はっきり認識できないが、愛らしい曲・歌唱だ。
[2024年2月作成]
|
| 1985年 「コパン」 (1985/6/21発売)の頃 |
| 彼女の時 かしぶち哲郎 (1985) Midi |
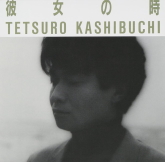 |
1. 緑の果て [作詞作曲編曲 かしぶち哲郎] B面2曲目
かしぶち哲郎: Vocal, Drums, Percussion, Synthesizer
大貫妙子: Vocal
渡辺等: Bass
Hammer: Computer Programming And Equipment
藤井丈司: Fairlight CMI Programming:
1985年7月7日発売
1. Midori No Hate (The End Of Green) [Words, Music & Arr: Tetsuro Kashibuchi]
B-2 from the album "Kanojyo No Toki (Her Time)" on 1985
|
かしぶち哲郎(1950-2013)は、はちみつぱい及びムーンライダースのドラム奏者、ボーカリスト。はちみつぱい加入前から弾き語りをしていたとのことで、グループのアルバムで独特の作風の曲を提供し歌った。また多くのアーティストに対し曲の提供や編曲を担当し、1983年に矢野顕子との共同作品として初ソロアルバム「リラのホテル」を発表した。
本作は1985年発売の2枚目の作品で、A・B面各3曲のミニアルバムという構成。全曲彼の作詞・作曲・編曲で、ストリングス・アレンジのみ坂本龍一が担当している。演奏面でかしぶちはドラム、パーカッションの他にシンセサイザーを弾き、他に矢野顕子(ピアノ)、白井良明(ギター)、渡辺等(ベース)等が主な参加者で、ボーカルでは大貫さん、矢野顕子、石川セリが参加している。
1.「緑の果て」は、かしぶちの作品に特有なヨーロッパのデカダンスの香りがする曲で、大貫さんと彼が交互に歌っている。3拍子のワルツなんだけど、ドラムは変則的な叩き方をしているのが面白い。聴く限り、ここではストリングスやアコースティックピアノ、ギターは入っておらず、打楽器とベース、シンセサイザーのみの演奏のようだ。
他の曲では「眩暈」(ストリングス編曲 坂本龍一)A面1曲目では、イントロに清水信之のアコーディオン、そして坂本龍一のピアノ、シンセイザー、そして彼が編曲したストリングスがフィーチャーされるラテン調の佳曲。「柔らかいポーズ」(ストリングス編曲
坂本龍一)A面2曲目は大貫さん、矢野顕子、石川セリの3人による豪華なコーラスが聴ける。白井良明のギター伴奏・ソロが効果的で、細野晴臣がベースを弾いている。「Dialogue」(ストリングス編曲
坂本龍一)A面3曲目は矢野とかしぶちが会話風に歌う、映画のワンシーンを観ているかのような曲。矢野顕子のピアノと佐藤野百合のバイオリンを中心とした伴奏で、間奏のシンセサイザー・ソロは清水信之。「S・Ex
(Sensuous Experience)」B面3曲目は石川セリとのデュエットで、タイトルの通り官能的な歌詞と矢野のピアノとかしぶちのシンセサイザーが素晴らしい。ここでは大村憲司がギターを弾いている。
聴き込むとどんどん良くなる作品だね。
[2024年12月作成]
|
| 永遠の遠国 あがた森魚 (1985) 永遠製菓 自主製作盤 (再発盤はKitty) |

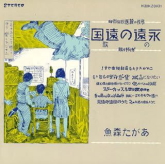
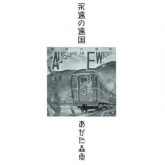
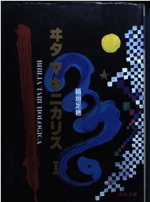 |
[1977年録音]
1. いとしの第六惑星 [作詞作曲編曲 あがた森魚] キャラメル A-1
2. 仁丹塔の歌 [作詞 田中正志 作曲 あがた森魚 編曲 渡辺勝] Solo Version キャラメル B-1
3. ルージュのワルツ~Smile (インストルメンタル)[作曲 あがた森魚、C. Chaplin 編曲 細野晴臣]
シガレット C-2
4. 春の夜の手品師 [作詞作曲 あがた森魚 編曲 渡辺勝] シガレット C-3
5. 仁丹塔の歌 [作詞 田中正志 作曲 あがた森魚 編曲 渡辺勝] Duet Version シガレット D-1
6. モンタギュー家最後の日 [作詞作曲 あがた森魚 編曲 ムーンライダース] シガレット D-3
あがた森魚: Vocal (1,4,5,6)
大貫妙子: Vocal (2,5), Chorus (1,2,3,4,5,6)
渡辺勝: Piano (1), A. Guitar (2,5), Bass (3,4), Recorder (3,4), Chorus (1)
鈴木慶一: E. Piano (6), Synthesizer (6)
岡田徹: Piano (6), Solina (6)
今井忍: E. Guitar (1,2,5), A. Guitar (3,4), Chorus (1,3,4)
小林清: A. Guitar (1), Ukulele (1), Chorus (1)
白井良明: Double Neck E. Guitar (6)
竹田祐美子: Piano (2,3,4,5), Accordion (1), Chorus (1,3,4)
佐久間順平: Violin (1), Chorus (1)
武川雅寛: Violin (6)
大庭昌浩: Bass (1,2,5), Chorus (1)
鈴木博文: Bass (6)
かしぶち哲郎: Drums (6)
安藤政広: Percussion (1,2,5), Chorus (1)
三島洋一: Percussion (1), Triangle (3,4), Conga (3,4), Chorus (1)
[1982年録音]
組曲 スターカッスル星の夜の爆発 [詩 稲垣足穂「星澄む郷」より 作曲 あがた森魚 編曲 ライオン・メリィ] チョコレット E-1~6
7. Part1 お伽劇の映画で観たようにラジオから...
8. Part2 ただ折ふし夢の中でのみ覗い得るもの
9. Part3 麓のステーションからアプト式の汽車に乗って
10. Part4 メロ僧正のお伽の広間の懸幕に似た星空
11. Part5 広島市民球場のくずれた溶鉱が
12. Part6 そしてまた遠国の諸侯の領地に...
13. スターカッスル星の夜の爆発 (Extra) 「永遠の遠国」(二十世紀完結編)CD2-16
あがた森魚: Vocal (8,9,10,11,12), A. Guitar (12,13)
大貫妙子: Vocal (7,8,11,13), Chorus (13)
ライオン・メリィ: Jupiter8 (7,8,10), Jupiter4 (10), MS-20 (10), TR-808 (9,11),
Piano (8,11,12), Vocoder (10), Radio Tuning Noise (7), Radio Collage (11),
Kalinba (9), Mandolin (9), Recorder (11), Tambourne (11), Conga (12,13),
Bongo (12,13), Snare Drum (13)
関端ひかる: Alto Sax (8), Chorus (9)
美尾洋乃: Violin (12,13), Chorus (9), Voice (10)
写真上 オリジナル盤 LP3枚組 (1985年11月30日発売) タイトル「永遠製菓」」
写真中上 CDダイジェスト盤「永遠の遠国の歌」(Kitty 1986年4月25日発売)
写真中下 CD再発盤「二十世紀完結編」 CD2枚組(Kitty 1999年3月17日発売) タイトル「あがた森魚」
写真下 稲垣足穂 「ヰタ マキニカリス II」 河出文庫 (1986年4月4日発売 「星澄む郷」を含む短編集)
[Recorded on 1977]
1. Itoshi No Dairoku Wakusei (My Beloved 6th Planet) [Words, Music &
Arr: Morio Agata] Caramel A-1
2. Jintan-Tou No Uta (Song Of Jintan Towner) [Words: Masashi Tanaka, Music:
Morio Agata, Arr: Masaru Watanabe] Caramel B-1
3. Rouge No Waltz~Smile (The Waltz Of Rouge) Instrumental [Music: Morio
Agata, C.Chaplin, Arr: Harunomi Hosono] Cigarette C-3
4. Haru No Yoru No Tejina-Shi (The Magician On A Spring Night) [Words &
Music: Morio Agata, Arr; Masaru Watanabe) Cigarette C-3
5. Jintan-Tou No Uta (Song Of Jintan Towner) [Words: Masashi Tanaka, Music:
Morio Agata, Arr: Masaru Watanabe] Cigarette D-1
6. Montague-Ke No Saigo (The End Of The Montague Family) [Words & Music:
Morio Agata, Arr: Moonriders] Cigarette D-3
[Recorded on 1982]
Kumikyoku "Star Castle Hoshi No Yoru No Bakuhatsu" (Suite "The
Explosion Of The Star Castle On A Starry Night") [Poem: Taruho Inagaki
From Hoshi Sumu Sato (Starry Land), Music Morio Agata, Arr: Lion Mary]
Chocolate E-1~6
7. Part1 Otogi-Geki No Eiga De Mita Yoni Radio Kara (From Radio Just Like
Seen On The Fairy Tale)
8. Part2 Tada Orifushi Yume No Naka Denomi Ukagai Eru Mono (Something That
Can Only Glimpsed Occasionally In Dreams)
9. Part3 Fumoto No Station Kara Aputo-Shiki No Kisha Ni Notte (Riding On
The Abt-Type Train From The Station At The Foot Of The Mountain)
10. Part4 Melo Sojyo No Otogi No Hiroma No Kakemaku Ni Nita Hoshizora (The
Starry Sky Resembles The Curtain Hanging In The Fairy Tale Hall Of Priest
Melo)
11. Part 5 Hiroshima Shimin Kyujo No Kuzureta Yokou Ga (The Collapsed Smelter
Of Hiroshima Municipal Stadium)
12. Part 6 Soshite Mata Ongoku No Shoko No Ryochi Ni (And Also In The Territories
Of Distant Lords)
13. Star Castle Hoshi No Yoru No Bakuhatsu (Extra) ("The Explosion
Of The Star Castle On Starry Night") CD2-16
By Morio Agata from the album "Eien No Ongoku" (Eternal Far Kingdom)
on November 30, 1985 (except 13 from the CD reissue on March 17, 1999)
|
1985年11月30日LP3枚組で発売されたあがた森魚の自主製作盤「永遠の遠国」には大変な思い出があります。1977年に私は街で見かけた限定150部の自主製作盤の宣伝チラシに魅せられ、当時の私にとっては目の玉が飛び出るような大金(今でも大金だと思うけど)だった2万5千円を振り込んだのです。当時のあがたさんは傑作「日本少年(ヂパング・ボーイ)」1976に続く「君のことすきなんだ」1977を出した直後でした。その時は半年・1年位で届くものと思っていましたが、後にあがたさんから遅れる旨の連絡があり、それから8年間も待たされることになったのです。その間「永遠製菓」よりガリ版印刷の通信「永遠の遠国ニュース」やソノシートが郵便で頻繁に届きましたので不安はなかったのですが、それにしても長かった!後からわかった話ですが、その間のあがたさんは大変だったようです。日本各地の旅行で採取した電車や街の音源と音楽からなる旅行記という当初の企画が頓挫し、しかもパンクとニューウェーブに席捲され従来の音楽が否定された当時のミュージックシーンのなかで、活動の場を失いフェードアウトしかねない危機的な状況にあったようです。
そういう閉塞的な環境と恐らくは経済的な苦境のなかで彼は耐え忍び、1980年の実験作「乗物図鑑」の成功を経て、自己の音楽性と当時流行りの新しい音楽との接点を見出すことで、1981年バージンVSというバンドでレコードを発売して突破口を見出すのです。実は一度永遠製菓オフィスに「まだですか?」という電話をしたことがありまして、その時は何とあがたさん本人が電話にでて、遅れの謝罪をされたことを覚えています。そしてとうとう1985年12月3日発送のペリカン便で届いた「永遠の遠国」はシリアル番号付きのボックス(私の番号は20番台でした)で、キャラメル、シガレット
(1977年録音)、チョコレット (1982年録音)という3枚のLPと読本、あがたさんからの贈り物袋からなる宝箱でした。当初150部の販売ということでしたが、その後の申し込みの増加により150部が追加製作され、それらは初版と区別するため表紙の印刷が青みがかった色だったと記憶しています。
本作は発売後に傑作との評価が高まったため、1986年4月25日に大手レーベルのキティからガリ版印刷のような表紙の「永遠の遠国の歌」(所謂「ガリガリ版」)という1枚のCDが発売されたが、それはダイジェスト盤として9曲のみが収められた。そしてその13年後の1999年に当時未発表となった曲を含むCD2枚組の完全盤「二十世紀完結編」が発売され、幻と言われた作品の全貌を多くの人が聴くことができるようになったのだ。
冒頭の1.「いとしの第六惑星」は11分を超えるゆったりした雰囲気で、当時の渡辺勝バンドが演奏している。ピアノの竹田祐美子は渡辺の音楽的相棒で、「およげたいやきくん」1975のB面なぎらけんいちの「いっぽんでもニンジン」の数字の掛け声が印象的だった人。エレキギターの今井忍は、その後渡辺とのキリギリスを経てボーイ・ミーツ・ガールでアルバムを出した。ベースの大庭昌浩は名前を「珍太」に変えて高田渡とヒルトップ・ストリング・バンド、マンドリン・ブラザースなどで活躍。小林清はウクレレ奏者として大成。安藤政浩はAnnsanとして西岡恭蔵と一緒に活動し、その後も多くのアーティストのバックを務めている。大貫さんのコーラスは目立たないけど、全員で歌っている雰囲気がとてもいい。
2.「仁丹塔の歌」は、外波山文明主催の劇団「はみだし劇場」が1977年10月27日~11月7日に浅草で行った舞台劇「浅草夜楽・仁丹塔奇譚」(田中正志作、外波山文明演出)で使われた曲で、劇においても渡辺勝バンドが演奏を担当した。大貫さんが一人で歌っていて、彼女としては最もナチュラルな声色での歌唱。バックで聞こえるコーラスも彼女によるものだ。短くシンプルながら聴いた後に余韻が残る。仁丹は森下仁丹が作る銀色小粒の口中清涼剤で、仁丹塔は浅草に設置された広告塔。1986年に解体され現在は記念プレートのみが残っている。同曲は2枚目のシガレットにおいても同じバッキング・トラックで再演されるが、そこでは大貫さんとあがたさんのデュエット・バージョンとなり、大貫さんの声はラジオ風の処理がされている。
3.「ルージュのワルツ」は音楽と電車の走る音、ラジオ、街の宣伝音を融合させた環境音楽で、チャップリンの映画「Modern Times」1936の「Smile」のメロディーが出てくる。当初企画された旅行記の面影が残った曲と言えよう。クレジット表示にはないが、次の曲の序曲的な位置付けになっていて、同じ演奏が出てくる。その次の曲
4.「春の夜の手品師」は、2.「仁丹塔の歌」と同じ劇で使われた曲で、あがたの真骨頂的作品。大貫さんのハミングがいい味を出している。6.「モンタギュー家最後の日」はムーンライダースがバックを務めていて、大貫さんはアンニュイな雰囲気のコーラスを付けている。キャラメル、シガレットからなる2枚のレコードは、渡辺勝バンドとムーンライダースのバックで素晴らしい音楽世界が味わえる。
そして3枚目のレコード、チョコレットは1982年の録音で、当時あがたと行動を共にしていたヴァージンVSの連中がバックを務めていて、ニューウェーブな香りが漂っている。そのA面を占める「組曲
スターカッスル星の夜の爆発」は傑作で、あがたが師とする稲垣足穂の「星澄む郷」の一部にあがたが曲をつけたもの。同短編は昭和2年(1927年)11月の「新潮」が初出で、昭和44年(1969年)の「稲垣足穂大全」に収められた。一番入手しやすい本は河出文庫の「ヰタ
マキニカリス I」1988で、その後1998年に新しい表紙で再発されたが、現在は絶版だ。文庫本5ページ相当の短い話で、電車の旅をする私と旅の友だちの会話という構成。耽美的な言葉による幻想的な内容は読む者を圧倒させる。これが昭和2年に書かれたとは思えない前衛作品だ。あがたさんは前半部分の二人の会話を切り取って曲をつけている。メロディーに合わせるため、一部において単語を削ったり語尾を変えているが、改変は最低限に留まっていて原作を尊重しているのがわかる。ただし短編の会話と曲の歌詞とは一部順序が入れ替わっている部分があるが、内容的には問題ない。なお「スターカッスル」はあがたの造語で、原作では「星ヶ城」になっている。
7.「Part1 お伽劇の映画で観たようにラジオから...」はラジオからノイズと一緒に歌が流れてくる感じで、あがたに続く大貫さんの声色は巫女さんのように清純で、彼女としては極めて異色の歌唱だ。8.「Part2
ただ折ふし夢の中でのみ覗い得るもの」は前の曲のシンセサイザーに対し、ピアノ伴奏と二人のボーカルは透明感に溢れている。歌が終わるとシンセベースが4ビートを奏で、ジャズっぽいピアノ演奏になるのが面白い。予算の関係でフルバンドを使えなかったため、伴奏編曲はヴァージンVSのライオン・メリィがほぼ一手に引き受けている。それがピュアな音空間を生み出していて、幻想的な曲とうまくマッチしたといえる。
9.「Part3 麓のステーションからアプト式の汽車に乗って」のアプト式とは勾配のきつい線路で使用される方式で、車輪の中央に歯車があって、それを線路の中央のギザギザに噛ませることで上ってゆくもの。碓氷峠の路線が廃線になったため、現在の日本では大井川鐡道のみとなっている。シンセとカリンバによる伴奏で、ヴァージンVSの関端ひかるとムーンライダースと親交があった美尾洋乃の二人がコーラスを担当。10.「Part4
メロ僧正のお伽の広間の懸幕に似た星空」は8分を超える長い演奏でシンセによるロックなインスト部分が前半とエンディングを占めている。11.「Part5
広島市民球場のくずれた溶鉱が」の「広島」は原作にない言葉で、原作が書かれたのは戦前、市民球場ができたのは戦後であることを考えると、このタイトルは時空を超えたイメージからだろう。鳥の囀りや駅のアナウンスなどがコラージュされた現代音楽的な味付けになっている。なおクレジットには表示はないが、最後にてくる女性ボーカルは明らかに大貫さんのものだ。最後の12.「Part6
そしてまた遠国の諸侯の領地に...」はピアノとバイオリニストの美尾洋乃を中心としたきりっとした感じの伴奏。以上で22分を超えるめくるめくイマジネーションの世界が終わる。
なおチョコレットのB面には「スターカッスル星の夜の爆発(ダブ・バージョン)」があるが、12.「Part6 そしてまた遠国の諸侯の領地に...」をベースとしたトラックで、そこには大貫さんのボーカルやコーラスは入っていない。また1999年に発売されたCD2枚組「二十世紀完結編」には、未発表トラックとして
13.「スターカッスル星の夜の爆発 (Extra)」が入っていが、これはPart6の別テイクといえる内容で、大貫さんのハーモニー・ボーカルとコーラスを聴くことができる。
ちなみに1982年に発売されたヴァージンVSのアルバム「Star★Crazy」には「スターカッスル星の夜の爆発」という曲名で内容的にはPart1とPart6を合わせたものが入っていて、女性コーラスは当然ながらヴァージンVSの二人(関端ひかるとリッツ、後者は遠藤健司の奥さん)が担当している。「永遠の遠国」に先行して発売され、インターネットがなかった時代に自主製作盤を持っていない人がスターカッスルを聴けるのはここだけという状況が1999年まで続いたことになる。
特異なアルバムで大貫さんの特異なボーカルが楽しめる逸品。
[2025年4月作成]
|
| 1987年 「A Slice Of Life」 (1987/10/5発売)の頃 |
| as close as possible オフコース (1987) Fun House |

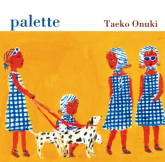 |
1. 嘘と噂 [作詞作曲 小田和正 編曲 オフコース] 10曲目
小田和正: Vocal, Keyboards
大貫妙子: Vocal
坂本龍一: Keyboards
松尾一彦: Guitar
清水仁: Bass
大間ジロー: Drums
望月英樹, Sawada Yoshiyuki: Synthesizer Programming
写真上: 「as close as possble」 1987年3月28日発売
写真下: ベストアルバム「palette」 2009年4月29日発売
1. Uso To Uwasa (Lies And Rumors) [Words & Music: Kazumasa Oda, Arr:
Off Course] 10th track by Off Course from the album "as close as possible"
on March 28, 1987
|
オフコースは1982年の鈴木康博脱退の際に活動を休止し解散を考えたが、メンバーの話し合いによって残りの4人であと数年続けることになった。結局1989年に解散することになるが、本作はその過程のなかで作られたアルバムだ。この頃小田和正はグループとは別の活動を始めて、アメリカ録音のソロアルバム「K.
Oda」を1986年に発表。本作でも外部の作詞家に歌詞を書いてもらったり、打ち込みの多用や小田と松尾一彦に加えて新たに清水仁が作曲・歌で加わるなど、活動が多様化している。
1.「嘘と噂」は小田色の強い作品。 大貫さん参加の経緯につき、彼は以下の通り語っている。
「外部の人と組むことには積極的になろうと思っていた」、「詩を書いているうちに、これだったら女の子が歌ったほうがいいだろうという考えがでてきた」、「女の子の気持ちを書いたわけで、それを女の子が歌えばストレートに気持ちが伝わる」、「彼女(大貫さん)の声も前から好きだったし」、「彼女のあの声であの歌い方でいったらこの曲にハマるだろうなと考えて」。
大貫さんの登場は歌詞のなかで女性側の思いを伝える2ヵ所のみであるが、そのひんやりとした感じの歌声が曲にぴったり合っている。オフコースの楽曲でこのようにゲストが歌うのは本曲のみだそうだ。そして坂本龍一のエレキピアノ・ソロが曲に彩りを添えている。彼の参加は1985年の松任谷由美、財津和夫との共作シングル「今だから」の演奏と編曲担当、および坂本のラジオ番組へのゲスト出演などの親交の延長線で実現したらしい。
なお本曲は後に大貫さんのベストアルバム「Palette」2009に、「オフコース featuring 大貫妙子」名義でボーナストラックとして収められた。
その他の曲について (特記ない場合は 編曲 オフコース)
全10曲中、松尾と清水が各2曲歌っているが、やはり興味は小田の曲に向かう。タイトル曲の「もっと近くに(as close as possible)」
[作詞 小田和正、Randy Goodrum 作曲 小田和正」1曲目、「It's Alright」[作詞作曲 小田和正] 2曲目はシングルカットされた後期の彼ららしい曲。「Love
Everlasting」 [作詞 Rabdy Goodrum 作曲編曲 Dann Huff] 6曲目のみアメリカ録音で、ジェフ・ポーカロ(ドラムス)とデビッド・ハンゲイト(ベース)のTotoのリズムセクションとダン・ハフのギター、ロビー・ブキャナン(キーボード)という小田のアルバム「K.Oda」と同じ連中によるバックになっている。
小田和正とのデュエットという珍しい取り合わせ。
[2025年7月作成]
|
| 1989年 「Purissima」 (1988/9/21発売)、「New Moon」 (1990/6/21) の頃 |
| Redmonkey Yellowfish 大江千里 (1989) Epic (Sony) |
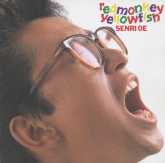 |
1. 向こう見ずな瞳 [作詞作曲 大江千里 編曲 清水信之] 9曲目
大江千里: Vocal, Back Vocal
大貫妙子: Vocal, Back Vocal
清水信之: Electric & All Instruments
田端ハジメ: Syntheoperator
大江千里: Producer
1989年10月21日発売
1. Mukomizu Na Hitomi (Reckless Eyes) [Words & Music: Senri Oe, Arr:
Nobuyuki Shimizu] 9th track by Senri Oe from the album "Redmonkey
Yellowfish" on October 21, 1989
|
大江千里(1960- 大坂府出身)については紹介不要でいいかな。本作は1983年デビューの彼が28歳で発表した8枚目のアルバム。1曲を除き清水信之が編曲していて、歌詞・メロディー、演奏・歌唱すべてにおいて軽やかでポップな音になっている。シンセポップの跳ねたサウンドをバックに、都会に暮らす若者の揺れる心が歌われていて、高齢者の私が聴いていると、全く同じ経験ではないにしても、昔そんな時もあったなあと思い出してニヤニヤしてしまう。
1.「向こう見ずな瞳」はアルバムにの中で群を抜いて印象的な曲。結婚の告白を受けて旅に出た恋人に訴える男の歌で、大貫さんの出番はブリッジの短い所だけど、それまで大江が歌ってきた男の心情に対し、女の思いを吐露する重要な場面になっていて、その後の曲(気持ち)の高ぶりに繋がってゆく。間奏におけるサックスのようなソロは、清水のシンセイザーだろう。本曲について、彼はファンクラブの会報冊子に以下の通りコメントしている。
大貫さんとのデュエットを想定してデモテープで大貫ヴォイスを真似て「まっつっげっうぉーぬうらっすう」(一コ一コ丹念におきながら、ちょっとすくい気味に切る感じで)やってみたら、それを聴いたター坊がスタジオでそのとおりに歌ってくれたのでびっくりした。実は自分で自分にリクエストしたいくらい気に入っている。
その他の曲について (全曲 作詞作曲 大江千里、特記ない場合 編曲 清水信之)
「We Are Travellin' Band」(編曲 The Travellin' Band) 1曲目 これのみ、同じレーベルに所属していたBe-Modernというロックグループが清水信之と一緒にバックと編曲を担当している。当時各地を巡るツアーをした時の心情・風景を歌ったロック調の曲。「おねがい天国(redmonkeycut)」2曲目はふわふわっとした軽さが独特の境地を開いている。いずれもシングルカットされた。
大江は2007年に日本での音楽活動を休止して渡米し、ニューヨークでジャズを学んでから当地でジャズ・ピアニストとしてデビュー。日本と米国の間を行ったり来たりしながら、現在に至っている。本作を聴くと、歳をとるにつれてこれらのようなラブソングが書けなくなったことがよくわかる。それにしても若い頃は音楽にジャズっぽさはなかったはずで、はたから見ると意外な転身だね。
大貫さんの出番は僅かだけど、はっとさせる場面になっていて、とても聴きごたえがある佳曲だと思う。
[2025年8月作成]
|
| 1990年 「New Moon」 (1990/6/21発売)の頃 |
| In The Pocket 中西俊博 (1990) For Life |
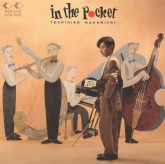 |
1. 遥かな想い [作詞 大貫妙子 作曲編曲 中西俊博] 4曲目
中西俊博: Violin, Conductor, Producer
大貫妙子: Vocal
山岸博、飯笹浩二: Horn
朝川朋之: Harp
桑野聖ストリングス
桑野聖、竹内純、後藤龍伸、上田眞仁、福森隆、鈴木星彦、酒井智子、金原千恵子、堀内かおる、原田美加、岩戸有紀子、後藤勇一郎: Violin
桑野千絵、遠山克彦、村山達哉、大沼幸江: Viola
堀内茂雄、寺井つねひろ、服部誠、松岡陽平: Cello
斉藤順、千葉一樹: Contra Bass
1990年12月5日発売
1. Harukana Omoi (Distant Feelings) [Words: Taeko Onuki, Music & Arr:
Toshihiro Nakanishi] 4th track by Toshihiro Nakanishi from the album "In
The Pocket" on December 5, 1990
|
中西俊博(1956- 東京都出身)は、デビューアルバム「不思議な国のバイオリン弾き」がヒットした以降クラシック、ジャズ、ポップスのジャンルをまたぐバイオリン奏者として活躍している。記録に残っている大貫さんとの最初の仕事は、1987年の最初のピュア・アコースティック・コンサートで、その模様を別途録音したCD「Pure
Acoustic」が残されている。そこには奏者としての参加の他に「横顔」、「新しいシャツ」、「突然の贈り物」の編曲も担当し、既存の曲に新しい命を与えている。そして1988年8月26日にNHK総合テレビで放送された大貫さんの「サマーナイトミュージック」に出演して彼女のバックを務め、その中でソロ曲「夏の朝に開くパレット」(中西のアルバム「太陽がいっぱい」1987収録曲)を陶器でできた仕掛け人形の印象的な映像とともに披露している(当該映像は近年YouTubeで観ることができたが、2017年のボックスセット「パラレルワールド」に収録され正式発売となった)。そして同年9月21日発売の大貫さんのアルバム「Purissima」の日本録音に参加し、「Rain
Dance」、「恋人とは・・・」の彼女の歌詞に曲をつけている。そして彼女のアルバムの仕事は1990年9月21日発売のアルバム「New Moon」の「地球ファミリー~The
Wind Of My Heart~」、「花・ひらく夢」が最後となる。
そんななかで、大貫さんが中西に歌詞を提供し彼のアルバムで歌ったのが 1.「遥かな想い」だ。この曲はアルバムのクロスオーバー風の曲が並ぶなか、ストリングス、ハープ、ホルンのみによるクラシカルな演奏になっていて、唯一の歌入り曲。硬質で透明感に満ちた別れの想いが伝わってくる。ライナーノーツの中西のコメントは以下のとおり。
女性の細やかな心情を美しい言葉でかきつづり、それを歌いあげる事の出来る数少ない女性シンガーソングライター大貫妙子さんに、これでもう3曲詩を書いてもらった事になる。彼女が歌うことによって、今までとは一味違う世界が広がったような気がする
ここでの「3曲」とは本曲と「Purissima」の2曲のこと。なお大貫さんと中西との共作はもう1曲あって、それは後の1992年に発表された原田知世のアルバム「Garden」に収録された「Walking」だ(中西が編曲と伴奏を担当、「Composer」の部参照)。
その他の曲について。
菅野洋子(キーボード)、鳥山雄司、古川昌義 (ギター)、渡辺直樹、Gregg Lee、美紅月千晴 (ベース)、石川雅春、山木秀夫 (ドラムス)などの強力なバックによるフュージョン系の曲が多く、特に菅野と鳥山の活躍が光っている。それら以外で「スキッド・エクスプレス」(作曲編曲
中西俊博)1曲目は、弦楽四重奏の編成で切れ味鋭い急速テンポの演奏をしていて、とても新鮮な響きだ。ちなみにこの曲のテレビ番組映像をYouTubeで観ることができる。最後の曲「森の木陰で夢見たら」(作曲
中西俊博)10曲目は、菅野のピアノとの二人だけの演奏でクラシカルな響きの静かな曲。
中西は現在(本稿を書いている2025年5月時点)69歳ということで、当時ハンサムだった男は白い髭ぼうぼうの老人の姿になっているが、まだまだ元気に頑張っている。
大貫作詞、中西作曲の4作品のなかで最後の曲。
[2025年5月作成]
|
| 1993年 「Shooting Star In The Sky」 (1993/9/22発売)の頃 |
| Heart Of Hurt 高橋幸宏 (1993) 東芝EMI (East World) |
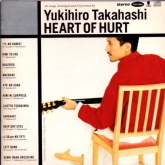
|
3. 蜉蝣 [作詞作曲 高橋幸宏 編曲 阿部雅士] 3曲目
高橋幸宏: Vocal
大貫妙子: Vocal
Unknown: Strings
1993年1月27日発売
3. Kagero (Mayfly) [Words & Music: Yukihiro Takahashi, Arr: Masashi
Abe] by Yukihiro Takahashi from the album "Heart Of Hurt" on
January 27, 1993
|
本作は、高橋幸宏(1952-2023)12枚目のアルバムの後に出したセルフカバー集だ。シンガー・シングライターとしての彼を強調した制作で、多くの曲はドラムスがないか控え目に、またドラムスや打ち込みのリズムが入っている曲でも、オリジナルに比べて歌を引き立てるような音作りになっている。
大貫さんが参加した3.「蜉蝣」は、アルバム「薔薇色の明日」1983からで、オリジナルがテクノっぽいバンドサウンドであるのに対し、ここではストリングスのみのバックで、高橋のボーカルもより陰影が濃くなっている。大貫さんのボーカルはサード・ヴァースとエンディング担当で、二人が一緒に歌う箇所はない。彼女の歌声は朝の冷気のなかに差した光のような透明感があって、聴く者の心にじわじわと染み入ってくる。アルバムのクレジットには曲毎のミュージシャンや編曲者の記載がないが、ストリングスのアレンジはクラシックのチェロ奏者である阿部雅士で間違いないだろう。ストリングスが誰かについては記載がないので不明とした(もしかすると打ち込みかも?)。
他の曲について [作詞作曲] オリジナルとその年。特記(編曲者は高橋幸宏、吉川忠英、徳武弘文、阿部雅士)
1. 1%の関係 [作詞 鈴木慶一 作曲 高橋幸宏] Broadcast From Heaven 1990
2. 君といる [作詞作曲 高橋幸宏] この曲のみ新曲
3. 蜉蝣 [作詞作曲 高橋幸宏]
4. 前兆 [作詞作曲 高橋幸宏] 薔薇色の明日 1983。ニッカウヰスキー「スーパーニッカ」CMの第4弾
5.今日の明日 [作詞作曲 高橋幸宏] Once A Frool, ... -遥かなる想い- 1985
6.君にサープライズ [作詞 矢野顕子 作曲 高橋幸宏] シングル「四月に魚(Poisson D'Avril)」B面
7. ちょっとツラインダ [作詞 鈴木慶一 作曲 The Beatniks] Exitentialist A Go Go ビートで行こう 1987。
鈴木慶一とのユニット The Beatniksのアルバム収録曲がオリジナル。
8. Saravah ! [作詞作曲 高橋幸宏] Saravah ! 1978。ボサノヴァの気怠い雰囲気がなんとも良いね。
9. Drip Dry Eyes [作詞 クリス・モスデル 作曲 高橋幸宏] Neuromatic 1981。ゲストボーカルは Sandii。英語歌詞の曲(タイトルは「ドライ・アイ」の意味)で、もともとはサンディーへの提供曲(「Sandii
& The Sunsets」1984 収録)だった。
10. 4:30A.M.のイェティ [作詞 鈴木慶一 作曲 The Beatniks] Broadcast From Heaven 1990。イェティは「雪男」のこと。
11. Left Bank [作詞 鈴木慶一 作曲 The Beatniks] Ego 1988。鈴木はアルバム「Suzuki白書」1991でセルフカバー。
12. 元気ならうれしいね [作詞 森雪之丞 高橋幸宏 作曲 高橋幸宏] 元気ならうれしいね 1991
4.「前兆」と6.「君にサープライズ」の2曲のみ打ち込みまたはドラムスの強いリズムが入っている。あとは吉川忠英(アコースティック・ ギター、マンドリン、バンジョー、ウクレレ)、徳武弘文(エレキギター、エレキシタール、アコースティック・ギター)、小原礼(ベース)、浜口茂外也(パーカッション)、松田幸一(ハーモニカ)による穏やかでアコースティックなサウンド。シンプルで素直なサウンドが曲の良さを引き立てた最高傑作という評価と、彼の持ち味であるテクノっぽさが薄くて物足りないとする評価に二分しているようだが、私にとってはニューミュージック(今で言うJ-Pop)におけるヨーロピアン・サウンドの先駆的作品のひとつだった初アルバム「Saravah
!」1978を発売当時聴いた時の衝撃が余りに大きかったので、何とも言えないですね。
高橋の優しく繊細なボーカルと大貫さんのクリスタルな歌声が楽しめる。
[2026年1月作成]
|
| 1995年 「Tchou」 (1995/4/18発売)の頃 |
| オフ・オフ・マザー・グース Various Artists (和田誠・訳詞/櫻井順・作曲) (1995) 東芝EMI |
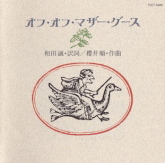


|
32. チャールズ一世
大貫妙子: Vocal
美野春樹: Piano
四家卯大: Cello
60. コマドリの死
[有志一同]
小室等: Vocal
大竹しのぶ、巻上公一、吉田日出子、大貫妙子、熊倉一雄、笈田敏夫、由紀さおり、露木茂、黒柳徹子、中井貴一、デーモン小暮閣下、雪村いづみ、岡村喬生:
Vocal (登場順)
安田祥子、藤本房子、スリー・グレイセス、タイムファイブ、ヂュークエイセス: Chorus
美野春樹: Piano
写真上: CD 1995年12月20日発売 (本作での和田の挿絵は控え目)
写真中: 筑摩書房 「オフ・オフ・マザーグ-ス」 和田誠訳 1989年出版
写真下: 講談社文庫「マザーグース<1>」 谷川俊太郎訳、和田誠挿絵 1981年出版
32. Charles Issei (Charles The First) by Taeko Onuki
60. Komadori No Shi (Who Killed Cock Robin) by All Volunteers
from the album "Off Off Mother Goose"by various artists, Makoto Wada (Nursly Rhyme Translated In Japanese) and Jun Sakurai (Composition) on December 20, 1995
|
イギリスその他のヨーロッパ諸国に伝わる古い童謡マザーグース(ナーサリー・ライムとも言う)をイラストレイター、文筆家の和田誠 (1936-2019)が和訳し、それらに作曲家の櫻井順
(1934-2021)が曲をつけた60曲を各分野で活躍する人々の歌声でCD化したもの。アルバム・タイトルは演劇世界における「オフ・オフ・ブロードウェイ」をもじったものかな?本アルバム制作の経緯は以下のとおり。
詩人の谷川俊太郎が訳した「マザー・グースのうた」が1975草思社から出版され、爆発的な売り上げを記録するブームとなリ、第5集まで出版された。そこでは堀内誠一が挿絵を描いていたが、1981年の講談社が4冊の文庫本で再出版するにあたり、挿絵を和田誠に依頼した。子供のころからそれらに接していた彼は、イラストを描きながら自分も韻を踏んだ訳ができないかと考え、60篇を翻訳し、1989年筑摩書房から「オフ・オフ・マザー・グース」を出版した。
マザー・グースは過去に北原白秋などにより翻訳されていたが、昔風の日本語によるもので、現代語による谷川俊太郎の訳は画期的だった。彼は自身の詩作で追及していた「ことばあそび」を応用してひらがなを多用し、音の豊かな響きでイメージを拡げることを目指した。そのため原作のニュアンスよりも日本語の響きを重視する傾向が強くなった。一方子供の頃から欧米のスタンダード曲に親しんでいた和田は、オリジナルの言葉の響きをなるべく残すべく、日本語訳においても韻を踏む(Rhyming)ように努めた。例えば
「Humpty Dumpty」で両者を比較すると以下のとおり。
[オリジナル]
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dunpty had a great fall,
All the king's horses and all the king's men,
Coudn't put Humpty together again
[谷川俊太郎訳]
ハンプティ・ダンプティ へいにすわった
ハンプティ・ダンプティ ころがりおちた
おうさまのおうまを みんああつめても
おうさまのけらいを みんなあつめても
ハンプティをもとにもどせない
[和田誠訳]
ハンプティ・ダンプティ 塀の上でらくらく
ハンプティ・ダンプティ おっとついらく
王さまの家来
馬に乗った部隊
誰もハンプティをもとにもどせない
どちらの訳が良いか悪いかでなく、日本語の響きを重視するか、韻を踏むことに注力するかの方向性の違いといえる。
マザーグースにはオリジナルのメロディーがないので、谷川の訳は独自の音楽が付けられてレコード・CD化されたが、朗読か、長めの日本語に対応するための語りのような歌い方になった。一方句会仲間だった作曲家の櫻井順(1934-2021)は、和田から贈られた本を読んで、ふと音楽を付けたくなり、まず作曲した10篇のテープを和田に渡したところ、「面白いね」という話になり、それで60篇全部に曲を付けてしまった。そこにプロデューサーが現れて「一流歌手に歌ってもらってCDを作ろう」という話になり企画がスタートし、本CDが完成したという。
本作に参加した人達は以下のとおり 登場順。括弧はごく簡単な紹介で、*は故人(2025年7月現在)を示す(30年前の作品なので物故者が多い)。
佐藤しのぶ*(オペラ歌手) おおたか静流*(歌手) 桐明学園 子供のための音楽教室(音楽を勉強する小学2年生) 岸田今日子* (俳優、声優、文筆家)
吉田日出子*(俳優 歌手) 柳葉敏郎(俳優) 白石冬美* (声優 ラジオパーソナリティー) 森山良子(歌手) 甲斐よしひろ(ロック・ミュージシャン)
的場愛美(子供歌手) 平野レミ(シャンソン歌手 料理研究家 和田の奥さん) 高泉淳子(俳優 劇作家) 坂本冬美(演歌歌手) 中山千夏(俳優 歌手
文筆家) 小坂一也*(カントリー歌手 俳優) 時任三郎(俳優) 斎藤晴彦*(俳優) イッセー尾形(俳優) 清水ミチコ(物真似歌手 タレント)
笈田敏夫*(ジャズ歌手) 天地総子*(歌手、声優、タレント) 田中朗(シャンソン歌手) 小室等 (シンガーソングライター) 石嶺聡子(沖縄の歌手)
藤本房子(歌手) 木村充輝(憂歌団のボーカリスト) 中島啓江* (ミュージカル歌手) 岩崎宏美(歌手) 黒柳徹子(俳優 TVパーナリティー 文筆家)
島田歌穂(ミュージカル歌手) 近田春夫 (ロック・ミュージシャン)
大貫妙子(和田誠による紹介「中学時代からアマチュア音楽活動を始め、1973年、シュガーベイブを結成。76年以降はソロ活動。アルバム制作、コンサートの傍ら、南極、アフリカなどを旅行して紀行文を書く。レコーディングには愛用のマイクを持参。」
小松政夫* (俳優 コメディアン) 岡村喬生*(オペラ歌手) 鳳欄(宝塚、ミュージカル歌手) 谷啓*(俳優 コメディアン クレージーキャッツ)
井上陽水(シンガーソングライター) スリーグレイセス(3人組女性コーラス) タイムファイブ(5人組男性コーラス) 知久寿焼(ミュージシャン たま)
大竹しのぶ(俳優 歌手) ジミー時田*(カントリー歌手) 野坂昭如*(作家) C.W. ニコル*(イギリス生まれで日本に帰化した作家) 辛島美登里(歌手)
露木茂(フジテレビ司会者) 忌野清志郎*(ロック・ミュージシャン) こうの・おさむ(総合インテリア(株)高野当主) 雪村いづみ* (歌手) 巻上公一(ロック・ミュージシャン
俳優 演出家) 松金よね子(俳優) デーモン小暮閣下(ロック・ミュージシャン) 水前寺清子(歌手) デューク・エイセス(男性コーラスグループ)
小椋佳(シンガーソングライター) 熊倉一雄*(俳優 声優) 中井貴一(俳優) 由紀さおり・安田祥子(姉妹歌手) 近藤房之介(ブルース歌手 踊るポンボコリン)
真田広之(俳優 プロデューサー)
以上のとおり物凄い顔ぶれ、個性あふれる声の大群で、大貫さんは32番目に登場。彼女が歌う 32.「チャールズ一世」は、「チャリング・クロスを通り過ぎて」というタイトルでも知られ、そこにあるチャールズ一世の騎馬像を歌った17~18世紀起源の童謡。専制政治に反対する人達が起こした清教徒革命に破れて処刑された王様の史実が背景にあるとされる。歌詞とオリジナルは以下のとおり。
チャーリング・クロスを騎士がゆく
黒い馬に黒い服
あれがチャールズ一世ときいた時
私の胸はドキドキドキ
As I was going by Charing Cross,
I saw a black man upon a black horse,
They told me it was King Charles the First
Oh dear, my heart was ready to burst !
「黒」は銅像の色を指しているんだね。訳詞では「ゆく」と「服」、「時」と「どき」で上手い具合に韻が踏まれている。美野春樹のピアノ(演奏面で本作の中心的存在)と、チェロのみによるシンプルな伴奏で大貫さんがうたう僅か30秒のショートショート。なお収録された60曲は演奏時間が23秒から5分35秒まで多様であるが、50秒以下の曲が大半を占めている。
大貫さんが参加した曲はこれひとつだけと思っていたが、よく見たらフィナーレの「有志一同」のなかにも含まれていた。
60.「コマドリの死」は「誰が殺したコックロビン (Who Killed Cock Robin?)」という曲名でも知られていて、「誰が〇〇したか?」という問いかけに対し、各異なる動物・魚・昆虫が「私です」と答えて歌うヴァースが13回続く、本アルバム最長(5分35秒)の曲。小室等の問いかけに対し、答えは毎回異なる人達(有志一同)が歌っている。4番目の大貫さんのヴァースの訳詞とオリジナルは以下のとおり。
誰が作ろう きょうかたびらを
私、と答えたのはアリ
私は持っている糸と針
私は作る きょうかたびらを
Who'll make the shroud?
I, said the Beeatle,
with my thread and needle,
I'll make the shroud
オリジナルは「Beetle(カブトムシ)」になっているが、和田の訳は「アリ」になっている。これは「針」(英語では「needle」)の韻を踏むために変えたのだろう。実際のところ、カブトムシがアリに代わっても大勢に影響ないもんね。
なお本作の好評を受けて、2年後の1997年に別の人々が歌う続編「またまた・マザー・グース」が発売され、翻訳数は計120となった。その後両作は長らく廃盤となり、2021年にディスク・クラシカ・ジャパンというレーベルから2枚組CDとして再発されたが、それは和田の死後3年経過、櫻井の死の直後だった。
ということで大貫さんの出番は2曲で、全部で30秒位の短い参加だ。アルバム全体としては今となっては亡くなった人も多く、時代の波に流された感もあるが、それでも捨てがたい魅力にあふれている。
[2025年7月作成]
|
| 1996年 Thou (1995/4/19) Lucy (1997/6/6) の頃 |
| LULU (Various Artists) (1996) Voyager Japan/Ariadne/Tohokushinsha/Satelite |
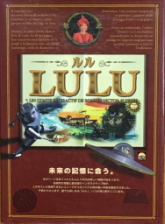
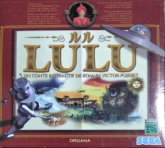
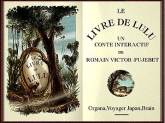
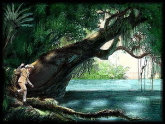
|
LULU (デジタル絵本 マルチメディアCD-ROM))
Romain Victor-Pujebet (ロマン・ビクトル・プジュベ): Author, Director, Producer
Jean Philippe Peugeot (ジーン・フィリッペ・プジョー):Programmer, Technical Director
Murielle Lefevre(ミュリエル・ルフェーブル) :Media Integration, Video, Animation, Special
Effects Expert
Brigitte Millon (ブリジッド・ミロン): Graphic Production, Animator, Colorizer
Marc Peyrucq (マーク・ペイリュック): 3D Animator
Olivier Pryszlak (オリヴィエ・プリズラック): Composer, Sound Recordist, Sound Mixer
Aleen Stein (アイリーン・スタイン):Producer
日本版
前田俊秀: Producer
高林久弥: Director
天沢退二郎、マリ林: Translation
大貫妙子: Recitation (朗読)
矢島晶子: Voice of Lulu
山口勝平: Voice of Nemo
発売
Windows/Macintosh版: 1996年6月
Playstation版、Sega Saturn版、Pippin@版: 1996年11月
iOS/iPadOS対応(復刻版): 2024年12月20日
写真上から
Windows/Macintosh版 紙製パッケージ
Sega Satern版 紙製パッケージ
冒頭ページ
ジャングルの挿絵(第5章「ジャングル」 68-69ページ)
|
1980年代の後半、これまで普及していたワープロに替わって、パソコンの使用が一般的になった。当初はオフィスに配備された少数のパソコン(当初は一人一台ではなかった)を使って、エクセルがまだない環境下でコマンドを使って簡単な計算表を作った記憶がある。その後パソコンの性能向上と価格低下、マック(マッキントッシュ)やマイクロソフトのウィンドウズ、エクセル、ワードの普及により、1990年代後半の頃から家庭でも容易に使える時代になった。一方インターネットは1990年代末から2000年代以降に一般に普及してゆくので、それまでの間は1996年に企画統一されたDVDによるCD-ROMにてソフトウェアのインストールが行われた。
「ルル」(原題「Le Livre de Lulu」、「Livre」は「本」のこと)は、パソコンが一般家庭に普及して間もない頃、まだインターネットがない時代に発表されたインターラクティブな(人とシステムが双方向にやり取りを行う)デジタル絵本である。フランスの作家ロマン・ビクトル・プジュベ(2016没)が娘のために作ったお話をCD-ROMで作ると面白いだろうと思い立った事が始まりで、その企画とサンプルを電子出版会社に持ち込んで開発がスタートし、オリジナルのフランス語版は1995年に発売され、当時のマルチメディアの出版物の中で名作といわれている。
日本版については、日本電主出版協会のサイトに、1995年フランクフルトブックフェアで本作の展示を見て開発に乗り出した前田俊秀の記事があり、以下の通り一部引用するが、本作が当時いかに斬新な作品だったかがよくわかる内容だ。
この頃のマルチメディア CD-ROM作品は、まだ初期の段階で実験的なものが多かったが、「Lulu」は、本のメタファーにヒントを得た斬新なコンセプトで、確固としたストーリーを持ったマルチメディアのお伽噺だった。ページを破いて3Dの主人公が飛び出てくるような破天荒な世界感がなんとも瑞々しく、本を読むように画面のページをめくりながら挿絵をクリックすると、その挿絵があたかもアニメ映画のように動きだすという高次元のインタラクティビティーを備えていた。ゲーム的な躍動感もバランス良く兼ね備え、画面の中には今までに見たこともない、でもいつかどこかで見た記憶がある懐かしい情景が拡がっていた。これには大人も子供も興奮するだろうと確信した。「Lulu」は読者の目を十分に楽しませてくれるタレントを持っていた。
[日本版制作についてのエピソード]
・複数のプラットフォームでの同時開発を想定してパートナー企業を募り、「ブレインプロジェクト」を結成して、広告宣伝活動を共有しながら各仕様を同時に発売する体制を構築した。
・フランス語版は原作者のロマンが自ら朗読していたが、日本語版では女性の声がいいだろうということで、大貫さんにお願いしたところ、原作を見て大喜びで快諾してくれた。そしてルル役は「クレヨン新ちゃん」の矢島晶子、ロボットのネモ役は「らんま」の山口勝平という二人の声優に決まった。
・日本語への翻訳は詩人・仏文学者・児童文学作家・翻訳家・宮沢賢治研究者の天沢退二郎(2023没)が奥様のマリ林(2025没)と一緒に担当した。彼女は「これだけは絶対に自分が翻訳したい。他人にまかせてなるものか」と言ってくれた(復刻版「ルル」Facebookより)。画面の設計上各ページにつき一定の文字数に収める必要があり、相当苦労した。
・完成したたたき台をパリで試写してロマンに観てもらったところ、日本語ができない彼が作品から感じ取って涙を流してくれた。
・パッケージは作品のオーガニックでブックライクなイメージに合わせて、CD-ROMとして通常のプラスチックでなく紙製にした。
・PCのウィンドウズ・マック・ハイブリッド版、ゲーム機のプレイステーション版、セガ・サターン版、バンダイとアップルによるピピン・アットマーク版でリリースした。
[その後]
私は発売年にWindows/Macintosh版を購入した。それはWindows3.1またはWindows95対応で、当時十分に楽しませてもらったが、その後のWindowsのバージョンアップのためCD-ROMの互換性がなくなり、いつしか読み込み不可となってしまった。パッケージは本棚の片隅で永遠の眠りにつき、作品は頭の中の過去の記憶として残ることとなった(マックおよび各社ゲーム機製品の互換性と使用可否については私は知らないが、同じようなものかと思われる)。
[復刻]
2016年に復刻作業がフランスで始まるが、原作者ロマンの死去とソフトの問題により中断。それを当初日本の開発に携わった株式会社ブレイン(代表取締役 前田俊秀)が引き継いで、2024年にアップルのOSに対応した日本語復刻版、翌年にフランス語版、英語版をリリースした。それらは同社のサイトから有料でダウンロードすることができる。
[現在の視点で観た感想]
縦横無尽に展開するRPGに慣れた人にはこの作品は全然物足りないだろう。ものや人物の動きが少しぎこちなく、プレイヤーの選択に応じてストーリーが変わることもない。ただクリックにより、背景の絵が夕方や夜の景色に替わったり、文字や挿絵の隠しボタンをクリックすると新たな絵が現れたり、絵の一部が変わったり、絵の中の者や人物が音楽に合わせて動いたりするだけ。画面の解像度も現在に比べると低い。それでもアイデアに溢れた創造性、何とも言えない品格とアーティスティックな奥深さがあるのだ。この作品には、昔のCD-ROMという単なるノスタルジー以上のものがあると思う。
[あらすじとコメント ネタバレがありますのでご注意ください]
お姫様のルルはお城の中で贅沢な生活をしていたが、孤独で憂鬱でした。そんな彼女は雑誌を見て冒険を夢見ます。(挿絵がとても綺麗でクリエイティブ。さらにカーソルが画面によりトーチ、蝶など様々な形に変化するのが凝っている。画面にあるアイコンのクリックにより流れる大貫さんの朗読は、過度に女っぽくなく、男っぽくもなく、中性風で何ともいい感じ。)
ルルが庭にいる時に突然UFOが降ってきて、ロボットのネモが登場します。(山口さんの声はエフェクト処理によりロボット声になっている。) 二人は互いに自己紹介をして、ネモが充電のために休息した後、ルルはネモの話を夢中になって聞きます。ネモは自分の星と主人の王さまの話をします。彼は王様の依頼で「暖かさ」を求めて派遣されましたが、円盤の欠陥で緊急着陸したと話します。ルルは頼み込んで修理を終えた円盤に乗って彼と一緒に旅に出ます。
宇宙飛行の後も円盤はサハラ砂漠へ不時着して、ラクダに乗って暑さの中を旅しますが、途中二人ははぐれてしまいます。ルルは砂漠の遊牧民に助けられてジャングル、サバンナに辿り着きます。(生い茂る植物とボタンを押すことにより現れ動く動物たちの挿絵が美しく素晴らしい。)
ネモはルルを探して中国、日本を回り、捕鯨船に忍び込みます。ネモには二次元の本の中から三次元の外の世界に飛び出して、ページ間を移動する能力があります。(意表をつく発想とそれを表現する3Dアニメが凄い!)
一方ルルは探検家と出会います。捕鯨船から放り出されたネモは北極に取り残され凍り付いてしまいます。探検家はルルに飛行機のパイロットを紹介し、そこでネモのSOSを受信した彼らは救出のため北極を目指して飛び立ちます。ルルは凍ったネモを見つけ、彼女に抱きしめられたネモはその暖かさで生き返りますが、それこそがネモが探していたものでした。
ふたりは飛行機でお城に帰り、ネモはルルに星に一緒に来てと頼みますが、ルルは怖いと言いました。そこでネモはいろいろ考えて、ルルがいる二次元の世界の本で持ってゆくことを提案します。(「想像力とか感動とか夢とか、そういうものを味わえるのは本の中だけってこと」というネモの言葉に、作者が子供達に言いたい想いが込められている。)
二人は本の中のサハラ砂漠のページから(戻り方が奇想天外で最高!)円盤に戻ります。円盤は飛び立ち、宇宙に彷徨っていたルルがいる本を掴み取り、ネモの任務は無事に終わりました。(二次元と三次元の世界がごっちゃになって、「幸せに暮らしました」的な終わりのないシュールな結末になっている。最後にルルの画面が出てきて「もう終わっちゃうの?」。「Oui」を押すとクレジット画面が出てお終い。)
[音楽について]
オリヴィエ・プリズラックによる音楽および効果音(動物の鳴き声、物の動き、ロボットの軋む音、風や水など)はシンセサイザーまたは打ち込みによる電子音楽で、その透明感溢れるサウンドは物語をしっかり支えている。前述の前田秀俊の記事によると、大貫さんとオリヴィエはウマが合ったそう。大貫さんはこの作品では朗読のみだったが、その後同タイトルで作曲して、坂本龍一編曲によりアルバム「Lucy」1997に収めた。本作品の世界を見事に捉えたファンタスティックな佳曲だ。
コンピューター、ソフトウェア技術の発達により視聴不可能となり、長らく埋もれた存在となっていたが、関係者の努力による復刻により、20数年ぶりに再会できた作品。
[2025年12月作成]
|
| 1997年 Lucy (1997/6/6) の頃 |
| Winter Gift Pops (Various Artists) (1997) Columbia |
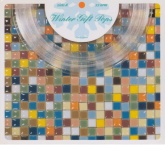
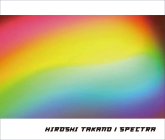 |
11. Silent Song [作詞作曲編曲 高野寛 コーラス編曲 高野寛 大貫妙子] 11曲目 高野寛 大貫妙子
高野寛: Vocal, Chorus, Guiter
大貫妙子: Guest Vocal, Chorus
鈴木正人: Keyboards, Bass
山崎哲也: Drums, Percussion
権藤知彦: Euphonium, Didgerido
高宮正史: Producer
杉真理: Co-Producer
写真上: Winter Gift Pops (1997年11月21日発売)
写真下: Spectra "30th All Time & Collaboration Best" (2018年10月10日発売)
本曲収録
11. Silent Song [Words, Music & Arr: Hiroshi Takano] 11th track by
Hiroshi Takano & Taeko Onuki from the album "Winter Gift Pops"
(Various Artists) on Novemeber 21, 1997
|
当時多くの企画盤の仕掛け人となったFM番組ディレクター高宮正史プロデュース、杉真理コ・プロデュースによるウィンター・シーズン向け企画盤。西洋人にとってこの季節の歌には、何かしらクリスマス絡みの宗教的な匂いがあるけど、ここでは日本人による日本人のための歌として、我々のクリスマスとこの季節に対する想いが、ひたすらポップな歌詞とメロディーのなかに込められている。杉真理の人脈で集まったアーティスト達による曲はどれも素晴らしい出来で、とても良いアルバムと思うが、販売戦略の失敗のためか発売当時はあまり売れずにすぐに廃盤になってしまったという。後になってファンの間で評判が高まり、中古盤が高値で取引されるようになったため、2007年にボーナストラックを追加して再発された。
ポップで明るい歌が多い中で、ゲスト・ボーカルに大貫さんを招いた高野寛の11.「Silent Song」は、タイトルの通り静かな曲調でアルバムの最後を飾っている。といっても控え目なドラムスがちゃんと入っているから他の曲との調和がとれているね。ファースト・ヴァースとコーラスを高野、セカンド・ヴァースの前半が大貫、それ以降は二人による歌唱。ユーフォニウム(チューバを小さくしたような金管楽器)を吹く権藤和彦は、高橋幸宏と親しく、その関連の音楽活動が多い人で、2015~2016年のNHK音楽番組「ムジカ・ピッコリーノ」にゴンドリー役で出演している。なお彼の楽器クレジットにあったディジュリドゥは、オーストラリア大陸先住民のアボリジニの金管楽器(シロアリに食われて中が空洞になったユーカリの木から作られる木製であるが、発音原理から金管楽器に分類される)で、イギリスのファンクバンド、ジャミロクアイが使用して有名になった。その不思議なドローン・サウンドは、曲の背景音作りに使われているようだ。
他の曲について
1. 冬の天使たち [作詞作曲 杉真理 松尾清憲 編曲 嶋田陽一&BOX] BOX。杉真理、松尾清憲、小室和幸、橋本哲によるビートルズ・サウンド。
2. チョコレートのブランケット [作詞作曲 かの香織 編曲 小倉泰治 コーラス編曲 かの香織] かの香織
3. 12月のエイプリル・フール [作詞作曲 EPO 編曲 小倉泰治 コーラス編曲 EPO] 伊豆田洋之。 EPO1985年の代表曲のカバーで、1999年に異なるアレンジでセルフカバーされている。
4. Miss You Baby [作詞 杉山清貴 作曲 村田和人 編曲 小倉泰治] 村田和人
5. あなただけ I Love You [作詞作曲 大瀧詠一 編曲 小倉泰治 コーラス編曲 杉真理] さいとうみわこ。須藤薫1981年のカバー。
6. 永遠のShangri-la [作詞作曲 杉真理 編曲 小倉泰治 コーラス編曲 杉真理] 杉真理、伊豆田洋之、峠恵子。杉真理1985年のアルバム「Symphony#10」のセルフカバー。峠恵子はカーペンターズを歌うことで有名なシンガー・ソングライター。
7. first flight [作詞 高野寛 かの香織 作曲 杉真理 松尾清憲 編曲 小倉泰治] 高野寛 かの香織。豪華な作家陣、デュエットによる佳曲。
8. 神様のプレゼント [作詞 田口俊 作曲 杉真理 村田和人 編曲 小倉泰治 コーラス編曲 杉真理] 長谷川真奈 ゲストボーカル EPO。詩子Withアロハ・ブラザース
1991のカバー。長谷川は2003年ハワイに移住して2018年の帰国後はハワイアン歌手として活躍。セカンド・ヴァースのEPOのボーカルがいいね。
9. Jet Rag Xmas Day [作詞 久保田洋司 作曲 杉真理 松尾清憲 編曲 嶋田陽一&Box] 久保田洋司 With Box
10. Sleeping Gypsy [作詞 山下久美子 作曲 松尾清憲 編曲 小室和幸 松尾清憲] 松尾清憲。山下久美子への提供曲1992のセルフカバー。
11. Silent Song
「Silent Song」は高野寛が2018年に出した音楽活動30周年記念3枚組ベストアルバム「Spectra "30th All
Time & Collaboration Best"」の3枚目(Collaboration)に収録された。
杉真理主導の豪華な顔ぶれによるウィンター・シーズン・コンピレーション・アルバム。大貫さんと高野寛の珍しいデュエットが楽しめる。なお高野寛はこの後2003年に大貫さんのシングル「裸のキリク」制作に参加している。
[2025年12月作成]
|
| 2010年 「Utau」 (2010/11/10発売)の頃 |
| 人間失格 オリジナル・サウンドトラック (中島ノブユキ) (2010) Universal Music |
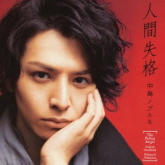
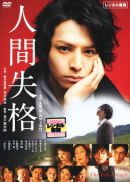
|
1. アヴェマリア [歌詩 Latin Caholic Prayer 作曲 Franz Shubert 編曲 中島ヒロユキ] 2曲目
大貫Mi妙子: Vocal
中島ノブユキ: Piano
徳永友美: 1st Violin
川口静華: 2nd Violin
御法川雄矢: Viola
多井智紀: Cello
松永孝義: Contrabass
カントゥス: Chorus
注: 曲毎のクレジットがないため、録音に参加した可能性のある人全てを表記しました。
写真上: サウンドトラック・アルバム (2010年2月10日発売)
写真下: 映画のDVD(2010年8月4日発売)
|
映画のサウンドトラック・アルバムであるが、作曲家中島ノブユキの作品として立派に成り立っている。
1848年入水自殺を遂げる太宰治が死の直前に書いた「人間失格」は、自分を欺き、周りの人々とりわけ女たちと絡みながら酒と薬に溺れてゆく男の半生を綴った作品で、現在に至るまで多くの人に読まれ続けていて、私も若い頃に新潮文庫を手にした一人である。映画は太宰の生誕100年を記念して角川映画が企画制作し、監督
荒戸源次郎、主演 生田斗真、その他の出演 伊勢谷祐介、寺島しのぶ、石原さとみ、小池栄子、坂井真紀、室井滋、石橋蓮司、森田剛、三田佳子などで、2010年2月20日に公開された。
映画については評価が両極端に別れているが、映画を観た印象として、大庭葉蔵という男についてのフィクションなのに実在の詩人(中原中也)が出てきたり、故郷で療養生活を送ることになった時に一緒に暮らすことになったテツという「ひどい赤毛の醜い女中」が、映画では三田佳子演じる「美しい老女中」になっていたり、最後に東京に逃げ帰った主人公がバーで女マスターと一緒に太平洋戦争勃発のラジオ放送を聴くシーンなど、原作と大きく異なる部分があり非常に気になったが、それなりに引き込まれた部分もあった。もともと不愉快極まりない内容なので、面白く作りようがないというハンディがあることを考慮しなければならないね。生田斗真にとって、ジャニーズのアイドルから出て、俳優としてテレビドラマで評価を上げた後の初めての映画主演作で、本作で第84回キネマ旬報新人男優賞をとったという点と、前半に榎本佑が端役で出ているのが特記事項。
音楽を担当した中島ノブユキ(1969- 群馬県生まれ)は、大学卒業後パリで学んだ作曲家、編曲家、ピアニスト、音楽プロデューサー。2006年からソロアルバムを発表し、本作が初の映画サウンドトラックとなった。主人公や登場人物の心象を表すピアノ、ギター、管弦楽器とストリングスからなる音楽(クラシック音楽2曲を除き中島の作品)①と、主人公が入り浸るバー(蓄音機にかかるSP盤やラジオの音楽)やカフェ(女給の接待付きで所謂キャバレーのこと、ハウスバンドの演奏として)でのラウンジ・ミュージックやスウィング・ジャズ(いずれも中島の作曲)②からなっている。実際のところ、アルバムに収められた①の多が映画ではボツになったり、②も演奏のごく一部のみしか使われなかったが、それらを敢えて収録し、中島本人がライナーノーツを書いて、何故この曲が使われたのか、使われなかったのかの経緯を説明しており、それが実に面白い。特に「ヒッチコックの映画などでスコアを書いていたバーナード・ハーマンの影響が強すぎて、(個人的には)聴いていて少々くすぐったい」というコメントは傑作。サウンドトラック特有の1分に満たない曲から、ピアノ主体によるエリック・サティのような「メインテーマ」まで、ボツになった曲も含めすべてが素晴らしい。
そのクラシック曲のひとつが、大貫さんが歌う「アヴェ・マリア」だ。映画冒頭の主人公と女マスターがいるバーで蓄音機にかかる。サントラでの演奏時間3分2秒に対し映画では1分半ほどでフェイドアウトするが、子供時代の写真から回想に入ってゆく導入部に流れるもので、主人公の女性観を象徴する大切な役割を担っている。中島のライナーによると、この曲は音楽を担当する前から、脚本に記されていたそうだ。また日本語は歌詞の意味が強く伝わり過ぎるということで、ラテン語バージョンで録音されたという。ラテン語によるカトリックの祈祷文にシューベルトが曲をつけたもので、歌詞は以下のとおり(本録音では後半の一部が省略されている)。
Ave Maria , gratia plena アヴェ、マリア、恵に満ちた方
Maria, gratia plena 恵みに満ちたマリア様
Maria, gratia plena 恵みに満ちたマリア様
Ave, Ave, Dominus 主よ
Dominus tecum 主はあなたと共におられます
Benedicta tu in mulierbus, et benedictus あなたは女からも、おとこからも祝福され
Et benedictus fructus ventris (tui) 胎内の子、イエスも祝福されています
Ventris tui, jesus あなたの胎内から
Ave Maria 素晴らしいマリア様
In hora, hora mortis nostrae 死を迎える時も
In hora mortis nostrae 死ぬときも
Ave Maria 素晴らしいマリア様
感情を込め過ぎない大貫さんの歌声を選んだのも上記と同じ理由なのだろう。それともちょっと退廃的な感じがするからかな?背景に聞こえるコーラスを歌うカントゥス(Cantus)は、ラテン語で「歌」という意味で東京で結成された女子聖歌隊。なお彼女らは2016年に坂本美雨と「Sing
With Me」というアルバムを録音していて、そこでは大貫さんの「メトロポリタン美術館」を歌っている。
中島ノブユキ氏は、大貫さんが主題歌を作詞作曲したアニメーション「たまゆら」2010~2015、NHK大河ドラマ「八重の桜」2013、ジェーン・バーキンのコンサートやアルバム
2011~2017 など、映画、テレビドラマ、CM、アーティストのアルバム・コンサート等で活躍し、2017年以降は拠点をパリに移して活動を続けている。
本作が配信で聴くことが出来るが、興味のある方はアルバムを手に取って、彼が書いたライナーノーツを読みながら楽しむことを強くお勧めします。大貫さんの歌う「Ave
Maria」、定番の豊かなオペラ声と違って、個性的でとてもいいよ!
[2025年10月作成]
|
| |
|
|

